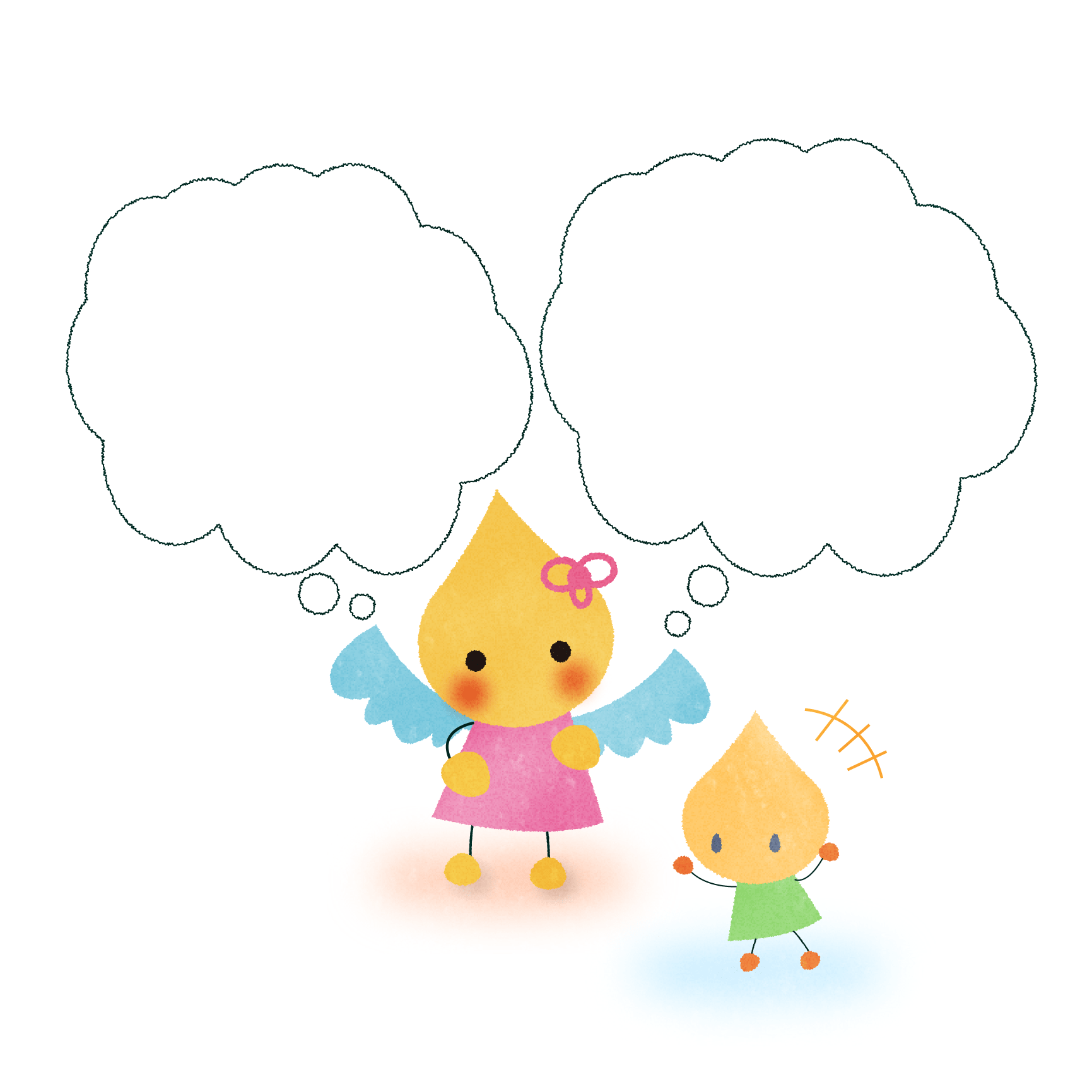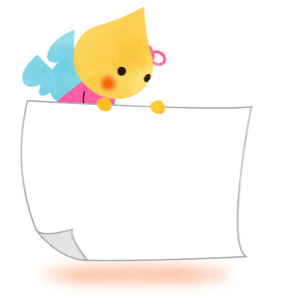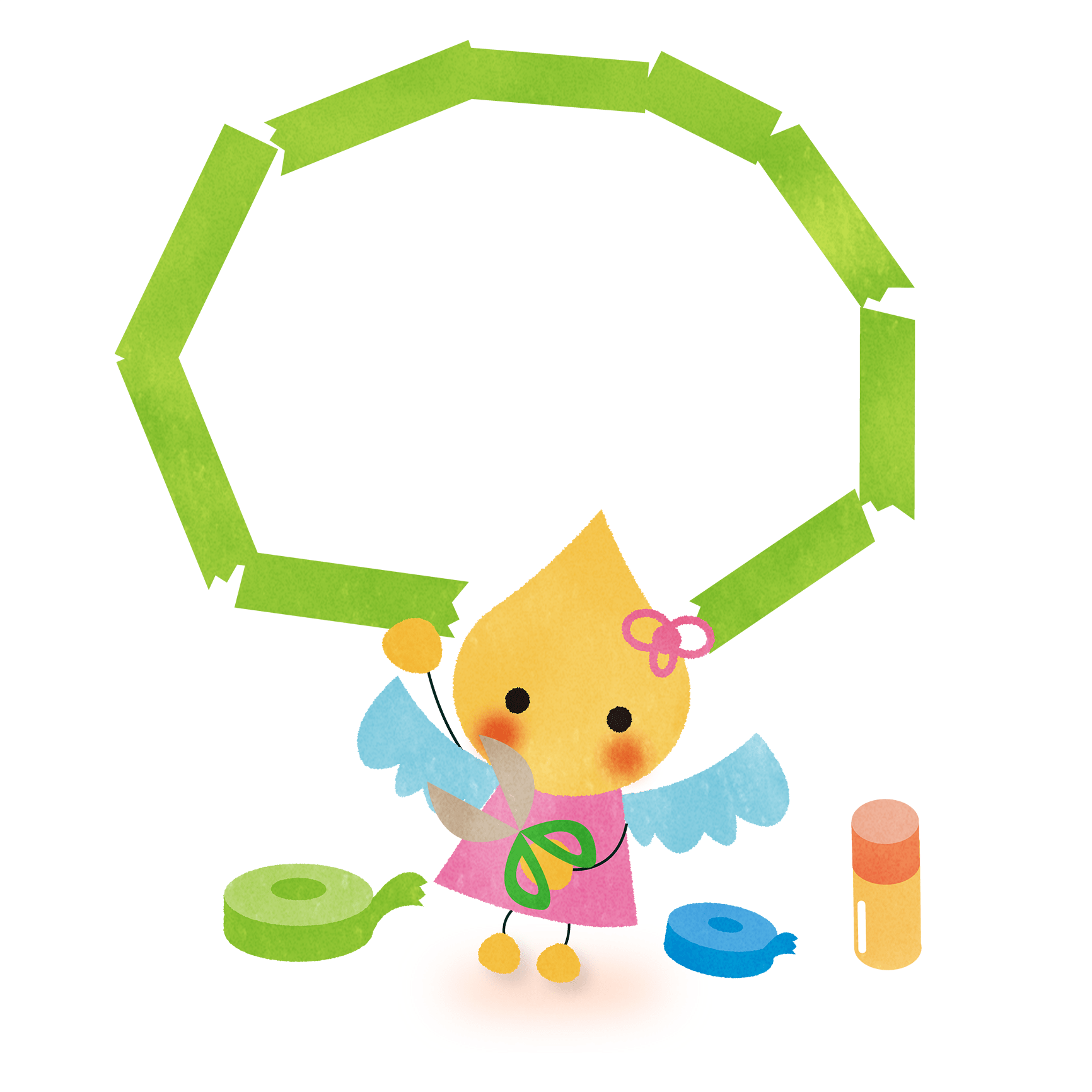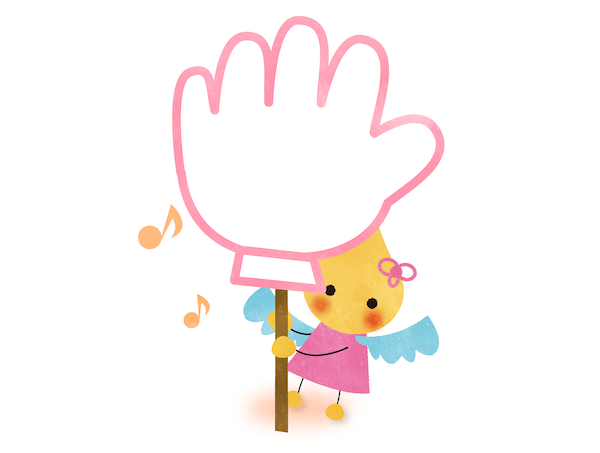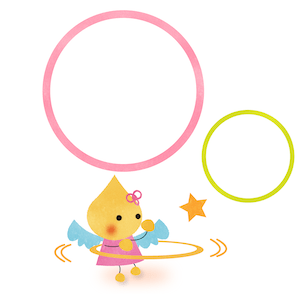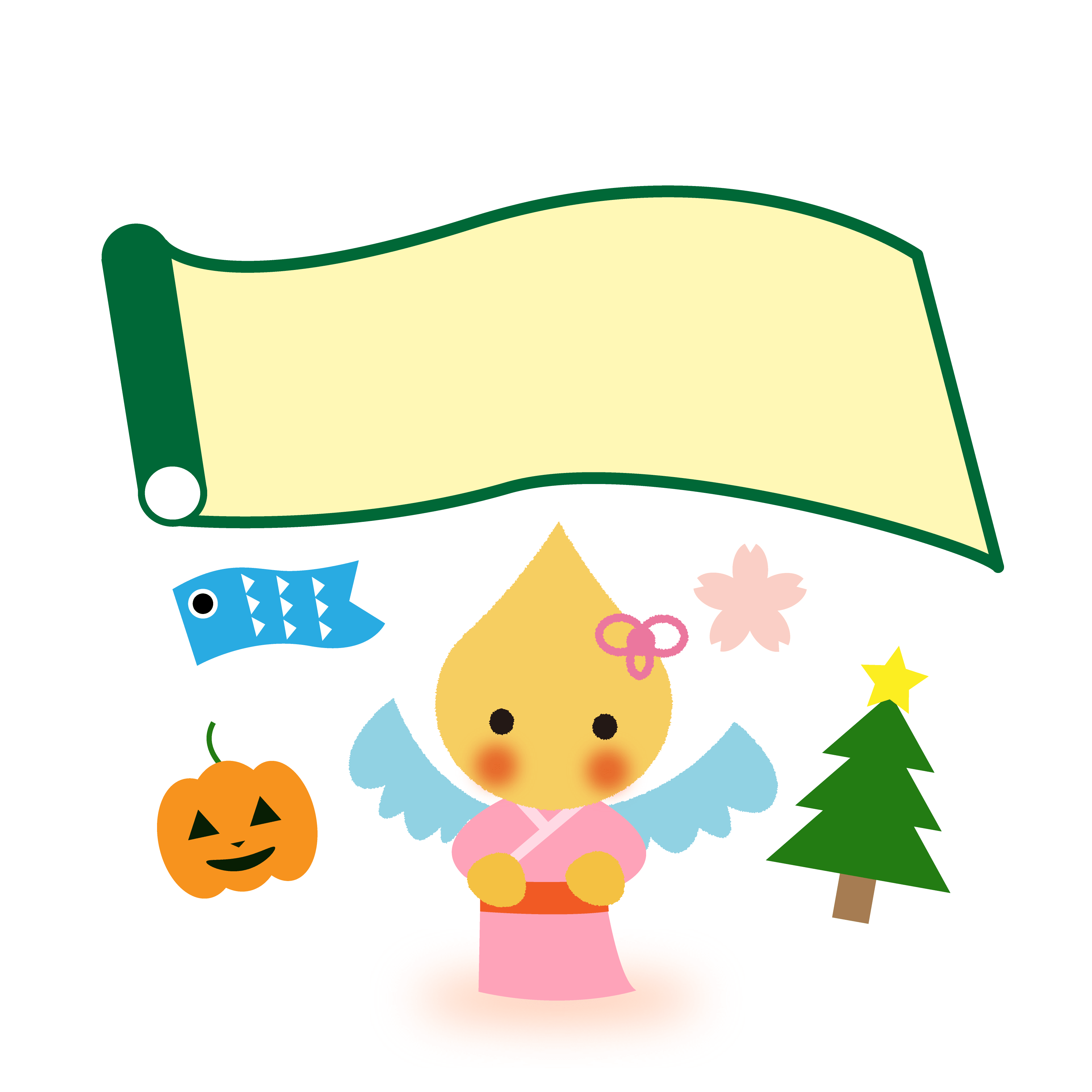もくじ
月案de動画
今月の保育のポイント
- 一つ先の見通しをつけ、身の回りの簡単なことを自分でしようとする時期。子どもがやりやすいように、上着を入り口にかけておく、着る順番に服を並べておくなどの環境的な配慮をしておくことで、意欲を引き出せる。
- 自分でできたことを認められ、自信につながっていくよう、子どもの差を考慮して個別で「今日はここまでできたね」「いつも自分でやりだして偉いね」など認め、褒める言葉かけをしていく。
- 遊びでは手指の操作がより細かくできるようになり、より速く走ることを実感できるようになってくる。それと共にイメージの共有も育ってくるので、ごっこ遊びや表現遊びを保育士と楽しんでいき、みんなで同じことや感覚を共有する楽しさを味わう。
月のねらい
- はさみやのりなどの道具を使って、保育者と一緒に楽しく製作をする。
- 寒さに負けず、戸外で身体を動かして遊ぶ。
- 身近な自然に触れながら、健康に過ごす。
- 友達や保育者と関わりながら遊ぶ楽しさを味わう。
ほいくのおまもりプラス
週のねらい
その1
- 1週目:はさみやのりなどの道具を使って、保育者と一緒に楽しく製作をする(教育)
- 2週目:寒さに負けず、戸外で身体を動かして遊ぶ(教育)
- 3週目:身近な自然に触れながら、健康に過ごす(教育)
- 4週目:友達や保育者と関わりながら遊ぶ楽しさを味わう(教育)
その2
- 1週目:身の回りのことを進んで自分でしようとする(養護)
- 2週目:感染症予防のために湿度、温度を気を付けてこまめに換気をする(養護)
- 3週目:ごっこ遊びや表現遊びを保育者などと楽しむ(教育)
- 4週目:戸外で遊具などを使用して全身を使って遊ぶ(教育)
ほいくのおまもりプラス
前月末の子どもの姿
養護(生活)
- スプーンやフォークの正しい使い方を覚え、きちんと持とうとする子どももいるが、まだ定着せずグーで握ってスプーンを持っている子どももいる。
- トイレでの排泄に成功する回数が少しずつ増え、喜びを感じている子が増えてきている。
- 着替えや食事などでは自分でやろうとする姿が見え、一生懸命行なっているが、上手くできない時には泣いたり甘えたりする姿がある。
💡
甘えるときは一緒にいてくれるからやろうと思えることもあるので、「大丈夫だよ」と安心させてあげましょう。 - 言葉を覚え、「先生」と保育者を呼んだり「いやだ」「おもしろいね」「もう一回やって」などの要求や感情を簡単な言葉で表せるようになってきている。
教育(遊び)
- 友達が遊んでいる玩具に興味を示し、一緒に遊ぼうとする姿が見られる。
- ペンやのりなどを使って絵を描いたり製作したりすることを楽しんでいる。
- 身体の使い方が分かり、くぐる、ジャンプするなどが少しずつ上手にできるようになってきている。
- 落ち葉や木の枝などに興味を持ち、自然に触れながら遊ぶ姿がある。
- 「貸して」などの言葉が上手く表現ができず、友達が使っている玩具を勝手に使ったりとってしまったりし、トラブルになることが多々ある。
💡
しょっぱい経験も人生です。トラブルを無くすのではなく、あっても大丈夫なように心構えておきましょう。
ほいくのおまもりプラス
活動内容(5領域対応)
養護(生活)
- 衣類の着脱だけでなく、服を畳む、畳んだ服を引き出しやカバンにしまうなど様々なことを自分でしようとする。(健康)
💡
大事な物は自分で管理しようとします。自分にとって大事な物だということを意識できるようにしてみましょう。 - 雪や氷、乾燥した葉っぱなど冬の自然に触れ、感触や冷たさなどを楽しむ。(表現・環境)
- トイレで排泄する感覚を覚え、行きたい時に行動や言葉で示そうとする。(健康)
- 親しみのある保育者や友達との関わりを喜び、安心できる環境の中で健康に過ごす。(人間関係・健康)
💡
自立を目指して色々声掛けしていきますが、その土台には安心があります。安心第一の保育を。 - 豆まきに参加し、異年齢児と楽しい雰囲気の中で関わりを持つ。(人間関係・環境)
- 自分で身の回りのことができる喜びを味わい、進んでやってみようとする。(健康)
- 自分で手を洗い、一人で出来た実感と清潔の快適さを味わい、うがいにも挑戦する。(健康)
- 室内ではゆったりと自分の好きな遊びを楽しみ、片づけを意欲的にしようとする。(健康・環境)
ほいくのおまもりプラス
教育(遊び)
- 保育者と一緒にごっこ遊びや表現遊びを楽しみ、同じイメージを持って遊ぶ楽しさを味わう。(人間関係・表現)
💡
まさに思いが響きあうような光景が2歳児保育の楽しいところ。細かい設定は置いといて、同じ感覚を楽しむところが肝です。 - はさみやのりなどの道具の危険のない使い方を知り、保育者と一緒に製作を楽しむ。(環境)
- 遊びの中で保育者に仲立ちされながら友達に「貸して」「いいよ」など簡単な言葉で気持ちを表現する。(言葉)
💡
貸してと言われたら、必ず貸さなくても良いことを伝えましょう。大事なのはその子の気持ちです。 - 友達に興味を持ち、関わって遊ぼうとする。(人間関係)
- リズム遊びや好きな歌を通して、様々な音の楽器を鳴らしたり歌ったりすることを楽しむ。(表現)
- 会話ややり取りを楽しみ、簡単なルールのある遊びを一緒に楽しむ。(人間関係・表現)
- 不思議なことや知りたいことを言葉にして尋ね、知ろうとする。(人間関係・環境・言葉)
- 身近な物から刺激を受け、想像したことを言葉で友達や保育士と共有し、言葉や行動で想像の世界を広げながら共有して楽しむ。(人間関係・環境・言葉・表現)
ほいくのおまもりプラス
環境構成と援助
養護(生活)
- 「手で食べない」「食べ終わっても立ち歩かない」など食事中のマナーを一人ひとりの成長に合わせて丁寧に繰り返し伝えていく。
- 排泄に成功する機会が増えたら男児は立って排尿する、女児は自分でトイレットペーパーを切ってみるなど次のステップへ挑戦できるように少しずつ促していく。
💡
子どもの次のステップを想像して保育しましょう。立って排尿できるような環境、一緒に付き添ってやってみるなど、時期や段階を見て失敗しても良いので取り組んでみることが大事です。 - 服を畳む際には、子どもができる程度に整えておき、実際にたたんで見せながら真似できるようにやって見せる。
- 戸外の寒さが厳しく、外に出るのを嫌がる子どももいるため、防寒できるように上着や手袋など必要に応じ準備しておく。厚着すぎると動きにくくなってしむため、動きやすいかどうかにはよく配慮する。
💡
子どもの考えたことを実際させてあげましょう。上着を嫌がる子は、持って行って寒ければ着るような形に落とすのがベストです。 - 子どもが実際に雪や氷などに気付いて触れられるよう、準備したり声をかけたりして知らせていく。
- 異年齢児と関わる際には、他クラスの職員と連携をとりながら未満児にも危険のないような環境を整える。
💡
環境が複雑になると見失いも多く発生しがちです。より安全管理に重点を置いて保育しましょう。 - 「自分でできたの?すごいね!」等、子どもがやる気になっているときは惜しまず褒める。服を順番に広げて置くなど、自分でやりやすい環境を用意する。
- 手洗い時、綺麗になったであろうタイミングで次に進めるよう促したり、子どもが適切な時間と感覚を掴めるように援助を行う。うがいでは口に水を含んで声を出すところから始め、徐々に慣れていくようにする。
- 室内で落ち着くようにゆったりと関わり、好きな遊びができるよう、昨日からの続きがあれば環境を残しておく。「片付け上手だね、ありがとう」などと意欲を引き出す言葉をかける。
ほいくのおまもりプラス
教育(遊び)
- ごっこ遊びでは、「ケーキ屋さん」「ご飯を食べる」など子どもにとって身近な遊びを提案し、イメージしやすいように援助する。
- はさみを使う際には怪我のないよう事前に約束事を伝え、使っているときにも必要に応じて危険のないよう繰り返し声をかけるようにする。
💡
はさみで指を切ることも大事な経験です。ぎこちないからと全て先立って手取り足取りやるのではなく、経験から学べることも大事にしましょう。 - カスタネットやすず、タンバリンなど簡単な楽器を準備し、一人ひとりがいろんな楽器に触れられるようにする。また、実際に音を鳴らしてみたり音楽に合わせて自由に鳴らしたりできるようにする。
💡
保育者進んで音の違いを比べてみたり、楽しみ方を提示していきましょう。 - 遊びの中で「貸して」と子どもと一緒に言うことで、子どもがどういう時に言うのか分かるように援助していく。
- 何をするかが分かる簡単なルール遊びの道具を用意しておき、保育士が先頭で遊びを示す。参加しない子がいても認めて無理に参加をさせないようにする。
- 子どもたちの関心を発生、広げられるように、図鑑を保育室に置いておく。子どもたちの質問には「どうなのかな?」「~だと思うけど、一緒に見てみようか」など、同じ目線で知るプロセスを辿ったり、想像をしながら楽しんで辿る。
- 例えば横たわる丸太を「あ、バイクだ!」と子どもが発想したとすれば、「もしかすると、空を飛ぶバイクかもしれない」など、保育者がイメージを膨らませるような声かけをし、楽しいごっこ遊びを展開する。子どもたちの会話からその木に名前をつけるなど、これからも楽しい実りある環境になるように進めていく。
ほいくのおまもりプラス
健康、安全面で配慮すべき事項
- 走り回ったり高いところに登りたい気持ちが強く、周りに関係なく行なってしまうことが多い時期。転倒しても危なくないよう、周囲の状況や環境に注意しながら遊びを見守る。
💡
危険なことを止めるところと認めるところのさじ加減を見極めましょう。保育者が受け止める位置にいるなど、リカバリーできるかどうかが判断基準です。 - 感染症が流行りやすいため、下痢や嘔吐、発熱があった際には職員で連携を取り、適切に対応して広めないように気をつける。また、保護者にも注意喚起を行っていく。
- 室内の環境を清潔に整え、健康に過ごせるようにする。
ほいくのおまもりプラス
今月の製作・歌・絵本・手遊び・室内室外遊び
製作
- 鬼のお面製作
- かわいい羊製作
- スノードーム製作
この他、【冬の自然】や【行事】の製作を『ちぎる、指で塗る、ビー玉で転がす』等、色々な素材と手法でご紹介!
歌
- うぐいす
- コンコンクシャンの うた
- かぜさんだって
絵本
- ゆき
- とりかえっこ
- こぐまちゃんありがとう
手遊び
- トントントントンひげじいさん
- いとまき
- てんぐのはな
室内室外遊び
- PEテープで引っこ抜き
- ストロー落とし
- しっぽつき鬼ごっこ
行事
- 誕生日会
- 避難訓練
- 身体測定
- 節分(豆まき)(2月3日)
- 建国記念日(2月11日)
- バレンタインデー(2月14日)
- 猫の日(2月22日)
- 天皇誕生日(2月23日)
食育
- 豆まきを通して豆に親しみ、豆を食べると身体を丈夫にしてくれることを知る。
- 食事のマナーを守り、楽しい雰囲気の中で意欲的に食事をする。
ほいくのおまもりプラス
異年齢保育
この項目はおまもりプラスで公開中!
職員間の連携
この項目はおまもりプラスで公開中!
地域と家庭との連携
- 身の回りのことなど自分でできることが増えたことを伝え、褒めたり励ましたりしながら見守って貰えるようにする。
- 感染症の流行状況を知らせるとともに、家庭でも手洗いうがいができるようにしてもらう。
- 年上の子どもとかかわって遊んでいる様子を伝えたり、進級することへの取り組みを伝え安心して準備をしてもらえるようにする。
長時間保育の配慮
この項目はおまもりプラスで公開中!
自己評価
- はさみの危険性を知り、気をつけて怪我なく使って製作を楽しめたか。
- 戸外での遊びを喜び、身体を動かして遊ぶことができたか。
- 氷や雪など冬の自然に触れ、興味を持つことができたか。
- 保育者や友達と楽しく関わることができたか。
- 衣類の着脱や排泄など、子ども自身が意欲的に行うことができたか。
ほいくのおまもりプラス
個人案はこちら♪
-

-
【2月】個人案の文例【2歳児】
続きを見る
↓その他の保育ネタ↓