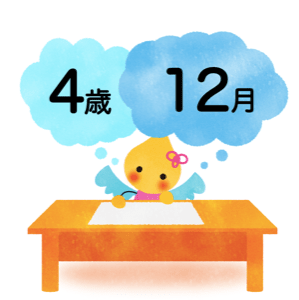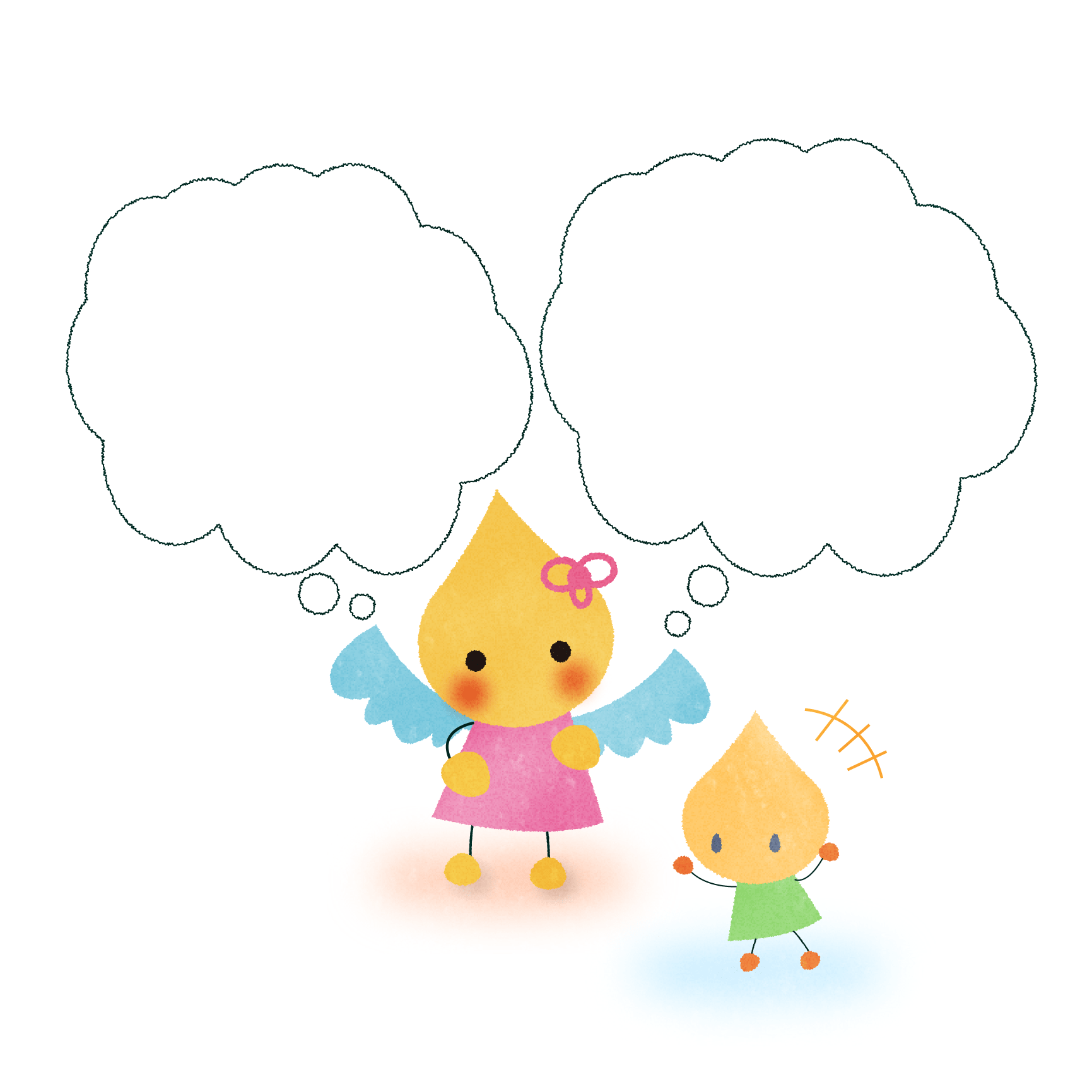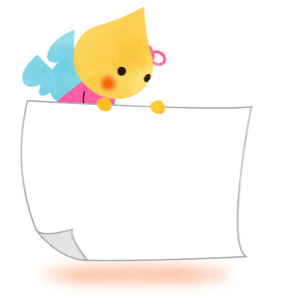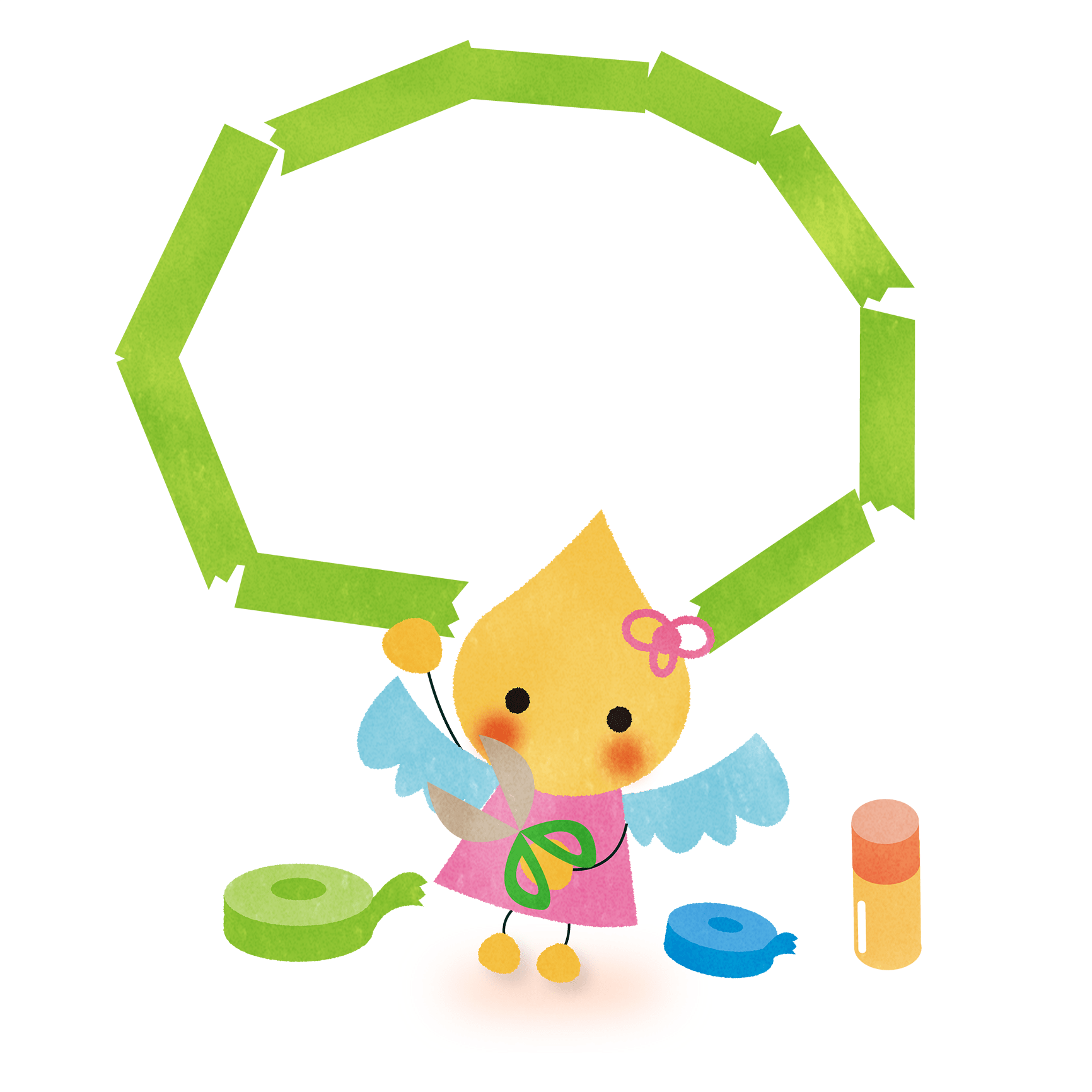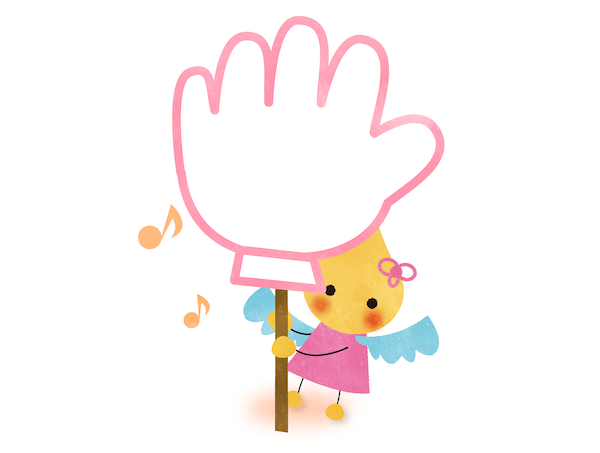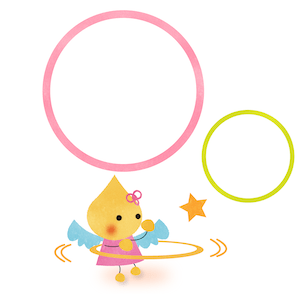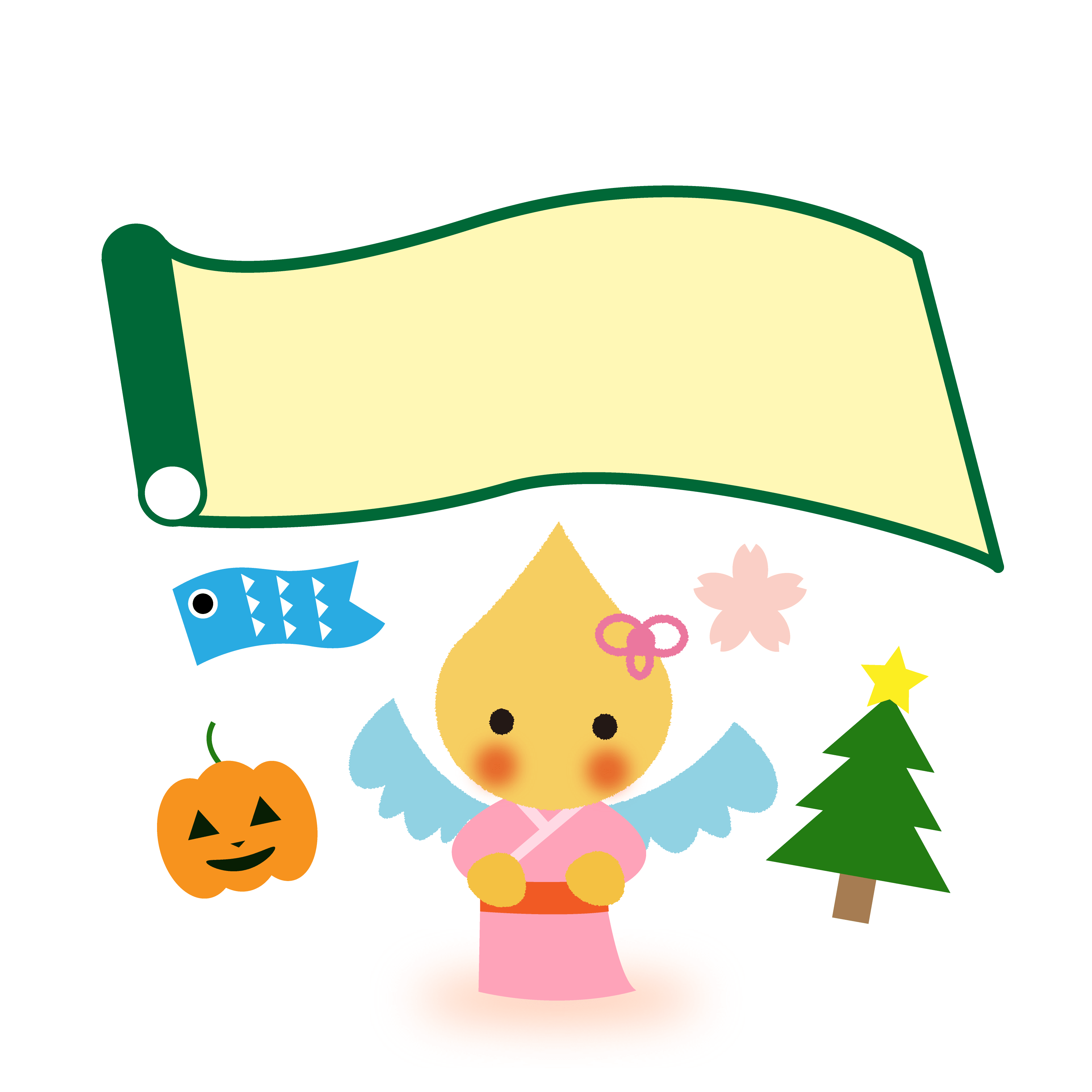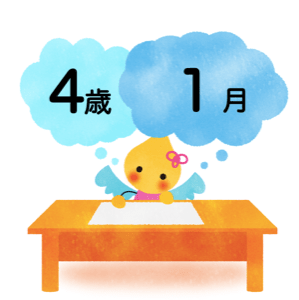
もくじ
月案de動画
今月の保育のポイント
- 手がかじかむ、息が白い、霜柱があるなどの、冬の自然現象に興味をもち、いつもとの違いに体で気付く子どもたちに「不思議だね」「どうしてこうなるんだろう」と一緒に共有しながら調べていくと、楽しく自然の変化を楽しめる。いくつかのバケツにちょっと水を張っておき、凍ったもので遊ぶのも面白い。
- 「寒いのは嫌い」「寒くても外が好き」各家庭のこれまでの生活によって、それぞれ好みが出てくる。子どもに合わせてどちらも楽しめるように環境を準備していく。
- トラブルや困ったことが続けば、クラスで共通のルールをもって話して考える機会も大切。ルールは保育士が子どもに与えるものではなく、みんなが快適に過ごすための決まりという認識を子どもがもつことが重要。
月のねらい
- 遊びのルールを守りながら、気の合う友達と一緒に遊ぶことを楽しむ。
- 冬の自然現象を知り、興味や関心を持つ。
- 必要な生活習慣を身につけ、健康に過ごせるようにする。
- 自分の気持ちや考えを保育者に伝えようとする。
- お正月料理や七草がゆなどの日本の風習に触れ、日本の文化に関心を持つ。
ほいくのおまもりプラス
週のねらい
その1
- 1週目:生活リズムを整え、遊びや活動を思いっきり楽しむ(養護)
- 2週目:お正月遊びやおもちつきを通して、日本の風習について知る (教育)
- 3週目:友達と一緒にルールを守って遊ぶ楽しさを味わう(教育)
- 4週目:気の合う友達に自分の気持ちを伝えたり相手の気持ちを受け止めたりしようとする(教育)
その2
- 1週目:お正月ならではの遊びに興味をもち、ルールを守って気の合う友達と一緒に遊ぶことを楽しむ(教育)
- 2週目:冬の生活に必要な習慣を身につけ、健康で快適に過ごせるようにする(養護)
- 3週目:身近な自然の変化に気づき見たり触れたりして興味や関心を持つ(教育)
- 4週目:お話のイメージを広げたり、友達と表現したりすることを楽しむ(教育)
ほいくのおまもりプラス
前月末の子どもの姿
養護(生活)
- 「○○ちゃんが泣いてる」「怖い顔をしている」など相手の変化に気付き、相手の思いに少しずつ気付くようになっている。
💡
気づかない子には「喜んでいる顔をしてる?どう思っているかな」と表情から考える声掛けを。 - 寒くなってきて水が冷たいため、手洗いやうがいが面倒になり適当に済ませようとする子がいる。
- 片付けの際には、自分が使っていない玩具も友達と協力して片付けようとしている。
💡
友達と協力して片付けると早い等、良さがあることを伝えましょう。 - 鼻水が出ていても気にならず放っておいてしまう子やうまく鼻がかめない子がいる一方で、「鼻水が出ているよ」など友達同士で声を掛け合う姿も見られる。
教育(遊び)
- 鬼ごっこなどの簡単なルールのある遊びを、気の合う友達と一緒に楽しんでいる。
💡
保育者もたまには思い切って一緒に遊んでみましょう。子どもの目線まで下がることが大切です。 - 遊びの中で友達とイメージを共有できるように、自分の思いや考えを言葉で相手に伝えようとしている。
- 落ち葉や雪などに関心を持ち、実際に葉っぱに触れたり絵本などを見たりして冬の自然を見たり楽しんでいる。
- 友達と一緒に歌を歌ったりダンスをしたりすることを楽しむ姿がある。
ほいくのおまもりプラス
活動内容(5領域対応)
養護(生活)
- 手洗いうがいを行う大切さを知り、自らきちんとしようとする。(健康)
- お餅つきやお正月料理、給食などを通して食材に関心を持ち、楽しんで楽しい雰囲気の中で食事をする。(環境・健康)
💡
「これは~だね」「こんな風にとれるんだよ」と大人にとっては知っていることも、子どもにとっては新たな世界であることが多いですよ。 - 白い息が出たり手が冷たくなったりすることに気づき、冬ならではの現象に興味や関心を持つ。(環境)
- 生活の中で自分の思ったことと、実際に起こっていることを結び付けて生活する。(環境・表現)
- トイレをマナーに配慮しながら使用し、自分や他者が快適に生活をする。(健康・環境)
- 人の考えを聞いたりみんなで話し合うことを通して、自分と考えや意見が違う人を知る。(人間関係)
ほいくのおまもりプラス
教育(遊び)
- 友達と遊びのイメージを共有し、一緒に話し合いながら遊びを進めることを楽しむ。(言葉・人間関係)
- かるたやコマ回しなどのお正月ならではの伝統的な遊びを楽しむ。(環境)
- 友達に自分の考えや気持ちを伝えるとともに相手の考えも受け止め、話に折り合いをつけようとする。(言葉)
💡
喧嘩をしたとき、お互いの嫌だったところを聞いてみましょう。向こう側に違う人の気持ちがあることを知るのがねらいです。 - 落ち葉や氷などを見つけ冬の自然に親しみ、遊びに取り入れようとする。(環境・表現)
💡
4歳児はイメージで遊ぶだけではなく、「~だからだ」などの理由付けも楽しみます。(「冷たいからバケツに入れて運ぼう」など) - 新しい内容やルールのある遊びに対して、負けや失敗をしても次がある安心感をもって挑戦する。(健康・人間関係)
- 自分の好きな遊びを友達と思いを出し合いながら進め、一体感や自己発揮の楽しさを味わう。(健康・人間関係・表現)
- 様々な素材を使って制作を行い、作ったもので友達と遊んだり、互いの表現を認め合いながら一緒に取り組む。(人間関係・表現)
ほいくのおまもりプラス
環境構成と援助
養護(生活)
- 手洗いうがいは風邪の予防になることを伝え、石鹸を使って丁寧に洗う方法を説明する。
💡
水が冷たいので、すぐに終わらせる子もいます。一緒に洗ってあげましょう。 - 料理に使われている食材について話をする機会を設け、子どもが食材に興味を持てるようにする。
- 寒いと息が白くなるなどの冬ならではの現象に、子ども自身が気付けるように声掛けをする。
💡
「何で息が白くなるのかな?」とみんなで考えてみてもいいかもしれません。 - 「福笑い」が食べ物だと思っている子どもがいたり、子どもの中でまだ曖昧なものが多い中で、想像、思考しながら実物やその内容を知る喜びを楽しめるよう、保育者が積極的に子どもたちに問いかけ、その後で実物を出したり、一緒に調べる等、1度は想像して期待するクッションを挟む。
- スリッパを並べることや、手洗いの水を床に落とさないことを、どっちが使いやすいか?を示しながら丁寧に伝えていく。つい粗雑になってしまう子には、一人ひとりの協力が必要であることも個別にお願いをする。
- 一人ひとりが考えられるよう、最初はどっちで遊びたいか?を提示するところから始め、二つのコーナーで責任をもって片づけをしたり、場所を確保することを経験していく。その際、自分の意見が通らなかったり、話す内容が分からない子の援助を保育者が代弁したり、励ましたり、注釈をつけるように分かりやすく説明をする。
ほいくのおまもりプラス
教育(遊び)
- 遊びのイメージがなかなか共有できず、友達の輪に入れない子がいないかよく注意してみておく。友達に一緒に声をかけたり、遊んでいる子にルールをゆっくり説明してもらうなど援助し、友達と遊ぶ楽しさを味わえるようにする。
- 遊んだことのない子にも分かるように、かるたやコマ回しなどのやり方を丁寧に伝える。
💡
実際に見せながら説明するのが1番です。視覚に訴える援助を。 - 友達と一緒に遊びを進められるよう玩具は十分な量を準備し、思いっきり楽しめるよう遊ぶ場所やルールを決めておく。
💡
片付け場所も見やすくわかりやすく用意しておきましょう。 - 落ち葉や氷を遊びの中で活かせるよう、必要に応じて遊びの提案が行えるようにしておく。
- 新しい遊びや集団でのルール遊びを行う時、「ちょっと難しいけどできるかな?」「負けても復活ができる」などの逃げ道を用意しておき、子どもたちの抵抗感なく入れるようにする。段々と慣れてくれば負けたら待つなどのルールに変更する。
- 空想の世界に入って遊べるよう、子どもが好きな絵本の内容などに沿って製作活動や探索活動などの活動を進める。想像の世界からクラスの物語を作っていく。
- 色んな素材を用意し、子どもの想像力を発揮できる環境を整える。作ったものを明日も使えるように残す場所を確保する。
ほいくのおまもりプラス
健康、安全面で配慮すべき事項
- インフルエンザなどの流行性の風邪が流行りやすい時期。発症が疑われるときには迅速な対応ができるよう、職員同士で対応を確認しておく。
- 子ども自身で気温に合わせて衣類の着脱を行おうとするがしっかりと自己管理することは難しいため、室内外の気温に合わせて適切な格好ができているか注意してみる必要がある。
💡
肌着が入っているかどうかなど、見てあげましょう。 - コマ回しは思った方向にコマが飛ばせない恐れもあり少し危険を伴うので、子どもが遊び込めるようにコーナーをしっかり準備し、安全に遊べる場を準備しておく。
ほいくのおまもりプラス
今月の製作・歌・絵本・手遊び・室内室外遊び
製作
- パクっとけん玉
- 紙皿で作る立体トラ
- 段ボール羽子板製作
この他、【冬の自然】や、【来月の行事】の製作を『ダンボール、紙粘土、毛糸、紙皿』等、色々な素材を使ってご紹介!
歌
- ゆげのあさ
- ゆきのプレゼント
- ゆきってながぐつ好きだって
絵本
- あけましておめでとう
- おおかみと七ひきのこやぎ
- 14ひきのもちつき
手遊び
- 大きくなったら何になる
- おにのパンツ
- せんせいとおともだち
室内室外遊び
- 転がしドッジボール
- ねことねずみ
- 画用紙で簡単凧揚げ
行事
- お餅つき
- 誕生会
- 避難訓練
- 元日(1月1日)
- 書き初め(1月2日)
- 人日の節句(1月7日)
- 鏡開き(1月11日)
- 成人の日(1月12日)
食育
- お餅つきやお正月料理を体験することでお米や黒豆などの食材に親しみ、食べ物に関心を持つ。
- 保育者や友達と会話しながら楽しく食事を進める一方で、食べながら話さないなどの食事のマナーを知り、守ろうとする。
ほいくのおまもりプラス
異年齢保育
この項目はおまもりプラスで公開中!
職員間の連携
この項目はおまもりプラスで公開中!
地域と家庭との連携
- 園だよりや掲示板でもちつきの日程について知らせ、準備の協力をお願いする。
- 元気に過ごすための情報や対策を共有し、家庭でも生活リズムに気をつけて過ごしてもらえるよう呼びかける。
- 連休明けで体調の変化も起こりやすいため、子どもの様子について細かに知らせていく。 自分の持ち物を自分で管理しようとできる時期であるため、子どもが自分の持ち物だと分かるように、一緒に準備したりマークをつけたりしてもらうよう協力を求める。
長時間保育の配慮
この項目はおまもりプラスで公開中!
自己評価
- 子ども同士がお互いに自分の気持ちを言葉で伝える機会が持てたか。
- 発熱などの症状があった時には職員で連携を取り、迅速な対応ができたか。
- 友達と一緒にルールを守りながら遊びを進める楽しさを味わうことができたか。
- 手洗いうがいなどの正しい行い方を知り、子どもが自ら行えるようになったか。
ほいくのおまもりプラス
↓その他の保育ネタ↓