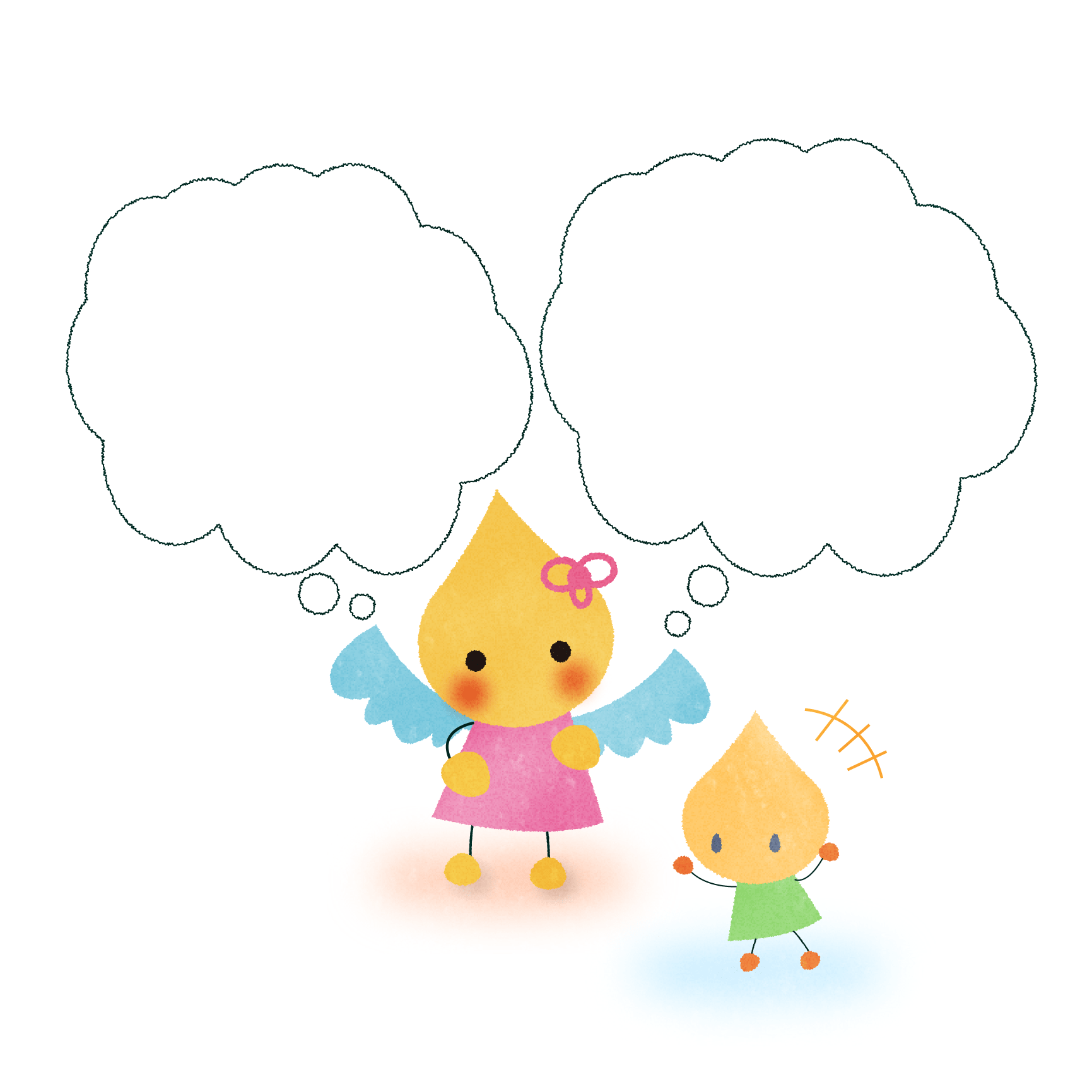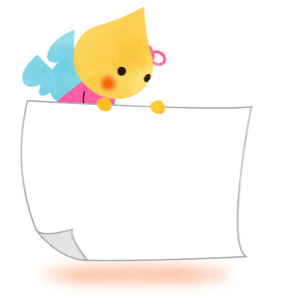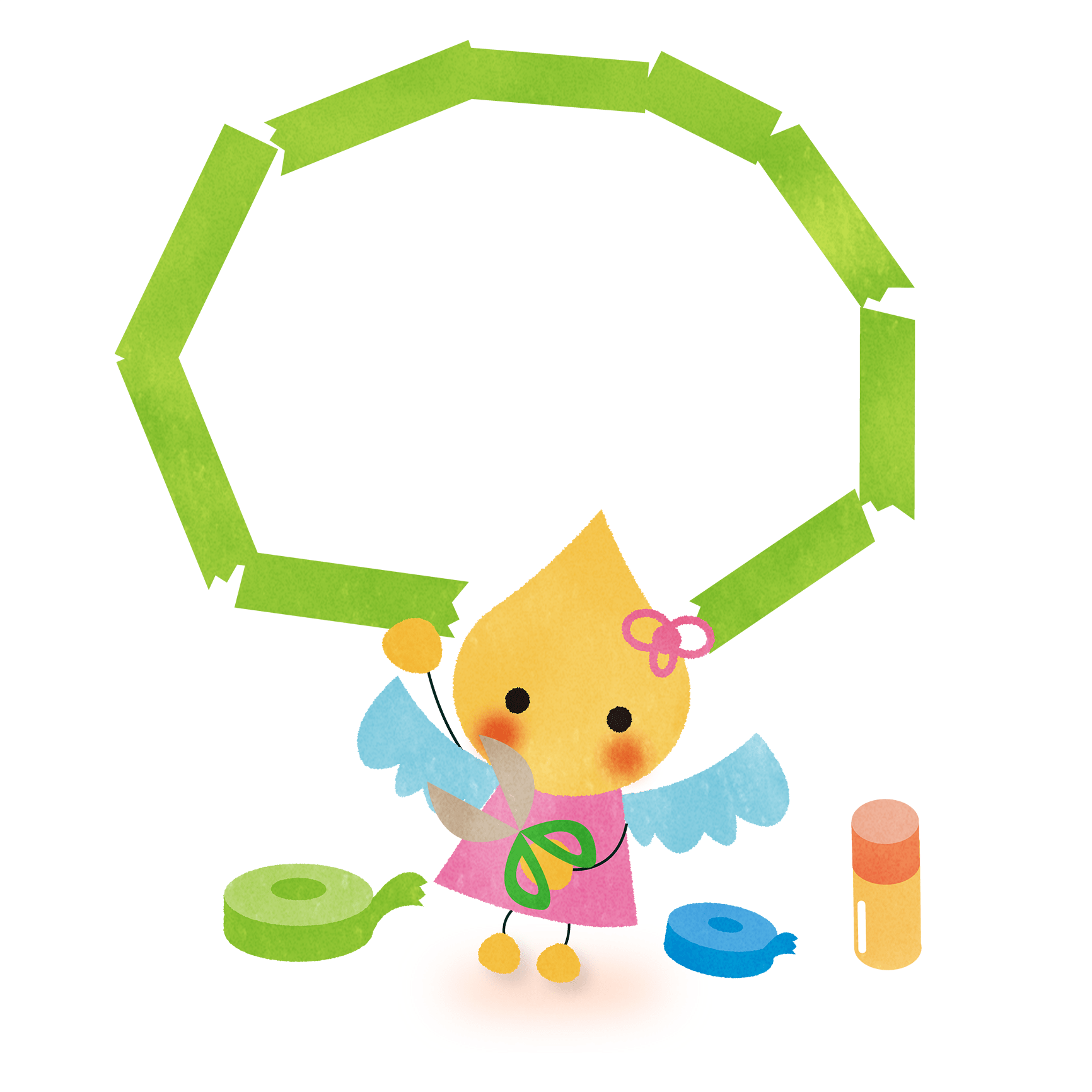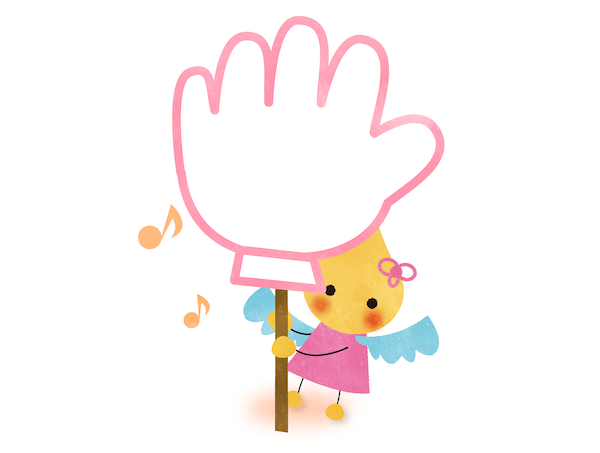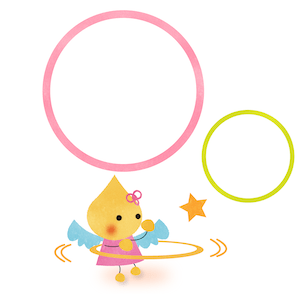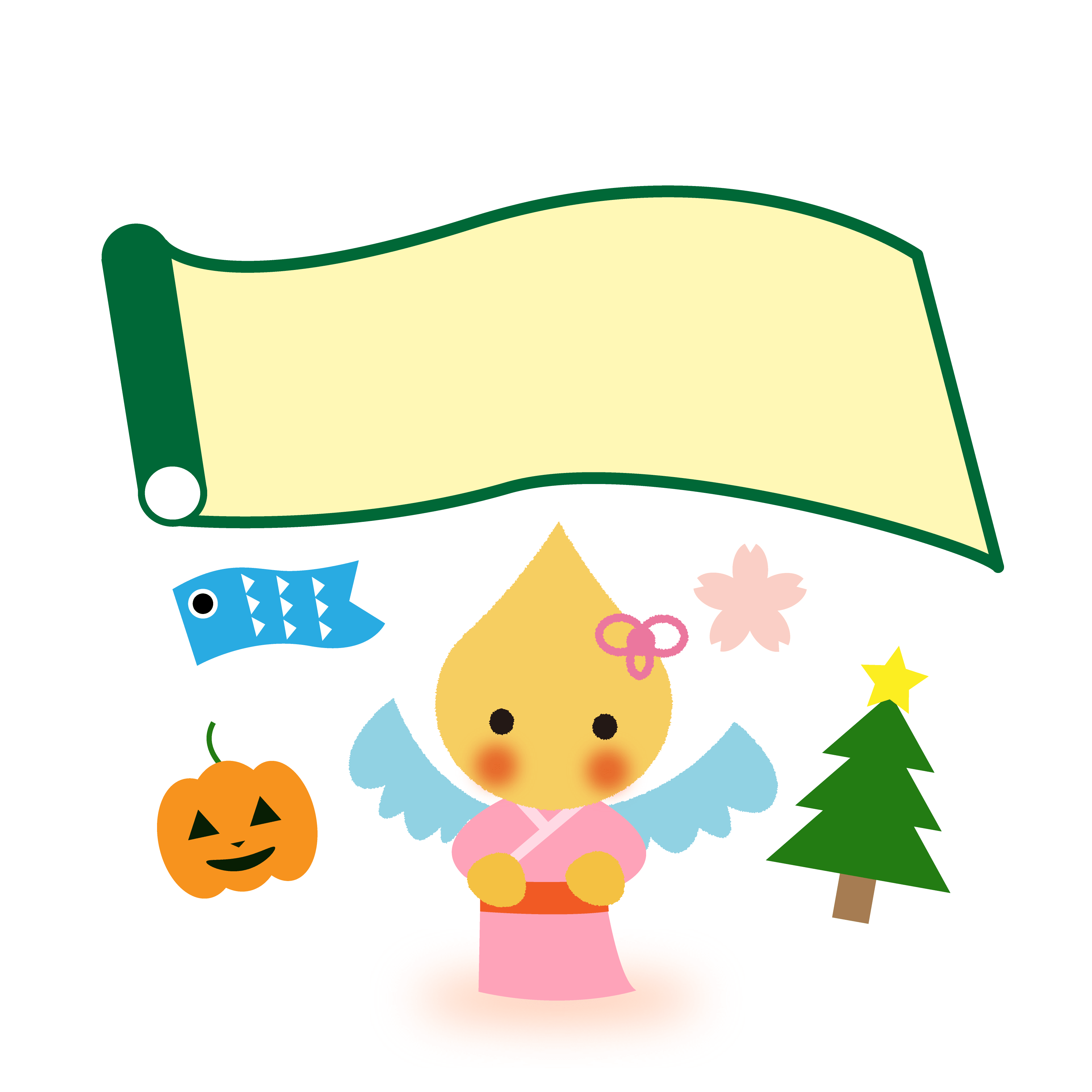もくじ
月案de動画
今月の保育のポイント
- 生活習慣を見ても、出来る出来ないの差がくっきりと表れ、発達もでこぼこな印象を受ける。手伝ってあげようとするのがおせっかいになってしまったり、一方で保育者にべったりと甘える子どもも。多様な姿をここで把握し、クラス全体としてどう運営していくかを今一度考えても良い。
- 友達と共有する、社会事象が分かってくる頃。正月の文化について鏡餅をかざってみたり、七草がゆをしてみたりし、文化的な楽しみを伝えていくと子ども達も文化の雰囲気を嗜むように楽しめる。
- 仲の良い友達と共有し、楽しめる時期ではあるが、一方で人の気持ちや状況を理解することはまだ難しい面もあるので、イメージを保育士が仲立ちして共有して援助しながら楽しむ。
月のねらい
- いろんな遊びや活動を通して友達や異年齢児と触れ合い、楽しく遊ぶ。
- 霜柱や雪などの冬の自然に触れ、興味や関心を持つ。
- 衣服の着脱や排泄など生活に必要な活動を自ら行おうとする。
- 自分の気持ちを相手に受け止めてもらう喜びを感じる。
ほいくのおまもりプラス
週のねらい
その1
- 1週目:生活リズムを整え、元気いっぱい遊ぶ(養護)
- 2週目:お正月遊びに興味を持ち、保育者や友達と楽しむ(教育)
- 3週目:ごっこ遊びなどを通して自分なりのイメージを持って遊ぶ(教育)
- 4週目:遊びの中で保育者や友達と言葉でやりとりする楽しさを味わう(教育)
その2
- 1週目:お正月の雰囲気を保育者や友達と一緒に楽しむ(教育)
- 2週目:友達や保育者との関わりの中で自分の思いを知らせようとする(教育)
- 3週目:日本の伝統的な遊びを楽しむ(教育)
- 4週目:感染症に気をつけて、寒い冬を元気に健康に過ごせるようにする(養護)
ほいくのおまもりプラス
前月末の子どもの姿
養護(生活)
- 生活の流れが分かり、自分でできることは自ら行おうとする姿が見られる子もいる。
💡
自分でできる子を「すごいね!」と褒めることで、周りの子もその時やる気になっていきます。しない子に焦点よりも、する子に焦点を当ててみましょう。 - 食事や排泄、着替えなどがかなり自立してくる一方で、遊びに夢中になって排泄が間に合わなくなってしまったり着替えが遅れてしまったりすることがある。
- 自分の気持ちや思いを言葉で表現しようとするが、うまく伝えられず友達とトラブルになってしまうことがある。
💡
まだ自分の気持ちさえも分からない時もあります。それに気づくには他者とぶつかって獲得していく必要があるので、あえての見守りも大切です。 - スプーンやフォークの正しい持ち方を覚え、きちんと使おうとする。
教育(遊び)
- 木の実や石、ままごとの道具などを使い、イメージを膨らませながら遊んでいる。
💡
イメージを膨らませて、人とつながる。人とつながる力は想像の世界の豊かさから生まれます。 - 保育者や友達とやりとりを楽しみながら遊び込む姿がある。
- 寒さに負けず、戸外でも思いっきり身体を動かすことを楽しんでいる。
- はさみやペンなどの道具の使い方を知り、正しく使おうとする。
- 月の歌や誕生会の歌など日々親しんでいる曲のリズムを覚え、楽しく活動に参加している。
ほいくのおまもりプラス
活動内容(五領域対応)
養護(生活)
- 自分の気持ちを言葉で表現しようとし、気持ちを受け止めてもらう喜びを感じる。(言葉・人間関係)
💡
気持ちを受け止めてもらった喜びが人の気持ちを受け止めるもとになります。受容が大事なのはその理由です。 - 着替えや食事の準備など生活の流れを覚え、自分で行う。(健康)
- 寒さに負けず、戸外でも元気いっぱい遊ぶ。(健康)
- 異年齢児と関わる機会を通して、優しくしてもらったり大きくなることへの憧れを持ったりする。(人間関係)
💡
自分より少し大きな人の存在は身近な憧れの対象になりやすいです。他者と自分の区別がつき始めた3歳児には良い刺激です。 - 久しぶりの登園で園生活を思い出しながら、朝シールを貼ったり、園での約束を守って生活する。(健康・人間関係)
- 改めて誕生日の意味を知り、友達を祝う気持ちをもって誕生会に参加する。(人間関係・言葉)
- 対立する思いを出し合いながら、他者と自分は違っていることを徐々に知る経験を積む。(人間関係)
ほいくのおまもりプラス
教育(遊び)
- 活動や遊びの中で友達と関わりを持ち、一緒に遊ぶ楽しさを味わう。(人間関係)
- 落ち葉や氷など自然にあるものを使って、自分なりにイメージを膨らませながら遊ぶことを楽しむ。(環境・表現)
💡
氷の中に落ち葉がはいっている等の光景にテンションがあがります。仕掛けておくと面白いでしょう。 - 冬ならではの自然に触れ、落ち葉のパリパリした感触や氷の冷たさなどに興味を持つ。(環境・表現)
- 歌や曲に合わせて友達と一緒に身体を動かし、身体を使って表現する楽しさを味わう。(表現)
💡
恥ずかしさなく自由に表現できる3歳児。その表現の自由さを発揮できるように、自由に踊ることも楽しいですよ。 - 造形遊びを通してクレヨンやペンなどのさまざまな道具に親しむ。(環境)
- お正月遊びを通して、日本の伝統的な遊びを知る。(環境)
- 思いを言葉で伝え、友達の気持ちを受け入れ、誘い合って遊ぶ。(人間関係・言葉)
- イメージを膨らませながら、気の合う友達と遊びを広げる。(人間関係・表現)
- 一つの遊びや好きなことに集中して取り組み、自分が納得し、自分が1つの遊びをつくる経験をする。(環境・表現)
ほいくのおまもりプラス
環境構成と援助
養護(生活)
- 排泄や食事の準備、片付けなど、少しずつ見通しを持って自ら行動できるよう、声掛けを工夫していく。
💡
「次は~をする」声掛けは必ず終わってから次の行動を話すようにしましょう。何をするか分からない子がでないような配慮を心がけましょう。 - 子どもの思いを引き出し、時には子どもの気持ちを代弁しながら友達との関わりに仲立ちをし、思いを伝え合う経験ができるように援助する。
💡
自分の本当の思いを問いかけながらゆっくり話すことが必要です。時間が無い中であれば、すぐの解決を目指さず子どもに考える時間を与えましょう。 - 身体を動かすと温かくなることや冬ならではの楽しい遊びを提案し、寒さに負けずに思いっきり遊び込めるようにする。
- 異年齢児とも関わって遊べるようにコーナーを作ることで、大きくなることへの期待を持ったり優しくしてもらう経験ができるようにする。
- 園生活に慣れ雑になってしまう子や、逆に久しぶりの園生活に慣れない子に合わせ、一緒に用意をしたり、用意するものが分かるように並べる等の援助を行う。
- 年齢が下の子ども、上の子どもと比較しながら大きくなる、成長することの意味や素晴らしさを「おめでとう」の言葉と共に伝えていく。
- 子どもたちの意見のぶつかり合いを認め、ぶつからないようにするではなく、ぶつかった後の対応を伝えていく。場合によってはしばらく間を置いて、どちらの子も快適に過ごせるように順番を交代するなどの提案を行う。
ほいくのおまもりプラス
教育(遊び)
- なりきることで身体や言葉を使って表現する楽しさを存分に味わえるよう、一緒にやりとりや雰囲気を楽しみ、遊びに寄り添うようにする。
💡
声かけでも何でも、子どもの世界に入ることは非常に大切です。子ども目線で物事を考え、援助ができるからです。 - 体操(ダンス)や歌の選曲の際には子どもが親しみやすい曲を選び、子どもが身体を動かしたくなるよう保育者自身も楽しんで踊ったり歌ったりする。
💡
子どもに何曲か聴かせて、1番食いつきの良いものに決めても良いでしょう。 - 活動の中でクレヨンやはさみなど、さまざまな道具に触れる機会を設けるとともに、使い方や危険な使い方の説明を繰り返し伝える。
- 友達と遊ぶ楽しさを味わえるよう、必要に応じて仲立ちや声掛けを行なうようにする。
- お正月遊びの際には伝統ある遊びであることを子どもに分かるように伝え、興味が持てるように遊びを進める。
- 言葉がなかなか出ない子どもの気持ちを少し代弁したり、言葉が出る故に沢山相手に要求してしまう子に待ってもらうなど、子ども同士のやりとりが進むように援助を行う。また、言えない表現できない悔しさを、心が満たされるようにしっかり受け止める。
- 子ども同士のイメージに入っていくように、保育者も遊びを盛り上げる。子どもが表現しきって満足できることを目指す。
- 時間を多少過ぎても、やりたい子にはしばらくやれるような環境を用意し、時間のゆとりと周りへの理解を得ながら、子どもの表現を保障する。
ほいくのおまもりプラス
健康、安全面で配慮すべき事項
- 子どもの様子や体調をよく観察し、少しでもいつもと違った様子が見られた場合はすぐに対応する。
- 感染症が出た場合には他職員と連携を取り合い、迅速に正しく対応できるように準備をしておく。
- 暖房などで部屋を必要以上に温め過ぎないよう、子どもの目線に立ってその都度室内の温度調節を行うようにする。
💡
少し肌寒いぐらいが適切と言われています。子どもは体温調節機能が未熟なので、温めすぎると暑くなってしまいます。 - 鳥肌が立っていたり汗をかいていたりする子どもには声をかけ、衣類による体温調節ができることに気付けるよう援助する。
ほいくのおまもりプラス
今月の製作・歌・絵本・手遊び・室内室外遊び
製作
- 簡単紙皿ゆきだるま
- 幼児向けししまい
- 段ボール羽子板製作
この他、【冬の自然】や、【来月の行事】の製作を『ダンボール、紙粘土、毛糸、紙皿』等、色々な素材を使ってご紹介!
歌
- ゆき
- ゆきのこぼうず
- どこでねるの
絵本
- おもちのきもち
- だるまちゃんとてんぐちゃん
- ねたあとゆうえんち
手遊び
- 大きくなったら何になる
- おにのパンツ
- せんせいとおともだち
室内室外遊び
- 転がしドッジボール
- ねことねずみ
- 画用紙で簡単凧揚げ
行事
- お餅つき
- 誕生会
- 避難訓練
- 元日(1月1日)
- 書き初め(1月2日)
- 人日の節句(1月7日)
- 鏡開き(1月11日)
- 成人の日(1月第2月曜日)
食育
- お正月にちなんだ行事や給食を通して様々な食材に興味を持ち、苦手なものも食べてみようとする。
- お餅つきではお米の形が変わる過程を見て学ぶとともに、食感や感触を楽しむ。
- スプーンやフォークの持ち方を覚え、正しく使おうとする。
- 友達や保育者と会話をしがら楽しい雰囲気の中で食事をする。
ほいくのおまもりプラス
地域と家庭との連携
- 園だよりでもちつきの日程について知らせ、準備物や保護者の方にも参加していただくなど協力を依頼する。
- 寒い季節を元気に乗り切るための情報を掲示し、体調管理に気をつけてもらえるようにする。
- 子どもの体調の変化があった場合には、些細な変化でもしっかりと家庭に伝達するようにし、いつでも連携がとれるようにする。
自己評価
- 生活の流れが分かり、子どもが自ら排泄や着替えを行うことができたか。
- お正月ならではの料理や食材に触れ、さまざまな食べ物に興味をもてたか。
- 気持ちを自分なりの言葉で表現し、保育者や友達に受け止めてもらう喜びを感じることができたか。
- 道具や自然にあるものを使って、遊びのイメージを膨らませながら遊ぶことを思いっきり楽しむことができたか。
- 遊びや活動の中で保育者や友達と言葉でやりとりすることを楽しんでいたか。
- 異年齢児と関わる機会を設けることができたか。
ほいくのおまもりプラス
↓その他の保育ネタ↓