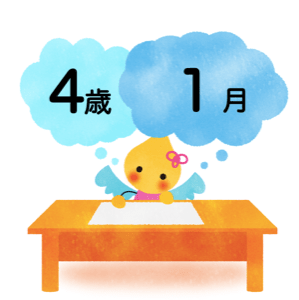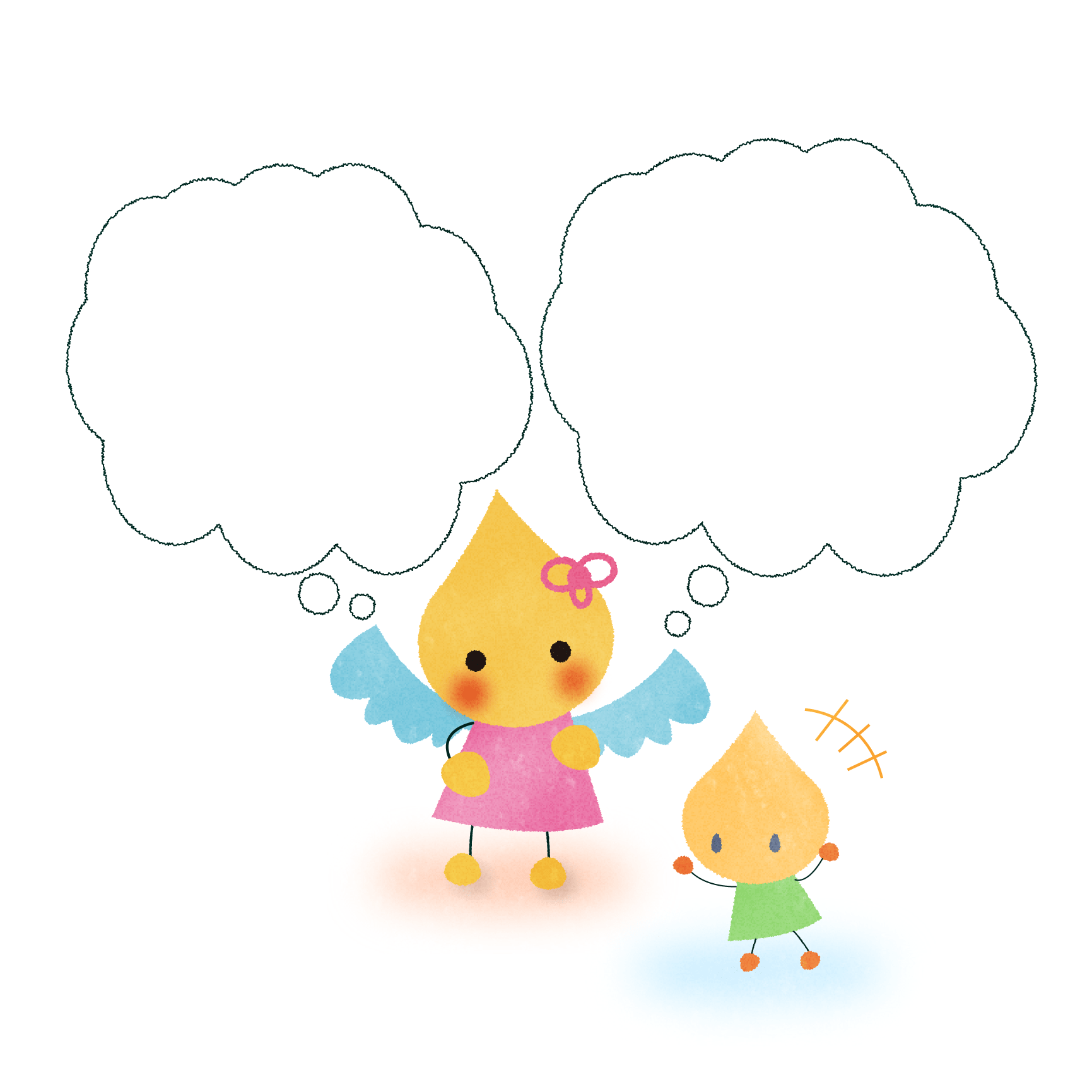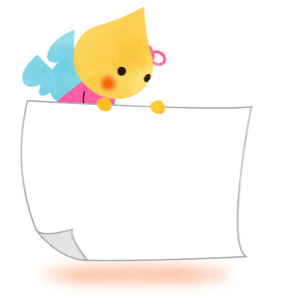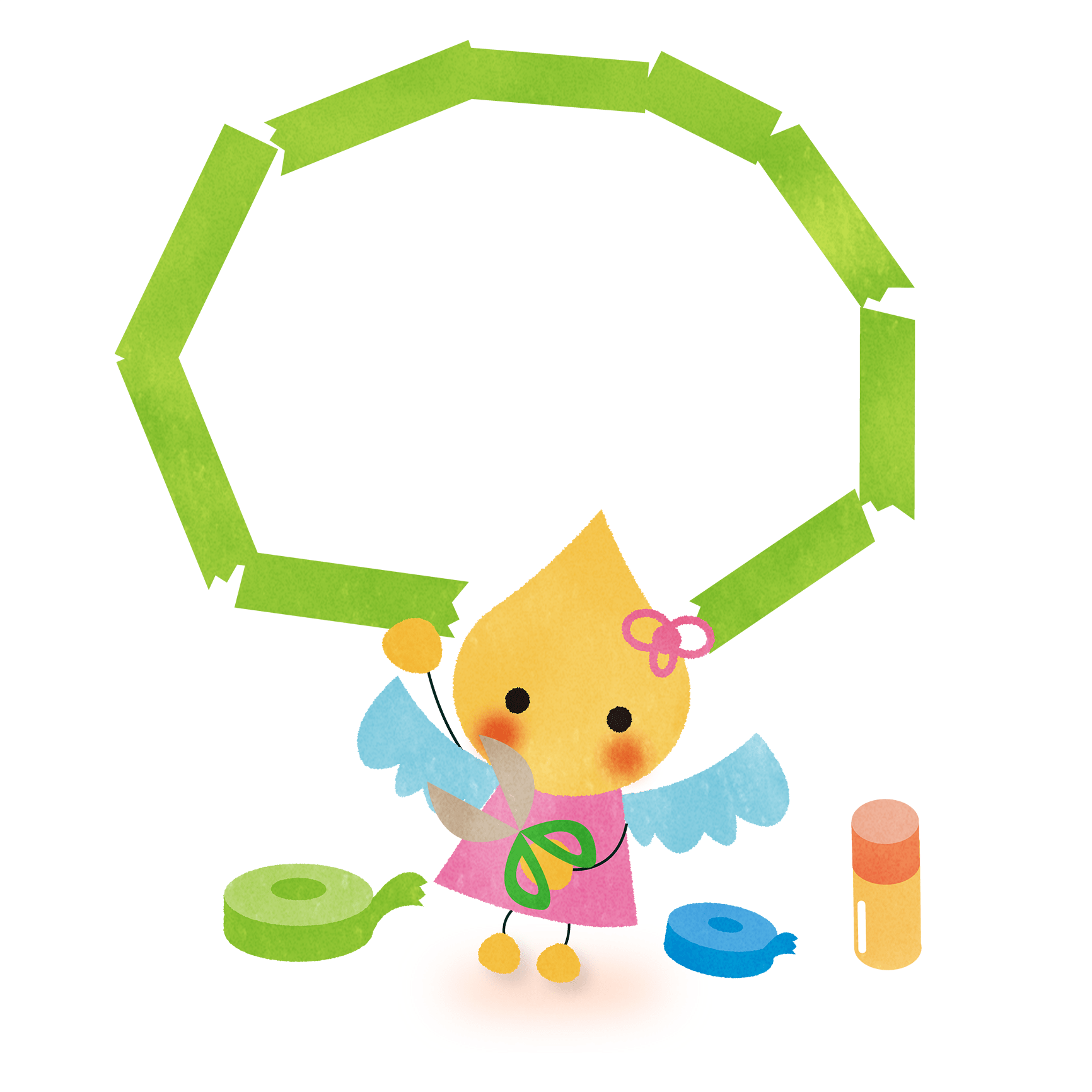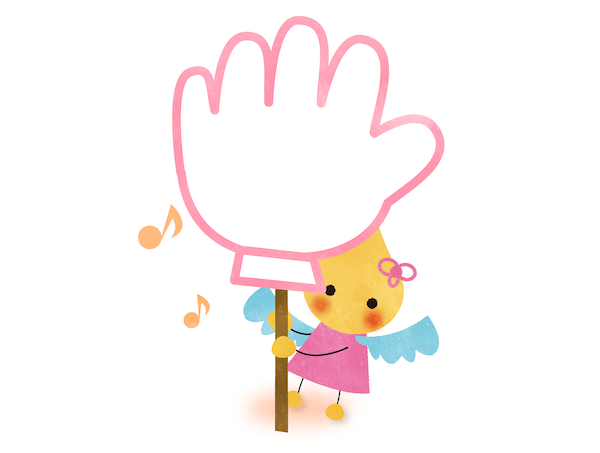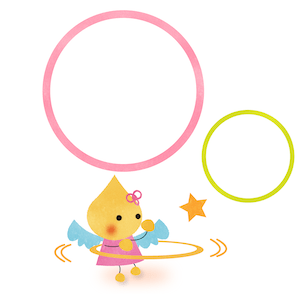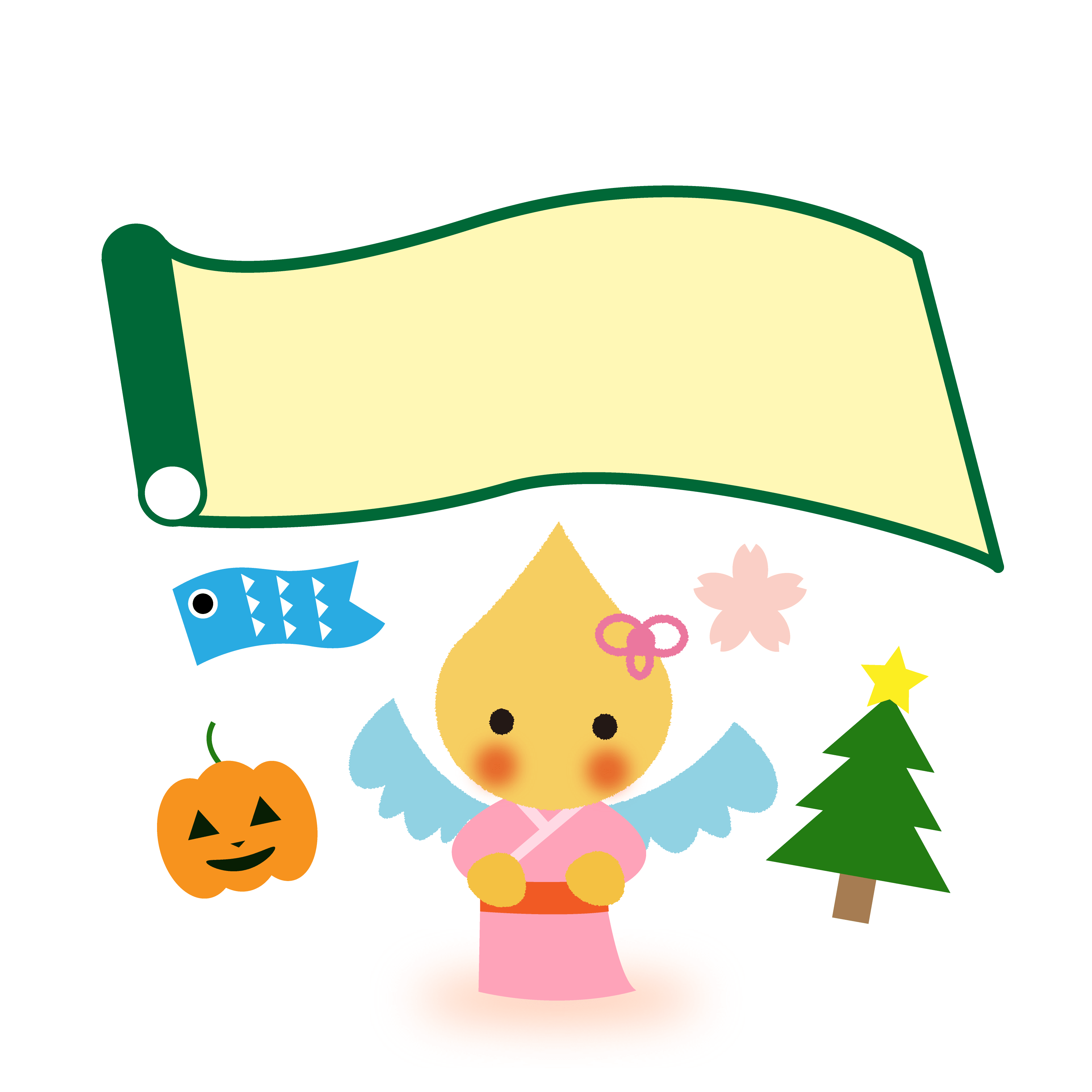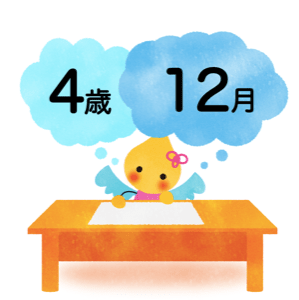
もくじ
月案de動画
今月の保育のポイント
- 落ち葉の山や木々を遊びの場に用意しておくと、子ども自身が気づいて崩したりおままごとに使ったりするので、そっと環境を用意しておくと良い。あえて保育者が「●〇あったよ」と知らせず、子どもの気づきと遊びへの発想力を見守る。
- 人との関わりは子どもによって大きな差が生まれてくる時期。他人の気持ちを考えられる子どももいれば、自分のやりたいことしか見えない子どももまだいる。他者の気持ちを考えて譲るなどの行動した子どもをしっかり認めて、まだ自分のことしか見えない子どもについても、叱らず代弁しながら手助けすると良い。また、この時期の子どもは自分の話をとにかく聞いてほしい時期。話をしっかり聞いてもらった経験は、他者の話を聞こうとする土台になるため温かく保育者が受け止めて聞くことが重要。
- 当番や生活においての簡単な仕事を分担して行うことで、子どもたちの責任感や協力する心が育っていくので、当番活動を子ども達と相談しながら行っていくと良い。
月のねらい
- 生活の中で必要なことや季節の変化などに気づき、健康に過ごせるようにする
- 仲の良い友達と思いきって体を動かして遊ぶ
- 遊びの中でイメージを共有しながら遊ぶ楽しさを味わう
- ルールのある遊びを通して、友達と関わることを楽しむ
- 見たことや聞いたこと、感じたことを自分なりに表現し、楽しむ
ほいくのおまもりプラス
週のねらい
その1
- 1週目:冬の支度を自立しながら、元気に戸外で楽しむ(教育)
- 2週目:クリスマス会の練習を通して、全員で同じ楽しさを共有する(教育)
- 3週目:クリスマス会やもちつきを通して、季節を味わい期待して発表に臨む(教育)
- 4週目:年末に向け、1年の終わりを自覚し健康に過ごす(教育)
その2
- 1週目:寒さや活動に応じて保健的な環境に留意して健康的に過ごせるようにする(養護)
- 2週目:感染症や予防についてわかりやすく伝え、積極的に予防をするように促す(養護)
- 3週目:友達と共有のことに取り組み、ともに活動することを楽しむ(教育)
- 4週目:見たことや感じたことをさまざまな方法で表現する楽しさを味わう(教育)
ほいくのおまもりプラス
前月末の子どもの姿
養護(生活)
- 生活の流れや当番活動など、進んでしようとしている。
💡
意欲が出てきたら「やってはいけない」とされている大人の手伝いもしようとします。その時ぐらいに当番のやることを増やす頃です。 - 保育者や友達との会話を楽しみ、自分の考えを伝えている。
- 手洗い、衣服の調節などを自分の状況に合わせて自ら行おうとしている。
教育(遊び)
- 年長児の遊びを見て、自分も真似をしてやってみようとしている。
- 戸外での遊びでは、身近な自然現象に興味を持ち、繰り返し取り組んだり思い切り体を動かしたりしている。
- 様々な素材を組み合わせて作ったり、作った物を使って遊ぶことを楽しんでいる。
- いろいろな友達と関わりながら、簡単なルールのある遊びを楽しんでいる。
💡
簡単なルールの見極め、いくつのルールならできるか?子どもの様子から探っておきましょう。 - 友達と互いに発想を出し合いながら、一緒に遊んでいる。
ほいくのおまもりプラス
活動内容(五領域対応)
養護(生活)
- 冬の生活を理解し、衣服の調節、手洗いなどの生活を自ら進んで行う。(健康)
- 当番活動の手順が分かり、友達と協力しながら行う。(健康・人間関係)
💡
協力して用意する環境(机を運ぶなど)を作っておきましょう。 - 大掃除に取り組み、自分たちが使う物を綺麗にする心地良さを感じる。(健康・環境)
- 自ら自分の生活空間の整備をし、その行為で人や自分のためになることや、綺麗になることの達成感を味わう。(人間関係・環境)
- 鼻をかむ、口をおさえてくしゃみをする等、自らの清潔を意識して気づき行動する。(健康・人間関係)
- 自分の持ち物を整理したり、自分たちが使う保育室や廊下、階段などを綺麗にする。(健康・環境)
ほいくのおまもりプラス
教育(遊び)
- 自分や友達との想像から、必要な素材を集めて作ることを楽しみ、作ったもので遊ぶ経験を積む。(表現・人間関係)
- 作った物を使って遊んだりすることを楽しむ。(表現)
- 友達との関わりでは、自分の思いを言葉で伝え、相手の話を聞いて気持ちや考えを理解しようとする。(人間関係・言葉)
- 鬼ごっこなどの簡単なルールのある遊びを通し、様々な友達と関わりながら体を十分に動かして活き活きと遊ぶ。(人間関係・健康)
💡
寒い時こそ運動遊びです。元気に走って自分の身体が温かくなる経験を。 - 風の冷たさや葉が落ちた木々など、身近な冬の自然に触れ気づく。(環境)
- 友達と歌、踊り、楽器を通して他者と表現する楽しさを味わう。(表現)
- 様々な素材や身近な自然物を使って、リースやクリスマスの飾りを作って飾る楽しさを味わう。(表現)
💡
まつぼっくり1つでも飾りはつくれます。まつぼっくりに小さな飾りを貼り付けたり、色を塗ったり。 - 異年齢児と一緒に過ごし、活動を通して年下へのかかわりを深める。(人間関係)
- 自然物を収集したり、変化を感じて冬の自然を楽しむ。(環境)
- 絵画やルールのある遊び等、友達と1つのことに共同で取り組み、友達と一緒に協力したり、共感して活動することの楽しさを味わう。(人間関係)
ほいくのおまもりプラス
環境構成と援助
養護(生活)
- 手洗いうがい、衣服の調節が子ども自身でしやすいように環境を整える。
- 会食を通して自分の食べられる量や、食事マナーに気づけるようにする。
💡
自分が食べられるかな?と思う量を普段から意識できることが大事です。 - 大掃除の必要性に気づけるよう、綺麗な空間での使いやすさ気持ち良さを実感できる導入を行う。
- 大掃除や普段の生活で机を運んだり、掃除をする経験を入れ、「綺麗になったよ」「自分たちでできたね」等の認める声掛けをセットで行い、子どもが気持ちよく自分の場所を作っていけるようにする。
- ティッシュとゴミ箱を使いやすい位置に設置したり、くしゃみのマナーを伝えながら、一人ひとりに丁寧に対応する。
- 必要な雑巾、バケツや水の温度、ほうき等、子どもが使うものとして使いやすい道具であるかを考えて用意する。
ほいくのおまもりプラス
教育(遊び)
- 遊びの場を見直し、遊具や用具の点検を行う。
- 友達と一緒に相談したり、自分達で遊びの場を作ろうとしたりしている姿を認める。
💡
子どもたちだけで作り上げることは難しい4歳児ですが、自分たちで作る経験をすることが大事な時期です。成功、失敗ではなく経験を。 - 子どもが自己発揮しやすいように、ゆったりとした空間をつくる。
💡
保育者も環境、空間のうちです。保育者の焦りは子供につたわるので、おおらかな対応を今一度心がけましょう。 - やりたい遊びのイメージを実現していくために、材料や道具の使い方などのアイディアを必要に応じて出す。
- 1日の中で戸外に出て積極的に遊べるような機械をつくる。鬼ごっこなどは、遊びの拠点となる場所を決めておき、同じ場所で同じ遊びを繰り返し楽しめるようにする。
- 簡単なルールがあることで、普段の人間関係に捉われずに仲間入りできることを意識し、友達との遊びの輪が広がっていくようにする。
- 子ども同士のやりとりで困っていないかを把握し、時に代弁するなどの援助を行う。
💡
子どもの葛藤を認めてあげるのは何も解決に向けた話だけではありません。落ち込む子どもに「そういうことあるよね」と共感するだけで立ち上がることもあります。 - 自分の思いや考えが伝えられる機会を多くつくる。
- 冬の自然に十分に触れられるよう、図鑑や冬眠の様子など分かる図鑑を用意しておく。
💡
木の中や隠れた場所に冬眠している虫。実際の様子は図鑑と違うこともあります。発見の意味でも図鑑の存在は大きいと言えるでしょう。 - 楽器を使った演奏を楽しめるよう、打楽器を準備しておき、みんなで歌い演奏する機会をつくる。
- みんなで踊りながら、リズムに乗って体を動かす楽しさを味わえる機会をつくる。
- リース作りや、飾り作りなどを通して、テーマに沿った造形遊びの楽しさを知る。
- 師走の社会事象に目を向け、正月のおせちについての絵本を読んだり、実際散歩してみたりし興味関心を深める。
💡
おせち、初詣など、正月の意味などが分かる絵本があると良いでしょう。 - 年下の子どもを助けたり、ルール等を教えること、自分よりまだ小さくて弱い存在ということを伝え、子どもが気持ちにやさしさや余裕を持った状態で関われるように伝える。
- 子どもが自然を収集できるように入れ物を用意しておく。「もう葉っぱは散ったね」など、冬が感じられる言葉をかけていく。
- 大きな紙や沢山の材料など、沢山の子どもが関われるように環境を用意する。
ほいくのおまもりプラス
健康、安全面で配慮すべき事項
- 個々の健康、室内外の温度差、換気などに配慮し、流行病の予防、早期発見に努める。
💡
クラスで2,3人出始めたら保護者に「体調の変化にはご注意ください」の呼びかけを - 手洗い、うがいのやり方を伝え、いつでも見られるように掲示しておく。
- 子ども同士の怪我がないよう、子ども個人の出来るところを超えて無茶な動きをしていないかなど見守る。
ほいくのおまもりプラス
今月の製作・歌・絵本・手遊び・室内室外遊び
製作
- さんかくツリー
- クリスマスつるし飾り
- 紙皿サンタ・トナカイさん
この他、【クリスマス、冬の季節】の製作を『牛乳パック、紙皿、わた、塗る、貼る、つなげる等、身近な素材と手法でご紹介!
歌
- そうだったらいいのにな
- こぎつね
- あわてんぼうのサンタクロース
絵本
- おもち!
- くまのこのとしこし
- かさじぞう
手遊び
- 大きくなったら何になる
- おにのパンツ
- せんせいとおともだち
室内室外遊び
- 「新聞紙の足場」レース
- もうじゅうがり
- まつぼっくりパチンコ
行事
- 世界人権デー(12/10)
- 正月事始め(12/13)
- 冬至(12/22頃)
- クリスマス(12/25)
- 大晦日(12/31)
食育
- 自分達でつき、まるめたもちを園外の人達と関わりながら温かい気持ちでいただく。
- 会食の機会を通して、食べる楽しさや食事のマナーなど、広く食事に関心を向けられるようにする。
ほいくのおまもりプラス
地域と家庭との連携
- クリスマス会などの行事で必要なものをお知らせする。
- 風邪やインフルエンザなどの感染情報や予防方法などを掲示し、注意を呼びかける。また、家庭でも手洗いうがいを習慣づくように子どもに知らせてもらえるようお願いする。
- 子どもの体調について、家庭と密に連絡を取り合う。
自己評価
- 子ども同士協力し合って生活できる環境がつくられていたか。
- 子どもの体調に気づき、適切な対処と連携がとれていたか。
- 子どもたちの遊びに発見や気づきがあり、友達同士や保育者と分かち合う姿が認められたか。
ほいくのおまもりプラス
↓その他の保育ネタ↓