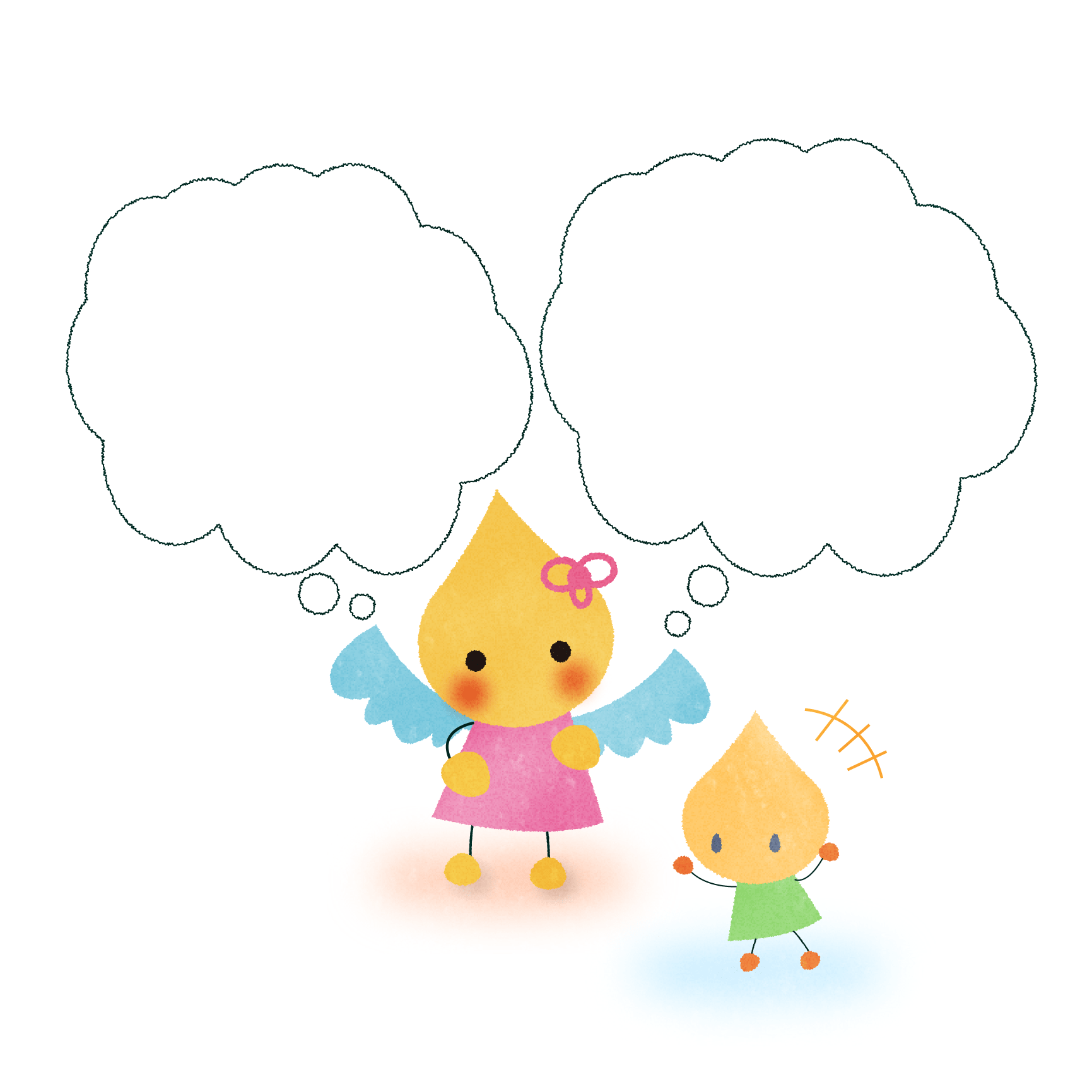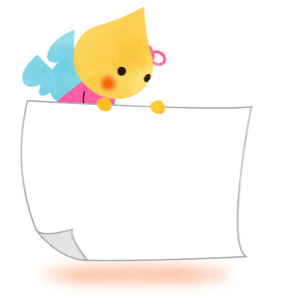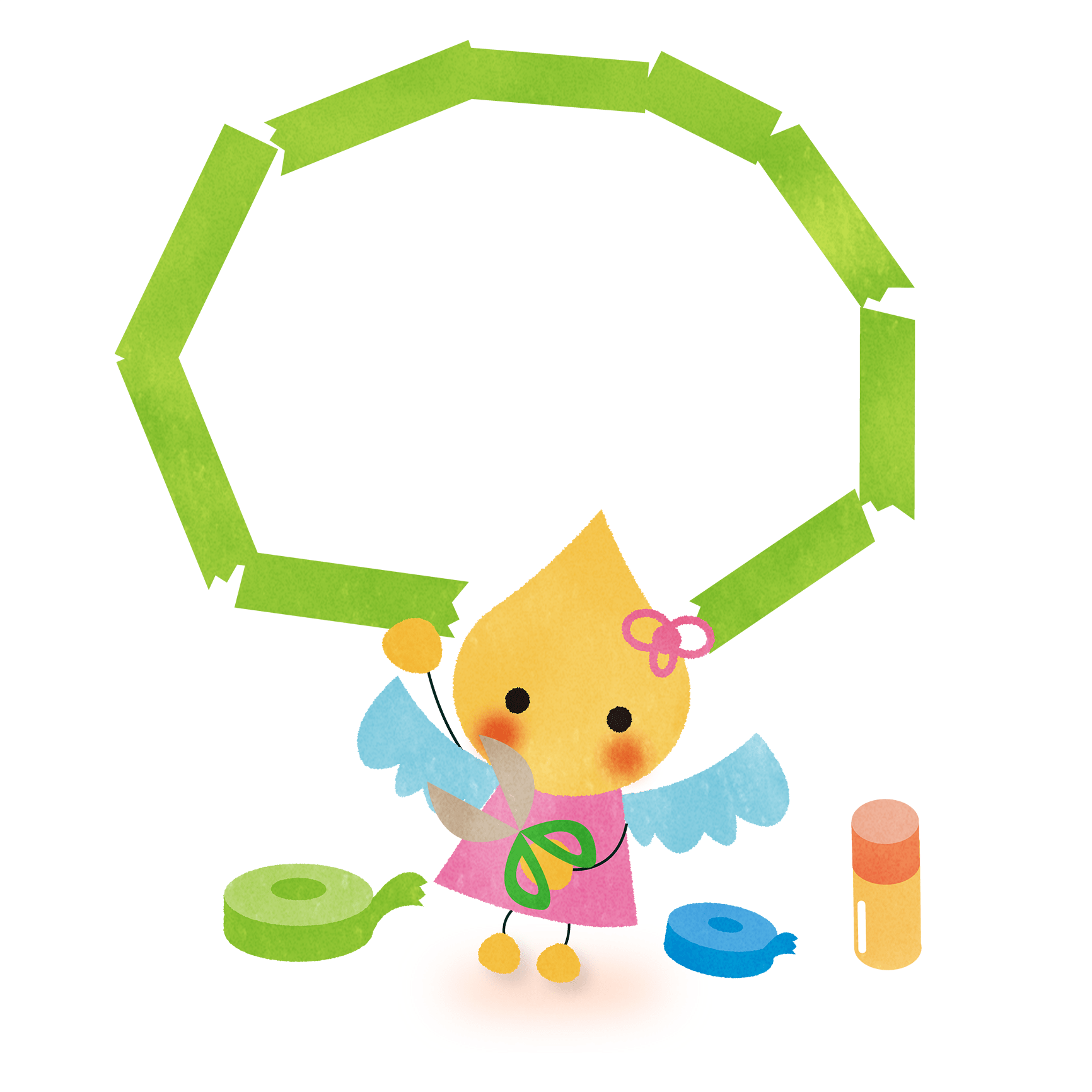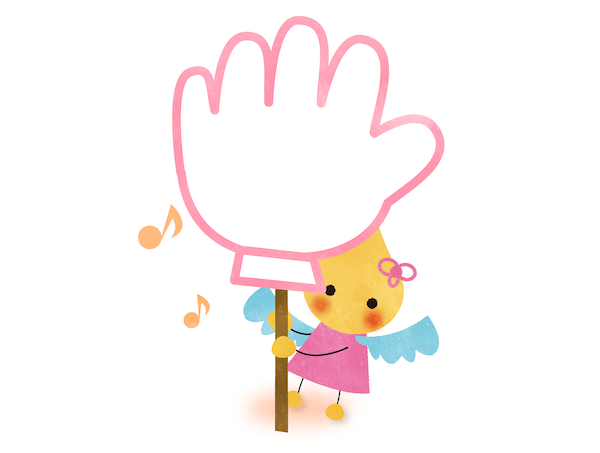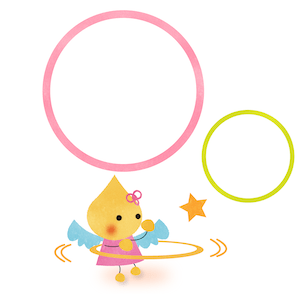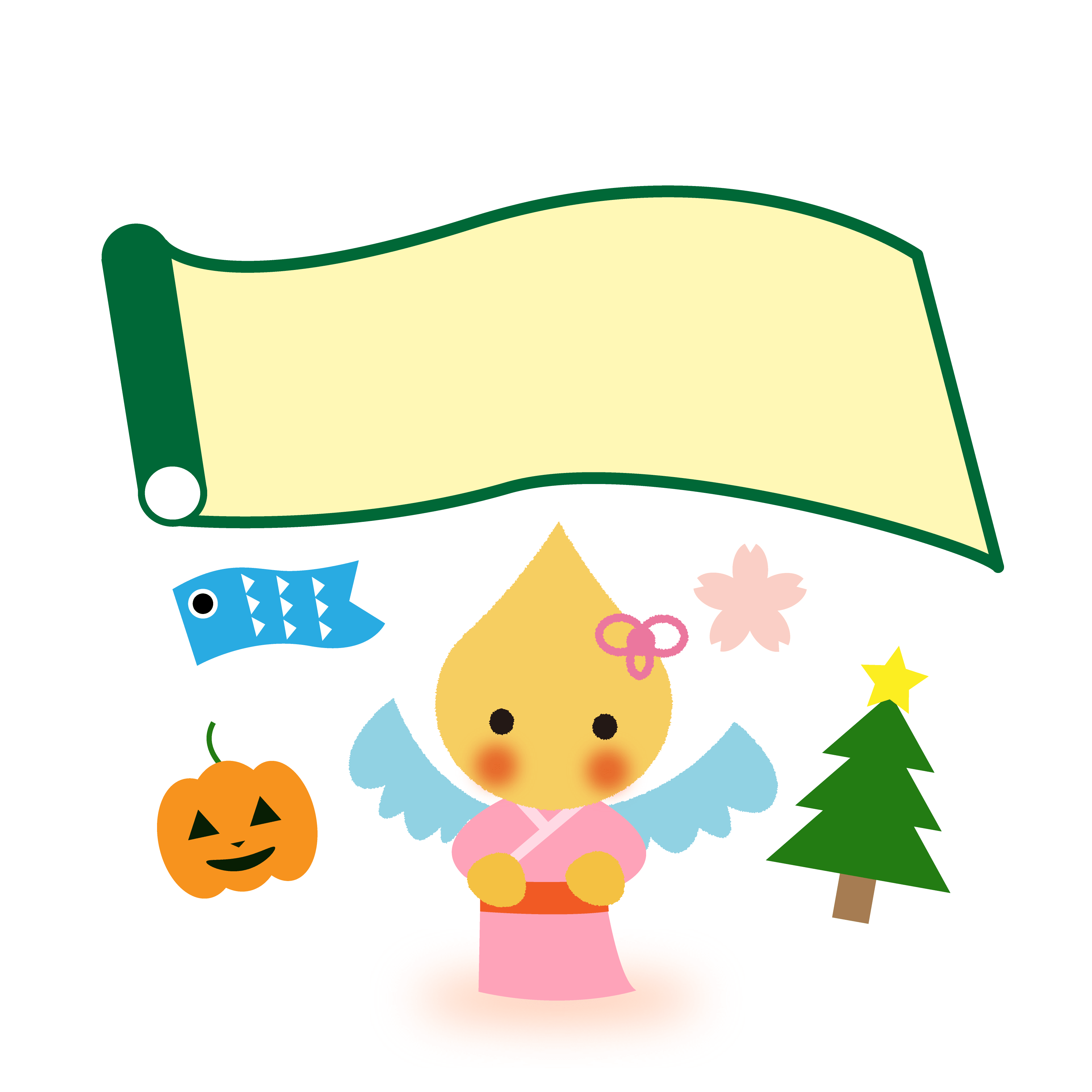もくじ
月案de動画
今月の保育のポイント
- 夏休み明け残暑が厳しい中、家庭のリズムから少しずつ園での生活リズムに慣れるよう、熱中症や疲れに気を付けながら、ゆったりと個々の発達に合わせた援助を行う。
- 子どもが久々の園生活に安心し、楽しい気持ちをもって登園できるよう、1学期に遊んでいた遊具や遊び環境づくりを整える。また、友達や保育者と安心して遊び、生活する楽しさを感じられるよう、保育者は楽しい温かい雰囲気で関わっていく。
- 同じ学年の友達や異年齢児と思い切って遊べることを大切にし、子どもの人と関わる自信へとつなげる。
- 子どもの心に残った思い出や出来事を話す機会を人の話を聞く土台として大切にする。夏休み中の話を子どもから聞き取り、親しんで会話を広げていく。
月のねらい
- 友達や保育者と一緒に遊ぶことを楽しむ。
- 自分のしたい遊びを見つけて、思う存分遊びこむ充実感を味わう。
- 季節の移り変わりに気づき、自然に興味や関心を持つ。
- 経験したことや思ったことを身振りや自分なりの言葉で伝えようとする。
ほいくのおまもりプラス
週のねらい
その1
- 1週目:生活リズムを整え、元気に過ごす(養護)
- 2週目:敬老の日のプレゼントを心込めて製作する(教育)
- 3週目:友達や保育者と一緒に身体を動かすことを楽しむ(教育)
- 4週目:秋の自然に触れ、生き物や植物に関心を持つ(教育)
その2
- 1週目:自分のしたい遊びを見つけて楽しむ (教育)
- 2週目:食器の片付けなど身の回りのことを自分でしようとする (養護)
- 3週目:保育者や友だちと一緒に、いろいろな遊びを楽しむ(教育)
- 4週目:身体を動かしたり表現する楽しさを感じる(教育)
ほいくのおまもりプラス
前月末の子どもの姿
養護(生活)
- 着替えの際には自分で服を畳もうとする子どももいるが、甘えて保育者にお願いしようとする子どももいる。
💡
甘えるときは何かしらの理由があります。家で全部やってもらっている子が今頑張っている途中かもしれませんし、何か不安な気持ちなのかもしれません。 - 喉が乾くと自ら水分補給をしようとする姿も見られるが、遊びに夢中で保育者に声をかけられるまで忘れてしまうこともある。
- 夏祭りでは、他のクラスの友達や年上の友達と関わることができ嬉しそうにしていた。緊張する子どももいたが、関わっているうちに慣れて楽しく過ごしていた。
- 座って食べる、スプーンの持ち方に気を付けるなど食事マナーを守って食べ進められる子どもが増えた。食べこぼしはあるが、自分で後始末をしようとする姿も少しずつ見られるようになってきている。
教育(遊び)
- 泥んこ遊びやプール遊びなど、夏ならではの活動には意欲的に参加する子どもがほとんどであった。顔に水がかかると泣いてしまう子どももいるが、回数を重ねるうちに慣れてきている様子が見られた。
- 運動遊びでは、しゃがむ、ジャンプするなど様々な身体の動かし方を取り入れながら思いっきり身体を動かすことを楽しんでいた。
- 虫を見つけると喜んで触ったり見たりする子どももいるが、苦手意識のある子どもは、遠くから眺めていることが多かった。友達が触る姿を見て、少しずつ興味が湧いてきている姿が見られる。
💡
何でも虫を触りにいく子がいます。噛む虫で痛さを覚えるぐらいならば良いのですが、毛虫など毒の虫には注意しましょう。 - 家で経験したことや楽しかったことを保育者に伝えようとすることが増えてきた。うまく言葉が出てこないこともあり、身振りなども使いながら一生懸命に伝えようとしている。
- 気の合う友達と一緒に遊ぶことを好み、自分から関わりにいく姿も見られるようになってきている。
ほいくのおまもりプラス
活動内容(5領域対応)
養護(生活)
- 園生活のリズムを思い出し、元気に過ごす。(健康)
- 着替える、服を畳む、などの身の回りのことを自分でする。(健康)
💡
自分で自分のことができ、次の活動にいける気持ち良さを味わうために、今のことが嫌で進まない子にはあえて手を貸すのも1つです。すぐやると良い景色があることを覚えていきます。 - 手洗いうがいをする理由を知り、自ら行おうとする。(健康)
- いつも関わっている気の合う友達だけでなく、いろんな友達と関わる楽しさを味わう。(人間関係)
💡
子どもによって多くの人と関わるのが苦のタイプがいます。そういった子に無理をさせるのではなく、みんな遊びの経験をする程度で大丈夫ですよ。 - 自分の身体について知り、水分補給や身体を休める時間をとる。(健康)
- 身体や服の汚れに気付き、着替えの意味を知りながら行う。(健康)
- 順番やルールを知り、守ろうとする。(人間関係)
ほいくのおまもりプラス
教育(遊び)
- みんなと一緒に身体を動かして遊ぶことを楽しむ。(健康・人間関係)
- 運動会の練習や運動遊びを通して、身体を思いっきり動かす心地よさを味わう。(健康・人間関係)
💡
運動会の練習で気分が高揚することもあります。移動時の接触事故にお気を付けを。 - 草花の種を見つける、色水遊びするなど自然に触れて遊ぶ。(環境)
- 生き物を見つけたり触れたりして、自然に興味を持つ。(環境)
💡
バッタが旺盛になる時期です。バッタは毒も無い捕まえやすい虫ですので、触れ合いにはピッタリですよ。 - 簡単なルールのある遊びを通して、ルールを守りながら遊ぶ大切さや楽しさを知る。(人間関係)
- 敬老の日を知り、心を込めて丁寧に製作をする。(環境・表現)
💡
敬老の日についてはこちらを参考にどうぞ! - 旬の味覚でクッキングをし、季節の食べ物を知る。(健康・環境)
- 楽器に触れ、表現活動を楽しむ。(表現)
- コーナーで自分の好きな遊びを選んで楽しむ。(健康)
ほいくのおまもりプラス
環境構成と援助
養護(生活)
- 休み明けで生活リズムが整わず、元気が出なかったり不機嫌になったりする子どもがいたら、ゆっくりと過ごせる時間を設けながらできる限り心地よく過ごせるように配慮する。
💡
3歳児はまだ思ったより幼い部分があります。時に2歳児にするような対応も必要です。 - 服の畳み方などを改めて子どもたちに伝え、子どもが自分でやってみようと思えるように促していく。
- 手洗いうがいをする際には、改めてなぜ行うのかを子どもたちに知らせ、必要性や大切さを子どもが考えながら行えるようにする。
💡
手洗いの紙芝居などを定期的に見せましょう。紙芝居後、意識が高い状態であろう手洗いの様子を見ながら、支援すべき子を見定めていきましょう。 - 子どもの様子に気を配り、水分補給や体調管理をしっかり行う。子どもに植物に水をあげないと枯れるなど、何かに例えながら伝える。
- 着替えるか着替えないかを子ども自身の様子によって決める。汚れている衣服とそうでない衣服の違いが分かるように話す。
- 順番やルールの必要性について、守らないとどんな気持ちになるかを見せながら子どもに伝える。
ほいくのおまもりプラス
教育(遊び)
- 大勢でできる遊びを知らせ、いろんな友達と関わる機会が持てるようにする。
💡
例え遊びに参加せずとも、見ていることで空気感を味わうなど効果はあるので、参加しないことに悩みすぎなくて大丈夫ですよ。 - 運動会の練習では、無理に子どもに提供しないように注意する。運動遊びで取り入れながら、楽しく進められるように工夫していく。また、苦手意識がある子どもには特に声かけを行いながら意欲が湧くように配慮する。
- 草花を観察したり色水遊びをしたりできるよう、使っていいものや遊ぶ時の約束を決めておく。また、子どもが工夫したり考えたりしながら自由に使えるように、環境を整えておく。
💡
必ず物の奪い合いが始まります。3歳では自己主張が特徴なので、折り合いをつける練習と思って1つ1つ援助していきましょう。 - ルールのある遊びを行う際には、前もって子どもたちにルールを知らせる。また、遊ぶ中でより理解が深まるように遊びながら繰り返しルールを伝えていく。
💡
ルールの知らせ方はできるだけ見てわかるものがおすすめです。大きくホワイトボードでペープサートのように出すなど、動的に分かりやすく説明することが有効です。 - 製作の際には子どもの様子をよく見ながら、怪我や危ない使い方をしないよう必要に応じて声をかけていく。
- 食材に実際触る機会を設けたり、食材に十分に触れる機会を作り、子どもが親しみを持った後でクッキングを行う。
- 細かなリズムまで求めることなく、楽しい雰囲気で行い、積極的に活動に取り入れるようにする。
- 好きな遊びを選べるようにコーナーを充実させる。また、作った物をままごとで遊ぶなど、各コーナーの動線を考えて配置する。
ほいくのおまもりプラス
健康、安全面で配慮すべき事項
- 涼しい日もだんだんと増えてくるが、まだまだ気温が高い日も多い時期。引き続き水分補給や休息を取り入れるよう、こまめに声をかけていく。
- 道具の使い方や遊びのルールなどを再確認し、好きな遊びを存分に楽しめる環境を整える。
ほいくのおまもりプラス
今月の製作・歌・絵本・手遊び・室内室外遊び
製作
- 野菜スタンプできのこ
- 敬老の日ハガキ製作
- 紙コップで作る、秋の動物さん
この他、【秋の行事】や【プレゼント】の製作を『フィルム、ストロー、ボンド、描く、折る、貼る』等、身近な素材と手法でご紹介!
歌
- こおろぎ
- おおきなくりのきのしたで
- つき
絵本
- パパ、お月さまとって!
- あいうえおうた
- ふくろうのそめものや
手遊び
- こんこんクシャン
- おいもころころ
- 3びきのこぶた
室内室外遊び
- ドッジボール(中当て)
- 葉っぱを合わせるゲーム
- トカゲ・カナヘビ・ヤモリの捕まえ方
行事
- 避難訓練
- 誕生会
- 身体測定
- 防災の日(9月1日)
- 救急の日(9月9日)
- 敬老の日(9月21日)
- 秋分の日(9月23日)
- 十五夜(9月25日)
食育
- 秋に旬を迎える食べ物を知り、食材や食事に興味を持つ。
- 食事の際のマナーに気をつけながら、友達や保育者と楽しく食べる。
- 食べこぼしをした際には、自分で拾ったり拭いたりしようとする。
ほいくのおまもりプラス
異年齢保育
この項目はおまもりプラスで公開中!
職員間の連携
この項目はおまもりプラスで公開中!
地域と家庭との連携
- 元気に園生活を送るために、家庭での生活リズムもできるだけ整えてもらえるようお願いする。
- 暑い日が続いて疲れも出やすい日が続くので、水分補給や休息を取り入れて健康に気をつけて過ごしてもらえるよう伝えていく。
- 敬老の日のプレゼントを渡すため、用意してもらうものを事前に知らせていく。
- 防災訓練には家庭の方にも参加してもらえるように、前もって呼びかける。
長時間保育の配慮
この項目はおまもりプラスで公開中!
自己評価
- 生活リズムを整え、元気に過ごすことができたか。
- 着替える、服を畳む、などの身の回りのことを自分でしようとしていたか。
- 手洗いうがいをする理由を知り、自ら行うことができていたか。
- いろんな友達と関わりながら遊ぶことができたか。
- みんなと一緒に楽しく身体を動かすことができていたか。
- 運動遊びを通して身体を思いっきり動かす心地よさを味わえたか。
- 自然のものを遊びに取り入れ、楽しく遊ぶことができたか。
- 生き物に触れたり見つけたりし、自然に興味を持てたか。
- 簡単なルールのある遊びでは、ルールを守りながら楽しく遊べたか。
ほいくのおまもりプラス
↓その他の保育ネタ↓