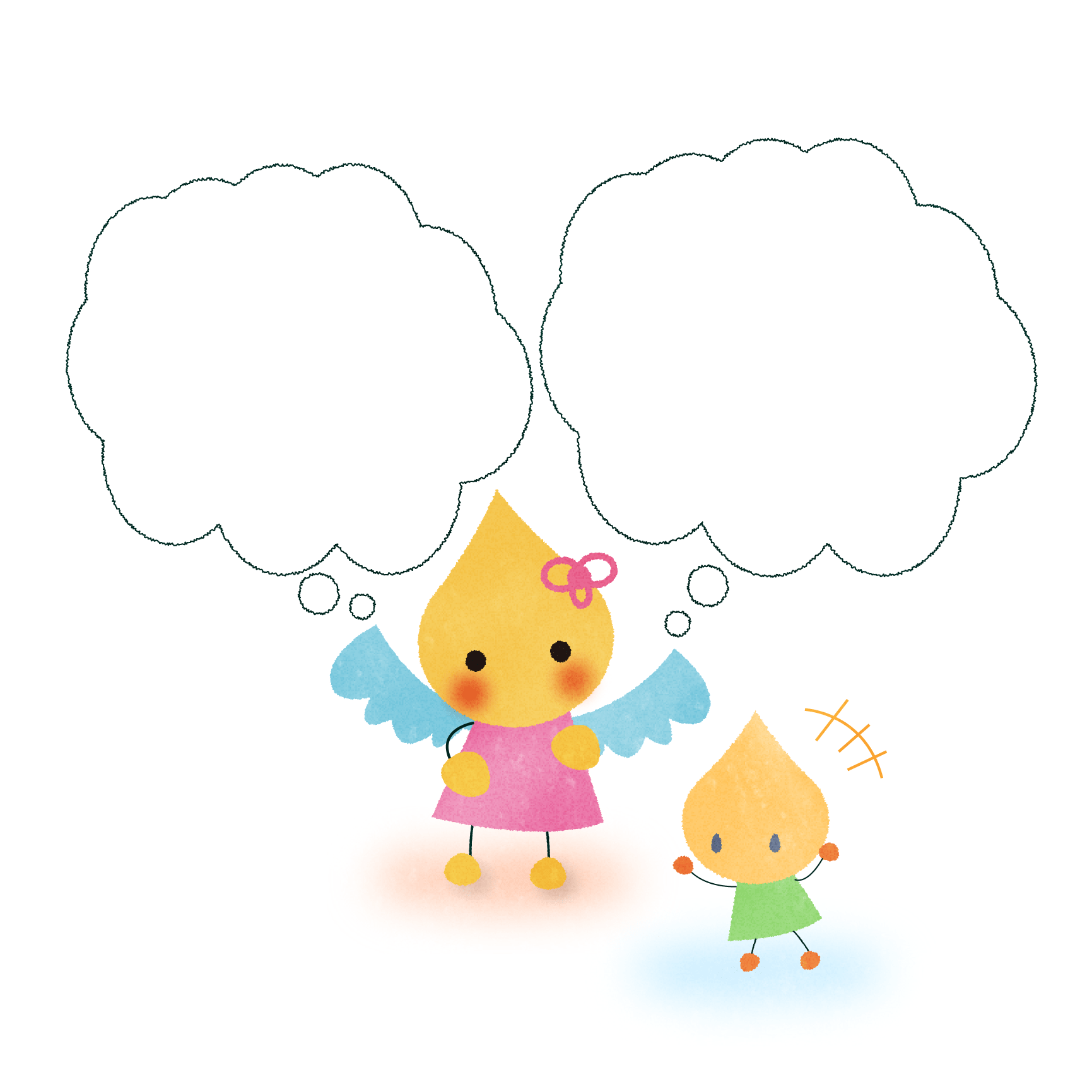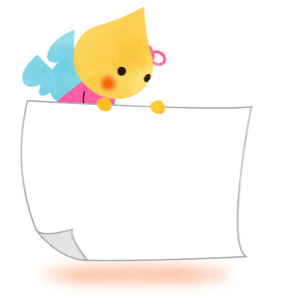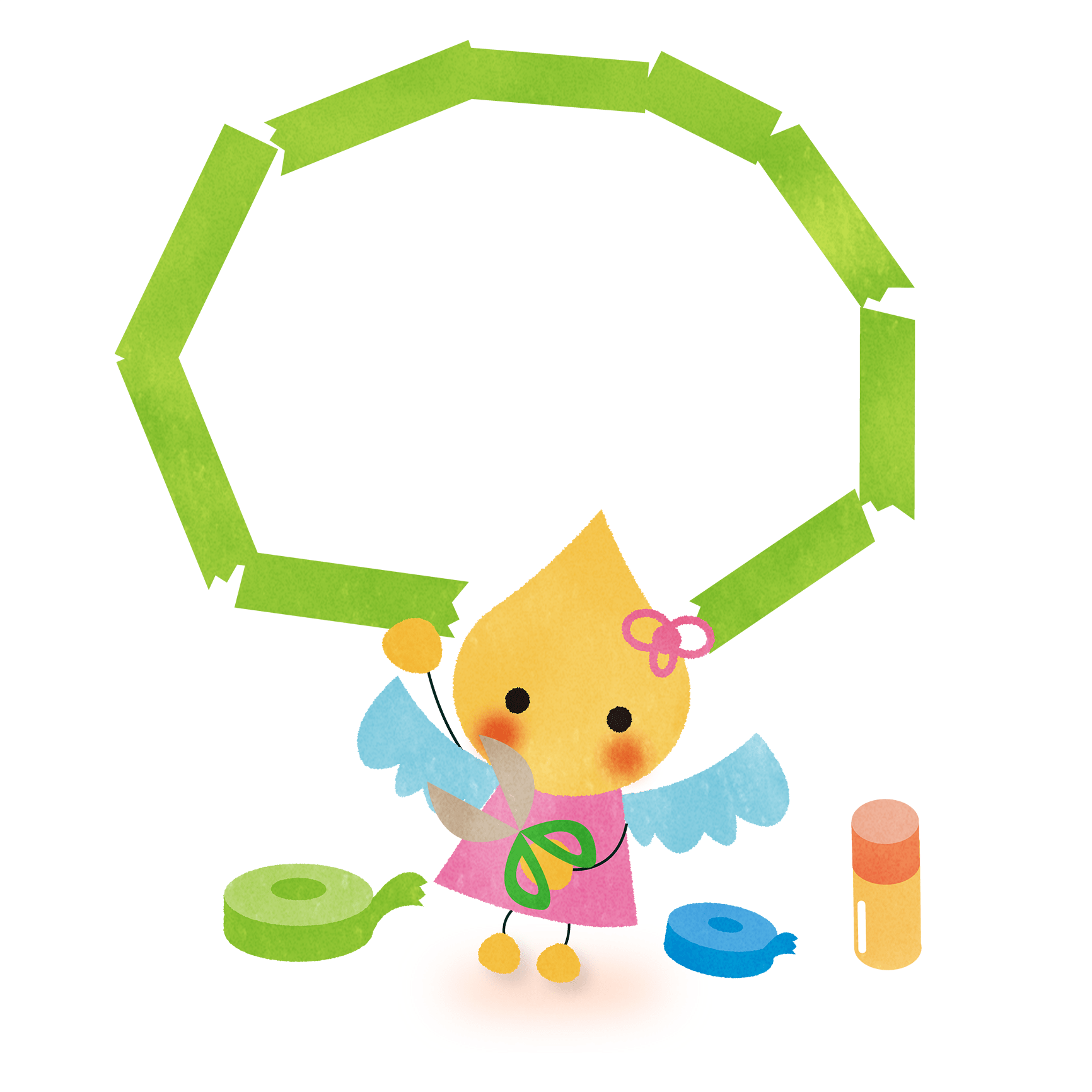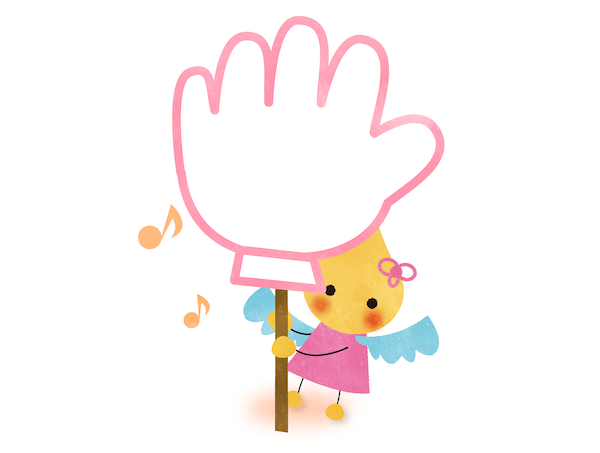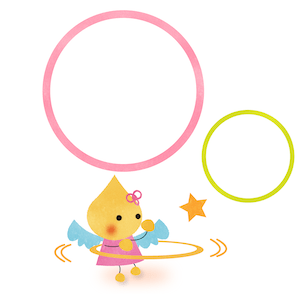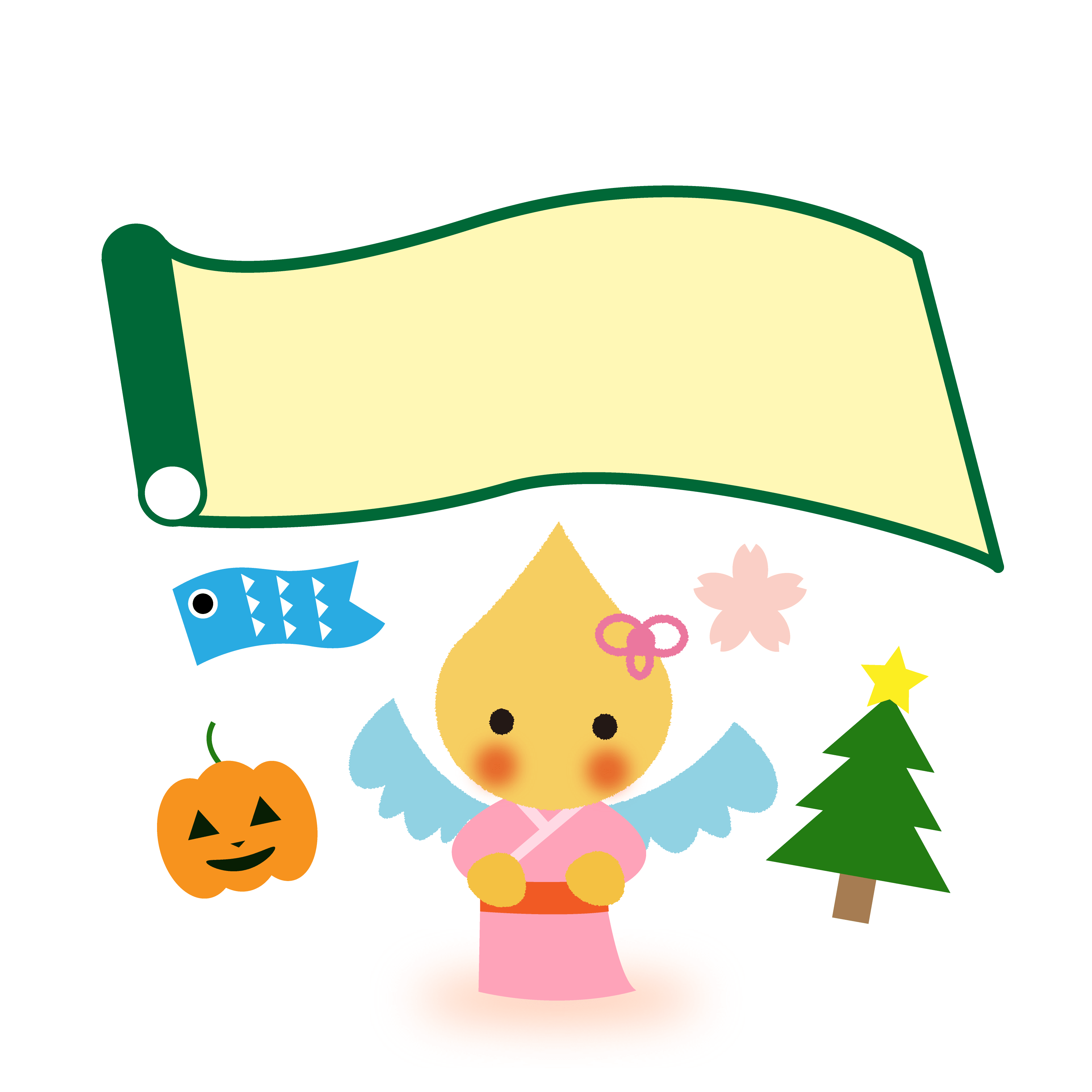もくじ
月案de動画
今月の保育のポイント
- 子どもの自立心と、大人への依存心の揺れを受け止めた上で、身辺の自立へ向けて出来るところ、苦手とするところ、できなかった状況を観察し、子ども一人ひとりの課題を明確にしておく。
- 身の回りのことを自分でしたがらない子どもに対しては、気持ちをしっかりと受け止め、保育者と一緒に自立へ歩んでいく形の援助をとる。一緒に行って出来たときは十分に誉め、徐々に次の意欲へとつなげていく。
- 秋の果物、落ち葉、どんぐりなどの秋の自然物に触れ、造形遊びに取り入れるなどして五領域の広がりを意識する。
- 友達と関わる、関心をもつことをそれぞれの姿の中から大切にし、子どもの社会性を尊重する。トラブルが起きた時は相手の気持ちをゆっくりと伝えながら、納得できる道を子どもと探していく。
月のねらい
- 生き物や植物、落ち葉などに触れ、秋の自然に親しむ。
- 保育者や友達と言葉でのやりとりを楽しむ。
- 環境に配慮してもらいながら、心地よく過ごす。
ほいくのおまもりプラス
週のねらい
その1
- 1週目:秋の自然に触れ、生き物や植物に興味を持つ(教育)
- 2週目:戸外で集めた木の実や落ち葉を使って製作を楽しむ(教育)
- 3週目:身体を思いっきり動かしながら楽しく遊ぶ(教育)
- 4週目:保育者や友達と関わりながら、好きな遊びを存分に楽しむ(教育)
その2
- 1週目:保育者や友達と言葉のやり取りやごっこ遊びを楽しむ(教育)
- 2週目:室内外の気温差に気をつけて、健康的に過ごせるようにする(養護)
- 3週目:手洗い、うがいなど衛生意識を育み、清潔を保ちながら健康的に生活する(養護)
- 4週目:戸外遊びを通して秋の自然に関心を深める(教育)
ほいくのおまもりプラス
前月末の子どもの姿
養護(生活)
- 手洗いうがいのやり方を覚え、自らやってみようとするがうまくできなかったりそのまま水道で遊んでしまったりする子どももいる。
💡
手を洗うことで、「さっぱりした」という実感がいまいちな子もいます。まずはそこから始めても良いかもしれませんね。 - 衣類を脱いだ後は、畳んでみようとする姿が見られる子どももいる。保育者に甘えてなかなか自ら着脱しない日もあるが、意欲的にやってみようとする子どもが多い。また、持ち物を自分の棚へ片付けることもできるようになり、身の回りのことへの関心が高まってきている。
- 遊んでいる途中でも自分のタイミングでトイレに向かうことができるようになってきている。しかし、遊びに夢中になっているときにはギリギリになってしまい、間に合わないこともある。
💡
間に合わなくても責めることだけはしないでおきましょう。例え振り向いて欲しくてわざと排尿したとしてもです。そうしないといけなかった何か理由があるはずです。 - スプーンやフォークを正しく持ち、メニューによって持ち替えながら上手に食事を進める姿が見られるようになってきた。すくいづらいメニューの時には手で支えながら食べることもあるが、ほとんどの子どもが最後まで意欲的に食事を進められている。
教育(遊び)
- 安定して走れるようになってきた子どもが多く、戸外ではかけっこを楽しんでいる姿が見られた。また、乗り物や遊具などでも積極的に遊び、年上の友達の真似をしている子どももいる。
- 運動遊びでは、しゃがんだりジャンプしたりし、いろいろな身体の使い方に挑戦することができていた。うまく出来なくても、楽しそうに真似する姿があった。
- 好きな遊びに熱中する子どももいれば、友達の遊びに興味を持ち、いろいろな遊びに取り組む子どももいた。遊びの中で友達との関わりも少しずつ深め、自ら関わっていこうとする姿が見られた。
💡
友達に興味をもつときは、友達のやっていることや持っているものに興味をもちはじめます。子どもを繋ぐこと、ものは生活の中に落ちています。 - 紙粘土で遊んだりマジックを使ってお絵かきをしたりする活動にも取り組み、楽しそうにする子どもが多かった。
ほいくのおまもりプラス
活動内容(五領域対応)
養護(生活)
- スプーンやフォークを正しく持って使おうとする。(健康)
- 朝の挨拶や食事の際の挨拶を覚え、自ら言葉やしぐさで言おうとする。(言葉・表現)
- 手洗いうがいや衣類の着脱など、身の回りのことを意欲的に行う。(健康)
💡
自分のことが自分でできたことで、1つ大きくなった気がするものです。意欲的に頑張っているときは援助はそっと。 - 自分のロッカーの場所を覚え、持ち物を自分の棚へ片付ける。(健康)
- トラブルややり取りを通して、相手の思いや気持ちに気付く。(人間関係)
- 鼻を自分でかもうとする。(健康)
- 手洗いやうがいを自分で行う。(健康)
ほいくのおまもりプラス
教育(遊び)
- 木の実や落ち葉を使用した、製作を楽しむ。(表現)
💡
木の実や落ち葉を拾うと小さな虫も一緒に拾うことになります。煮沸消毒するか、なるべく早く使うようにしましょう。 - リズム遊びや運動遊びを通して、思いっきり身体を動かすことを楽しむ。(健康・表現)
- 保育者や友達に自分の気持ちを言葉で伝えようとする。(言葉・人間関係)
- ごっこ遊びなどを通して、友達とやりとりすることを楽しむ。(人間関係・表現)
💡
2歳児は偉大なる模倣者といわれるように、何でもごっこ遊びに変えます。料理や洗濯、戦いまで。ごっこを通して言語力やコミュニケーション能力を育んでいきます。 - 固定遊具などにも興味を持ち、挑戦してみようとする。(環境)
- 保育士や友達と歌ったり、踊ることを楽しむ。(表現)
- 描く、切る、貼ることと、秋の自然物と組み合わせ、表現することを楽しむ。(表現)
- 落ち葉や虫など、見つけた物の色、形、手触りなどに興味をもち、その違いについて保育者と一緒に分かち合ったり調べる。(環境・言葉)
ほいくのおまもりプラス
環境構成と援助
養護(生活)
- 食事の際には、スプーンなどを使って食べる姿を認めつつ、嫌になってしまわないように気をつけながら繰り返し正しい持ち方を伝えていく。
💡
スプーンの持ち方には段階があります。つまむように持っているか、握りしめるように持っているか、見極めましょう。 - 場面ごとの挨拶も少しずつ覚えてきているため、言葉で表現できるように声をかけていく。
- 手洗いの際には、袖をまくることも自分でできるよう、やり方を伝える。また、手を洗った後はタオルですぐに手を拭くことも知らせ、自分で流れが分かるようにしていく。
💡
袖がめくりにくい服を着ている子がいます。そういった子には保護者へのお願いも必要になるかもしれませんね。 - 子どもが自分のロッカーを把握できるよう、マークをつけておく。マークが外れたり見えにくくなったりしていないか定期的に確認をし、見えにくい時には貼り直しを行うようにする。
- 子どもの気持ちを受け止めながら、「~だと辛い気持ちになるよ、~と言うと伝わるよ」等、相手の気持ちに気付けるような言葉かけと、適切な言葉を丁寧に伝える。
- ティッシュを子どもの手の届く場所に置き、汚れたら自分で拭ける環境を整える。
- 手洗いうがいがしやすいように、コップを置く位置を近くしたり、台を置き、身長が低い子でも手洗い場に届きやすい高さにする。
ほいくのおまもりプラス
教育(遊び)
- 戸外で子どもと一緒に落ち葉や木の実を集め、製作に取り入れる。実際に使ったり触れたりすることで、より自然のものに興味が湧くようにする。
💡
落ち葉やドングリの下にはムカデが潜んでいることも・・・土の中までダイナミックに手を入れるのはやめておきましょう。また、持って帰ったらチェックしましょう。 - いろいろな身体の使い方を覚え、走ったりジャンプしたりするのが楽しい時期になってくる。思いっきり発散できるよう、広々した場所で運動遊びなどを行っていく。
💡
走りながら飛んだり、ゆっくりから速く走ったり、強弱を楽しめる時期です。保育者も存分に楽しみましょう! - 嫌なことがあった時にうまく言葉で表現できず、手が出てしまったり泣いたりしてしまうこともある。気持ちを代弁しながら、自分の気持ちを言葉で表現できるように援助していく。
- 異年齢の友達の姿を見て、固定遊具や乗り物などに興味が湧くようにしていく。異年齢時も一緒に戸外で遊んでいる際には、ぶつかったり転倒したりしないように気をつけて見ていく。また、2歳児だけで戸外で遊ぶ時間も設け、思いっきり遊び込めるようにするなど、環境も工夫していく。
- 子どもたちの好きな曲や、楽しくリズムに乗れる曲を用意し、子ども達の振り付けも取り入れながら楽しい雰囲気で踊る。
- 十分に満足できる量の材料を用意し、子どもの表現したいものや動作自体を楽しむ行為を肯定しながら、何に興味をもって取り組んでいるかを観察する。
- 「この羽は透明だね」「落ち葉ざらざらしているね」等、感触や見た目などの気づきを子ども達と共有し、図鑑でその物と一致させて、子ども達の興味や言葉、調べて名前が分かる楽しさを引き出すようにする。
ほいくのおまもりプラス
健康、安全面で配慮すべき事項
- 室内が暖かくなりすぎないよう、室温に気を付ける。また、動きやすくできるだけ薄着を心がけて、子どもが快適に過ごせるようにしていく。
- 寒暖差が出てきて体調を崩しやすく、また流行性の感染症がでてくるため、予防にしっかりと努める。体調不良に早く気づけるよう、普段の様子を一人ひとりよく観察しておく。
💡
体調がすぐれない子が現れたら注意が必要です。3日後にはほとんどの子が鼻水、咳なんてことも。
ほいくのおまもりプラス
今月の製作・歌・絵本・手遊び・室内室外遊び
製作
- かわいい!みの虫製作
- 落ち葉でポンポン
- 紙皿でフクロウさん
この他、【秋の自然】や【遊びや行事】の製作を『葉っぱ、トイレットペーパーの芯、ビーズ、描く、貼る、』等、身近な素材と手法でご紹介!
歌
- でぶいもちゃん ちびいもちゃん
- きくのはな
- もみじ
絵本
- どんぐりとんぽろりん
- タンタンの ずぼん
- ぼうし とったら
手遊び
- やきいもグーチーパー
- 大きなクリの木の下で
- やさいのうた
室内室外遊び
- 電車ごっこ
- どんぐりころころお絵描き
- 大地の窓
行事
- 避難訓練
- 誕生会
- 身体測定
- 文化の日(11/3)
- 七五三(11/15)
- 新嘗祭(11/23)
- 勤労感謝の日(11/23)
- 絵本の日(11/30)
食育
- 食べこぼしに気をつけながら食事を進めようとする。
- 友達や保育者と「おいしいね」など話をしながら、楽しい雰囲気の中で食事をする。
ほいくのおまもりプラス
地域と家庭との連携
- 寒暖差が大きくなってくる時期だが、厚着になりすぎないようにお願いをする。また、温度調節しやすい服や動きやすい服を着せてもらえるように声をかけていく。
- 冬に流行りやすい感染症などについてまとめ、家庭でも予防に取り組んでもらえるようにしていく。体調が悪い様子が見られたら、家庭と情報共有できるようにコミュニケーションをとる。
自己評価
- スプーンやフォークを正しく持って使おうとしていたか。
- 朝の挨拶や食事の際の挨拶を覚え、自ら言葉やしぐさで表現することができたか。
- 手洗いうがいや衣類の着脱などを意欲的に行っていたか。
- 自分のロッカーの場所を覚え、持ち物を自分の棚へ片付けることができたか。
- 木の実や落ち葉を使用した製作を楽しみ、自然にも興味を持つことができたか。
- リズム遊びや運動遊びを通して、思いっきり身体を動かすことを楽しんでいたか。
- 保育者や友達に、思ったことや自分の気持ちを言葉で伝えようとする姿が見られたか。
- 遊びなどを通して友達と関わって遊び、やりとりすることを楽しめたか。
- 固定遊具などにも興味を持ち、楽しく遊ぶことができたか。
ほいくのおまもりプラス
個人案はこちら♪
-

-
【11月】個人案の文例【2歳児】
続きを見る
↓その他の保育ネタ↓