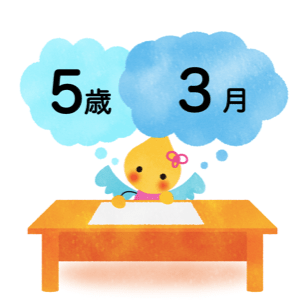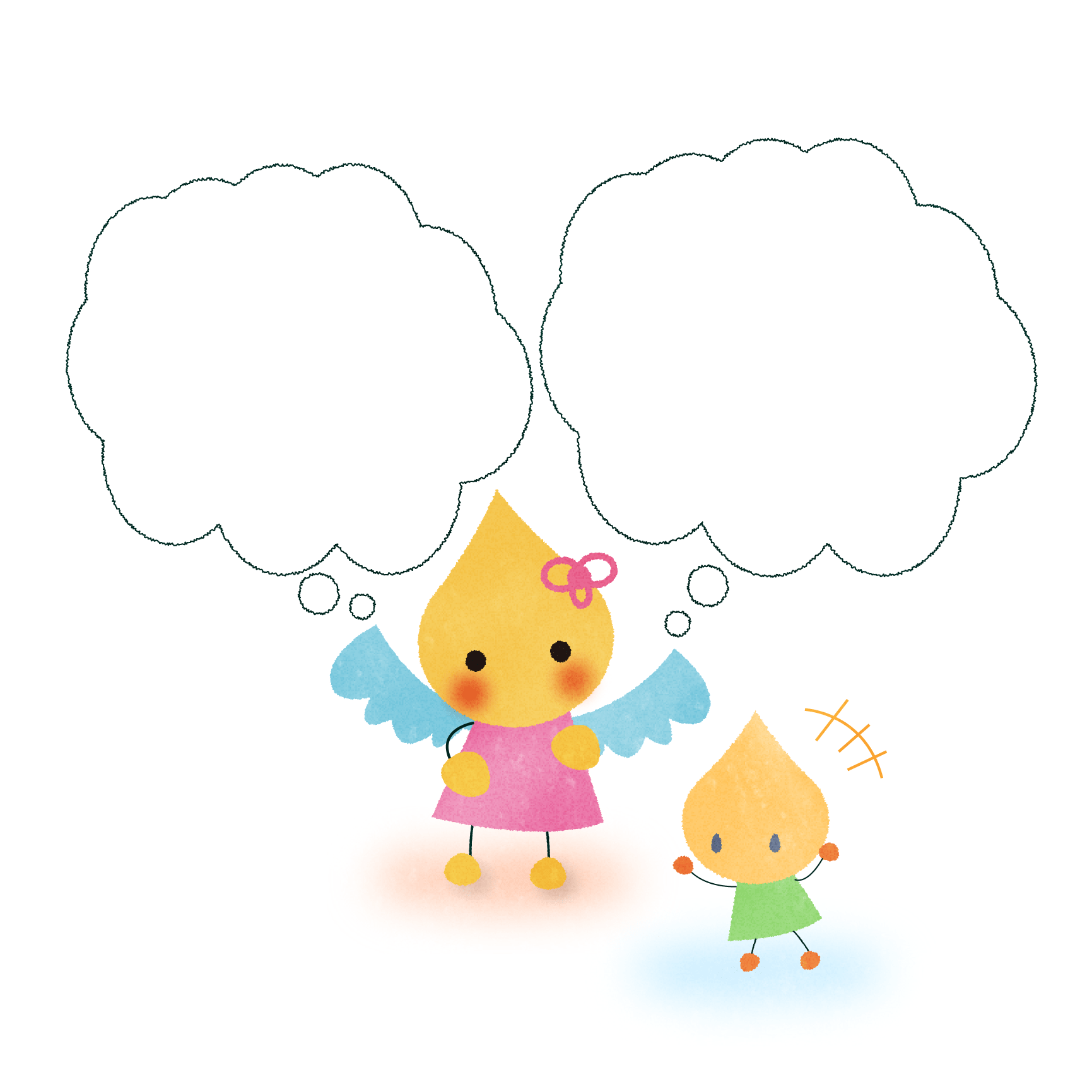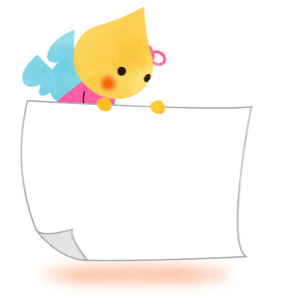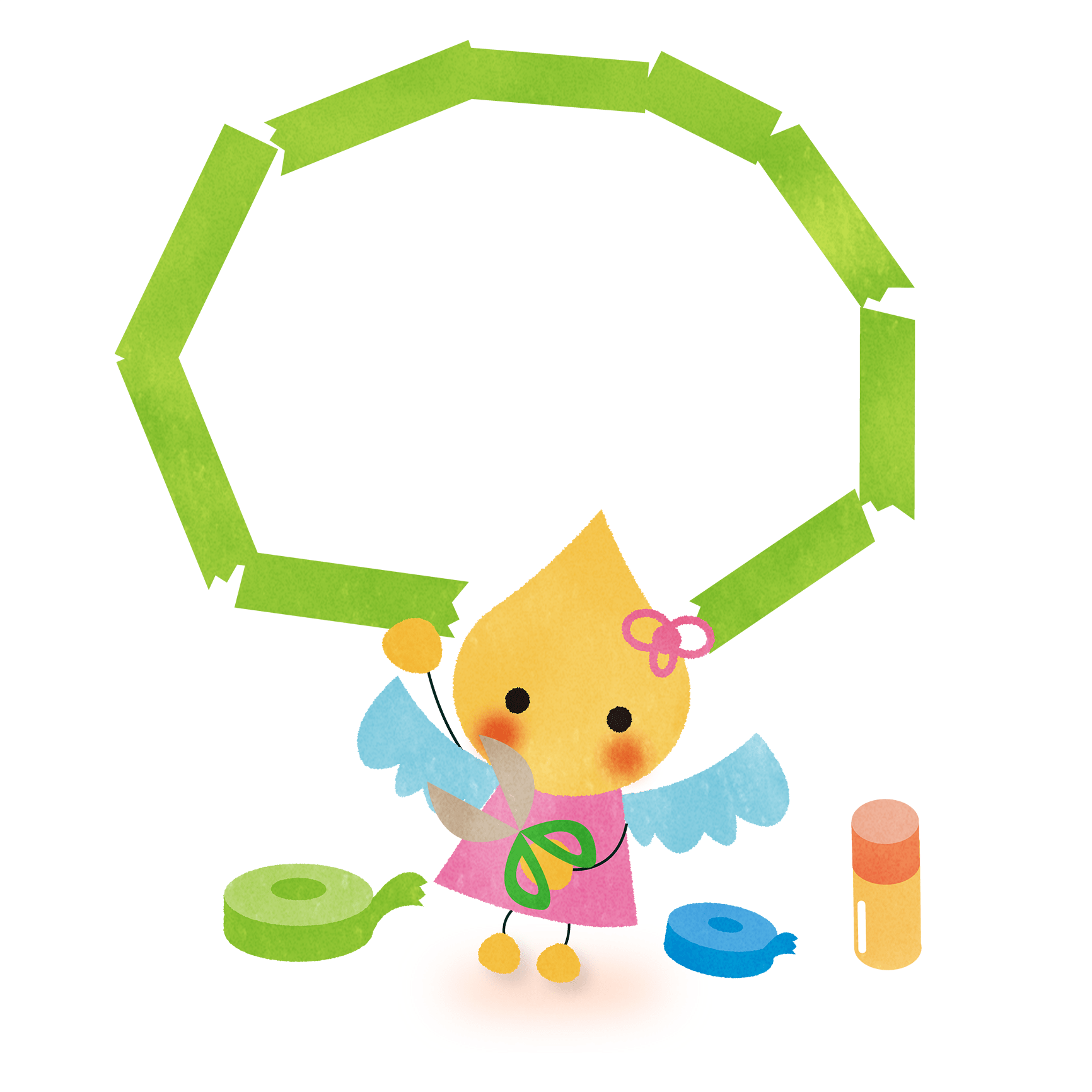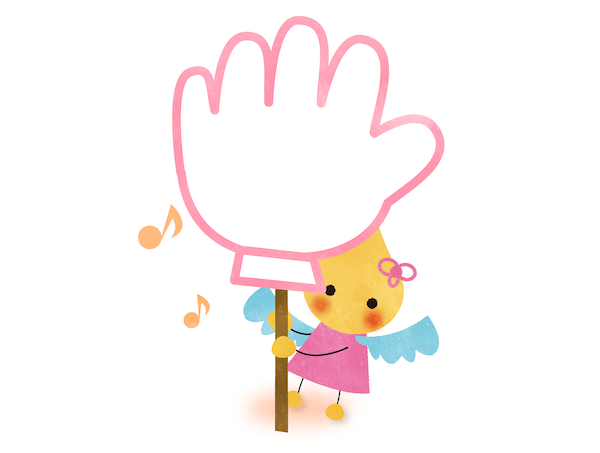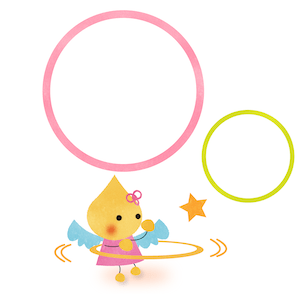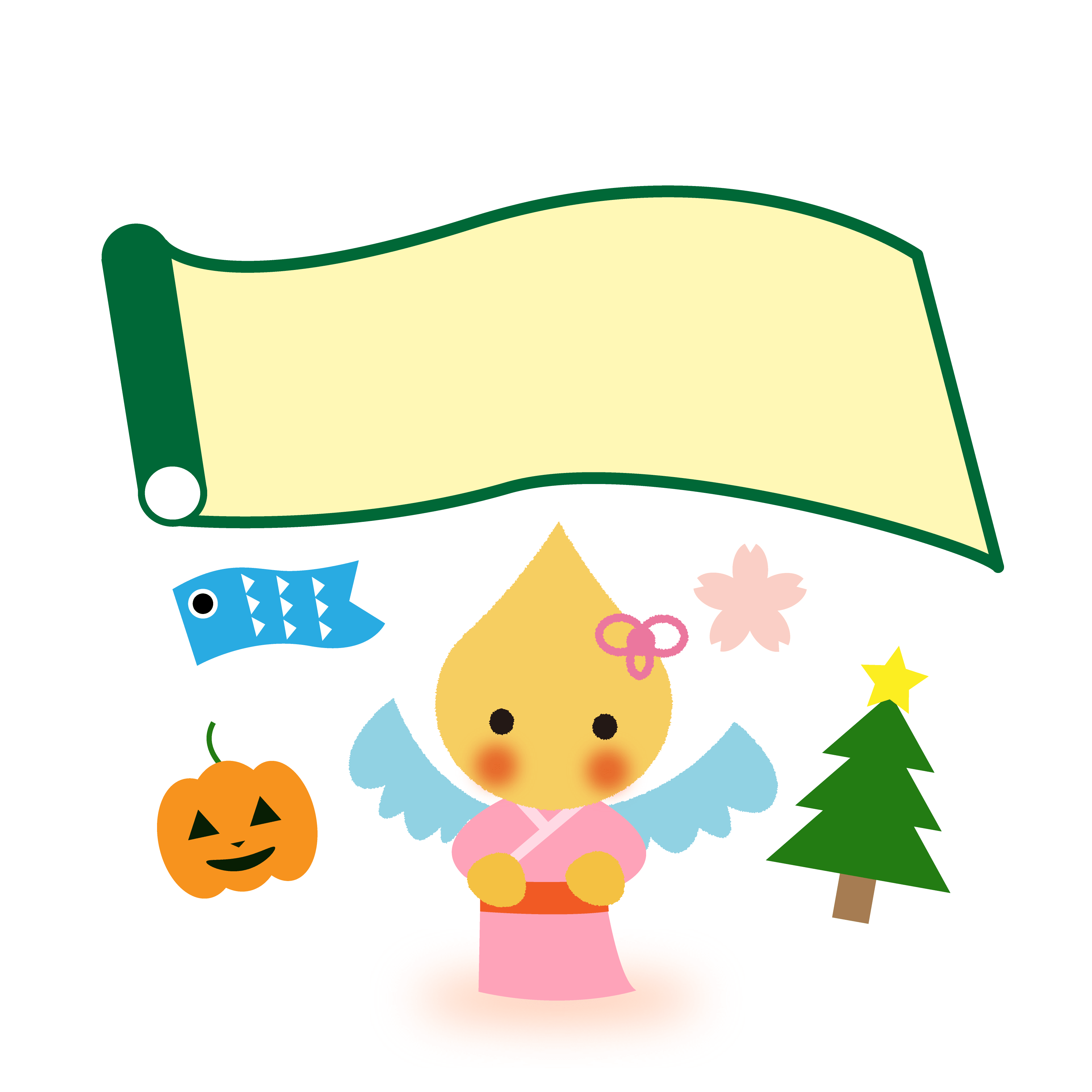もくじ
月案de動画
今月の保育のポイント
- 今まで培ってきた子ども個人で取り組む力、集団で取り組む力を子どもが発揮できるよう、さまざまな経験をじっくり取り組める環境を用意し、学び、生活、精神的な自立に関われるようにていねいに関わって過ごす。
- 集団で協力し合う時間が多いこの時期だからこそ、子ども一人ひとりの育ちを振り返り、苦手な子や意見を言いにくい子のサポートをしながら、ひとりひとりの今の課題を見つけておく。
- 小学校入学を控え、保護者も不安があり相談を受けることも増える。その時に子どもの育ちを踏まえながら話を聞き、家庭でできることを伝えるなどし、安心して保護者、子どもが小学校へ向かえるようにする。
- 冬から春への小さな変化を伝えてみたり、身近な冬の自然を体感し、保育士が気づいたことを子どもに伝え、子ども同士で目を向けられるようにする。
月のねらい
- 就学への期待を持って生活し、自分で生活の見通しを持ちながら活動を行う。
- 友達と協力しながら遊びや活動を進め、お互いの気持ちを認め合う心地よさを感じる。
- バケツの水が凍るなどの身近な冬らしい現象に興味を持ち、遊びの中に取り入れ遊ぶ。
- 発表会に向け、友達と一緒に作り上げる楽しさを味わい、やり遂げたことに喜びを感じる。
ほいくのおまもりプラス
週のねらい
その1
- 1週目:寒い中でも戸外遊びを思いっきり楽しむ(教育)
- 2週目:友達と協力しながら遊びを進め、お互いの気持ちを認め合う心地よさを感じる(教育)
- 3週目:活動や遊びの中で目標を持って諦めずに取り組み、達成感を味わう(教育)
- 4週目:就学への期待を持ち、生活の見通しを持ちながら準備や片付けを行う(養護)
その2
- 1週目:文字や数などを、遊びの中で楽しみながら活用する(教育)
- 2週目:友達の良さを認め合いながら遊びや生活を進める楽しさを味わう(教育)
- 3週目:卒園をひかえての異年齢児との活動を通して、年下の友だちに対し思いやりを持って遊ぶ(教育)
- 4週目:就学への期待や不安を受け止めながら自信をもって生活できるようにする(養護)
ほいくのおまもりプラス
前月末の子どもの姿
養護(生活)
- お正月休みの話では、「おばあちゃんと神社に行ったよ」「新幹線で遠くまで行って、3回お泊まりしてきた」「お昼にはおせちを食べて、夜は家族でお寿司を食べたよ」など、経験したことの具体的な話ができるようになってきている。
💡
楽しかったことを発表する機会を設けてみましょう。自分の話を聞いてもらう機会、話すことに慣れることは就学に向けての取り組みにもなります。 - 手が寒いから手袋をする、外は寒いから上着を着て行くなど自ら理由を考えて衣類の着脱を積極的に行う姿がある。
教育(遊び)
- けん玉やコマ回しなどそれぞれの好きな遊びに熱中し、できるようになるまで諦めずに何度も練習する姿がある。また、できなかったことができるようになり、喜びを感じ満足気にしている子がいる。
- 遊びや活動の際にはなかなかできない友達を励ましたり、「こうするとできるよ」と声をかけたりしている。できるようになると「頑張ったね」「やったね」など一緒に喜ぶ姿がみられる。
- 時計の読み方や数字の計算に興味・関心が深まり、時計が読めるようになったり簡単な足し算ができるようになっている子もいる。
💡
数字を読むところと、実際の数の概念がどこまで育っているかを見てみましょう。1の次は2と規則的なことしか知らず、物を数えることができない子も稀にいます。
ほいくのおまもりプラス
活動内容(5領域対応)
養護(生活)
- 友達と話をする中で自分の考えを伝えると共に相手の意見も聞き、認め合う心地よさを味わう。(表現・人間関係・言葉)
💡
人を受け入れる力については一朝一夕では身に尽きません。根気よくその子に関わり、協調した方が良い結果になる経験が一定量必要です。 - 戸外遊びの際には、自分で積極的に衣類の調節を行う。また、脱いだ上着は畳むなど、衣類を丁寧に扱おうとする。(健康)
- 風邪予防のために手洗いうがいを自らきちんと行う。(健康)
💡
雑に済ませる子もいます。たまに見ておき指導するようにしましょう。 - 劇に必要な小道具を考え、生活の中で使えそうなものを工夫しながら準備をする。(環境)
- 一日の生活の見通し、目標をもって活動に取り組む。(健康)
- 安全に道を歩けるように交通ルールを身に着ける。(健康・環境)
- 既存のルールや決まりに捕らわれず、自分たちの要求や状況を踏まえてルールや決まりをクラスで導き出していく。(人間関係・環境)
ほいくのおまもりプラス
教育(遊び)
- 遊びを通して仲間意識を持ち、友達と遊び方を工夫しながら一緒に遊ぶ楽しさを味わう。(人間関係)
💡
「友達に入れてあげない」こんなやり取りも。どうして嫌なのか、何でそうなってしまうのかを把握しておきましょう。保育をデザインする時だけでなく、保護者に説明する時にとても重要になります。 - 次にする活動にも見通しを持ち、準備や片付けを積極的に行う。(人間関係・健康)
💡
次の活動に見通しが立たない子もいます。次の活動、その次と提示したり、聞くことで遠くを見つめられるように視点誘導しましょう。 - 友達とアイディアを出しながら、劇やダンスなどの身体を動かす表現を楽しむ。(表現)
- 様々な楽器や音に触れ、みんなで合奏することでひとつの音楽ができることを楽しむ。(表現)
- 小学校にて体験をし入学への期待を膨らませる。(健康)
- 遊びの中で文字、数量を使い、関心を持つ。(環境・言葉・表現)
- 良い、悪いではなく、色んな考え方を受け入れ、友達の肯定的な面を見る。(人間関係)
ほいくのおまもりプラス
環境構成と援助
養護(生活)
- 衣類の着脱など自分でなんでも行えるようになっているが、畳んだり邪魔にならない場所に置いたりなどに気が向かない子どももいる。きちんと畳む、忘れないところに置くなど衣類を大切に扱うことにも気付けるよう、声をかけていく。
- 発表会の劇作りでは、小道具などを子どもと一緒に準備することで、自分たちで作り上げていく経験をしっかりと味わえるようにする。また、身近なものを取り入れることで、使い方を工夫したり考えたりすることができるようにする。
💡
自分たちで途中でオリジナルストーリーを入れても楽しい活動になりますよ。保育者主導よりも結果として子どもが食いつき、充実した活動になることも。 - しっかりと言葉で自分の意見を言える一方で、相手の気持ちを蔑ろにしてしまうこともある。意見が違ってもお互いの気持ちを認め、認め合える心地よさを感じられるように必要に応じて援助する。
💡
自分の意見が通らないと思うや否や、わざと小馬鹿にしたような態度をとる子もいます。ここには本人の諦めが隠れています。そこの本音を聞くように言葉をかけてみましょう。 - 一日の生活スケジュールを貼り出し、時間と場所と内容が分かるようにする。時間の感覚があいまいな子や、刺激を受けるとすぐにやるべきことを忘れてしまう子には、声掛けや小さい時計を見せて思い出せるようにする。
- 横断歩道では信号を見ているか、歩道を占領して歩いていないか、交差点を渡るときは左右を確認しているか等を観察し、進学へ向けて現在の子どもの力を確実に知る。危険個所にはさりげなく保育者がつき、あくまで子ども自身が判断できるように援助を留める。
- 子どもが生活を作る一員という実感を得られるよう、決まりをやぶってしまうなどの行為の時、子どもがどう考えて何を願っているのかを丁寧に聞き取る。クラスの中で実現できそうか、実現するにはどうすればいいかを話し合う場を設け、決まりやルールを可能な範囲でその都度変えていく。
ほいくのおまもりプラス
教育(遊び)
- 子どもが生活の見通しを持てるよう、1日の流れを書いて見えるようにおいておくようにする。時間なども分かるようにすることで、子ども自ら時間に気づき、行動できるようにしていく。
💡
時間のゆとりをもたせることは特に重要です。「もう少し遊びたい」子どもたちの要望に応え、「その分早く片付けようね」と見通しにもなります。 - 表現遊びではポーズやダンスをするのを恥ずかしがってしまう子もいる。子ども一人ひとりの表現を認め、楽しい雰囲気の中でできるように援助する。
- 楽器を触る際には子どもが実際に触れ、音を出すことを楽しむ時間をもてるようにゆとりある時間を設ける。
💡
楽器に触れ、どんな仕組みで音が出るのかを味わうように、ゆっくりと時間をとった活動が望ましいですね。我先に奪い合わないためにも、少人数交代制もアリです。 - 一緒に遊ぶ仲間や気の合う友達グループができ、仲間に入りづらいこともある。いつも遊んでいない子の「遊んでみたい」という気持ちも汲み取り、必要に応じて友達の輪を広げられるように声をかける。
- 入学体験が実りあるものとなるように緊張している子には寄り添う。その後、入学してみたいか、小学校はどんなところかを聞き、子どもたちの理解と意欲を高める。
- 廃材で作ったものや途中の物に自ら名前を書く習慣をつけ、書けない子も書きたいと思わせるような仕組みをつくる。エンピツや紙を用意し、手紙遊びが楽しめるように環境設定する。
- 子ども個人の考え、願いや思いをしっかり聞く場を設け、トラブルにも丁寧に対処する。トラブル後、友達の良いところを伝えたり、子どもに聞くようにし、子どもの中で楽しいことや困ったことなど、色々な側面があることを体験できるような声掛けを意識する。
ほいくのおまもりプラス
健康、安全面で配慮すべき事項
- 感染症が流行りやすい時期である。一人ひとりの体調の変化に気付けるよう普段の様子を注意してみていく。
💡
理由もなく、無理をする子もいます。目が潤んでいる、食欲がないなど、体調の変化を見極められるように基準を設けておきましょう。 - 手洗いうがいなどが習慣となり、率先して行う姿が見られるが、適当に済ませたりもしやすい。改めて手洗いうがいを行う意味などを伝え、やり方を確認したりする必要もある。
ほいくのおまもりプラス
今月の製作・歌・絵本・手遊び・室内室外遊び
製作
- 鬼のかざり製作
- アレンジラーメン製作
- ふくらむ雪だるま
この他、【冬の自然】や【行事】の製作を『マジック、スタンプ、毛糸』等、色々な素材と手法でご紹介!
歌
- しっぽの きもち
- ゆきまつり
- まっくらもりの うた
絵本
- ふゆのようせい ジャック・フロスト
- ゆきのひ
- だいくとおにろく
手遊び
- 大きくなったら何になる
- おにのパンツ
- せんせいとおともだち
室内室外遊び
- 手つなぎ鬼
- 色鬼
- 氷で遊ぼう
行事
- 誕生日会
- 避難訓練
- 身体測定
- 小学校訪問
- 節分(豆まき)(2月3日)
- 建国記念日(2月11日)
- バレンタインデー(2月14日)
- 猫の日(2月22日)
- 天皇誕生日(2月23日)
食育
- お箸の持ち方や左手をお皿に添えるなどの食事のマナーに気をつけながら食事をする。
- 豆まきを通して、日本の風習や由来を知る。
- 就学に向けて、食事の時間も気にしながら食べ進める。
ほいくのおまもりプラス
異年齢保育
この項目はおまもりプラスで公開中!
職員間の連携
この項目はおまもりプラスで公開中!
地域と家庭との連携
- 子どもの成長を言葉で伝えることで自信をもって小学校へ入学できるように家庭での協力もお願いする。
- 日々の生活や行事などを通して保護者とともに成長を分かち合い喜び、協力に対する感謝の気持ちを伝える。
- 就学に向けて生活習慣の見直しを園と家庭で行う機会を作る。家庭でも意識をもってもらうように協力をお願いする。
長時間保育の配慮
この項目はおまもりプラスで公開中!
自己評価
- 子どもが先を見通しながら準備や片付けを行えていたか。
- 積極的に衣類の着脱や手洗いなどを行い、風邪をひかないように気をつけていたか。
- 就学に向けての不安を減らし、自信を持って生活できたか。
- 豆まきの由来や伝統を知り、興味関心を持てたか。
- 友達と一緒に話し合いをする機会があり、お互いの気持ちや考えを聞き、認め合う経験ができていたか。
- 冬の自然に触れ、理由を考えたり遊びに取り入れたりすることができたか。
ほいくのおまもりプラス
↓その他の保育ネタ↓