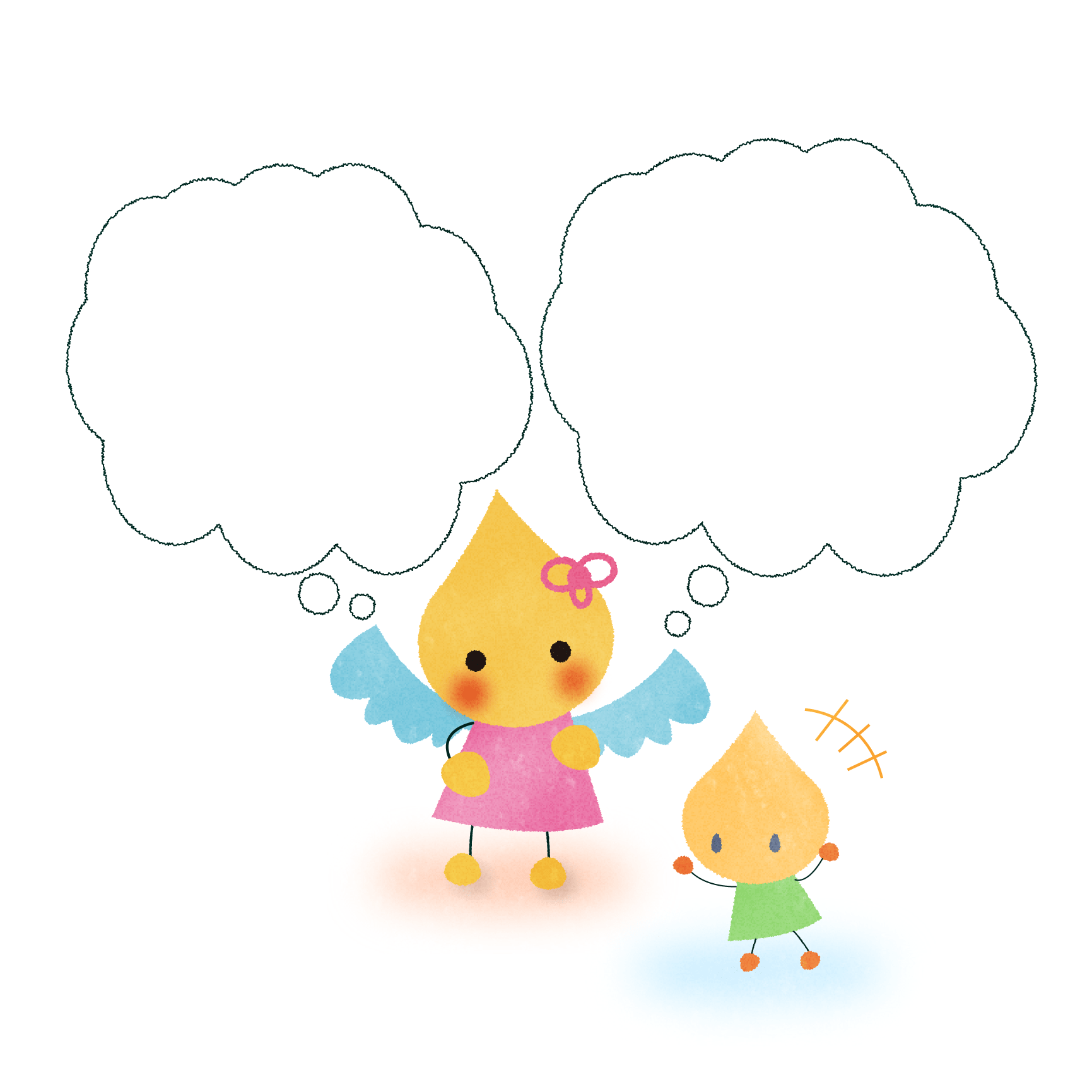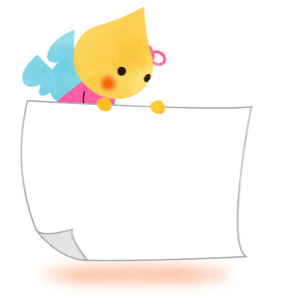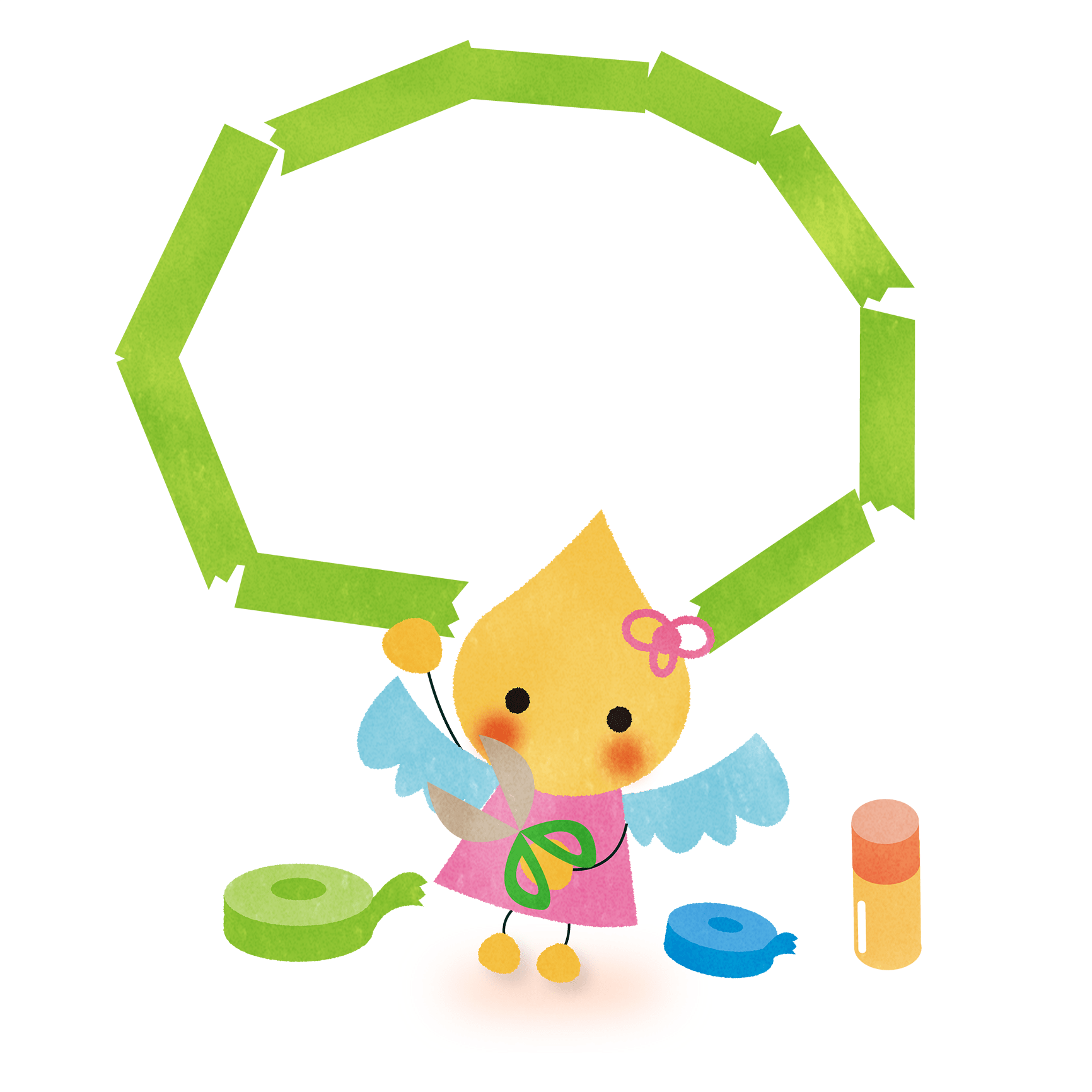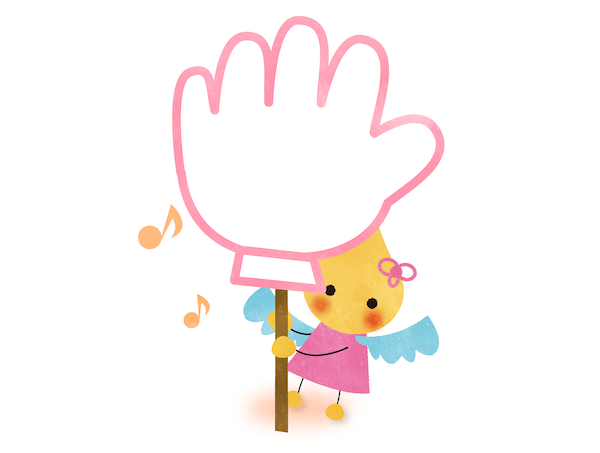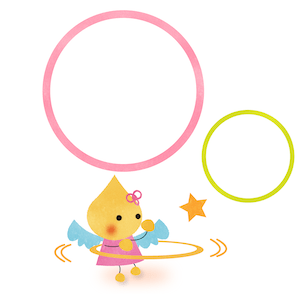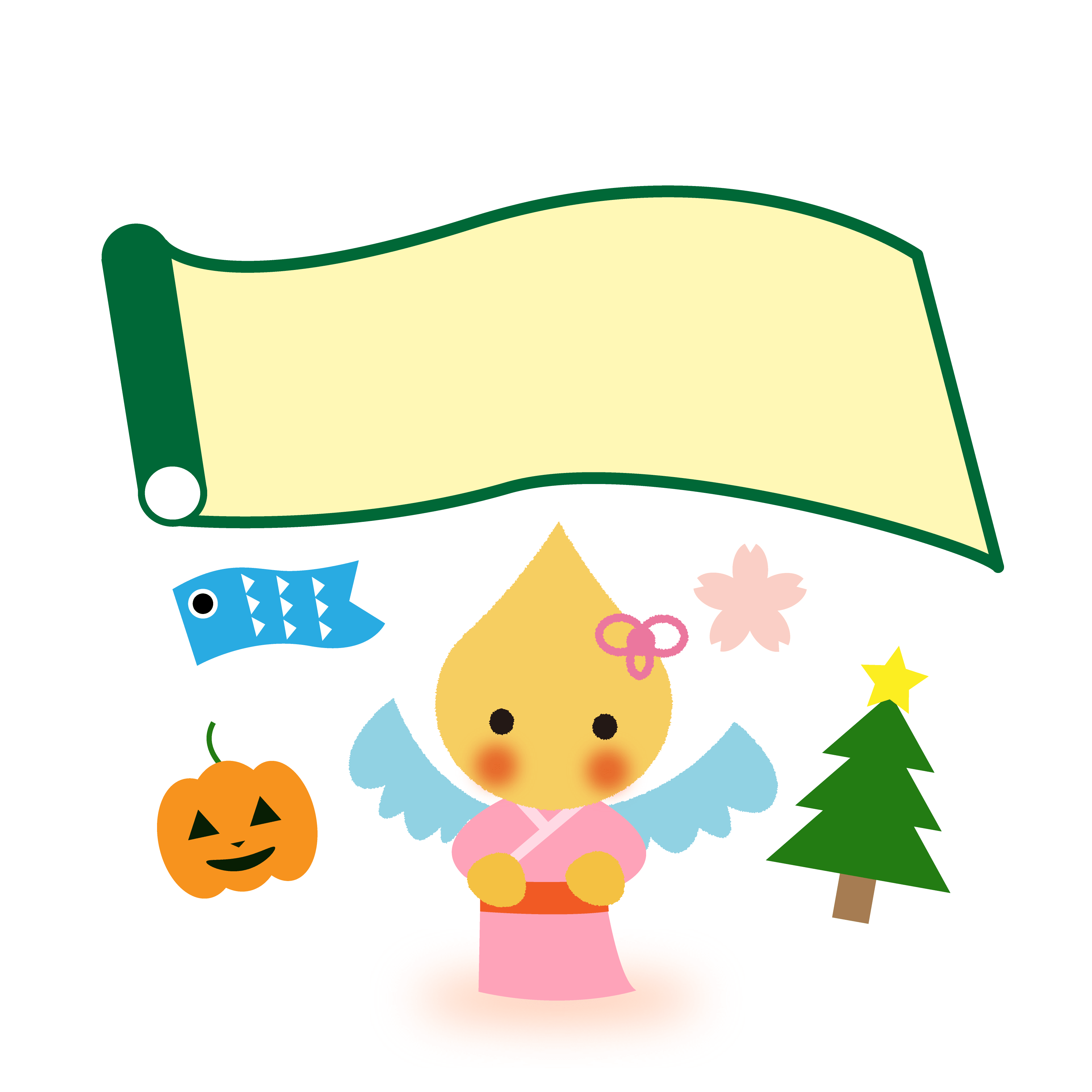もくじ
月案de動画
今月の保育のポイント
- 2月は寒さのピークで室内での遊びが増えるが外遊びも大切。機嫌よく、快で過ごすことをねらいとし、子どもの体調や天気に応じて外遊びを入れる。
- 室内遊びの環境を充実させ、トンネルや坂などハイハイで探索遊びができるようにする。
- 病気休み後の登園は心身ともにまだ不安定。他の病気にかかりやすく、心も不安で泣きやすい。子どもの安定した生活を第一に考えて、いつもよりも余裕をもった保育を。
- 子どもが手づかみで食べる、行きたいところへ移動するなど、自分の意志で動くようになってきた時期。子どもの興味関心に合わせた触れ合い遊びや、衣服の着脱、排泄などの生活を通して保育士とのやりとりを楽しみ、自分の意志を受け止められ、甘えられる安心感を得られるように保育する。
月のねらい
- 室内外で機嫌よく過ごす。
- 遊びや活動を通してハイハイやつかまり立ちなどを楽しむ。
- 探索遊びを楽しみ、身の回りにある様々なものに興味を持つ。
ほいくのおまもりプラス
週のねらい
その1
- 1週目:寒い中でも機嫌よく過ごす(養護)
- 2週目:探索遊びで身の回りの様々なものに興味を持つ(教育)
- 3週目:ハイハイやつかまり立ちをし、身体を動かすことに喜びを感じる(教育)
- 4週目:保育者の言葉を繰り返したり、発語することを楽しむ(教育)
その2
- 1週目:保育者に仲立ちしてもらいながら、他児との関わりを楽しむ(教育)
- 2週目:食事や衣服の着脱など保育者と行うことで、できる喜びを知る(養護)
- 3週目:保育者と関わりながら、室内や戸外で体を動かして遊ぶことを楽しむ(教育)
- 4週目:身支度など身の回りのことに興味を持つ(養護)
ほいくのおまもりプラス
前月末の子どもの姿
養護(生活)
- オムツが濡れて不快感がある時には泣いたりオムツを触ったりして、仕草や行動で示す子どももいる。
- ご飯やおやつを食べる際には自ら手づかみで口に運び、積極的に食べ進める姿がある。時にはスプーンやフォークを持ちながら食べ進めることも増えてきている。
- 戸外に出ることを喜び、自分の靴を指差したり上着を掴んだりしている。
💡
このタイミングで靴を自分で履いてみたり、上着を自分で着てみたり、チャレンジしてみましょう。 - 休み明けで不安な時には保育者に甘えることもあるが、生活リズムが整うと安定した情緒で過ごせる日が増えてきた。
💡
0歳児はしっかり甘えましょう。スキンシップや欲求を満たしてもらうことで信頼関係、未来のアイデンティティへとつながります。
教育(遊び)
- 玩具を箱に出し入れしたり、机から落としたりすることを楽しんでいる。
💡
おもちゃは飽きるときが来ます。興味に合わせて新しいものに変えましょう。 - 柵を支えにしてつかまり立ちをしたり、ハイハイしたり、身体を動かすことに喜びを感じている。また、少しずつ歩くことができるようになってきた子もいる。
- 布団やタオルなどに顔を隠して「いないいないばあ」と顔を出すことを喜び、保育者の反応や表情を見て楽しんでいる。
- 気に入った絵本を繰り返し読み、保育者の真似をしながら「ばあ」「ない」「ね」など発語が見られる。
💡
沢山の言葉で話しかけることで、3歳以降、学ぶ力を底上げします。気に入った絵本は何回も読んであげてください。 - 体操やリズム遊びの音楽に合わせて身体を揺らし、楽しむ姿がある。
ほいくのおまもりプラス
活動内容(3つの視点対応)
養護(生活)
- 排泄の際にはおまるに興味を持ち、座ってみようとする。(健やか)
- 豆まきの行事を通して異年齢児と関わりを持ち、いろんな友達と触れ合う。(ヒト・モノ)
💡
大勢の場所は0歳児にとって負担でもあります。無理しない程度の参加にとどめましょう。 - 自分の思いを泣いたり怒ったりして保育者や友達に伝えようとする。(ヒト・モノ)
💡
泣く表現は大切です。すぐにおもちゃや抱っこで泣き止ませるのではなく、何で泣いているか「どうしたの?」と寄り添う対応を。 - 着替えなどにも意欲的になり、自分でやってみようとする。(健やか)
- 食事の際には自らスプーンやフォークを使って食べようとする。(健やか)
- 排泄したことに気づき、表情やしぐさで知らせる。(健やか)
- 着替え、エプロンの脱着、自分のコップの片付け等、自分の身の回りのものに興味をもつ。(健やか・モノ)
- 手遊びを真似たり、自分の思いを身振り手振りや喃語、言葉で伝え、思いが伝わる満足感ややり取りを楽しみ、言葉の獲得につなげる。(ヒト)
ほいくのおまもりプラス
教育(遊び)
- トンネルくぐりやマットの上を歩くなどの活動を取り入れ、身体を存分に動かして遊ぶ。(健やか)
- ハイハイしたり伝い歩きをしたりすることを喜び、自分で立ったり歩いたりしようとする。(健やか)
💡
伝い歩きをするようになると、上に興味を持つようになります。天井から紐を垂らしてとどかないぐらいにキャラや星など吊り下げておくと効果的。 - 歌遊びや触れ合い遊びでは、音楽に合わせて身体を揺らすことを楽しむ。(モノ)
- 名前を呼ばれると返事をしたり、保育者の言葉の真似したりして発語しようとする。(ヒト)
- 紙を破ったりシールを貼ったりし、指先を使って進める遊びを楽しむ。(モノ)
💡
手の感触は非常に大事です。毎日感触遊びを入れて良いくらい、大切なので、「やりすぎかな?」と思うことはありませんよ。 - 戸外で多様な道を歩いたり、冬の自然に触れながら遊ぶ。(健やか・モノ)
- マットやボール遊びを通し、室内においても十分に身体を動かして遊ぶ。(健やか)
- フライパンやコップといったままごとの玩具を使い、食べ真似を楽しむ。(ヒト・モノ)
ほいくのおまもりプラス
環境構成と援助
養護(生活)
- 嫌いな食べ物にも興味を持てるように、保育者が美味しそうに食べる姿を見せたり友達が食べる姿を褒めたりする。
💡
「食べると力が出るよ~」など肯定的な声掛けを。 - スプーンを使ってうまく食べ進められない時には、スプーンにおかずをのせて口まで運びやすくするなど必要に応じて援助し、少しずつ使って食べる喜びを感じられるようにする。
💡
ある保育者だと食べるということもあります。ゆるやかな担当制でも問題ありません。 - おまるに座ることを嫌がる子どももいるが、焦らず一人ひとりの様子に合わせて少しずつ興味が持てるように声をかけてく。
- 異年齢児と関わる際には安全面に特に注意し、他学年の職員ともよく連携をとるようにする。また、年長児などのダイナミックな動きに圧倒されて怖がらないよう、ゆったりした空間で楽しい雰囲気を作れるように配慮する。
- 排泄間隔に合わせ、子どもの状態を見ながら「おしっこ出たかな?」と声をかける。排泄した時は、「でたね」と言葉と行為をつなげていく。
- 着替えの時、場所、手順をいつも同じように合わせる。声掛けは「今から足を出すよ」「頭入れるよ」など、今の動作を伝えていく。
- 積極的に「あれは~だね」「美味しいね」等、話をし、子どもの気持ちを読んで共感を行う。また、子どもの興味がある遊びや手遊びを展開し、リアクションを引き出す。
ほいくのおまもりプラス
教育(遊び)
- トンネルくぐりなど探索活動の準備の際には、周囲に危険なものがないかよく注意して環境を整え、安全に遊びを進められるようにする。
- マットの上など安定しない場所は保育者が子どもの手を取り、転倒しないように配慮しておく。
- 紙を破って遊ぶ際には、手に擦り傷ができないよう柔らかい紙を準備する。
- 「ばあ」「はい」「ね」など簡単な言葉が繰り返し出てくる絵本を準備し、子どもが真似して発語しやすいようにする。
💡
「もこもこ」や「だっだぁー」や「ごぶごぶ ごぼごぼ」などおすすめですよ。 - 音楽に合わせて身体を動かしていれば、保育者も一緒に身体を揺らし、楽しい雰囲気が味わえるようにする。また必要に応じてスキンシップを取り、人と関わる楽しさを味わえるようにしていく。
💡
スキンシップは子どもが求めるだけとりましょう。抱き癖はつきません。抱っこなどのスキンシップを取った方が早く自立します。 - でこぼこ道や坂道等、散歩先でしっかり身体を動かして歩いたり、旬の柑橘系の果実に触れ香りを味わうなど、五感や体幹を刺激するような活動を取り入れる。また、風や天気、気温などから外へ出る時間を判断する。
- 室内の遊具や配置スペースを工夫し、確保する。室内の衛生管理を徹底し、なめ回しが起こらないように消毒をこまめに行う。
- 子どもがつもりになって遊べるよう、おもちゃや人形を必要分以上用意する。新鮮な気持ちでいられるように、時々おもちゃを交換する。
ほいくのおまもりプラス
健康、安全面で配慮すべき事項
- 上手に歩けるようになってくると走ることも楽しくなってくる時期。身体を動かして遊ぶ際には一人ひとりの発達も踏まえ、子ども同士がぶつかって転倒することのないよう注意する。
- まだまだ体温の調節が難しいため、戸外で遊ぶ際には長時間遊ぶことを控えるなど、体調管理の意識も持つ。
- 感染症なども流行りやすいため、少量の嘔吐でも甘く考えず、体調の変化を見落とさないように気をつける。
- 豆まきの際には誤って誤飲することがないよう、よく注意する。
ほいくのおまもりプラス
今月の製作・歌・絵本・手遊び・室内室外遊び
製作
- バレンタイン製作
- 画用紙de鬼製作
- 簡単ペンギン製作
この他、【冬の自然】や、【行事】の製作を『ちぎる、指で塗る、ビー玉で転がす』等、色々な素材と手法でご紹介!
歌
- うぐいす
- コンコンクシャンの うた
- かぜさんだって
絵本
- とっとこ とっとこ
- へっこぷっとたれた
- りんごがドスーン
手遊び
- トントントントンひげじいさん
- いとまき
- てんぐのはな
室内室外遊び
- PEテープで引っこ抜き
- しっぽつき鬼ごっこ
行事
- 誕生日会
- 避難訓練
- 身体測定
- 節分(豆まき)(2月3日)
- 建国記念日(2月11日)
- バレンタインデー(2月14日)
- 猫の日(2月22日)
- 天皇誕生日(2月23日)
食育
- スプーンやフォークに興味を持ち、使ってみようとする。
- 「いただきます」や「ごちそうさま」の言葉を真似したり自分なりのしぐさで表現する。
- 嫌いなものを嫌がって食べない時には、必要に応じて声をかけ、少しでも食べてみようとする。
- 豆まきに参加し、食材に興味を示す。
ほいくのおまもりプラス
異年齢保育
この項目はおまもりプラスで公開中!
職員間の連携
この項目はおまもりプラスで公開中!
地域と家庭との連携
- 日中の園での様子や家庭での状態などを共有し、家庭と共に成長を喜び分かち合う。
- 感染症が流行りやすいため、健康状態に気を付けて感染症予防の方法を家庭にも伝えていく。
- 冷え込む時期になることから厚着になりやすいので、調節しやすい衣服を用意してもらう。
長時間保育の配慮
この項目はおまもりプラスで公開中!
自己評価
- 豆まきに安全に参加し、雰囲気を楽しみ食材に興味を持つことができたか。
- 異年齢児と関わりを持ち、いろんな友達と関わることができたか。
- 食事の際には意欲的に食べ、時にはスプーンなどを使ってみることができたか。
- 戸外で過ごすことも喜び、機嫌よく遊ぶことができたか。
- つかまり立ちやハイハイをして探索遊びを楽しみ、存分に身体を動かすことができたか。
- 着替えや排泄の際には自分でやってみようとする気持ちを子どもが持てていたか。
ほいくのおまもりプラス
個人案はこちら♪
-

-
【2月】個人案の文例【0歳児】
続きを見る
↓その他の保育ネタ↓