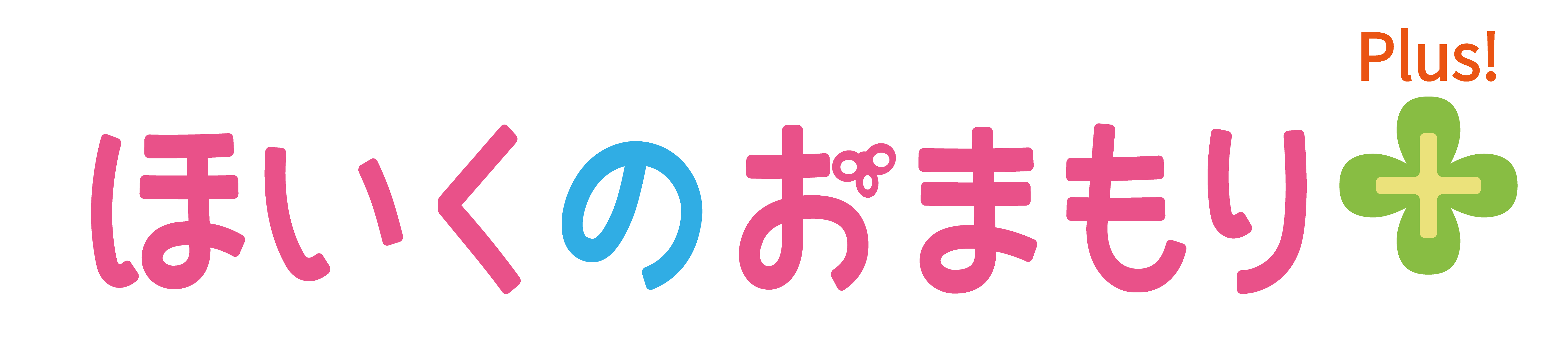もくじ
- 個人案PDF
- 敬称と性別表記について
- Aさん(高月齢/男児/活発) (1歳10カ月/4月生まれ)
- Bさん(高月齢/女児/活発) (1歳9カ月/5月生まれ)
- Cさん(高月齢/男児/静か) (1歳8カ月/6月生まれ)
- Dさん(高月齢/女児/静か) (1歳7カ月/7月生まれ)
- Eさん(中月齢/男児/活発) (1歳6カ月/8月生まれ)
- Fさん(中月齢/女児/活発) (1歳5カ月/9月生まれ)
- Gさん(中月齢/男児/静か) (1歳4カ月/10月生まれ)
- Hさん(中月齢/女児/静か) (1歳3カ月/11月生まれ)
- Iさん(低月齢/男児/活発) (1歳2カ月/12月生まれ)
- Jさん(低月齢/女児/活発) (1歳1カ月/1月生まれ)
- Kさん(低月齢/男児/静か) (1歳0カ月/2月生まれ)
- Lさん(低月齢/女児/静か) (0歳11カ月/3月生まれ)
- その他、ほいくのおまもりプラスのコンテンツ
個人案PDF
敬称と性別表記について
LGBTQ+の観点から、保育士が園児を表記する際は『くん』『ちゃん』を使わず、『さん』で統一、園児が自身を称する際や園児同士のやり取りを記載する場合は『ちゃん』で統一しています。また、発達段階の観点では性差はあると考えられるため、男児/女児としています。
Aさん(高月齢/男児/活発) (1歳10カ月/4月生まれ)
子どもの姿
- 便器に座ることはできるが、すぐに降りてしまい、排尿はなかった。(養護)
- 積み木やブロック遊びでは、友だちが近づいてくると玩具を取られると感じ、「だめ!」と怒る姿が見られた。(教育)
- 先月から徐々に鼻水の量が少なくなり、機嫌や食欲が戻ってきた。(家庭との連携)
ねらい/内容/環境構成・配慮・援助/評価・反省
養護
| 子どもの姿(再掲) | 便器に座ることはできるが、すぐに降りてしまい、排尿はなかった。(養護) |
| ねらい | 嫌がらずに便器に座る |
| 内容 | 保育者に誘われてトイレに行き、見守られる中で安心して便器に座る。 |
| 環境構成・配慮・援助 | リラックスして便器に座ることができるように、手をつないだり、一緒に数を数えたり、歌を歌いながら見守る。排尿しなくても、「トイレに座れたね」「また行こうね」と伝えて次につながるようにしたり、絵本を通じてトイレに興味を持てるようにする。 |
| 評価・反省 | 保育者や友だちと一緒に数を数えることを喜び、便器に座っていられる時間が延びた。排尿はないが、引き続き無理強いしないように配慮しながら見守る。 |
教育
| 子どもの姿(再掲) | 積み木やブロック遊びでは、友だちが近づいてくると玩具を取られると感じ、「だめ!」と怒る姿が見られた。(教育) |
| ねらい | 安心して好きな遊びを楽しむ |
| 内容 | 保育者と一緒に、積み木やブロック遊びを十分に楽しむ。 |
| 環境構成・配慮・援助 | 積み木やブロックの数を十分に用意し、個々に落ち着いて遊べる環境を整える。保育者も一緒に遊んで楽しさを共有し、本児が友だちの接近を気にするときは不安に寄り添い、「取らないから大丈夫だよ」と言葉をかけて安心感を得られるようにしたり、友だちと心地よく関わることができるように仲立ちする。 |
| 評価・反省 | 友だちの接近を気にする姿が徐々に減り、集中して遊べていた。安心して遊ぶ中では友だちと簡単なやり取りをする姿が見られたので、子ども同士の関わりを見守りながら仲立ちしていく。 |
食事
(幼児食)
- 日によって食欲にムラがあるので、食が進まないときは本児の様子を観察しながら必要に応じて介助し、体調不良や疲れ、眠気が見られるときは、完食にこだわらず切り上げる。
- 汁物を飲む際にお椀を傾けすぎてこぼすことがあるので、後ろからさりげなく手を支え、こぼさずに飲む感覚を味わえるように援助する。
家庭との連携
子どもの姿(再掲):先月から徐々に鼻水の量が少なくなり、機嫌や食欲が戻ってきた。
- 本調子に戻ってきたが、風邪をひきやすい季節が続くので、引き続き感染症の予防を呼びかけつつ、体調の変化が見られたときは情報を共有する。
- 靴や服のサイズが小さくなっていたら保護者に伝え、体に合い、自分で着脱しやすい素材の物を準備してもらえるようにする。
Bさん(高月齢/女児/活発) (1歳9カ月/5月生まれ)
子どもの姿
- オムツに排尿したことを言葉やしぐさで保育者に知らせたり、トイレで排尿できる回数が増えた。(養護)
- 気候が良く体調が良い日には、園庭に出て遊具や探索を楽しんだ。(教育)
- 咳と鼻水がひどく戸外へ出られなかった日は、低月齢児たちと室内で活動し、積極的に関わろうとする姿が見られた。(家庭との連携)
ねらい/内容/環境構成・配慮・援助/評価・反省
養護
| 子どもの姿(再掲) | オムツに排尿したことを言葉やしぐさで保育者に知らせたり、トイレで排尿できる回数が増えた。(養護) |
| ねらい | トイレで排尿する心地良さを感じる |
| 内容 | 保育者の声かけで尿意に気づいたり、オムツが濡れていないタイミングでトイレに行き、便器に座って排尿する。 |
| 環境構成・配慮・援助 | オムツが濡れていないタイミングや、尿意を感じているサインを見逃さず、「ちっちが出そうかな」「トイレに行ってみようか?」と誘い、尿意を感じられるように関わる。排尿できたときはその姿を大いに認め、排尿しなくても「トイレに座れたね、また行こうね」といった言葉がけを行い、次への意欲を育てる。 |
| 評価・反省 | 保育者の声かけだけではなく、食前や午睡明けなど、生活の流れの中でトイレに行くと排尿できる姿が増えた。「出た!」という本児の喜びに共感し、さらに自信を持てるように関わる。 |
教育
| 子どもの姿(再掲) | 気候が良く体調が良い日には、園庭に出て遊具や探索を楽しんだ。(教育) |
| ねらい | 全身を動かす心地よさを味わう |
| 内容 | 室内での運動遊びを通じて、のぼる、おりる、またぐ、バランスを取って歩くなど、様々な動きを楽しむ。 |
| 環境構成・配慮・援助 | 牛乳パックで手作りした低い台を利用し、一列に並べて一本橋を作ったり、間隔を開けて並べ、のぼりおりやまたぐ動きを楽しむことができるようにする。また、バランスを取って歩く面白さを味わえるように、マットの下にクッションなどを入れたでこぼこ道を用意し、他児との衝突や転倒に注意しながら見守る。 |
| 評価・反省 | マットのでこぼこ道では、バランスを崩しても手をついてすぐに立ち上がり、くり返し歩いて楽しんでいた。戸外遊びの機会が増えてくるので、遊具で遊んだり、土の上や砂利道など様々な場所で歩く経験ができるように計画し、運動機能の発達を促していく。 |
食事
(幼児食)
- スプーンを使ってほとんどこぼさずに食べる姿を見守る中で、さりげなく下握りができるように手を添える。
- 苦手な食材に手をつけようとしないときは、「先生と一緒に食べてみようか」「一緒にすくって食べようか」といった提案をして、本児が「食べてみようかな」と思えるきっかけを作る。
家庭との連携
子どもの姿(再掲):咳と鼻水がひどく戸外へ出られなかった日は、低月齢児たちと室内で活動し、積極的に関わろうとする姿が見られた。
- 低月齢児に対して優しく接する姿を通じて、本児の心身の成長を丁寧に伝えていく。
- 育児の悩みに対して、必要に応じて個別の面談の時間を設けて保護者の話をじっくりと聞き、不安を軽減できるように関わる。
Cさん(高月齢/男児/静か) (1歳8カ月/6月生まれ)
子どもの姿
- 保育者に励まされながら、自分でズボンや靴下を履いていた。(養護)
- 園庭で探索を楽しむ中で、年長児が見つけた氷に触れたり、テラスに降り込んだ雪に興味を示していた。(教育)
- 保育者と一緒に絵本を読む中で、簡単なくり返しの言葉をまねしていた。(家庭との連携)
ねらい/内容/環境構成・配慮・援助/評価・反省
養護
| 子どもの姿(再掲) | 保育者に励まされながら、自分でズボンや靴下を履いていた。(養護) |
| ねらい | 簡単な着脱を自分でしようとする |
| 内容 | 保育者に励まされたり見守られる中で、衣服や靴下、靴の着脱を行う。 |
| 環境構成・配慮・援助 | 着脱の際には時間に余裕を持たせ、本児なりに生活の流れを理解して自らやろうとする姿を焦らずに見守りつつ、難しい部分をさりげなく援助する。保育者にやってもらいたがるときは、その甘えを受け止めながら途中まで一緒に行い、最後の仕上げは本児自身で行えるように働きかけて、自信につなげる。 |
| 評価・反省 | 自分でやりたがらず怒る姿も見られたが、保育者に甘えを受け止めてもらうと落ち着き、最後に自分で仕上げができると満足そうだった。自分でできる部分を増やせるように、焦らずに関わっていく。 |
教育
| 子どもの姿(再掲) | 園庭で探索を楽しむ中で、年長児が見つけた氷に触れたり、テラスに降り込んだ雪に興味を示していた。(教育) |
| ねらい | 冬ならではの自然物に触れ、感触を味わう |
| 内容 | 園庭で探索を楽しむ中で、空気の冷たさを感じたり、霜柱や氷に触れる。 |
| 環境構成・配慮・援助 | 気候と体調に合わせて園庭に出て、寒さに負けずに探索を楽しむ中で、「寒いね」「風が冷たいね」といった言葉がけを行い、冬の空気の冷たさに気づくことができるようにする。また、氷や霜柱などの自然物に興味を持って触れる姿を見守り、「硬いね」「冷たいね」と本児が感じる面白さや不思議さに共感し、興味を育む。 |
| 評価・反省 | 寒さが厳しく戸外に出られた日は少なかったが、園庭やテラスで、雪や氷の感触を味わうことができた。来月は積極的に戸外へ出て探索を楽しみ、自然物に対する興味がさらに高まるようにする。 |
食事
(幼児食)
- 落ち着いてスプーンを使って食べているので、バランスよく食べ進められるように、「この野菜もすくえるかな?」とさりげなく声をかける。
- 同じ机で食べている友だちがふざけて遊び始めるとまねしてしまう姿が増えてきたため、食事に集中できるように食事の席を変更し、様子を見る。
家庭との連携
子どもの姿(再掲):保育者と一緒に絵本を読む中で、簡単なくり返しの言葉をまねしていた。
- 絵本の中で気に入っているフレーズを保護者の前で一緒に披露し、本児が楽しさと喜びを保護者と共有できるようにする。
- 着脱に取り組む本児の姿を共有し、成長を感じてもらうとともに、家庭でも時間に余裕のあるときに、自分で着脱に挑戦する機会を作ってもらえるようにする。
Dさん(高月齢/女児/静か) (1歳7カ月/7月生まれ)
子どもの姿
- 靴下を脱ぐことを面白がり、戸外から帰ってくると自分で引っ張り、脱ごうとしていた。(養護)
- リズム遊びを楽しみ、立ち上がって自分なりに体を動かして参加していた。(教育)
- 好きな絵本を保育者の所へ持って行って差し出し、「読んで」と自分なりに伝えようとしていた。(家庭との連携)
ねらい/内容/環境構成・配慮・援助/評価・反省
養護
| 子どもの姿(再掲) | 靴下を脱ぐことを面白がり、戸外から帰ってくると自分で引っ張り、脱ごうとしていた。(養護) |
| ねらい | 簡単な身の回りのことを自分でしようとする |
| 内容 | 保育者に見守られたり手伝ってもらいながら、靴や靴下を脱いで片づける。 |
| 環境構成・配慮・援助 | 自分で脱ごうとする姿を大切にしながら見守る中で、難しい部分はさりげなく援助し、「できた!」という感覚を味わえるように関わる。また、脱いだ物を片づける場所がわかりやすいように、靴箱やロッカーに本児のマークなどわかりやすい目印を貼り、「靴はここにしまおうね」「靴下はここに入れようね」と丁寧に伝え、最後は「お片付けができたね」と自信につながる言葉がけをする。 |
| 評価・反省 | 靴や靴下を脱いだあとは、自分で片づけることが習慣づいてきた。本児ができるようになった部分を見逃さず、大いに認めながら意欲を育てていく。 |
教育
| 子どもの姿(再掲) | リズム遊びを楽しみ、立ち上がって自分なりに体を動かして参加していた。(教育) |
| ねらい | 歌やリズムに合わせて体を動かす楽しさを感じる |
| 内容 | リズム遊びや手遊びを楽しむ中で、自分なりに体を動かしたり、保育者の動きをまねする。 |
| 環境構成・配慮・援助 | 動きをまねしやすいように、見本となる保育者は大きくわかりやすく体を動かす。援助を担当する保育者は、転倒や他児との衝突を防ぎながら見守るとともに、「楽しいね」「まねっこできたね」など、体を動かす楽しさを言葉にして伝えながら共感する。 |
| 評価・反省 | 「あたま・かた・ひざ・ポン」などの歌に合わせて、自分なりに保育者の動きをまねようとして楽しんでいた。今月は室内で十分に体を動かして楽しむことができたので、来月は気候や体調に合わせながら戸外に出る機会を増やしたい。 |
食事
(完了食)
- 最初のうちは自分から手を出すが、徐々に飽きて意識が逸れてしまうため、「次はどれを食べる?」「おいしそうだね」と言葉をかけ、食事に意識を戻せるように関わる。
- 小さく切った肉は口に残らず飲み込めるようになってきたので、引き続き咀嚼の様子を観察しながら食材の大きさを調整していく。
家庭との連携
子どもの姿(再掲):好きな絵本を保育者の所へ持って行って差し出し、「読んで」と自分なりに伝えようとしていた。
- 本児の思いを汲み取れない瞬間があるという保護者の悩みに寄り添い、園で見られる本児なりの表現の仕方や、それに対する保育者の応答的な言葉がけや対応を伝え、家庭での関わり方の参考になるようにする。
- 気候の良い日は体調に合わせて園庭やテラスに出て遊べるように、靴や防寒具を忘れずに持ってきてもらうように伝える。
Eさん(中月齢/男児/活発) (1歳6カ月/8月生まれ)
子どもの姿
- 眠りが浅く、物音などに敏感に反応して目を覚まし、再入眠できない日があった。(養護)
- 戸外に出られない日は、室内遊びに飽きると走り出したり、棚や机にのぼろうとする姿が見られた。(教育)
- 散歩の際にショベルカーや救急車などの乗り物を発見すると、指を差しながら声を出して喜んでいた。(家庭との連携)
ねらい/内容/環境構成・配慮・援助/評価・反省
養護
| 子どもの姿(再掲) | 眠りが浅く、物音などに敏感に反応して目を覚まし、再入眠できない日があった。(養護) |
| ねらい | 心地よく一定時間眠る |
| 内容 | 午睡の途中で目が覚めてしまったときには、保育者にトントンしてもらい、心地よく再入眠する。 |
| 環境構成・配慮・援助 | 物音などで目覚めたときは「びっくりしたね」と落ち着いて伝え、リラックスして再入眠できるように優しく体をトントンする。眠れない場合は、保育者と絵本を読むなど静かに過ごせるように対応し、睡眠時間について夕方の職員に申し送りを行い、必要に応じて夕方にも眠れるように配慮する。 |
| 評価・反省 | 再入眠できずに睡眠時間が少なくても、夕方に眠くなる日は少なかった。来月は戸外での活動が増えてくるため、本児の様子に合わせて十分に休息を取ることができるよう配慮する。 |
教育
| 子どもの姿(再掲) | 戸外に出られない日は、室内遊びに飽きると走り出したり、棚や机にのぼろうとする姿が見られた。(教育) |
| ねらい | 十分に体を動かして遊ぶ楽しさを味わう |
| 内容 | 運動遊びを通じて、のぼる、くぐる、またぐ、飛びおりるなどの動きを十分に楽しむ。 |
| 環境構成・配慮・援助 | 室内でも体を動かす欲求を十分に満たせるように、高月齢児と一緒に運動遊びを楽しめる環境を整える。広いスペースにすべり台や巧技台、トンネル、マットの山などの遊具を配置し、保育者も一緒に遊びながら順番や安全な遊び方を示したり、のびのびと体を動かして遊ぶ姿を見守る中で、楽しさに共感する言葉がけを行う。 |
| 評価・反省 | 運動遊びを通じて、よじのぼったり低い台から飛びおりるなどの動きを十分に楽しむと、その後はパズルなどの静的な活動にも集中していた。「動きたい」という欲求が強い本児の様子に合わせながら、動と静の活動をバランスよく楽しめるように関わっていきたい。 |
食事
(幼児食)
- よく噛まずに飲み込もうとするときは、「カミカミしようね」と伝えて保育者の口元を見せ、まねできたときは大いにほめる。
- 好きなおかずを食べ切ってしまうと遊び始める姿が見られるので、食事に意識を戻せるように、スプーンに食材を乗せて「どうぞ」と手元に置いたり、「次はどれにしようかな」と声をかける。
家庭との連携
子どもの姿(再掲):散歩の際にショベルカーや救急車などの乗り物を発見すると、指を差しながら声を出して喜んでいた。
- 本児の興味を把握して保護者と共有し、家庭での会話のきっかけとなるようにする。
- 活発に体を動かす中でケガも増えてくるため、小さな傷でも園と家庭で伝え合うことで、不安やトラブルを減らしていく。
Fさん(中月齢/女児/活発) (1歳5カ月/9月生まれ)
子どもの姿
- トイレでの排尿はないが、便器に座ることに意欲的だった。(養護)
- タライに集めた雪に興味を持ってすぐに触り、冷たさに驚きながらも、手のひらやスコップで叩いて楽しんでいた。(教育)
- 同じ遊びを楽しむ友だちと、玩具のやり取りをする姿が見られた。(家庭との連携)
ねらい/内容/環境構成・配慮・援助/評価・反省
養護
| 子どもの姿(再掲) | トイレでの排尿はないが、便器に座ることに意欲的だった。(養護) |
| ねらい | 便器に座って排尿しようとする |
| 内容 | オムツが濡れていないタイミングでトイレに行き、保育者に見守られながら便器に座る。 |
| 環境構成・配慮・援助 | 本児の排尿間隔を把握してトイレに誘い、進んで便器に座ろうとする姿を見逃さず、「座れたね」「ちっちが出るといいね」と言葉をかけながら意欲を育む。タイミング良く排尿できたときは本児の驚きや喜びに共感し、「ちっちが出たね」「すっきりしたね」と心地よさを言葉にして伝え、次へとつなげていく。 |
| 評価・反省 | 午睡明けにオムツが濡れていない日が増えてきた中で、タイミングが合い排尿できた。本児の喜びに共感しながら、引き続き意欲を育てていく。 |
教育
| 子どもの姿(再掲) | タライに集めた雪に興味を持ってすぐに触り、冷たさに驚きながらも、手のひらやスコップで叩いて楽しんでいた。(教育) |
| ねらい | 冬の自然に親しみ、様々な感触を味わう |
| 内容 | 保育者と一緒に雪や氷、霜柱などの自然物を発見し、興味を持って触れる。 |
| 環境構成・配慮・援助 | 気候の良い日は、体が冷えないように時間を調整しながら園庭に出て、冷たい空気を感じたり、氷や霜柱など、冬の自然に触れられる機会を作る。また、雪や氷の感触を十分に楽しめるように室内に持ち込み、一緒に触りながら「硬いね」「冷たいね」と言葉をかけることで、本児の興味や好奇心を刺激していく。 |
| 評価・反省 | 室内での雪遊びを喜び、保育者と一緒に雪を握って溶かしたり、雪玉を崩して感触を楽しんでいた。来月は積極的に戸外に出て、さらに自然物に対する興味が育つように関わりたい。 |
食事
(幼児食)
- こぼしながらも自分で食べる姿を大切にしながら見守り、必要に応じてさりげなく援助する。
- 自分の皿が空になると隣の友だちの皿に手を伸ばす姿が見られるため、食器の位置や食べる場所に配慮しつつ、皿が空になったときは「ごちそうさまかな?おかわりかな?」と本児に問いかけ、思いを受け止めながら対応する。
家庭との連携
子どもの姿(再掲):同じ遊びを楽しむ友だちと、玩具のやり取りをする姿が見られた。
- 本児なりの言葉やしぐさで友だちと関わろうとする姿を共有し、成長を感じてもらえるようにする。
- 体調を崩しやすく、感染症も流行しやすい時期なので、疲れや体調の変化が見られたときは情報を共有し、十分に休息を取りながら健康に過ごせるようにする。
Gさん(中月齢/男児/静か) (1歳4カ月/10月生まれ)
子どもの姿
- 手洗いをしたあとに拭くことを忘れて、濡れたまま戻ろうとしていた。(養護)
- 戸外では動きが少なく、砂遊びを楽しむ姿が多かったが、室内ではよく歩いて探索し、気に入った玩具を持って移動していた。(教育)
- オムツ交換の際は、必ず便器に座りたがっていた。(家庭との連携)
ねらい/内容/環境構成・配慮・援助/評価・反省
養護
| 子どもの姿(再掲) | 手洗いをしたあとに拭くことを忘れて、濡れたまま戻ろうとしていた。(養護) |
| ねらい | 清潔にする心地よさを感じる |
| 内容 | 保育者と一緒に丁寧に手洗いを行い、きれいになった心地よさを感じながら次の活動に移る。 |
| 環境構成・配慮・援助 | 手洗いの際は必ず保育者が側で見守り、必要に応じて手を添えて援助したり、隣で一緒に洗いながらやり方を示す。最後に「タオルで拭こうね」と声をかけ、拭き上げながら「さっぱりしたね」「きれいに拭けたね」と伝えることで、心地よさを感じながら手洗いの順序が身につくようにする。 |
| 評価・反省 | 最後に手を拭く習慣が少しずつ身についてきた。まだまだ一人ではうまくできずに援助が必要な部分が多いため、見守りながら丁寧に関わりたい。 |
教育
| 子どもの姿(再掲) | 戸外では動きが少なく、砂遊びを楽しむ姿が多かったが、室内ではよく歩いて探索し、気に入った玩具を持って移動していた。(教育) |
| ねらい | 体を動かして遊ぶ楽しさを味わう |
| 内容 | 保育者や友だちと一緒に、室内でのぼる、おりる、くぐるなど様々な動きを楽しむ。 |
| 環境構成・配慮・援助 | 安全に運動遊びを楽しめるように、トンネルやマットの山、巧技台、すべり台などを、十分な間隔を空けて設置する。職員間で連携しながら危険のないように見守るとともに、トンネルや山の先で待ち構えながら「こっちまで来られるかな」と誘ったり、保育者自身が様々な動きを見せることで、楽しさを共有しながら体を動かす楽しさを味わえるように関わる。 |
| 評価・反省 | 保育者の動きをまねしながら、本児のペースで運動遊びを楽しんでいた。歩行も安定してきたので、暖かくなってきたら積極的に戸外へ出かけ、探索や体を動かす遊びを楽しめるようにしたい。 |
食事
(完了食)
- 汁物にスプーンを入れて遊び始めたときは、「こぼれるからやめようね」と簡潔に伝えて止め、「こうやって飲もうね」と保育者がお椀を持って飲む姿を見せ、本児が興味を持ったら手を添えて援助する。
- スプーンで食材をすくえるようになってきた姿を見守り、「自分で食べられたね」とさりげなく声をかけることで自信につなげる。
家庭との連携
子どもの姿(再掲):オムツ交換の際は、必ず便器に座りたがっていた。
- 排尿はまだないものの、トイレに興味を持っている姿を保護者に伝え、家庭でもトイレに親しむきっかけを作るようにする。
- お迎えに来る人や時間が連絡なく変更となり、引き渡しに時間がかかった家庭があったため、子どもの安全を確保するために、必ず事前に連絡をしてもらえるように再度周知し、協力をお願いする。
Hさん(中月齢/女児/静か) (1歳3カ月/11月生まれ)
子どもの姿
- 午睡の途中で目を覚まして起き上がったり泣くこともあるが、保育者にトントンしてもらうと再入眠できた。(養護)
- タライに集めた雪に興味を持っていたが、自分からはなかなか手を出さず、保育者や友だちが触っているのをじっと見ていた。(教育)
- わらべうたあそびを楽しみ、本児なりのしぐさや表情で「もう一回」と要求し、くり返し楽しんでいた。(家庭との連携)
ねらい/内容/環境構成・配慮・援助/評価・反省
養護
| 子どもの姿(再掲) | 午睡の途中で目を覚まして起き上がったり泣くこともあるが、保育者にトントンしてもらうと再入眠できた。(養護) |
| ねらい | 保育者に見守られながら安心して眠る |
| 内容 | 途中で起きてしまったときは、保育者の姿を見たりトントンしてもらい、安心して再入眠する。 |
| 環境構成・配慮・援助 | 本児が目を覚ましたときにすぐに対応できるように、午睡を見守る保育者は近くにいるようにする。本児が目を覚ましたときは、「目が覚めちゃったんだね」「もう一回ねんねしようね」と安心できる声かけをしながら、手を握ったり額や耳を優しくなでて、心地よく再入眠できるように対応する。 |
| 評価・反省 | 目覚めたときに保育者が視界に入ると安心し、自ら目を閉じて再入眠できることが増えた。泣いてしまうときは抱っこをするなど、応答的に関わり、安心感を得られるようにする。 |
教育
| 子どもの姿(再掲) | タライに集めた雪に興味を持っていたが、自分からはなかなか手を出さず、保育者や友だちが触っているのをじっと見ていた。(教育) |
| ねらい | 冬の自然に興味を持ち、感触を味わう |
| 内容 | 空気の冷たさを肌で感じたり、雪や氷を見たり触ったりして、感触の面白さや不思議さを感じる。 |
| 環境構成・配慮・援助 | 戸外に出られる日が減る季節なので、窓を開けたりテラスに出ることで冬の冷たい空気を感じられるようにしたり、室内でも雪や氷に触れられる機会を作る。雪や氷をタライやバケツに集め、保育者が触って見せながら「ふわふわだよ」「硬くて冷たいよ」など感触の面白さや不思議さを言葉で伝え、本児が興味を持ち自ら触れられるようにする。 |
| 評価・反省 | 保育者が小さな雪玉を作って並べると、興味を持って手を伸ばし、指先で触れることができた。新しい物を警戒して自ら手を出さない姿が多い本児だが、今後も無理強いして関わらせるのではなく、安心して好奇心を満たせる環境を整えながら根気よく見守りたい。 |
食事
(完了食)
- 好き嫌いが出てきたため、無理なく食べ進められるように、苦手な食材は小さくしたり、好きな物と交互に食べられるように援助する。
- 本児なりにスプーンを使おうとする姿を見守り、保育者が食べて見せたり、さりげなく手を添えて援助しながら意欲を育てる。
家庭との連携
子どもの姿(再掲):わらべうたあそびを楽しみ、本児なりのしぐさや表情で「もう一回」と要求し、くり返し楽しんでいた。
- 気に入っているわらべうたあそびを家庭でも楽しめるように、お迎えの際に実際にやって見せながら紹介する。
- お迎えの時間が遅くなる日は夕方にも眠れるように配慮し、園と家庭で連携しながら生活リズムの乱れを防ぐ。
Iさん(低月齢/男児/活発) (1歳2カ月/12月生まれ)
子どもの姿
- オムツ交換の際に保育者と一緒にオムツやズボンを履き、ほめられると喜んでいた。(養護)
- 一人歩きが安定してきたが、まだ転倒することも多かった。(教育)
- 様々な場面で自己主張が激しくなり、登園時に保護者と離れることを嫌がって泣く日が増えた。(家庭との連携)
ねらい/内容/環境構成・配慮・援助/評価・反省
養護
| 子どもの姿(再掲) | オムツ交換の際に保育者と一緒にオムツやズボンを履き、ほめられると喜んでいた。(養護) |
| ねらい | 保育者と一緒に簡単な着脱をやってみようとする |
| 内容 | 保育者に見守られたり手伝ってもらいながらズボンを履く。 |
| 環境構成・配慮・援助 | オムツ交換や着替えを行う際は時間に余裕を持たせ、本児なりに体を動かして着脱に参加する姿を大いに認め、意欲を育てる。最後にズボンを上げる部分を自分でできるように、手を添えながら「ぎゅっと上げるよ」とわかりやすく伝えたり、難しそうなときにはさりげなく援助することで、「自分でできた!」という感覚を味わえるようにする。 |
| 評価・反省 | 「ぎゅー」と言いながら意欲的にズボンを上げようとし、上がったことがわかると保育者の顔を見て喜んでいた。自分でできる部分を増やせるように、保育者が手を出し過ぎないように配慮しながら関わる。 |
教育
| 子どもの姿(再掲) | 一人歩きが安定してきたが、まだ転倒することも多かった。(教育) |
| ねらい | 体を動かす楽しさを味わう |
| 内容 | 室内でハイハイや高ばい、歩行など、様々な体の動きを楽しむ。 |
| 環境構成・配慮・援助 | 室内で過ごすことが多くなる時期なので、十分に体を動かしたり一人歩きを楽しむことができるように、広く安全なスペースを整えておく。また、小さな段差やトンネル、人工芝や緩衝材を利用した様々な手触りのシートを配置し、好奇心を満たしながらハイハイや歩行を楽しむことができる環境を作る。 |
| 評価・反省 | 異素材のシートに興味を持ち、感触に慣れてくると何度もハイハイしたり、保育者と手をつなぎながらシートの上を歩いて楽しんでいた。室内での一人歩きも安定してきたので、来月は戸外で歩く機会を増やしたい。 |
食事
(完了食)
- 本児なりにスプーンを使おうとする姿を見逃さず、すくいにくそうなときはさりげなく手を添える。
- 汁物やお茶を飲むときにこぼしやすいため、お椀やコップを持つ本児の手を後ろから支え、こぼさずに飲めるように援助する。
家庭との連携
子どもの姿(再掲):様々な場面で自己主張が激しくなり、登園時に保護者と離れることを嫌がって泣く日が増えた。
- 「ママがいいね」と本児の気持ちを受け止め、好きな絵本や玩具を見せたり手遊びに誘うことで気持ちを切り替えやすいように援助するとともに、お迎えの際にはその後の様子を伝えて、保護者の不安を減らせるように関わる。
- 自分で着脱しやすい衣服を準備してもらい、園と家庭で連携しながら本児の意欲を育てていく。
Jさん(低月齢/女児/活発) (1歳1カ月/1月生まれ)
子どもの姿
- 午睡の際は、保育者にトントンしてもらいながら落ち着いて眠れるようになったが、短時間で目覚めることが多かった。(養護)
- 保育者と一緒にペンギン歩きや支え歩きを楽しみ、一人で1~2歩ほど歩くこともできた。(教育)
- ぽっとん落としで遊ぶ中で、物が入ると手を叩いたり、保育者の顔を見て喜んでいた。(家庭との連携)
ねらい/内容/環境構成・配慮・援助/評価・反省
養護
| 子どもの姿(再掲) | 午睡の際は、保育者にトントンしてもらいながら落ち着いて眠れるようになったが、短時間で目覚めることが多かった。(養護) |
| ねらい | 安心して一定時間眠る |
| 内容 | 保育者に見守られながら入眠し、途中で起きたときは、抱っこしてもらったりトントンしてもらい再入眠する。 |
| 環境構成・配慮・援助 | 午睡に誘う際は「一緒にねんねのお部屋に行こうね」と伝え、本児が見通しを持って行動できるように関わるとともに、優しく体をさすったり子守唄を歌い、自分の布団で心地よく入眠できるように援助する。午睡の途中で起きてしまったときは、静かに側に付いてトントンしたり、泣いてしまうときは抱っこをするなど、安心して再入眠できるように、本児の様子に合わせて対応する。 |
| 評価・反省 | 短時間で目が覚めてしまっても、再入眠できる日が増えてきた。本児の様子に合わせながら、十分に休息を取ることができるように援助する。 |
教育
| 子どもの姿(再掲) | 保育者と一緒にペンギン歩きや支え歩きを楽しみ、一人で1~2歩ほど歩くこともできた。(教育) |
| ねらい | 保育者に見守られながら歩行を楽しむ |
| 内容 | 大箱や手押し車につかまりながら歩いたり、一人歩きを楽しむ。 |
| 環境構成・配慮・援助 | 床に玩具が散乱しないように注意し、安全に大箱や手押し車を押したり、一人歩きができる環境を整える。他児との衝突や転倒によるケガを防ぎながら見守り、「歩くの楽しいね」と言葉をかけることで、本児の楽しさや喜びに共感する。 |
| 評価・反省 | 活発に一人歩きを楽しみ、倒れながらも歩ける歩数が増えてきた。室内でも戸外でも安全に歩行を楽しめるように、職員間で連携して環境を整えながら見守っていく。 |
食事
(完了食)
- 意欲的に食べているが、口に詰め込み過ぎる姿も見られるため、スプーンに一口分をすくって手渡したり、「もぐもぐだよ」と口元を見せながら伝える。
- 苦手な食材は、好きな食材と交互に食べられるように保育者が介助し、「野菜も食べられたね」「交代で食べられるね」と声をかけつつ、バランスよく食べ進められるようにする。
家庭との連携
子どもの姿(再掲):ぽっとん落としで遊ぶ中で、物が入ると手を叩いたり、保育者の顔を見て喜んでいた。
- 気に入っている玩具や遊び、活動の際の様子を詳しく伝え、園での姿をより具体的に想像できるようにする。
- 室内で一人歩きを楽しむ姿を観察し、様子を見ながら戸外でも歩行を楽しめるように、足に合った歩きやすい靴を準備してもらう。
Kさん(低月齢/男児/静か) (1歳0カ月/2月生まれ)
子どもの姿
- オムツ交換に誘われると、対応する保育者によっては嫌がる姿が見られた。(養護)
- 様々な場所でつかまり立ちをするようになった。(教育)
- 保育者と一緒に、室内から雨や雪が降る様子を見たり、年長児が見せに来てくれた雪だるまや氷に興味を示して触れていた。(家庭との連携)
ねらい/内容/環境構成・配慮・援助/評価・反省
養護
| 子どもの姿(再掲) | オムツ交換に誘われると、対応する保育者によっては嫌がる姿が見られた。(養護) |
| ねらい | 安心してトイレに行こうとする |
| 内容 | 信頼する保育者と一緒にトイレに行き、オムツを交換してもらうことで、清潔にしてもらう心地よさを感じる。 |
| 環境構成・配慮・援助 | 職員間で連携し、本児の思いを受け止めながら柔軟に対応するとともに、担任以外の保育者と本児が信頼関係を深めていけるように、関わる機会を増やす。一緒に遊ぶ中でさりげなくトイレに誘い、オムツ交換の際にはわらべうたあそびを交え、心地よさを感じられるように関わったり、「すっきりしたね、また一緒にトイレに行こうね」と伝えて意欲を育てる。 |
| 評価・反省 | 一緒に遊んでいる保育者であれば、嫌がらずにオムツ交換に応じる姿が増えてきた。まだ人見知りや甘えが出て担任を求める姿も見られるため、焦らずに気持ちを受け止めながら柔軟に対応する。 |
教育
| 子どもの姿(再掲) | 様々な場所でつかまり立ちをするようになった。(教育) |
| ねらい | 体を動かす楽しさを味わう |
| 内容 | 保育者に見守られながら、ハイハイやつかまり立ちを十分に楽しむ。 |
| 環境構成・配慮・援助 | 十分にハイハイを楽しめるよう、広いスペースにマットの山や段ボールのトンネルを配置したり、目線の高さに玩具を設置してつかまり立ちを促し、「立っちができたね」と本児の楽しさや喜びに共感する。棚やベビーゲートに危険な箇所がないか点検し、安全につかまり立ちを楽しめる環境を整える。 |
| 評価・反省 | つかまり立ちから、伝い歩きをするようになった。引き続き安全に配慮するとともに、歩く楽しさに共感する言葉がけをしながら見守る。 |
食事
(後期食)食後ミルク80cc
- スプーンを片手に握りながら手づかみ食べをしているので、様子を見ながら本児の後ろから手を添え、スプーンを使って食べられるように援助する。
- 自分で食べようとする姿を大切にし、「たくさん食べられるようになったね」と本児の姿を認めて意欲を育てつつ、時間がかかりそうな場合はさりげなく介助する。
家庭との連携
子どもの姿(再掲):保育者と一緒に、室内から雨や雪が降る様子を見たり、年長児が見せに来てくれた雪だるまや氷に興味を示して触れていた。
- 活動の中での本児の様子を伝え、自然に対する興味や好奇心を大切に育てていけるようにする。
- 寒さから体調を崩しやすい時期なので、登園時に必ず体調を確認し、無理なく活動に参加できるよう個別に配慮する。
Lさん(低月齢/女児/静か) (0歳11カ月/3月生まれ)
子どもの姿
- 午睡の際に途中で目覚めることが減ってきた。(養護)
- 気になる玩具や物を見つけると、手を伸ばしたり指を差して伝えようとしていた。(教育)
- 保育者と一緒にハイハイしたり、追いかけられることを喜んでいた。(家庭との連携)
ねらい/内容/環境構成・配慮・援助/評価・反省
養護
| 子どもの姿(再掲) | 午睡の際に途中で目覚めることが減ってきた。(養護) |
| ねらい | 安心して一定時間眠る |
| 内容 | 快適な環境で眠り、目が覚めたときは保育者にトントンしてもらいながら、安心して再入眠する。 |
| 環境構成・配慮・援助 | 室温や湿度を適切に保つことで心地よく入眠できる環境を整えるとともに、「お昼寝をしようね」と言葉をかけながら午睡に誘い、生活の見通しを持って自ら布団に向かえるように促す。午睡の途中で目が覚めたときは、優しく体をさすったりトントンし、心地よく再入眠できるように援助する。 |
| 評価・反省 | 他児の泣き声や戸外からの音などで目が覚めてしまうこともあったが、足の裏を握って温めると再入眠しやすかった。日中の運動量も増えているため、十分に休息を取ることができる環境を整える。 |
教育
| 子どもの姿(再掲) | 気になる玩具や物を見つけると、手を伸ばしたり指を差して伝えようとしていた。(教育) |
| ねらい | 自分なりに表現した思いや要求が伝わる喜びを感じる |
| 内容 | 自分なりの発声や指差しで思いを表現し、保育者に受け止めてもらう。 |
| 環境構成・配慮・援助 | 遊びや生活の中で本児の発声や目線、指差しを見逃さず、「おいしそうな給食だね」「電車が来たね」「ワンワンがいるね」などと丁寧に言葉にして返し、思いが伝わる喜びを感じられるように関わる。また、室内での活動が多くなる時期なので、本児が興味を持つような玩具や素材を用意し、好奇心が刺激される環境を整える。 |
| 評価・反省 | 指差しや喃語に保育者が応えると、目を合わせ、満足そうな様子だった。「○○したいんだね」「○○を見つけたんだね」と言葉にして返しながら受け止め、他者とやり取りする楽しさを味わえるように関わっていく。 |
食事
(後期食)食後ミルク100cc
- 好き嫌いが変わりやすいため、食材に興味を持てるように「これはニンジンだよ」と名前を伝えたり、保育者がおいしそうに食べて見せる。
- 手づかみへの意欲や遊び食べをする好奇心を受け止め、テンポよく食べ進められるように介助するとともに、食べられた瞬間を見逃さずに大いに認めて意欲を育てていく。
家庭との連携
子どもの姿(再掲):保育者と一緒にハイハイしたり、追いかけられることを喜んでいた。
- 高ばいやつかまり立ちなど、本児ができるようになったことやもうすぐできそうなことをこまめに共有し、ケガを防ぎながら関わることができるようにする。
- 家庭では離乳食を嫌がって食べる量が少ないという悩みが続いているため、保護者の不安に寄り添いながら話を聞き、共に見守りながら不安を解消していけるように関わる。
その他、ほいくのおまもりプラスのコンテンツ