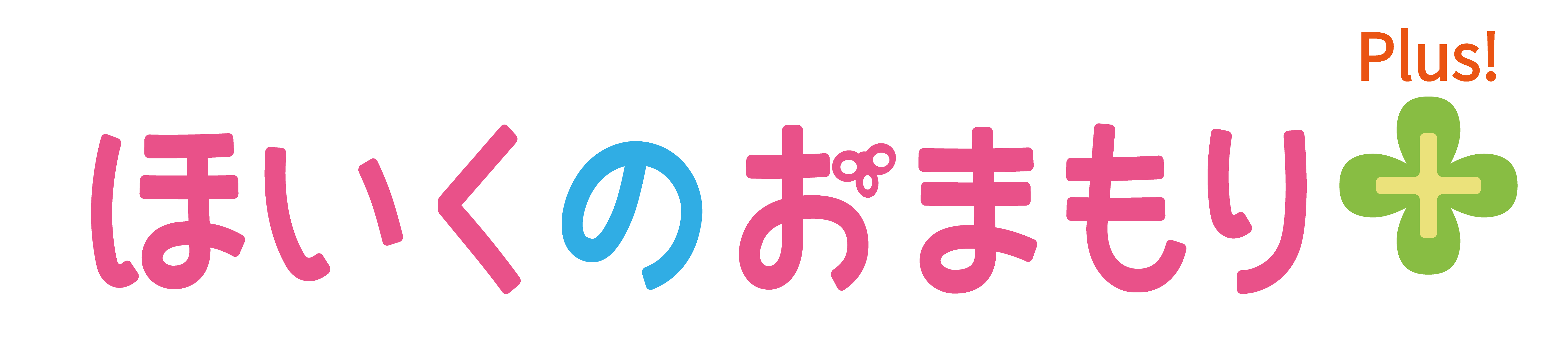もくじ
- 個人案PDF
- 敬称と性別表記について
- Aさん(高月齢/男児/活発)(1歳6カ月/4月生まれ)
- Bさん(高月齢/女児/活発)(1歳5カ月/5月生まれ)
- Cさん(高月齢/男児/静か)(1歳4カ月/6月生まれ)
- Dさん(高月齢/女児/静か)(1歳3カ月/7月生まれ)
- Eさん(中月齢/男児/活発)(1歳2カ月/8月生まれ)
- Fさん(中月齢/女児/活発)(1歳1カ月/9月生まれ)
- Gさん(中月齢/男児/静か)(1歳0カ月/10月生まれ)
- Hさん(中月齢/女児/静か)(0歳11カ月/11月生まれ)
- Iさん(低月齢/男児/活発)(0歳10カ月/12月生まれ)
- Jさん(低月齢/女児/活発)(0歳9カ月/1月生まれ)
- Kさん(低月齢/男児/静か)(0歳8カ月/2月生まれ)
- Lさん(低月齢/女児/静か)(0歳7カ月/3月生まれ)
- その他、ほいくのおまもりプラスのコンテンツ
個人案PDF
敬称と性別表記について
LGBTQ+の観点から、保育士が園児を表記する際は『くん』『ちゃん』を使わず、『さん』で統一、園児が自身を称する際や園児同士のやり取りを記載する場合は『ちゃん』で統一しています。また、発達段階の観点では性差はあると考えられるため、男児/女児としています。
Aさん(高月齢/男児/活発)(1歳6カ月/4月生まれ)
子どもの姿
- 午睡時には自ら布団に向かう姿が見られるが、決まった保育者以外にトントンされることを嫌がり、怒る様子が見られた。(養護)
- 気に入った絵本をくり返し読んでもらいながら、声を出して指差しをしたり、言葉をまねて楽しんでいた。(教育)
- 延長保育が始まり、部屋の移動や関わりの少ない保育者の存在に不安な様子も見られたが、保育者に遊びに誘われると興味を示し、安心して玩具で遊び始める姿があった。(家庭との連携)
ねらい/内容/環境構成・配慮・援助/評価・反省
養護
| 子どもの姿(再掲) | 午睡時には自ら布団に向かう姿が見られるが、決まった保育者以外にトントンされることを嫌がり、怒る様子が見られた。(養護) |
| ねらい | 安定した生活リズムの中で、安心して休息を取る |
| 内容 | 食後の満足感を味わいながら布団に向かい、保育者に見守られる中で、心地よく入眠する。 |
| 環境構成・配慮・援助 | 食後に午睡に誘う際は、「たくさん食べたね」「おいしかったね」と優しく声をかけることで、満足感を味わいながら布団へ向かえるように関わる。入眠の援助は、できるだけ決まった保育者が安定して行えるよう職員間で連携し、本児が落ち着いて眠れる環境を整える。 |
| 評価・反省 | 決まった保育者に見守られることで安心し、トントンしてもらわずに自分で入眠できる日も増えた。今後も安心感を育む関わりを続けながら、様子を見守っていく。 |
教育
| 子どもの姿(再掲) | 気に入った絵本をくり返し読んでもらいながら、声を出して指差しをしたり、言葉をまねて楽しんでいた。(教育) |
| ねらい | 簡単な言葉を使いながら、保育者とのやり取りを楽しむ |
| 内容 | 絵本を読んでもらいながら、簡単な言葉をまねたり、指差しで表現する発見や思いを丁寧に受け止めてもらい、伝わる喜びを味わう。 |
| 環境構成・配慮・援助 | 落ち着いた雰囲気の中で、一対一で絵本を楽しみ、簡単なくり返しの言葉をまねしようとする姿を温かく受け止め、楽しさを共有する。また、指差しや本児なりの言葉で思いを表現しようとする姿には、「そうだね、○○がいるね」「笑っているね」などと丁寧に言葉を添えて応じ、やり取りの楽しさを感じられるように関わる。 |
| 評価・反省 | 絵本の中で知っているものを見つけると、指差しをしたり「ワワ(ワンワン)」「ブブ(ブーブ」などと言葉で伝えようとする姿が見られた。本児の言葉を丁寧に受け止め、応答的に関わりながら言葉の発達を促していく。 |
食事
(完了食)
- よく噛まずに飲み込みやすいため、保育者が咀嚼する様子を見せ、まねできたときには「モグモグできたね」と声をかけて認め、噛む習慣が身につくように関わる。
- 保育者に食べ物を分けようとする場面では、本児の気持ちに寄り添い、食べるしぐさをして応えながら、一緒に食べる楽しさを感じられるようにしていく。
家庭との連携
子どもの姿(再掲):延長保育が始まり、部屋の移動や関わりの少ない保育者の存在に不安な様子も見られたが、保育者に遊びに誘われると興味を示し、安心して玩具で遊び始める姿があった。
- 延長保育で楽しく過ごした様子を丁寧に伝えることで、保護者の不安を和らげていく。
- 保育時間が長くなることで生活リズムが乱れたり、疲れが出やすくなるため、家庭とこまめに情報を共有しながら、体調の変化に留意する。
Bさん(高月齢/女児/活発)(1歳5カ月/5月生まれ)
子どもの姿
- オムツ交換の際に、保育者に「トイレに座ってみる?」と声をかけられると、少し緊張した表情を見せながらも応じていた。(養護)
- 戸外では、ボールやシャボン玉を追いかけたり、ベンチや遊具によじのぼろうとするなど、興味のあるものに積極的に関わろうとする姿が見られた。(教育)
- 戸外遊びへの期待から、簡単な身支度への意欲が高まり、靴下や帽子の着脱に自分なりに取り組もうとする姿が増えてきた。(家庭との連携)
ねらい/内容/環境構成・配慮・援助/評価・反省
養護
| 子どもの姿(再掲) | オムツ交換の際に、保育者に「トイレに座ってみる?」と声をかけられると、少し緊張した表情を見せながらも応じていた。(養護) |
| ねらい | トイレに親しみを持ち、便器に座ることに少しずつ慣れる |
| 内容 | 保育者に見守られたり体を支えてもらいながら、安心して便器に座る。 |
| 環境構成・配慮・援助 | オムツ交換時やオムツが濡れていないタイミングで、「トイレに座ってみようか」と優しく誘う。本児の様子に応じて手をつないだり体を支えたりしながら、安定して座れるよう配慮し、嫌がる場合は無理強いせず、「また座ろうね」と伝えて次の機会につなげる。 |
| 評価・反省 | タイミングが合い、便器に座った際に排尿できることがあった。今後も焦らずに声をかけながら、少しずつトイレ習慣につなげていきたい。 |
教育
| 子どもの姿(再掲) | 戸外では、ボールやシャボン玉を追いかけたり、ベンチや遊具によじのぼろうとするなど、興味のあるものに積極的に関わろうとする姿が見られた。(教育) |
| ねらい | 戸外での探索を通じて、秋の自然に親しむ |
| 内容 | 保育者と一緒に公園内を探索し、ドングリや松ぼっくり、落ち葉に触れて、感触や音の面白さを味わう。 |
| 環境構成・配慮・援助 | 探索を始める前に、木の棒やゴミ、タバコの吸い殻などの危険物が落ちていないかを確認し、安全に配慮する。一緒に探索を楽しむ中で、本児の発見を丁寧に受け止めるとともに、木の実や落ち葉に触れて見せながら、「ツルツルするね」「カサカサ音がするね」など、感触の面白さを言葉にして伝え、自然物に対する興味を育んでいく。 |
| 評価・反省 | 様々な自然物を拾って保育者に見せたり、保育者が見つけたドングリや松ぼっくりに興味を示して嫌がらずに触れるなど、十分に探索を楽しむことができた。徐々に日中の気温が低くなってきたため、衣服の調整に配慮し、快適に散歩や戸外遊びを楽しめるようにする。 |
食事
(完了食)
- スプーンを使おうとする姿を大切にし、食べにくそうな場面ではさりげなく手を添えて援助しながら、徐々に慣れていけるようにする。
- 苦手な食材があるときには、保育者が食べて見せたり、食材にちなんだ歌を取り入れて興味を引き出しながら、楽しく食べられるように関わる。
家庭との連携
子どもの姿(再掲):戸外遊びへの期待から、簡単な身支度への意欲が高まり、靴下や帽子の着脱に自分なりに取り組もうとする姿が増えてきた。
- 身支度に意欲的に参加する姿を丁寧に保護者に伝え、家庭でもゆったりとした気持ちで見守ってもらえるよう働きかけながら、意欲を育んでいく。
- 保護者参加の行事について、持ち物や活動内容などを文章と口頭の両方でわかりやすく伝え、安心して参加できるよう配慮する。
Cさん(高月齢/男児/静か)(1歳4カ月/6月生まれ)
子どもの姿
- 手洗いの際には、保育者と一緒にスムーズに行えることもある一方で、水に興味を示してじっと見つめたり、手を濡らして遊びたがる姿も見られ、水を止められると泣いてしまうこともあった。(養護)
- 室内では意欲的に歩行を楽しんでいるが、戸外での歩行にはまだ消極的で、座り込んで遊んだり、靴を脱ごうとする様子もあった。(教育)
- 手遊びが始まると喜んで参加し、保育者の歌や動きをまねて楽しんでいた。(家庭との連携)
ねらい/内容/環境構成・配慮・援助/評価・反省
養護
| 子どもの姿(再掲) | 手洗いの際には、保育者と一緒にスムーズに行えることもある一方で、水に興味を示してじっと見つめたり、手を濡らして遊びたがる姿も見られ、水を止められると泣いてしまうこともあった。(養護) |
| ねらい | 保育者と一緒に手を洗い、清潔になった心地よさに気づく |
| 内容 | 手洗いの一連の流れを、保育者に手を添えてもらったり、自分なりにまねをしながら、楽しく行う。 |
| 環境構成・配慮・援助 | 「一緒に手を洗おうね」と優しく声をかけて手洗いに誘い、保育者が手を添えて一緒に行いながら、「気持ちいいね」「きれいになるね」と肯定的な言葉をかけていく。本児なりに手を洗おうとするしぐさが見られたときには、「上手にゴシゴシできたね」と認め、意欲を育む。 |
| 評価・反省 | 好きな歌に合わせて援助されることで、楽しみながらスムーズに行う姿が見られた。手洗いの流れが少しずつ身についてきているが、まだ水遊びをしたがることもあるため、気持ちに寄り添いながら焦らずに関わっていく。 |
教育
| 子どもの姿(再掲) | 室内では意欲的に歩行を楽しんでいるが、戸外での歩行にはまだ消極的で、座り込んで遊んだり、靴を脱ごうとする様子もあった。(教育) |
| ねらい | 靴を履いて歩くことを楽しむ |
| 内容 | 園庭や公園の平らで歩きやすい場所を、保育者に励まされたり手をつないでもらいながら、安心して歩く。 |
| 環境構成・配慮・援助 | 座って遊ぶ姿に寄り添いながら、少し離れた場所から名前を呼んだり、「あそこに○○があるね」と声をかけて周囲への興味を引き出し、さりげなく歩行に誘う。自ら立ち上がったり歩こうとする姿を温かく見守り、意欲はあるものの難しさが見られる場面では手をつないで援助し、「あんよができたね」「楽しいね」と声をかけながら、歩く楽しさに寄り添う。 |
| 評価・反省 | 靴での歩行を楽しむ姿が増えてきた。転倒して泣く場面では、「びっくりしたね」と声をかけて寄り添い、安心感を持てるようにしながら、再び歩き出せるよう働きかけていく。 |
食事
(完了食)
- 汁物やお茶を自分で飲もうとする姿を見守り、必要に応じてさりげなく支えて飲みやすくなるように配慮し、「自分で飲めたね」と声をかけて自信につなげていく。
- 手づかみで食べる姿も大切にし、食事の楽しさや喜びを感じられるような雰囲気づくりに努めながら、食への意欲を育む。
家庭との連携
子どもの姿(再掲):手遊びが始まると喜んで参加し、保育者の歌や動きをまねて楽しんでいた。
- 家庭でも模倣やふれあいをゆったりと楽しめるよう、園での本児の様子を丁寧に伝え、親しんでいる手遊びやわらべうたあそびを紹介していく。
- 身の回りのことに興味を持って自分なりにやろうとする姿を、家庭でも温かく見守ってもらえるよう、日々の様子や保育者のさりげない援助の方法を伝え、共に意欲を育んでいく。
Dさん(高月齢/女児/静か)(1歳3カ月/7月生まれ)
子どもの姿
- 保育者に「お外へ行こうね」と声をかけられると扉の方へ向かったり、食事の時間だとわかると自ら机に向かう姿が見られた。(養護)
- 室内では意欲的にハイハイで探索を楽しみ、興味のある玩具を見つけると手に取り、手指でじっくりと感触を味わっていた。(教育)
- 保育者に支えられて立つことを喜び、柵や保育者の体につかまって、自ら立ち上がろうとする動作も見られた。(家庭との連携)
ねらい/内容/環境構成・配慮・援助/評価・反省
養護
| 子どもの姿(再掲) | 保育者に「お外へ行こうね」と声をかけられると扉の方へ向かったり、食事の時間だとわかると自ら机に向かう姿が見られた。(養護) |
| ねらい | 安定した生活リズムの中で、主体的に過ごす |
| 内容 | 保育者の声かけを聞き、自分なりに次の活動への見通しを持ちながら、安心して行動する。 |
| 環境構成・配慮・援助 | 活動の切り替わりの際には、時間に余裕を持たせて無理なく気持ちを切り替えられるよう配慮し、遊びの切れ目を見計らいながら「これからごはんにしようね」「お外に行こうね」など、わかりやすい言葉で次の活動へと誘う。自ら次の活動やその準備に参加できたときは、「自分で来られたね」「楽しみだね」と肯定的な声かけを行い、安心感と主体性を育んでいく。 |
| 評価・反省 | 保育者の声かけで、喜んで次の行動へと移る姿が見られた。一方で、対応する保育者や本児なりのタイミングによっては気持ちの切り替えが難しい場面もあったため、気持ちに寄り添いながら、焦らずに関わっていきたい。 |
教育
| 子どもの姿(再掲) | 室内では意欲的にハイハイで探索を楽しみ、興味のある玩具を見つけると手に取り、手指でじっくりと感触を味わっていた。(教育) |
| ねらい | 好きな玩具を見つけ、集中して遊ぶ |
| 内容 | 室内をハイハイで探索し、ビジーボードやいたずらボックスなど好きな玩具を見つけ、つまむ、押す、引っ張るなど手指を使って遊ぶことを楽しむ。 |
| 環境構成・配慮・援助 | 手に取りやすい場所に、色彩豊かで指先を使って遊べる玩具を複数配置し、探索意欲を引き出す。玩具を手に取り、集中して遊ぶ姿を温かく見守り、本児が保育者に顔を向けた際には「引っ張ったら伸びたね」「音が鳴ったね」など、動きや感覚を言葉にして伝え、面白さを共有する。 |
| 評価・反省 | まずは気に入っている玩具で十分に遊び、満足すると再び探索を始める姿が見られた。この一カ月でつかまり立ちや伝い歩きが始まり、探索範囲が広がっているため、引き続き室内の安全に配慮していく。 |
食事
(後期食)食後ミルク120cc
- 好きなおかずを食べて笑顔を見せる姿に、「おいしいね」と目を合わせて声をかけ、食べる喜びに共感する。
- 手づかみで食べた際に手の汚れを気にする様子が見られるため、「気になるんだね」「一度きれいにしようか」と気持ちに寄り添いながら拭き取り、安心できるようにする。
家庭との連携
子どもの姿(再掲):保育者に支えられて立つことを喜び、柵や保育者の体につかまって、自ら立ち上がろうとする動作も見られた。
- つかまり立ちへの意欲が見られる姿を保護者と共有し、適切な援助の方法や、つかまり立ちを楽しめる環境について丁寧に伝えながら、発達を共に見守っていく。
- 保護者の普段の様子や悩みの内容に応じて、個別に面談の機会を提案し、じっくりと話を聞いて寄り添いながら、信頼関係を深めていく。
Eさん(中月齢/男児/活発)(1歳2カ月/8月生まれ)
子どもの姿
- 排便時に体に力を入れる様子が見られ、出たあとは遊びに戻ることもあれば、保育者に「オムツを替えようか」と声をかけられてトイレに向かうこともあった。(養護)
- 「抱っこしてほしい」「もっと食べたい」などの要求を、大きな声を出したり指差しをしたりして表現していた。(教育)
- 戸外では転びながらも自由に歩行を楽しみ、ベビーカーに乗ることを嫌がったり、保育者と手をつなぐことを拒んで逃げる姿も見られた。(家庭との連携)
ねらい/内容/環境構成・配慮・援助/評価・反省
養護
| 子どもの姿(再掲) | 排便時に体に力を入れる様子が見られ、出たあとは遊びに戻ることもあれば、保育者に「オムツを替えようか」と声をかけられてトイレに向かうこともあった。(養護) |
| ねらい | オムツが汚れたことに気づく |
| 内容 | 排泄したことを保育者に察してもらうことで不快感に気づき、嫌がらずにオムツ交換に応じ、清潔になった心地よさを感じる。 |
| 環境構成・配慮・援助 | 本児の排泄のサインを見逃さず、「出たかな?」と優しく声をかけて不快感に気づけるようにし、自然にオムツ交換へと誘う。交換時は、一対一のゆったりとした関わりを大切にしながら、「すっきりしたね」「きれいになって気持ちいいね」と清潔になった心地よさを言葉にして伝えていく。 |
| 評価・反省 | オムツが汚れると気づく様子が増え、オムツを触って保育者に伝えようとする姿も見られた。今後もその様子を丁寧に受け止め、自ら不快に気づく感覚を育みながら、清潔になる心地よさを味わえるように関わっていく。 |
教育
| 子どもの姿(再掲) | 「抱っこしてほしい」「もっと食べたい」などの要求を、大きな声を出したり指差しをしたりして表現していた。(教育) |
| ねらい | 自分なりの言葉やしぐさで思いを表現する |
| 内容 | 思いやしてほしいことを、喃語やしぐさで表現し、保育者に言葉で受け止めてもらうことで、伝わる喜びを味わう。 |
| 環境構成・配慮・援助 | 喃語やしぐさ、泣くことなどで表現する本児の気持ちを汲み取り、「そうだね、○○だね」「こうしたいんだね」「これが欲しいのかな?」といった落ち着いた語りかけで、丁寧に受け止めていく。また、本児の言葉をまねて返すことでやり取りを楽しみ、伝わる喜びや発語への意欲につなげていく。 |
| 評価・反省 | 喃語やしぐさを通して保育者とやり取りする姿が見られ、思いが通じると笑顔を見せていた。引き続き丁寧なやり取りの経験を重ねながら、思いを伝えようとする意欲をさらに育んでいく。 |
食事
(完了食)
- 食材の乗ったスプーンを握って口に運ぼうとする様子を見守り、必要に応じてさりげなく手を添えて援助し、徐々に慣れていけるようにする。
- 空になった皿を落として遊ぶ姿が見られるため、「きれいに食べられたね」と声をかけて認めながら、皿は本児の手の届かない場所に下げ、食事への集中が続くようにする。
家庭との連携
子どもの姿(再掲):戸外では転びながらも自由に歩行を楽しみ、ベビーカーに乗ることを嫌がったり、保育者と手をつなぐことを拒んで逃げる姿も見られた。
- 活発に体を動かしたり、自己主張する日々の姿を通じて、本児の心身の成長を保護者に伝えていく。
- 家庭での食事の様子や環境について丁寧に聞き取り、保護者の不安や大変さに寄り添いながら、必要に応じて環境や関わり方の助言を行い、園と家庭で協力しながら食への意欲を育んでいく。
Fさん(中月齢/女児/活発)(1歳1カ月/9月生まれ)
子どもの姿
- 先月から保育時間が延びたものの、体調を崩して早退したり、欠席する日が多かった。(養護)
- 室内での歩行が徐々に安定し、盛んに探索を楽しむ中で、発見した玩具や絵本を手に取り持ち歩いていた。(教育)
- 靴での歩行にはまだ慣れず、座って遊ぶことが多いものの、履く際に嫌がる様子は見られなくなった。(家庭との連携)
ねらい/内容/環境構成・配慮・援助/評価・反省
養護
| 子どもの姿(再掲) | 先月から保育時間が延びたものの、体調を崩して早退したり、欠席する日が多かった。(養護) |
| ねらい | 十分に休息を取りながら、健康的に過ごす |
| 内容 | 疲れや眠気のサインを保育者に受け止めてもらい、見守られながら安心して眠ったり、無理のないペースで心地よく過ごす。 |
| 環境構成・配慮・援助 | 登園時に本児の様子を保護者から聞き取り、園でも丁寧に観察しながら無理なく過ごせるよう配慮する。午前中や夕方の様子に応じて休息を促す際には、安心して眠れるよう、できるだけ決まった保育者が安定して関わり、心地よい入眠を援助する。 |
| 評価・反省 | 朝と夕方の決まった時間に眠る生活リズムが少しずつ整い始め、体調も安定してきた。気温が下がり体調を崩しやすい時期になるため、来月も無理なく過ごせるよう配慮する。 |
教育
| 子どもの姿(再掲) | 室内での歩行が徐々に安定し、盛んに探索を楽しむ中で、発見した玩具や絵本を手に取り持ち歩いていた。(教育) |
| ねらい | 歩行での探索を十分に楽しむ |
| 内容 | 室内を探索し、さまざまな玩具や遊具に興味を持って関わる。 |
| 環境構成・配慮・援助 | 本児の興味を引き出す玩具や遊具を安全に配置し、探索活動を見守る中で発見の喜びに寄り添い、「何を見つけたの?」「いいものがあったね」と声をかける。また、指先や体全体を使って遊ぶ姿には、「押したら音が鳴ったね」「トンネルをくぐれたね」と語りかけて楽しさを共有し、周囲のものに関わる意欲や好奇心を育んでいく。 |
| 評価・反省 | 自由に探索する中で、棚から次々と玩具を引き出したり、友だちの玩具に手を伸ばす姿も見られた。本児の好奇心を大切にしつつ、安全に探索できるよう配慮するとともに、友だちとの心地よい関わりを経験できるよう援助する。 |
食事
(完了食)
- 口に詰め込みそうなときは、「たくさん食べられるね」と声をかけながらさりげなく止め、「モグモグしようね」と伝えてよく噛めるよう促し、安全に配慮する。
- 自分で食べる意欲を大切にしながら見守り、必要に応じてさりげなく介助し、無理なく食べ進められるようにする。
家庭との連携
子どもの姿(再掲):靴での歩行にはまだ慣れず、座って遊ぶことが多いものの、履く際に嫌がる様子は見られなくなった。
- 家庭ではまだ靴を履くことを嫌がる様子が見られるとのことから、園での関わりや声かけを保護者と共有したり、お迎え時に靴を履いて帰ることができるよう援助する。
- 戸外遊びや製作遊びでついた衣服の汚れが落ち切らなかった場合は、保護者に実際に見せながら説明し、誤解やトラブルを未然に防ぐ。
Gさん(中月齢/男児/静か)(1歳0カ月/10月生まれ)
子どもの姿
- 食事の流れを理解し、食前には自分なりにエプロンをつけようとしたり、食後には取ろうとする姿が見られた。(養護)
- つかまり立ちや伝い歩きを盛んに楽しみ、そばで同じようにつかまり立ちをして遊ぶ友だちに興味を示し、関わろうとする様子が見られた。(教育)
- 砂場では、自ら両手で砂に触れて握ったり、スコップで砂を叩くなどして、感触を楽しんでいた。(家庭との連携)
ねらい/内容/環境構成・配慮・援助/評価・反省
養護
| 子どもの姿(再掲) | 食事の流れを理解し、食前には自分なりにエプロンをつけようとしたり、食後には取ろうとする姿が見られた。(養護) |
| ねらい | 簡単な身の回りのことをやってみようとする |
| 内容 | 保育者に見守られながら、エプロンや靴下など簡単な衣服の着脱に取り組み、できたことの喜びを味わう。 |
| 環境構成・配慮・援助 | 保育者の声かけを聞いたり、自分なりに見通しを持って着脱に参加しようとする姿を大切にしながら見守り、難しい部分はさりげなく手を添えて援助する。最後には「できたね」と声をかけ、身の回りのことを自分で行う喜びに共感しながら意欲を育む。 |
| 評価・反省 | 時間に余裕がない場面では、本児の自発的な行動を待たずに保育者が声をかけて促したり、介助してしまうこともあり、以前よりも本児自ら行おうとする姿が減っている。焦らずに関わりながら意欲を育めるよう、職員間で連携や対応について再度話し合っていく必要がある。 |
教育
| 子どもの姿(再掲) | つかまり立ちや伝い歩きを盛んに楽しみ、そばで同じようにつかまり立ちをして遊ぶ友だちに興味を示し、関わろうとする様子が見られた。(教育) |
| ねらい | 友だちと関わる心地よさを感じる |
| 内容 | 探索活動を楽しむ中で、友だちの動きや遊びに興味を持ち、自分なりにまねしたり、保育者に思いを代弁してもらいながら、簡単なやり取りをする。 |
| 環境構成・配慮・援助 | 遊ぶスペースや玩具を十分に確保し、友だちの姿が自然に目に入る環境を整える。本児が友だちに関心を示した際は、安全に配慮しながら見守り、「○さんも上手に立っているね。おんなじだね」「○さんの持っている玩具が気になるんだね」「面白そうだね」と気持ちを代弁し、保育者も一緒に遊びながら、簡単なやり取りが生まれるよう丁寧に仲立ちする。 |
| 評価・反省 | 保育者の仲立ちにより、友だちと機嫌よく関わる姿が見られた。玩具の取り合いなどのトラブルも発生しやすい時期であるため、安全に配慮しながら見守っていく。 |
食事
(完了食)
- スプーンに興味を示し始めた姿を大切にし、手を添えて持ち方を知らせながら援助し、食具を使おうとする意欲を育む。
- 日によって好き嫌いが見られるため、声かけを工夫したり、目の前で小さくして見せるなどして興味を引き出し、一口でも食べられた際には「食べられたね」と声をかけ、食べる喜びや自信につなげていく。
家庭との連携
子どもの姿(再掲):砂場では、自ら両手で砂に触れて握ったり、スコップで砂を叩くなどして、感触を楽しんでいた。
- 本児の好きな遊びを保護者と丁寧に共有し、じっくりと楽しめる環境を整えることで、好奇心を満たしていく。
- 持ち物の記名忘れや忘れ物については、保護者の日々の大変さに寄り添いながら丁寧に伝え、協力を依頼する。
Hさん(中月齢/女児/静か)(0歳11カ月/11月生まれ)
子どもの姿
- 「お外へ行こうね」という保育者の声かけに喜び、戸外遊びの準備に参加していた。(養護)
- 棚や柵、保育者の体といった室内の様々な場所で、機嫌よくつかまり立ちを楽しんでいた。(教育)
- 園や家庭において、体調や疲れにより甘えが強くなり、抱っこを求める姿が見られた。(家庭との連携)
ねらい/内容/環境構成・配慮・援助/評価・反省
養護
| 子どもの姿(再掲) | 「お外へ行こうね」という保育者の声かけに喜び、戸外遊びの準備に参加していた。(養護) |
| ねらい | 楽しみながら着脱に参加する |
| 内容 | 戸外に出ることへの期待を持ち、保育者の声かけに合わせて自分なりに体を動かしながら上着を着たり、手を添えてもらいながら帽子を被る。 |
| 環境構成・配慮・援助 | 戸外遊びの準備時は、職員間で連携して時間差をつけながら、一人ひとりの着脱に丁寧に対応できる体制を整える。戸外に出る喜びに寄り添い、上着を着る際は「ここに手を入れて上着を着ようね」とわかりやすく動作を伝えて介助し、帽子を被る際は手を添えて一緒に行い、楽しく準備に参加できるように関わる。 |
| 評価・反省 | 少人数ずつでゆったりと準備を行う中で、保育者の声かけに応じた動作を行おうとする姿が見られた。自分でできる部分はまだ少ないが、着脱に参加する姿を丁寧に認めながら、意欲を育んでいきたい。 |
教育
| 子どもの姿(再掲) | 棚や柵、保育者の体といった室内の様々な場所で、機嫌よくつかまり立ちを楽しんでいた。(教育) |
| ねらい | 意欲的に体を動かして遊ぶ |
| 内容 | 室内で保育者に見守られ、安心感を持ちながらハイハイやつかまり立ち、伝い歩きでの探索を楽しむ。 |
| 環境構成・配慮・援助 | 本児が興味を示す玩具や絵本を見やすい場所に配置し、探索意欲を引き出す。つかまり立ちや伝い歩きの様子をそばで見守りながら安全に配慮し、本児が発見の喜びを共有しようと目を合わせた際には、「いいものを見つけたね」と共感する声かけを行う。 |
| 評価・反省 | ハイハイでの移動が多く、本児のペースで探索を楽しんでいた。つかまり立ちから伝い歩きをする姿も見られるが、すぐに座ってハイハイに戻るため、本児の体の使い方を見守りながら、伝い歩きを促す環境づくりを継続していく。 |
食事
(後期食)食後ミルク100cc
- 好き嫌いが見られる際には、「甘いニンジンだよ」と味や食材の名前を伝えたり、保育者がおいしそうに食べて見せることで、興味を引き出せるように関わる。
- 手づかみ食べする様子を見守りながら、「おいしいね」「次はどれにしようね」といった食べる喜びに寄り添う声かけを行い、食への意欲を育む。
家庭との連携
子どもの姿(再掲):園や家庭において、体調や疲れにより甘えが強くなり、抱っこを求める姿が見られた。
- 週明けには休日の過ごし方を丁寧に聞き取り、本児の疲れや体調を把握し、甘えを受け止めながら無理なく過ごせるよう、個別の配慮を行う。
- 送迎時のやり取りや連絡帳を通じて、保護者の育児に対する心配事や悩みに気づいて受け止め、相談しやすい雰囲気づくりを大切にしながら関わっていく。
Iさん(低月齢/男児/活発)(0歳10カ月/12月生まれ)
子どもの姿
- 睡眠中に泣いて目覚めることが増えてきた。(養護)
- 散歩に出かける際、ベビーカーに乗ることを嫌がり、激しく体を動かしたりのけ反る姿が見られた。(教育)
- 室内では、ハイハイやつかまり立ちなどを意欲的に行い、体を動かすことを楽しんでいた。(家庭との連携)
ねらい/内容/環境構成・配慮・援助/評価・反省
養護
| 子どもの姿(再掲) | 睡眠中に泣いて目覚めることが増えてきた。(養護) |
| ねらい | 快適な環境で、一定時間安心して眠る |
| 内容 | 落ち着ける姿勢で心地よく入眠し、睡眠の途中で目覚めた際には、保育者にすぐに対応してもらうことで安心し、再入眠する。 |
| 環境構成・配慮・援助 | 室内環境を快適に保ちながら、入眠の様子をそばで見守り、うつぶせ寝の場合はあおむけに姿勢を直して安全に配慮する。途中で目覚めた際には、子守唄を歌いながら優しく体をトントンしたり、足の裏に触れて温めるなどして、本児が心地よく再入眠できるように関わる。 |
| 評価・反省 | 保育者がすぐに対応することで落ち着いて再入眠し、十分に休息を取ることができていた。家庭でも夜間に目覚めやすいとのことから、保護者の大変さに寄り添いながら丁寧に様子を聞き取り、生活リズムが整うように関わっていきたい。 |
教育
| 子どもの姿(再掲) | 散歩に出かける際、ベビーカーに乗ることを嫌がり、激しく体を動かしたりのけ反る姿が見られた。(教育) |
| ねらい | 保育者と一緒に散歩を楽しむ |
| 内容 | 信頼する保育者の優しい声かけや歌いかけにより、安心してベビーカーに乗り、景色を眺めたり戸外の空気に触れる心地よさを味わう。 |
| 環境構成・配慮・援助 | 安心してベビーカーに乗れるよう、職員間で役割分担を行い、決まった保育者が対応できる体制を整える。「これからベビーカーに乗ってお散歩に行こうね」「ベルトをカッチャンしようね」といった優しい声かけや、本児の好きな手遊びの歌いかけを通じて楽しい気持ちで出発できるように関わり、発声や表情を丁寧に受け止めながら、散歩の楽しさや戸外の心地よさに寄り添っていく。 |
| 評価・反省 | 決まった保育者との関わりの中で、ベビーカーに乗る流れに徐々に慣れ、機嫌よく出発できる姿も増えてきた。見通しを持って安心して散歩に向かえるよう、引き続き職員間で連携しながら対応していく。 |
食事
(後期食)食後ミルク120cc
- 皿や食材を指差すときには、「次は○○が食べたいんだね」と本児の思いを言葉にしながら応答的に関わり、食べる意欲を育てていく。
- 周囲の様子に興味が向いて食事に集中しにくいときには、親しんでいる季節の歌やわらべうたを通じて気分転換を図りながら、無理なく食べ進められるように関わる。
家庭との連携
子どもの姿(再掲):室内では、ハイハイやつかまり立ちなどを意欲的に行い、体を動かすことを楽しんでいた。
- 活発に体を動かす様子とともに、転倒などの危険が起こりやすい場面についても保護者と共有し、安全に配慮しながら発達を見守っていく。
- 製作遊びを楽しんだ様子を保護者が思い浮かべやすいよう、完成品は見やすい場所に掲示し、作品を見ながら活動の様子を具体的に伝えていく。
Jさん(低月齢/女児/活発)(0歳9カ月/1月生まれ)
子どもの姿
- 体力がついてきたことで、日によって午前睡の時間にばらつきが見られるようになった。(養護)
- 戸外遊びでは、嫌がらずに地面や芝生の上をハイハイし、土や葉っぱ、石などに触れて感触を味わっていた。(教育)
- 月の後半から土曜保育が始まり、普段は関わりの少ない保育者の受け入れを嫌がって泣く姿もあったものの、保護者と離れたあとはすぐに気持ちを切り替えて遊び始めることができていた。(家庭との連携)
ねらい/内容/環境構成・配慮・援助/評価・反省
養護
| 子どもの姿(再掲) | 体力がついてきたことで、日によって午前睡の時間にばらつきが見られるようになった。(養護) |
| ねらい | 心地よい生活リズムで、機嫌よく過ごす |
| 内容 | その日の体調や疲れに応じて十分に午前睡を取り、元気に午前の活動に参加したり、機嫌よく離乳食を食べる。 |
| 環境構成・配慮・援助 | 登園後は本児の様子に合わせて、ハイハイでの探索活動やふれあい遊びに誘い、適度に体を動かしながら心地よい疲れを感じられるように関わる。眠気のサインを見逃さず、「眠くなってきたね」「お散歩の前に、ねんねしようね」と優しく声をかけて午前睡に誘い、機嫌よく午前の活動に参加できるよう生活リズムを整えていく。 |
| 評価・反省 | 登園後に眠気が見られるタイミングが安定してきた一方で、布団を嫌がり、抱っこやおんぶで眠ることが多かった。職員間で連携しながら、本児が心地よく眠れるよう柔軟に対応していく。 |
教育
| 子どもの姿(再掲) | 戸外遊びでは、嫌がらずに地面や芝生の上をハイハイし、土や葉っぱ、石などに触れて感触を味わっていた。(教育) |
| ねらい | 秋の自然に親しむ |
| 内容 | 園庭や散歩先で、保育者に見守られながらハイハイで自由に探索し、落ち葉や木の実に触れて感触の面白さを味わう。 |
| 環境構成・配慮・援助 | 探索の前には、タバコの吸い殻やゴミなどが落ちていないか確認するとともに、石などを口に入れないよう注意しながら、自然と触れ合う姿を見守る。落ち葉を集めて音や感触を一緒に楽しんだり、ドングリや松ぼっくりに触れながら、「固いね」「コロコロ転がるね」と感触や形状の面白さを言葉にして伝え、自然に対する興味を育む。 |
| 評価・反省 | 容器に集められたドングリに興味を示し、握ったり離したりしながら感触や音を楽しんでいた。ペットボトルにドングリを入れてマラカスを作るなど、室内でも目や耳で秋の自然に触れて楽しめる工夫を取り入れていきたい。 |
食事
(中期食)食後ミルク160cc
- 食材を口から出す姿が見られるときは、味に対する苦手さか調理形態が合っていないことによるものかを見極め、無理なく食べられるよう、調理員と情報を共有しながら丁寧に対応していく。
- 皿やコップなど周囲の様々なものに興味を示して手を伸ばすため、落ち着いて食べられるよう、食事の環境や食器の配置を工夫する。
家庭との連携
子どもの姿(再掲):月の後半から土曜保育が始まり、普段は関わりの少ない保育者の受け入れを嫌がって泣く姿もあったものの、保護者と離れたあとはすぐに気持ちを切り替えて遊び始めることができていた。
- 登園時は笑顔で迎え入れながら、「Jさんの好きな○○で遊ぼうね」と優しく声をかけ、お迎え時にはその日楽しく過ごせた様子を丁寧に保護者に伝えることで、信頼関係を育んでいく。
- 戸外遊びで衣服が汚れることがあるため、着替えを多めに用意してもらえるよう、おたよりや掲示を通じて保護者に依頼する。
Kさん(低月齢/男児/静か)(0歳8カ月/2月生まれ)
子どもの姿
- 人見知りが強くなり、担任から離れると泣く姿が増えてきた。(養護)
- 腹ばいになるとお腹を軸にして回転したり、玩具に手を伸ばした勢いで少し前進する様子が見られた。(教育)
- すべり台では、保育者に支えられながら滑ることを楽しみ、緊張した表情も見せていた。(家庭との連携)
ねらい/内容/環境構成・配慮・援助/評価・反省
養護
| 子どもの姿(再掲) | 人見知りが強くなり、担任から離れると泣く姿が増えてきた。(養護) |
| ねらい | 信頼する保育者のそばで、安心して過ごす |
| 内容 | 信頼する保育者の優しい声かけや抱っこなどのスキンシップを通じて、思いや不安を丁寧に受け止めてもらい、安心感を得る。 |
| 環境構成・配慮・援助 | 職員間で連携し、決まった保育者を中心に関わることで、本児が安心感を持って過ごせるよう配慮する。泣いたり、しぐさで思いやしてほしいことを表現する姿を受け止め、「びっくりしたね」「○○がいいんだね」などと言葉にしながら、応答的に関わる。 |
| 評価・反省 | 決まった保育者のそばで遊んだり、抱っこされることで、落ち着いて過ごす姿が見られた。人見知りは続いているため、引き続き安心感を育む環境づくりや関わり方を職員間で共有していく。 |
教育
| 子どもの姿(再掲) | 腹ばいになるとお腹を軸にして回転したり、玩具に手を伸ばした勢いで少し前進する様子が見られた。(教育) |
| ねらい | 体を動かして楽しむ |
| 内容 | 身近にある玩具に興味を持ち、手足を動かして掴もうとしたり、保育者の援助を受けながらずりばいをして、前に進む楽しさを味わう。 |
| 環境構成・配慮・援助 | ベビーサークルやマットを活用して安全に遊べるスペースを確保し、色彩豊かで握りやすい玩具を本児のそばに配置して興味を引き出す。玩具に手を伸ばそうと体を動かす姿を見守りながら、「届きそうだね!」「がんばって!」と励ましたり、足裏を支えてずりばいの援助を行い、玩具に手が届いた喜びに共感しながら、ずりばいへの意欲につなげていく。 |
| 評価・反省 | 興味のあるものに向かって盛んにずりばいを楽しんでおり、月末にはハイハイのような動きも見られるようになった。自分で移動できる喜びに寄り添いながら、さらに探索意欲を促す環境づくりを行いたい。 |
食事
(中期食)食後ミルク180cc
- ほうれん草を口から出して嫌がる姿を受け止め、保育者が食べて見せたり、無理に食べさせず次の機会にするなどして対応し、安心感を育みながら徐々に慣れていけるようにする。
- コップやお椀からお茶や汁物を飲む際には、口を閉じて飲めているかを観察しながら援助し、「飲めたね」と声をかけて自信につなげる。
家庭との連携
子どもの姿(再掲):すべり台では、保育者に支えられながら滑ることを楽しみ、緊張した表情も見せていた。
- 本児なりに様々な活動に参加する姿を具体的に保護者に伝え、成長を感じてもらうとともに、家庭での遊びや関わり方の参考となるようにする。
- 日中も肌寒くなってきたため、戸外遊び用の薄手の上着の用意を保護者に依頼する。
Lさん(低月齢/女児/静か)(0歳7カ月/3月生まれ)
子どもの姿
- 物音や自分の動きによって泣いて目覚めることがあるものの、保育者に抱っこされると安心し、指しゃぶりをしながら再入眠できた。(養護)
- 保育者にあやされると、声を出して笑ったり、自分なりに喃語で応じる姿が見られた。(教育)
- 機嫌のよいときには、腹ばいになると手足をバタバタと動かしたり、飛行機のように手足を持ち上げるポーズをとって遊ぶ様子が見られた。(家庭との連携)
ねらい/内容/環境構成・配慮・援助/評価・反省
養護
| 子どもの姿(再掲) | 物音や自分の動きによって泣いて目覚めることがあるものの、保育者に抱っこされると安心し、指しゃぶりをしながら再入眠できた。(養護) |
| ねらい | 一定時間安心して眠る |
| 内容 | 睡眠の途中で目覚めた際は、保育者に抱っこやトントンをしてもらうことで、安心して再入眠する。 |
| 環境構成・配慮・援助 | 本児の生活リズムに合わせて熟睡できるよう、眠る場所を遊んでいる他児から離れた位置にしたり、必要に応じて仕切りを活用するなど、室内環境を工夫する。途中で目覚めた際には、体を優しくトントンしながら子守唄を歌ったり、本児の様子に応じて抱っこすることで、安心して再入眠できるよう援助する。 |
| 評価・反省 | トントンだけでは再入眠しづらく、抱っこで対応することが多かった。途中で目覚めない日も増えてきたため、本児が安心できる関わりを今後も継続していきたい。 |
教育
| 子どもの姿(再掲) | 保育者にあやされると、声を出して笑ったり、自分なりに喃語で応じる姿が見られた。(教育) |
| ねらい | 保育者とのやり取りを楽しむ |
| 内容 | わらべうたあそびを楽しむ中で、保育者の歌いかけや話しかけに喃語やしぐさで応じ、それらを丁寧に受け止めてもらう。 |
| 環境構成・配慮・援助 | わらべうたあそびは落ち着いた場所で、目を合わせながらゆったりと行う。本児の喃語や表情、しぐさを丁寧に受け止め、「くすぐったいね」「楽しいね」「もう一回やろうね」と言葉にして返すことで、思いが伝わる喜びを感じられるように関わる。 |
| 評価・反省 | 保育者のまねをして様々な声を出したり、喃語を話して楽しんでいた。本児なりの思いをくみ取り、「○○なんだね」と言葉にしながら丁寧に応えることで、他者と関わろうとする意欲や言葉の発達を促していく。 |
食事
(初期食)食後ミルク200cc
- 食べ慣れていない食材は口から出しやすいため、無理に食べさせず、「これは○○だよ」と食材の名前を伝えたり、「また今度にしようね」といった安心できる声かけを行い、次の機会につなげる。
- 周囲の物音や声に気を取られて集中できないときは、食べる場所を工夫し、落ち着いて食事に向かえるよう配慮する。
家庭との連携
子どもの姿(再掲):機嫌のよいときには、腹ばいになると手足をバタバタと動かしたり、飛行機のように手足を持ち上げるポーズをとって遊ぶ様子が見られた。
- 本児の体の使い方や手足の動きを丁寧に観察し、現在の発達の様子を踏まえながら、ずりばいやお座りにつながる援助の仕方や遊びについて、保護者にわかりやすく伝えていく。
- 徐々に肌寒くなり体調を崩しやすくなるため、日々の体調の変化に留意し、保護者とこまめに情報を共有する。
その他、ほいくのおまもりプラスのコンテンツ