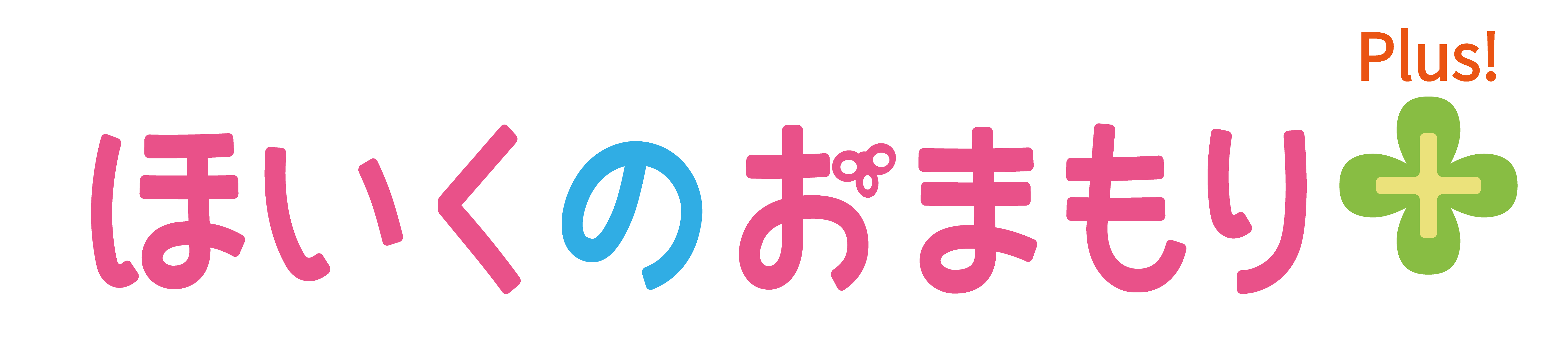個人案PDF
ダウンロードはこちら
敬称と性別表記について
LGBTQ+の観点から、保育士が園児を表記する際は『くん』『ちゃん』を使わず、『さん』で統一、園児が自身を称する際や園児同士のやり取りを記載する場合は『ちゃん』で統一しています。また、発達段階の観点では性差はあると考えられるため、男児/女児としています。
Aさん(高月齢/男児/活発)(2歳11カ月/4月生まれ)
子どもの姿
- 上着や靴の着脱の際に、「できない」と言って保育者にやってもらいたがって怒ったり、泣く姿が見られた。(養護)
- ままごとやブロックを楽しむ中で、気の合う友だちとやり取りしたり、「かして」と言葉で思いを伝えていた。(教育)
- 母親の出産が近くなり、登園時や午睡の前に泣いて嫌がるなど、情緒が不安定な姿が増えた。(家庭との連携)
ねらい/内容/環境構成・配慮・援助/評価・反省
養護
| 子どもの姿(再掲) |
上着や靴の着脱の際に、「できない」と言って保育者にやってもらいたがって怒ったり、泣く姿が見られた。(養護) |
| ねらい |
身の回りのことを自分で行う喜びを感じる |
| 内容 |
保育者に手伝ってもらったり見守られながら、簡単な衣服の着脱を行う。 |
| 環境構成・配慮・援助 |
本児の甘えを受け止めながら「一緒にやろうね」と伝え、安心して着脱に気持ちが向くように関わる。着脱の最初の部分は手を添えて援助し、本児の様子に合わせて、自分でできそうな部分はさりげなく手を離して見守りつつ、できた部分を大いにほめて自信につなげる。 |
| 評価・反省 |
外に出たい気持ちが強く焦っているときには、「一緒に準備をしてお外に出ようね」と声をかけて寄り添うと、落ち着いて着脱に向かうことができた。引き続き、できた部分を見逃さずにほめて、自信と意欲を育てていく。 |
教育
| 子どもの姿(再掲) |
ままごとやブロックを楽しむ中で、気の合う友だちとやり取りしたり、「かして」と言葉で思いを伝えていた。(教育) |
| ねらい |
友だちとやり取りする楽しさを味わう |
| 内容 |
友だちとままごとを楽しむ中で、簡単な言葉を使って思いやしてほしいことを伝えようとする。 |
| 環境構成・配慮・援助 |
子ども同士のやり取りを見守り、必要に応じて「Aさんはこうしたいのかな」「○さんはこうしたいんだね」と言葉を補い、双方の思いが伝わるように仲立ちする。また、保育者も一緒に遊びながら、「おいしいお弁当を作って、遠足に行こう」といったイメージが膨らむような具体的な提案をさりげなく行い、友だちと楽しさを共有できるように関わる。 |
| 評価・反省 |
一緒に遊ぶ友だちに話しかけられると応えたり、料理を作って机に並べて「できたよ!」と自ら声をかける姿も見られた。玩具の貸し借りでトラブルになる場面はまだ多いため、言葉を補いながら仲立ちする。 |
食事
- おしゃべりに夢中で食事が進んでいないときは、「次はどれを食べようね」「先生も同じものを食べようかな」など、食事に意識が戻るような声かけを行う。
- 「見ててね」と言って自信を持って食べる姿を大いに認め、「大きなお口で食べられたね」「よくかんで食べられてかっこいいね」と伝えながら意欲を育てる。
家庭との連携
子どもの姿(再掲):母親の出産が近くなり、登園時や午睡の前に泣いて嫌がるなど、情緒が不安定な姿が増えた。
- 登園時は明るい笑顔と挨拶で受け入れ、本児も保護者も安心感を持てるようにしたり、日中の様子や保育者の対応を伝え、園と家庭で連携しながら情緒の安定を図る。
- 進級に向けて2歳児の部屋に遊びに行く機会を多く持ち、その際の様子を丁寧に保護者に伝え、来年度の姿を想像しやすいようにする。
Bさん(高月齢/女児/活発)(2歳10カ月/5月生まれ)
子どもの姿
- 下痢が続いたあとはしばらくオムツを履いて過ごしたが、布パンツも履きたがり、オムツの上から履く日もあった。(養護)
- ひな祭りのちぎり絵製作では、好きな色の折り紙を選び、ちぎって楽しんだ。(教育)
- 体調不良が続き欠席が多く、室内で過ごしたり、午睡時間が長くなる日が多かった。(家庭との連携)
ねらい/内容/環境構成・配慮・援助/評価・反省
養護
| 子どもの姿(再掲) |
下痢が続いたあとはしばらくオムツを履いて過ごしたが、布パンツも履きたがり、オムツの上から履く日もあった。(養護) |
| ねらい |
体調や気候に合わせて衣服の調整を行いながら、快適に過ごす |
| 内容 |
遊ぶ場所や気候、体調に合わせてオムツと布パンツを履き替えながら、安心して過ごす。 |
| 環境構成・配慮・援助 |
体調が落ち着いてきたので、オムツと布パンツのどちらを履いて過ごすかについて、本児の意思を尊重しつつ、体調や気候に合わせて時にはオムツを履くことを提案するなど、柔軟に対応していく。また、朝晩と日中の気温差も出てくる時期なので、必要に応じて衣服の調整を促し、健康的に過ごせるように援助する。 |
| 評価・反省 |
体調が安定し、再び布パンツで過ごせる日が増えてきた。今後も、本児と丁寧にやり取りしながら衣服の調整ができるように援助していく。 |
教育
| 子どもの姿(再掲) |
ひな祭りのちぎり絵製作では、好きな色の折り紙を選び、ちぎって楽しんだ。(教育) |
| ねらい |
様々な素材に触れ、感触の面白さを十分に味わう |
| 内容 |
粘土あそびや新聞紙あそびを楽しむ。 |
| 環境構成・配慮・援助 |
粘土や新聞紙に触れて楽しむ姿を見守る中で、「柔らかいね」「ちぎれたね」「小さくなったね」など、素材の感触や形が変わる面白さを言葉にして共感する。また、ままごと用の皿や鍋を用意して見立てあそびを楽しめるようにし、保育者も遊びに参加しながらイメージが膨らむように関わる。 |
| 評価・反省 |
粘土あそびでは長時間集中し、ちぎったりつぶしたり丸めたりしながら感触を楽しんだ。皿や鍋などの道具を利用した見立てあそびでは、友だちと盛んに言葉のやり取りをしながら楽しめたので、必要に応じて言葉を添えながら、楽しさを共有できるように仲立ちしていく。 |
食事
- 器に手を添えることを忘れているときは、「手で持つと食べやすいよ」とわかりやすく伝える。
- よく噛んで食べられるように、一緒に食事を楽しむ中で保育者の口元を見せたり、「よく噛んで食べようね」と声をかける。
家庭との連携
子どもの姿(再掲):体調不良が続き欠席が多く、室内で過ごしたり、午睡時間が長くなる日が多かった。
- 登園時に機嫌や体調を聞き取るとともに、日中の様子をよく観察し、普段と変わった様子があればこまめに伝え合う。
- 気候に合わせて衣服の調整をしやすいように、自分で着脱しやすい服装で登園してもらうように伝える。
Cさん(高月齢/男児/静か)(2歳9カ月/6月生まれ)
子どもの姿
- 月の後半は咳や鼻水が多く、機嫌が悪い日が続いた。(養護)
- 決まった絵柄のパズルや気に入った玩具で遊びたがり、友だちが使っていると「かして」と言葉で伝えていた。(教育)
- 思いが通らなかったり、着脱がうまくできないときなどには、泣いて怒る姿が見られた。(家庭との連携)
ねらい/内容/環境構成・配慮・援助/評価・反省
養護
| 子どもの姿(再掲) |
月の後半は咳や鼻水が多く、機嫌が悪い日が続いた。(養護) |
| ねらい |
季節の変わり目を健康的に過ごす |
| 内容 |
気温や活動に合わせて衣服を調整したり、十分に休息を取りながら、快適に過ごす。 |
| 環境構成・配慮・援助 |
一日の中で気温差が激しく体調を崩しやすい時期なので、活動場所や気温に応じて、「汗をかいたから着替えようか」「寒いから上着を着よう」などと声をかけながら、衣服の調整を促す。また、体調が優れない様子や疲れが見られるときは、静かな場所で体を休められるように配慮し、無理なく過ごせるようにする。 |
| 評価・反省 |
咳や鼻水が落ち着き、元気に登園していた。新年度は不安や緊張が体調に影響しやすいので、ゆったりと好きな遊びを楽しむ時間を設け、表情や機嫌を観察しながら必要に応じて休息や水分補給を促す。 |
教育
| 子どもの姿(再掲) |
決まった絵柄のパズルや気に入った玩具で遊びたがり、友だちが使っていると「かして」と言葉で伝えていた。(教育) |
| ねらい |
友だちと簡単な言葉でやり取りする中で、思いが通じる喜びを感じる |
| 内容 |
同じ遊びを楽しむ友だちと玩具のやり取りを行う中で、「かして」「いいよ」「あとでね」など、簡単な言葉で思いを伝える。 |
| 環境構成・配慮・援助 |
子ども同士のやり取りを見守ることを基本としつつ、必要に応じて丁寧に言葉を添えて仲立ちし、互いの思いが伝わるように援助する。「貸してもらえて嬉しいね」「どうぞ、ってできたね」と、友だちと思いが通じ合った喜びに共感することで、言葉でやり取りする意欲を育てる。 |
| 評価・反省 |
「かして」「だめよ」など、言葉で思いを伝える姿が増えた一方、気に入った玩具をめぐり友だちとぶつかる場面も見られた。「これが欲しいんだね」と思いを受け止めたり、「順番に使おうね」と交代で遊ぶ提案を行うなど、やり取りを援助する。 |
食事
- 最後に食材をすくい切れずに困っているときは、「あと少しだね」「お手伝いがいるかな?」と声をかけ、手を添えて援助する。
- 好きなものを先に食べ切ってしまうことが多いため、「このお野菜はどんな味かな」「いいにおいがするね」と様々な食材に興味を持てるように声をかけ、バランスよく食べられるようにする。
家庭との連携
子どもの姿(再掲):思いが通らなかったり、着脱がうまくできないときなどには、泣いて怒る姿が見られた。
- 本児の葛藤を受け止めつつ、気持ちを切り替え、安心して再挑戦できるような保育者の関わり方や声かけを共有する。
- 親子共に進級への不安が和らぐように、友だちとの関わりが増えたことや、トイレで排尿できるようになったことなど、この一年間での具体的な成長を挙げ、ともに喜ぶ。
本登録をして
他の文例を見る
Dさん(高月齢/女児/静か)(2歳8カ月/7月生まれ)
子どもの姿
- 保育者のまねをして、着替えの際に脱いだ衣服や口拭きタオルなどを、自分なりに畳もうとしていた。(養護)
- 室内でのサーキット遊びでは自分なりのペースで体を動かし、段差から飛びおりたり、でこぼこ道の上をバランスを取りながら歩いて楽しんだ。(教育)
- 園に飾ってある雛人形に興味を持ち、「うれしいひなまつり」を歌うたびに「おひなさまいたよね」とうれしそうに話していた。(家庭との連携)
ねらい/内容/環境構成・配慮・援助/評価・反省
養護
| 子どもの姿(再掲) |
保育者のまねをして、着替えの際に脱いだ衣服や口拭きタオルなどを、自分なりに畳もうとしていた。(養護) |
| ねらい |
身の回りの物を丁寧に扱おうとする |
| 内容 |
脱いだ衣服や上着を、保育者と一緒に楽しみながら畳み、自分のカゴに入れるなどの始末をする。 |
| 環境構成・配慮・援助 |
自分からやろうとする姿を大切にしながら見守る中で、「こちらの袖をパタンと折るよ」と言葉で伝えつつ、さりげなく手を添えて援助する。所定の場所への片づけまで一緒に行い、「自分で畳めたね」「きれいに持って帰れるね」と伝え、丁寧に物を扱う心地よさを感じられるようにする。 |
| 評価・反省 |
援助を嫌がり、時間をかけて自分で畳む姿が増えた。本児の自立心や物を丁寧に扱う姿勢をさらに育むため、職員同士で連携し、時間に余裕を持たせて見守るとともに、「できたね」と認めることで、達成感を味わえるようにする。 |
教育
| 子どもの姿(再掲) |
室内でのサーキット遊びでは自分なりのペースで体を動かし、段差から飛びおりたり、でこぼこ道の上をバランスを取りながら歩いて楽しんだ。(教育) |
| ねらい |
体を動かす楽しさを十分に味わう |
| 内容 |
遊具を通じて、のぼる、おりる、くぐる、飛びおりるなどの様々な動きを楽しむ。 |
| 環境構成・配慮・援助 |
好きな遊具で遊ぶ姿を見守る中で、「上までのぼれたね」「ジャンプできたね」と体を動かす楽しさに共感したり、一緒に遊びながら「トンネルの向こうまで行けるかな」と言葉をかけ、様々な動きに挑戦できるように関わる。事故やケガを防ぐため、保育者同士で声をかけ合うとともに、人気のある遊具では保育者が丁寧に順番を伝え、安全に遊べるように配慮する。 |
| 評価・反省 |
年上の友だちとの関わりが増え、一緒にすべり台をしたり、鉄棒にぶら下がるなど、のびのびと体を動かしていた。今後も安全に十分配慮し、必要に応じて声かけや援助を行いつつ、子ども同士のやり取りを見守る。 |
食事
- 苦手な食材を自ら食べる姿を見逃さず、「自分で食べられたね」と認めたり、同じ食材を食べながら「甘いね」など味や食感を共有し、食材への興味を育てる。
- 同じ机の友だちが食べ終わると、本児も「もうおしまい」と言うので、無理なく食べ進められるように、「先生と一緒に食べよう」と励ましたり、「お手伝いしようか?」と提案する。
家庭との連携
子どもの姿(再掲):園に飾ってある雛人形に興味を持ち、「うれしいひなまつり」を歌うたびに「おひなさまいたよね」とうれしそうに話していた。
- 家庭でも、伝統行事について触れるきっかけとなるように、雛人形に興味を示す姿を具体的に伝えたり、ひな祭りがテーマの絵本を紹介する。
- 布パンツで過ごす様子を園と家庭で共有し、トイレで排尿できたり、自ら尿意を伝えられた姿を伝え合い、大いに認めることで自信につなげる。
本登録をして
他の文例を見る
Eさん(中月齢/男児/活発)(2歳7カ月/8月生まれ)
子どもの姿
- オムツに排尿することが多いが、登園後すぐや主活動の前などの決まったタイミングでトイレに行く習慣が定着してきて、排尿できることも増えた。(養護)
- リズムあそびやわらべうたあそびを楽しむ中で、保育者や友だちと手をつなぎたがる姿が見られた。(教育)
- 他学年の部屋に遊びに行っても緊張せず、好きな玩具を出して楽しんでいた。(家庭との連携)
ねらい/内容/環境構成・配慮・援助/評価・反省
養護
| 子どもの姿(再掲) |
オムツに排尿することが多いが、登園後すぐや主活動の前などの決まったタイミングでトイレに行く習慣が定着してきて、排尿できることも増えた。(養護) |
| ねらい |
トイレで排尿する心地よさを感じる |
| 内容 |
保育者の声かけで尿意に気づいたり、自ら尿意を感じてトイレに行き、排尿する。 |
| 環境構成・配慮・援助 |
本児の排尿サインを見逃さず、「おしっこが出そうかな?」「トイレに行く?」と誘い、便器に座って排尿できたときは、「トイレで出てすっきりしたね」と心地よさに共感する。遊びに夢中な場面ではトイレに行くことを嫌がる姿が多いため、無理強いはせず、タイミングを見計らって改めて誘い、焦らずに意欲を引き出す。 |
| 評価・反省 |
保育者に誘われてトイレに行き、排尿できると誇らしげだった。オムツに排尿した際に気にしつつも言い出さないことが多いため、「おしっこが出たかな?」と優しく聞き、自ら伝えられるように促す。 |
教育
| 子どもの姿(再掲) |
リズムあそびやわらべうたあそびを楽しむ中で、保育者や友だちと手をつなぎたがる姿が見られた。(教育) |
| ねらい |
友だちと簡単なやり取りをしながら遊ぶ楽しさを味わう |
| 内容 |
わらべうたあそびを通じて、友だちとふれあったり一緒に歌いながら、心地よく関わる。 |
| 環境構成・配慮・援助 |
「いっぽんばしこちょこちょ」「おせんべやけたかな」などの、ふれあいを楽しめる簡単なわらべうたあそびに誘い、楽しさを共有する。遊びを通じて友だちと関わりたがる姿を大切にし、保育者が手本を見せながら本児の手に優しく触れ、力加減を示すことで、友だちと心地よく安全に関われるように援助する。 |
| 評価・反省 |
友だちと遊びたい思いから手を引っ張る姿も見られたが、徐々に力加減がわかり、「いっぽんばししよう」と言葉のやり取りをしながら穏やかに関わる姿が増えた。子ども同士のやり取りに介入し過ぎず、安全に配慮しながら見守る。 |
食事
- 口に物を入れたまま話す姿が見られるので、少しずつマナーが身につくように、「もぐもぐごっくんしてからお話を聞かせてね」と優しく伝えていく。
- 苦手な野菜を机や床に落とそうとする姿が増えたので、抵抗感を減らすために盛り付けを一口程度にし、食べられたときは大いにほめ、次への意欲につなげる。
家庭との連携
子どもの姿(再掲):他学年の部屋に遊びに行っても緊張せず、好きな玩具を出して楽しんでいた。
- 新年度に向けて2歳児の部屋で遊ぶ機会を増やし、興味を持った玩具を自分で選んで遊びながらのびのびと過ごす本児の様子を伝えていき、進級に対する保護者の不安を和らげる。
- 感染症の流行が続く時期なので、日々の健康状態や体調の変化をこまめに伝え合い、悪化を防ぐ。
本登録をして
他の文例を見る
Fさん(中月齢/女児/活発)(2歳6カ月/9月生まれ)
子どもの姿
- 鼻水が出ると「鼻出た」と保育者に伝え、ティッシュを受け取ると自分なりに拭いてきれいにしようとしていた。(養護)
- 友だちとのトラブルでは、「いやだ」「だめだよ」などの言葉で思いを伝えられるようになってきたが、とっさに押してしまう場面もあった。(教育)
- 発熱はないが鼻水が増え、午睡の途中で目覚めたり、機嫌の悪い日が続いた。(家庭との連携)
ねらい/内容/環境構成・配慮・援助/評価・反省
養護
| 子どもの姿(再掲) |
鼻水が出ると「鼻出た」と保育者に伝え、ティッシュを受け取ると自分なりに拭いてきれいにしようとしていた。(養護) |
| ねらい |
清潔に関する簡単な身の回りのことを自分で行い、気持ちよさを感じる |
| 内容 |
鼻水などで顔や手が汚れたときは、保育者と一緒に拭いたり、自分で拭いてみる。 |
| 環境構成・配慮・援助 |
鼻水が出たときは「きれいにしようね」と声をかけ、手を添えて一緒に拭いたり、自分で拭く姿を見守り、「きれいに拭けたね」「さっぱりしたね」と認め、清潔になった気持ちよさを伝える。ティッシュを手が届く場所に配置し、取り方を伝えながら自分で拭けるように促し、清潔にする意識を育てる。 |
| 評価・反省 |
鼻水が出ると、ティッシュを自分で取りに行き拭く姿が見られるようになった。まだ鼻をかむことは難しいため、自分で拭けた姿を認め、「最後に仕上げをしようね」と誘い、鼻をかむ援助を行う。 |
教育
| 子どもの姿(再掲) |
友だちとのトラブルでは、「いやだ」「だめだよ」などの言葉で思いを伝えられるようになってきたが、とっさに押してしまう場面もあった。(教育) |
| ねらい |
思いやしてほしいことを言葉で伝える |
| 内容 |
ままごとやごっこあそびを通じて、友だちと簡単な言葉のやり取りを楽しむ。 |
| 環境構成・配慮・援助 |
トラブルを防ぎながら楽しく遊べるように、遊びのスペースを広く取り、道具や玩具を十分に用意する。保育者も遊びに参加し、「この玩具を貸してくれる?」「これと交換しようよ」といった言葉のやり取りを見せて自然とコミュニケーションが生まれるように関わり、本児が言葉で気持ちを伝えられたときは受け止め、必要に応じて言葉を添えて仲立ちする。 |
| 評価・反省 |
遊びの中で「これはFちゃんが使ってるの」「あとでね」と言葉で伝える姿が増え、トラブルの場面が減った。引き続き、遊びの場を広く取ったり少人数で遊べる環境を整えつつ、友だちと心地よいやり取りを楽しみながら遊べるように配慮する。 |
食事
- 自分で食べる姿を見守りながら、「温かくておいしいね」「甘いお芋だね」と会話を交わし、楽しい雰囲気で食べられるようにする。
- 鉛筆握りが安定してきた姿を大いに認め、「かっこよく持てているね」「お姉さんの持ち方だね」と伝えながら、自信につなげる。
家庭との連携
子どもの姿(再掲):発熱はないが鼻水が増え、午睡の途中で目覚めたり、機嫌の悪い日が続いた。
- 一日の中の寒暖差に留意して衣服の調整を行うとともに、日々の体調や午睡の様子を伝え合い、家庭と協力しながら健康に過ごせるよう配慮する。
- 新年度に向けて準備が必要な持ち物をわかりやすく一覧にまとめ、余裕を持って保護者に伝える。
本登録をして
他の文例を見る
Gさん(中月齢/男児/静か)(2歳5カ月/10月生まれ)
子どもの姿
- 保育者や気の合う友だちに誘われてトイレに行き、タイミングが合うと便器で排尿できることもあった。(養護)
- 折り紙をちぎったりシールを貼るなど、指先を使った製作あそびに喜んで参加していた。(教育)
- 泣いたり怒っている友だちのことを気にして、「どうしたの?」「泣いちゃったね」と言って慰めようとする姿が見られた。(家庭との連携)
ねらい/内容/環境構成・配慮・援助/評価・反省
養護
| 子どもの姿(再掲) |
保育者や気の合う友だちに誘われてトイレに行き、タイミングが合うと便器で排尿できることもあった。(養護) |
| ねらい |
トイレで排尿する心地よさを感じる |
| 内容 |
保育者に誘われて嫌がらずにトイレに行き、安心して便器に座り、排尿する。 |
| 環境構成・配慮・援助 |
無理なくトイレに行く経験を重ねられるように、遊びの切れ目を見計らって「トイレに行こう」と優しく誘う。便器に座る姿を大いに認めて自信を育み、排尿が成功したときは、「出たね」「すっきりしたね」と一緒に喜び、トイレで排尿する心地よさを感じられるようにする。 |
| 評価・反省 |
友だちがトイレに誘われる姿を見て、「Gちゃんも!」と一緒に向かい、便器で排尿できる姿も増えた。気分により拒否するときもあるため、思いを受け止めつつ、「これが終わったら」など、気持ちを切り替えるきっかけを作りながら対応する。 |
教育
| 子どもの姿(再掲) |
折り紙をちぎったりシールを貼るなど、指先を使った製作あそびに喜んで参加していた。(教育) |
| ねらい |
素材の感触を味わいながら、自分なりの表現を楽しむ |
| 内容 |
様々な大きさの紙に、クレヨンやペンでお絵描きをしたり、シールを貼って楽しむ。 |
| 環境構成・配慮・援助 |
クレヨンやペン、扱いやすい大きさのシールを十分に用意し、自由にお絵描きやシール貼りを楽しめる環境を整え、本児のつぶやきを見逃さず、「これは○○なんだね」と表現を受け止める。また、複数人で大きな模造紙や段ボールに描ける場を提供し、保育者も一緒に楽しみながら、「大きく描けたね」「たくさん貼ったね」と楽しさを共有し、ダイナミックな表現を促す。 |
| 評価・反省 |
シール貼りを集中して楽しみ、同じ場所に重ねようとしたり、並べて貼ろうとする姿も見られた。今後も夢中で取り組む姿を見守り、自由に表現する楽しさを味わえるように関わる |
食事
- 下握りになっているときは、鉛筆握りが安定するように、さりげなく手を添えて援助する。
- 友だちとふざけ合って足を動かしたり椅子に座りながら跳ねるときは、「危ないからやめましょう」と簡潔に伝えて止め、食事に意識を戻せるように、「次はどれにしようかな」といった声かけを行いながら、落ち着くまで側で見守る。
家庭との連携
子どもの姿(再掲):泣いたり怒っている友だちのことを気にして、「どうしたの?」「泣いちゃったね」と言って慰めようとする姿が見られた。
- 友だちに興味を持ち、優しく関わろうとする具体的なエピソードを通じて、本児の心の成長を保護者に感じてもらえるようにする。
- 園と家庭で協力しながらトイレに親しめるよう、お迎えの際に「トイレに座れたね」「おしっこが出たね」とできた部分を大いにほめ、意欲を育てる。
本登録をして
他の文例を見る
Hさん(中月齢/女児/静か)(2歳4カ月/11月生まれ)
子どもの姿
- 保育者に手伝ってもらったり励まされたりしながら、衣服や上着の着脱に挑戦していた。(養護)
- 体操や季節の歌、手遊びを楽しむ中で、保育者の姿を見て、体や手の動きをまねしていた。(教育)
- トイレに行くことを嫌がる姿が少しずつ減ってきた。(家庭との連携)
ねらい/内容/環境構成・配慮・援助/評価・反省
養護
| 子どもの姿(再掲) |
保育者に手伝ってもらったり励まされたりしながら、衣服や上着の着脱に挑戦していた。(養護) |
| ねらい |
自信を持って簡単な着脱を行う |
| 内容 |
保育者に見守られながら、自分で衣服を着たり、靴下を履く。 |
| 環境構成・配慮・援助 |
着脱を行う時間に余裕を持たせ、本児のペースで着脱に取り組む姿を急かさずに見守る。着脱しやすいように、「こうやって置こうね」と伝えながら衣服の向きを整えたり、難しい部分をさりげなく援助し、最後は「できたね」「頑張ったね」と本児の姿を大いに認め、達成感や自信を感じられるようにする。 |
| 評価・反省 |
上の服の着脱にも慣れ、時間をかけつつ自分で行う姿が見られた。うまくできない場面で「あー!」と言って怒る姿を受け止めつつ、「お手伝いがいるかな?」と問いかけ、助けを求められるように促す。 |
教育
| 子どもの姿(再掲) |
体操や季節の歌、手遊びを楽しむ中で、保育者の姿を見て、体や手の動きをまねしていた。(教育) |
| ねらい |
音楽に合わせて体を動かす楽しさや心地よさを感じる |
| 内容 |
リズムあそびに参加し、音楽や楽器の音に合わせて自由に動いたり、保育者や友だちの動きをまねする。 |
| 環境構成・配慮・援助 |
のびのびと動けるように広いスペースを用意し、友だちとの間隔を空けるように促し、衝突を防ぐ。保育者が楽しそうに楽器を鳴らしたり、大きく体を動かして見せる中で、「まねっこできたね」と声をかけながら本児の動きや表現を受け止め、体を動かす楽しさや模倣する面白さを共有する。 |
| 評価・反省 |
保育者の動きを模倣しようとする姿が多かったが、自由に動く友だちの姿にも目を向けるようになった。「○さんみたいにジャンプしよう」など、一緒に活動する友だちと楽しさを共有できるような言葉がけを意識的に行いたい。 |
食事
- 食事に時間がかかると飽きて手が止まるので、無理なく食べられるように、隣に座り「一緒に食べよう」と誘ったり、甘えを受け止めながら適切に介助する。
- 苦手な食材を一口でも食べられたときには、「自分で食べられたんだね」とその姿を認める言葉をかけ、様々な食材を食べてみようという意欲を育む。
家庭との連携
子どもの姿(再掲):トイレに行くことを嫌がる姿が少しずつ減ってきた。
- 園のトイレに慣れてきた姿を共有するとともに、家庭での様子を丁寧に聞き取ったり、対応に関する助言をしながら、保護者の不安を和らげる。
- この数カ月で少しずつ言葉数が増えてきた姿を大いに認め、保護者とともに成長を喜び合うとともに、本児の言葉の発達を来年度の担任に引き継ぎ、園全体で見守っていく。
本登録をして
他の文例を見る
Iさん(低月齢/男児/活発)(2歳3カ月/12月生まれ)
子どもの姿
- 排泄や着替えの際には進んで着脱を行うが、途中で引っかかると「できない!」と泣いて怒る姿が見られた。(養護)
- 友だちと玩具のやり取りをする中で、「これちょうだい」「どうぞ」など言葉で思いを伝えることができる一方で、とっさに言葉が出ずに無理やり取ってしまうこともあった。(教育)
- 遊びの中で楽しくなり興奮すると、ふざけて玩具を投げることがあり、保育者に止められると泣いてしまうこともあった。(家庭との連携)
ねらい/内容/環境構成・配慮・援助/評価・反省
養護
| 子どもの姿(再掲) |
排泄や着替えの際には進んで着脱を行うが、途中で引っかかると「できない!」と泣いて怒る姿が見られた。(養護) |
| ねらい |
簡単な着脱を行い、自分でできた喜びを味わう |
| 内容 |
保育者に見守られたり手伝ってもらいながら、自分のペースで衣服の着脱を行う。 |
| 環境構成・配慮・援助 |
安心して着脱に挑戦できるよう、「見てるね」と伝えて側で見守り、必要に応じて援助を行い、「できた」という喜びを味わえるようにする。うまくできずに怒る場面では、気持ちを受け止めながら、「お手伝いしようか」「一緒にやろう」と声をかけることで、気持ちを落ち着けて再挑戦できるようにする。 |
| 評価・反省 |
うまくできないときも、側にいる保育者と目を合わせると安心し、再び自分で挑戦したり、「やって」と助けを求める姿が見られた。自立心の育ちを大切にしながら見守りたい。 |
教育
| 子どもの姿(再掲) |
友だちと玩具のやり取りをする中で、「これちょうだい」「どうぞ」など言葉で思いを伝えることができる一方で、とっさに言葉が出ずに無理やり取ってしまうこともあった。(教育) |
| ねらい |
自分の思いを簡単な言葉で表現し、伝わる喜びを感じる |
| 内容 |
友だちとミニカーや電車の貸し借りをする中で、「ちょうだい」「いいよ」「あとでね」などの簡単な言葉を使って思いを伝える。 |
| 環境構成・配慮・援助 |
保育者も遊びに加わり、「ちょうだい」「いいよ」「あとでね」といった言葉でのやり取りを示し、思いが伝わる喜びを感じられるようにする。友だちとの関わりでとっさに言葉が出ないときは本児の思いを受け止め、「○○が使いたいんだね、かしてって聞いてみよう」「まだ使ってるんだね、あとでねって教えてあげよう」と言葉を促しながら仲立ちする。 |
| 評価・反省 |
「かして」などの言葉ともに身振り手振りを使い、友だちに思いを伝えようとする姿が増えた。思いが通じたときの喜びに共感しながら、他者とのやり取りを促していく。 |
食事
- 好きなおかずをよく噛まずに飲み込む姿が見られるため、「これが大好きなんだね」「おいしいよね」と共感しつつ、よく噛んで食べることを伝えていく。
- こぼしながらも下握りで食べる姿を見守り、本児自身で食材をすくいやすいようにさりげなく皿の手前に集め、「自分で食べられた」という経験を重ねていけるようにする。
家庭との連携
子どもの姿(再掲):遊びの中で楽しくなり興奮すると、ふざけて玩具を投げることがあり、保育者に止められると泣いてしまうこともあった。
- 本児の姿と合わせて、玩具の扱い方のルールや投げる危険性について根気よく丁寧に伝えたり、楽しい気持ちを表現する別の方法を一緒に考えるなどの園での関わり方を共有し、家庭と協力しながら一貫した対応を行う。
- 何でも自分でしようとする姿を具体的に伝え、家庭でも意欲を尊重し、寄り添った関わりをしてもらえるよう促す。
本登録をして
他の文例を見る
Jさん(低月齢/女児/活発)(2歳2カ月/1月生まれ)
子どもの姿
- 午睡の際に眠り過ぎてしまうことが減り、おやつの前に心地よく目覚め、夕方も機嫌よく過ごせた。(養護)
- 園庭あそびや延長保育の際には、年上の友だちの遊びに興味を持ち、ままごとやお絵描きに加わり、やり取りを楽しんでいた。(教育)
- 語彙が豊富で、園での日中の出来事や家庭であったことなどを盛んに話していた。(家庭との連携)
ねらい/内容/環境構成・配慮・援助/評価・反省
養護
| 子どもの姿(再掲) |
午睡の際に眠り過ぎてしまうことが減り、おやつの前に心地よく目覚め、夕方も機嫌よく過ごせた。(養護) |
| ねらい |
安定した生活リズムの中で、季節の変わり目を健康的に過ごす |
| 内容 |
午前中に十分体を動かし、食事の満足感を味わいながら心地よく入眠することで、休息を取りつつ元気に過ごす。 |
| 環境構成・配慮・援助 |
午前中は戸外や広い室内で全身を使う遊びを取り入れ、のびのびと体を動かせる環境を整える。食事中は「楽しかったね」「お腹がいっぱいになったね」と声をかけることで満足感を高め、午睡への移行をスムーズにし、入眠時は安心できるように側で見守るとともに、室温や湿度、調光を適切に保ち、心地よく眠れる環境を整える。 |
| 評価・反省 |
安定した生活リズムで過ごすことができ、体調不良も見られず、元気に過ごしていた。新年度になると環境が変わり疲れが出やすくなるため、様子をよく観察し、必要に応じて休息を促す。 |
教育
| 子どもの姿(再掲) |
園庭あそびや延長保育の際には、年上の友だちの遊びに興味を持ち、ままごとやお絵描きに加わり、やり取りを楽しんでいた。(教育) |
| ねらい |
異年齢の友だちとやり取りしたり、一緒に遊ぶ楽しさを味わう |
| 内容 |
異年齢の友だちとの手遊びやわらべうたあそびを通じて、簡単なやり取りやふれあいを楽しむ。 |
| 環境構成・配慮・援助 |
園庭で年上の子と「くまさんくまさん」を歌いながら体を動かしたり、室内で「ここはてっくび」「いとまき」を楽しみながら、動きの模倣やふれあいを楽しめるようにする。体格や力の差に留意して安全に関われるように見守りつつ、必要に応じて双方の思いを橋渡しし、楽しさを共有できるように援助する。 |
| 評価・反省 |
よく関わる友だちにはすっかり慣れて、姿を見かけると「○ちゃん」と自分から声をかけて交流を楽しんでいた。楽しくなってくると、年上の子の動きも激しくなり危険な場面が出てくるため、安全に配慮しながら関わりを見守る。 |
食事
- 疲れや苦手な食材の影響で、食べるペースが遅くなる姿が見られるため、「お手伝いしようか?」と優しく声をかけ、無理なく食べ進められるよう、適切に援助する。
- 鉛筆握りができているときには、「かっこよく持てるね」「先生や○さんと一緒だね」と認め、自信につなげていく。
家庭との連携
子どもの姿(再掲):語彙が豊富で、園での日中の出来事や家庭であったことなどを盛んに話していた。
- お迎えの際には、「今日はこんなことをしたね」と声をかけ、本児自らその日の出来事を保護者に伝えられるように促し、保護者と共に本児の話を受け止めながら、応答的に関わる。
- 衣服や靴が小さくなってきた際には、自分で着脱しにくそうな様子や歩きにくい姿を保護者に伝え、適切なサイズのものを準備してもらうよう依頼する。
本登録をして
他の文例を見る
Kさん(低月齢/男児/静か)(2歳1カ月/2月生まれ)
子どもの姿
- トイレに誘われると嫌がらずに便器に座ることができるようになり、一度だけタイミングが合い、トイレで排尿できた。(養護)
- 体力がついてきたことで、散歩の行きだけでなく、帰りも機嫌良く歩けるようになった。(教育)
- 月の後半から、家族が順番にインフルエンザに感染しており、二週間ほど休んでいる。(家庭との連携)
ねらい/内容/環境構成・配慮・援助/評価・反省
養護
| 子どもの姿(再掲) |
トイレに誘われると嫌がらずに便器に座ることができるようになり、一度だけタイミングが合い、トイレで排尿できた。(養護) |
| ねらい |
便器で排尿する心地良さを感じる |
| 内容 |
オムツが濡れていないタイミングで、保育者に見守られながら便器に座り、排尿する。 |
| 環境構成・配慮・援助 |
オムツが濡れていないタイミングや遊びの切れ目を見計らって優しくトイレに誘い、便器に座れた姿を大いにほめて、次への意欲につなげる。排尿できたときは、「出たね」「すっきりしたね」と心地よさを言葉にすることで、トイレで排尿する心地良さを感じられるようにする。 |
| 評価・反省 |
遊びのタイミングや体調によっては便器に座ることを嫌がる姿も見られたが、給食後や午睡明けに数回、トイレで排尿できた。排尿できた喜びに共感しながら、さらに意欲を育てたい。 |
教育
| 子どもの姿(再掲) |
体力がついてきたことで、散歩の行きだけでなく、帰りも機嫌良く歩けるようになった。(教育) |
| ねらい |
春の自然に親しみながら、戸外で活動する気持ちよさを味わう |
| 内容 |
保育者と手をつないで公園に出かけて歩く楽しさを感じたり、公園でゆったりと散策を楽しむ中で、草花や虫に興味を持つ。 |
| 環境構成・配慮・援助 |
散歩の道中では、季節の歌を歌いながら歩いて楽しさを共有したり、乗り物を発見して喜ぶ姿には、「電車が見えたね」「ショベルカーかっこいいね」と本児の思いを代弁しながら寄り添う。公園に到着したら危険物がないかを確認し、散策に誘う中で「タンポポが咲いてるね」「チョウチョが飛んでるね」と発見を伝え、春の訪れを感じられるようにする。 |
| 評価・反省 |
タンポポやシロツメクサを摘んで、収集バッグに集めて楽しんだ。日中の気温が高くなる日が増えたので、衣服の調整やこまめな水分補給を促しながら、心地よく活動できるように援助する。 |
食事
- こぼしながらも自分で食べる姿を見守りつつ、食べやすいように、必要に応じてさりげなく手や腕を支えて援助する。
- おかわりの際に「これ」と言いつつ皿を指差す姿には、「おかわりが欲しいんだね」と代弁しながら応じ、「たくさん食べられるね」「おいしいね」と声をかけて、食べる喜びや楽しさを感じられるように関わる。
家庭との連携
子どもの姿(再掲):月の後半から、家族が順番にインフルエンザに感染しており、二週間ほど休んでいる。
- 休み中の様子を詳しく聞き取り、体力の低下や生活リズムの乱れに留意しながら、職員間で連携して無理なく過ごせるよう配慮する。
- 日中の気温が上がっていく時期なので、調整しやすい服装で登園してもらえるよう依頼する。
本登録をして
他の文例を見る
Lさん(低月齢/女児/静か)(2歳0カ月/3月生まれ)
子どもの姿
- トイレに玩具を持ち込もうとする姿が減り、便器にも進んで座れるようになった。(養護)
- 室内でも戸外でもままごとがブームで、友だちと共にお手玉やチェーン、砂、石などの様々な素材を食材に見立て、皿に盛って保育者に渡したり、机に並べて楽しんでいた。(教育)
- 製作あそびではシール貼りに挑戦し、台紙や指から剥がすことに苦戦する姿も見られたが、楽しく取り組んでいた。(家庭との連携)
ねらい/内容/環境構成・配慮・援助/評価・反省
養護
| 子どもの姿(再掲) |
トイレに玩具を持ち込もうとする姿が減り、便器にも進んで座れるようになった。(養護) |
| ねらい |
トイレに親しみ、安心して便器に座って排尿しようとする |
| 内容 |
活動の切れ目やオムツが濡れていないタイミングで、嫌がらずにトイレに行き、便器に座る。 |
| 環境構成・配慮・援助 |
本児の排尿間隔を把握し、オムツが濡れていないタイミングで、「おしっこが出るかもしれないからトイレに行こう」と誘う。便器に座れたときは「座れたね」と認め、排尿しなくても「また座るところを見せてね」と言葉をかけ、次回からも自信を持ってトイレに行けるようにする。 |
| 評価・反省 |
トイレでの排尿はなかったが、便器に座ることへの抵抗感は見られなかった。トイレに対する拒否感が再び生じないよう、焦らずに見守る必要があることを、来年度の担任に引き継ぐ。 |
教育
| 子どもの姿(再掲) |
室内でも戸外でもままごとがブームで、友だちと共にお手玉やチェーン、砂、石などの様々な素材を食材に見立て、皿に盛って保育者に渡したり、机に並べて楽しんでいた。(教育) |
| ねらい |
見立てあそびを十分に楽しむ |
| 内容 |
保育者や友だちと一緒に、戸外で様々な自然物を利用しながらままごとを楽しむ。 |
| 環境構成・配慮・援助 |
砂場の近くにシートを敷いたり、机と椅子を配置して、友だちと一緒にままごとを楽しむことができる環境を整える。皿やコップ、自然物などを十分に用意し、保育者も遊びに加わる中で、「Lさんが作ったんだね」「おいしそうだね」と本児の行動を受け止めて共感したり、「お花の乗ったケーキはありますか?」といった言葉がけを行い、イメージをさらに広げられるようにする。 |
| 評価・反省 |
園庭に出るとすぐに砂場に向かい、草花や砂を食材に見立てて皿やカップに盛り付けてままごとを楽しんだ。友だちとの道具の貸し借りの場面では、本児なりの言葉やしぐさで思いを表現しようとしていたので、言葉を添えながら仲立ちしていく。 |
食事
- 手づかみを交えながらも意欲的に食べる姿を見守りつつ、「スプーンですくえるかな」と声をかけて意欲を引き出し、できたときには大いにほめて、自信につなげる。
- 汁物をスプーンですくったり、かき混ぜて遊んでいるときは、お椀を両手で持つと飲みやすいことをわかりやすく伝えながら、手を添えて援助し、習慣付くようにする。
家庭との連携
子どもの姿(再掲):製作あそびではシール貼りに挑戦し、台紙や指から剥がすことに苦戦する姿も見られたが、楽しく取り組んでいた。
- シール貼りを楽しむ姿を伝え、家庭でも取り入れやすいように、扱いやすいシールの大きさや援助の工夫を伝え、指先の発達を促していく。
- 家庭では遊び食べが続いているため、保護者の話を丁寧に聞きながら思いを受け止めるとともに、本児がよく食べる献立や無理なく食べられる量を伝え、一緒に見守っていく。
本登録をして
他の文例を見る
その他、ほいくのおまもりプラスのコンテンツ
> その他の【月案・週案・個人案】を見る。