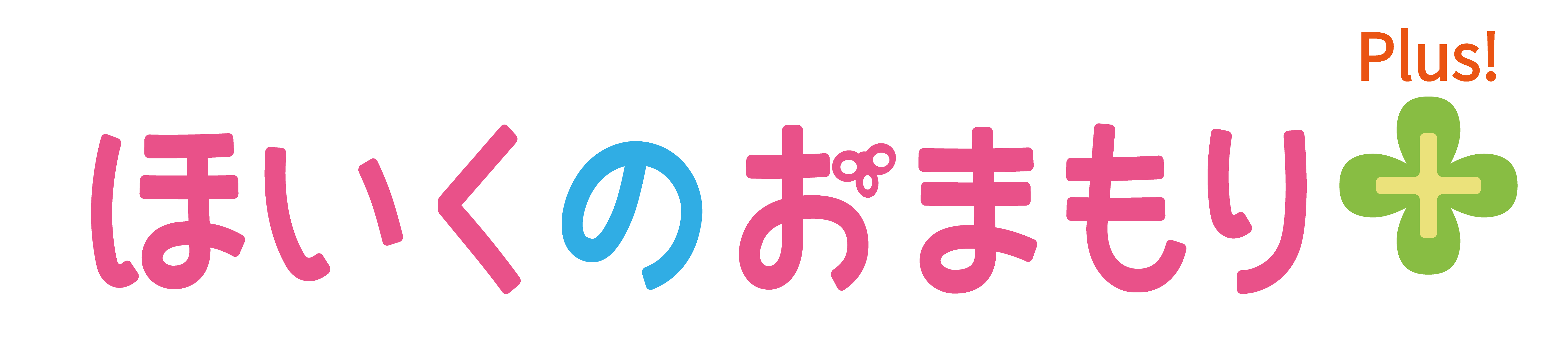個人案PDF
ダウンロードはこちら
敬称と性別表記について
LGBTQ+の観点から、保育士が園児を表記する際は『くん』『ちゃん』を使わず、『さん』で統一、園児が自身を称する際や園児同士のやり取りを記載する場合は『ちゃん』で統一しています。また、発達段階の観点では性差はあると考えられるため、男児/女児としています。
Aさん(高月齢/男児/活発)(2歳2カ月/4月生まれ)
子どもの姿
- 排泄や着替えの際に自分でズボンを履こうとする意欲が見られ、前後が反対になったり、お尻の部分が上がりきらなくても気にせず、「できた」と保育者に伝えていた。(養護)
- 友だちが使っている玩具に興味を示し、黙って取ってしまうことでトラブルになることがあった。(教育)
- 思い通りにいかない場面では、大きな声を出したり、その場で座ったり寝転がったりして怒る様子が見られた。(家庭との連携)
ねらい/内容/環境構成・配慮・援助/評価・反省
養護
| 子どもの姿(再掲) |
排泄や着替えの際に自分でズボンを履こうとする意欲が見られ、前後が反対になったり、お尻の部分が上がりきらなくても気にせず、「できた」と保育者に伝えていた。(養護) |
| ねらい |
簡単な着脱を自分でしようとする |
| 内容 |
保育者に見守られたり手伝ってもらいながら、ズボンの着脱を自分で行い、達成感を味わう。 |
| 環境構成・配慮・援助 |
安定した手作りのベンチや床に座りながら、安全に着脱できるよう配慮し、本児の意欲を尊重しながら見守る中で、必要に応じてズボンを履きやすいよう整えて置いたり、苦戦している部分をさりげなく援助する。最後までできた姿を大いに認め、「頑張ったね」と声をかけ、次につなげる。 |
| 評価・反省 |
落ち着いて自分で取り組み、難しい部分では、そばにいる保育者に助けを求める姿も見られた。衣服の着脱の機会が増える時期のため、時間に余裕を持たせて見守りながら、意欲を育んでいく。 |
教育
| 子どもの姿(再掲) |
友だちが使っている玩具に興味を示し、黙って取ってしまうことでトラブルになることがあった。(教育) |
| ねらい |
思いやしてほしいことを簡単な言葉で表現する |
| 内容 |
保育者の仲立ちのもと、友だちと玩具をやり取りする中で、「かして」「どうぞ」「あとでね」といった簡単な言葉で自分の思いを伝える。 |
| 環境構成・配慮・援助 |
保育者も一緒に遊びながら、玩具のやり取りを行い、「これ貸して」「どうぞ」といった簡単な言葉で思いを表現する見本を示す。子ども同士のやり取りの中で、とっさに言葉が出ないときは、「貸してって一緒に聞いてみようか」「あとでねって伝えてみよう」と言葉を補いながら仲立ちし、本児なりに思いを表現できたときは、「言えたね」と認め、自信につなげる。 |
| 評価・反省 |
保育者の仲立ちで、「かして」「ちょうだい」といった言葉で気持ちを表現できた。本児の希望が通らない場面では、納得いかず怒ることもあるが、その気持ちに寄り添いつつ、相手にも思いがあることを丁寧に伝えていく。 |
食事
- 苦手な食材を嫌がるときは、一緒ににおいをかいでみたり、保育者が食べて見せながら味や食感を伝え、本児が少しずつ「食べてみようかな」という気持ちを持てるようにする。
- 姿勢が崩れているときは、「前を見て食べようね」と優しく伝えつつ椅子の位置を調整し、前を向いて食べられた姿を大いに認め、自信につなげる。
家庭との連携
子どもの姿(再掲):思い通りにいかない場面では、大きな声を出したり、その場で座ったり寝転がったりして怒る様子が見られた。
- 「○○したかったんだね」と本児の気持ちを言葉にして受け止めつつ、落ち着いて必要な行動に移れるよう援助するとともに、園と家庭で様子を伝え合い、声かけや対応を統一しながら、一貫した関わりを行う。
- 自分でズボンの着脱を行う姿を伝え、家庭でもその姿を大切にしてもらえるように働きかけながら、意欲を育む。
Bさん(高月齢/女児/活発)(2歳1カ月/5月生まれ)
子どもの姿
- 排泄後にオムツやズボンを履くことを嫌がって拒否する姿が見られ、保育者に時間をかけて説得され、履かせてもらうことがあった。(養護)
- 寒天の感触あそびでは、興味を示しつつも触ることを嫌がっていたが、保育者や友だちの様子を見て、徐々に触れられるようになった。(教育)
- 休日は家で布パンツを履いているが、園では「いや」と言って履きたがらなかった。(家庭との連携)
ねらい/内容/環境構成・配慮・援助/評価・反省
養護
| 子どもの姿(再掲) |
排泄後にオムツやズボンを履くことを嫌がって拒否する姿が見られ、保育者に時間をかけて説得され、履かせてもらうことがあった。(養護) |
| ねらい |
保育者と一緒に楽しみながら着脱を行う |
| 内容 |
信頼する保育者に甘えを受け止めてもらったり、難しい部分を手伝ってもらいながら、オムツやズボンを履く。 |
| 環境構成・配慮・援助 |
解放感からオムツやズボンを履きたがらないときは、本児の気持ちに寄り添いながら、「お腹が冷えるから履こうね」と必要性を伝えたり、「お手伝いするよ」と優しく誘う。甘えを受け止めつつ援助し、自分でできそうな部分はさりげなく手を離して見守り、「履けたね」と大いに認め、できた喜びや達成感を感じられるようにする。 |
| 評価・反省 |
布パンツで過ごすようになり、履くことを嫌がる姿は見られなくなった。着脱を手伝ってほしがるときは、気持ちを受け止めながら、焦らずに自立を促していく。 |
教育
| 子どもの姿(再掲) |
寒天の感触あそびでは、興味を示しつつも触ることを嫌がっていたが、保育者や友だちの様子を見て、徐々に触れられるようになった。(教育) |
| ねらい |
保育者や友だちのしていることに興味を持ち、まねして遊ぼうとする |
| 内容 |
保育者や友だちと一緒に、園庭で水や泥に触れて遊び、感触を楽しむ。 |
| 環境構成・配慮・援助 |
泥あそび用の玩具や遊ぶスペースを十分に確保し、ゆったりと遊べる環境を整える。泥を触ることを嫌がる場合は無理強いせず、周りの様子を見られるようにし、保育者が泥団子を作ったり、水を流して遊ぶ姿を見せることで興味を引き出したり、小さなバケツや容器に水や泥を入れて、指先で触ったりこぼして遊ぶ楽しさを感じられるようにする。 |
| 評価・反省 |
泥に触ることに抵抗がなくなり、保育者や友だちと一緒に水を流したり、スコップや手で柔らかくなった地面を叩いたり掘ったりして楽しんでいた。来月からも水遊びに加え、寒天や粘土、氷など、様々な素材を使った感触あそびも取り入れていく。 |
食事
- 片手が机の上に出ていないときは、「手を机の上に出そうね」「器を持とうね」と声をかけながら、さりげなく手を添えて食べやすくなるよう援助する。
- 皿に食材が残っている場合は、「一緒に集めようか」「お手伝いしようか」と提案し、本児の後ろから手を添えて援助しながら、「全部食べられたね」と声をかけ、最後まできれいに食べられた喜びを感じられるようにする。
家庭との連携
子どもの姿(再掲):休日は家で布パンツを履いているが、園では「いや」と言って履きたがらなかった。
- 「お家でパンツを履いてるんだね」「お兄ちゃんとおそろいでかっこいいね」と伝えながら、園でも履く意欲が高まるようにする。
- 持ち物の名前を確認し、記名がなかったり消えかけているときは、改めて書いてもらうよう丁寧に伝える。
Cさん(高月齢/男児/静か)(2歳0カ月/6月生まれ)
子どもの姿
- 手洗いの際、腕まくりを忘れて洗い始めたり、タオルで拭かずに濡れたままで部屋に戻ろうとすることがあった。(養護)
- 友だちがそばに来ると、玩具や場所を取られると感じるのか、保育者の近くへ移動したり、相手を押そうとする姿が見られるようになった。(教育)
- オムツ交換や着替えの際、保育者に促されると自分でズボンを履こうとするものの、うまくできないと諦めて座っていることがあった。(家庭との連携)
ねらい/内容/環境構成・配慮・援助/評価・反省
養護
| 子どもの姿(再掲) |
手洗いの際、腕まくりを忘れて洗い始めたり、タオルで拭かずに濡れたままで部屋に戻ろうとすることがあった。(養護) |
| ねらい |
手洗いのやり方を知り、自分なりにやってみようとする |
| 内容 |
戸外あそびや給食の前に、保育者と一緒に丁寧に手を洗う。 |
| 環境構成・配慮・援助 |
手洗いを一緒に行う中で、保育者がやって見せながら、「できるかな?」とまねできるように促したり、必要に応じて「腕まくりをしようね」「石けんをつけてゴシゴシしようね」「タオルで拭こうね」など、具体的な声かけや援助を行い、手洗いのやり方が身につくよう関わる。できた部分を大いに認めたり、清潔になった気持ちよさに寄り添いながら、意欲を育む。 |
| 評価・反省 |
保育者のまねをしながら、丁寧に手洗いを行うことができた。腕まくりを忘れたり、拭くのが不十分なこともあるため、必要に応じて声をかけたり手を添えて援助し、習慣として身につくようにしていく。 |
教育
| 子どもの姿(再掲) |
友だちがそばに来ると、玩具や場所を取られると感じるのか、保育者の近くへ移動したり、相手を押そうとする姿が見られるようになった。(教育) |
| ねらい |
好きな遊びを十分に楽しみ、満足感を味わう |
| 内容 |
保育者に見守られながら安心して一人遊びを楽しんだり、仲立ちしてもらいながら、友だちと気持ちよくやり取りする。 |
| 環境構成・配慮・援助 |
玩具の種類や数、スペースを十分に確保して落ち着いて遊べる環境を整え、集中して遊ぶ姿を見守り、時には遊びに加わり楽しさを共有する。友だちとの関わりが見られた際は、保育者がそばで見守り、安心感を与えながら、必要に応じて双方の思いを代弁し、気持ちよくやり取りができるよう橋渡しを行う。 |
| 評価・反省 |
玩具の数と遊ぶスペースを十分に確保したことで、玩具や場所の取り合いが減り、一人ひとりが集中して遊べていた。友だちとの関わりでは手が出ることがあるため、すぐに止めて思いを受け止めながら、心地よい関わり方を伝えていく。 |
食事
- 本児のペースで食べ進める様子を見守り、手が止まっているときは「次はどれにしようか?」と声をかけたり、スプーンに食材をすくって渡し、食事に意識が向くよう働きかける。
- 体調や眠気、疲れによって食事が進まない場合は、無理なく食べられるよう介助したり、様子を見て切り上げるなど、柔軟に対応する。
家庭との連携
子どもの姿(再掲):オムツ交換や着替えの際、保育者に促されると自分でズボンを履こうとするものの、うまくできないと諦めて座っていることがあった。
- 本児が自分でできそうな部分を見極め、必要に応じて援助しながら見守り、自らできたときは大いにほめて保護者にも共有し、家庭と連携して意欲を育てていく。
- 苦手な食材でも、保育者に励まされたり友だちの姿に刺激を受けたりしながら食べられることが増えてきた様子を伝え、成長を感じてもらえるようにする。
本登録をして
他の文例を見る
Dさん(高月齢/女児/静か)(1歳11カ月/7月生まれ)
子どもの姿
- 体調不良で数日欠席したあとから甘えが強くなり、普段はできる簡単な着脱や給食を自分で食べることを嫌がり、保育者に手伝いを求めることがあった。(養護)
- 机上あそびコーナーのパズルを気に入り、保育者と一緒に楽しむだけでなく、一人で集中して取り組む姿も見られるようになった。(教育)
- お迎えの際に帰りたがらなかったり、直前に遊んでいた玩具を持って帰りたがって泣くことがあった。(家庭との連携)
ねらい/内容/環境構成・配慮・援助/評価・反省
養護
| 子どもの姿(再掲) |
体調不良で数日欠席したあとから甘えが強くなり、普段はできる簡単な着脱や給食を自分で食べることを嫌がり、保育者に手伝いを求めることがあった。(養護) |
| ねらい |
甘えを受け止めてもらいながら安心して過ごす |
| 内容 |
自分なりに表現した思いを信頼する保育者に受け止めてもらい、励まされたり手伝ってもらいながら、安心して簡単な身の回りのことに取り組む。 |
| 環境構成・配慮・援助 |
体調の変化に留意しながら甘えを受け止め、普段はできることでも本児の様子に合わせて、「一緒にお着替えしようね」「一緒に食べようね」と優しく声をかけて援助し、安心できるようにする。自分でできそうな部分はそばで見守り、できたときには「自分でできたね」と伝えて認め、焦らずに自信を育む。 |
| 評価・反省 |
甘えを受け止めてもらうことで、徐々に情緒が安定し、着脱などを自分でしようとする姿が増えてきた。自分でできた喜びや達成感を味わえるよう、声かけや援助の工夫を職員間で共有し、対応を統一していく。 |
教育
| 子どもの姿(再掲) |
机上あそびコーナーのパズルを気に入り、保育者と一緒に楽しむだけでなく、一人で集中して取り組む姿も見られるようになった。(教育) |
| ねらい |
好きな遊びを十分に楽しみ、満足感を味わう |
| 内容 |
机上あそびのコーナーで、好きな玩具を選び、保育者に見守られながら遊ぶ。 |
| 環境構成・配慮・援助 |
本児の発達に合ったパズルや指先を使う玩具を、自ら選んで手に取りやすいように配置し、落ち着いて遊べる環境を整える。保育者が一緒に楽しみながら遊び方を示し、できる部分は見守り、集中できるよう配慮しながら、できた喜びや達成感に寄り添う。 |
| 評価・反省 |
パズルに加え、ひも通しやれんげすくいに興味を持ち、くり返し楽しむ様子が見られた。徐々に慣れてきたため、パズルの絵柄や大きさ、玩具の種類を入れ替えながら、「試したい」「遊びたい」という気持ちを満たせるようにする。 |
食事
- スプーンの下握りが安定し、こぼすことが減ってきたため、「こぼさずにすくえたね」とその姿を認め、自信を持って食べられるようにする。
- 食べさせてもらいたがるときは、甘えを受け止めて介助しながら「次はどれを食べる?」「おいしいね」とゆったりとやり取りを楽しみ、食べる喜びを感じられるようにする。
家庭との連携
子どもの姿(再掲):お迎えの際に帰りたがらなかったり、直前に遊んでいた玩具を持って帰りたがって泣くことがあった。
- 帰りたがらなかったり玩具を手放したくない気持ちを受け止めながら、その日にあった楽しかったことやできたことについて、「今日は○○したんだよね」「自分で○○ができたんだよね」と保護者の前で伝え、気持ちを切り換えやすいようにする。
- 暑い日はシャワーで汗を流すことがあるため、体拭き用タオルを用意してもらう。
本登録をして
他の文例を見る
Eさん(中月齢/男児/活発)(1歳10カ月/8月生まれ)
子どもの姿
- オムツに排尿しても気にする様子はなく、保育者に「出た?」と聞かれても、「ない」と返事をする姿が見られた。(養護)
- 保育者と一緒に絵本を読みながら、「これなに?」「これは?」と様々な物を指差し、やり取りを楽しんでいた。(教育)
- 園庭で泥あそびを楽しみ、泥のついた手を木のベンチや乾いたコンクリートに押しつけて手形を作り、喜んでいた。(家庭との連携)
ねらい/内容/環境構成・配慮・援助/評価・反省
養護
| 子どもの姿(再掲) |
オムツに排尿しても気にする様子はなく、保育者に「出た?」と聞かれても、「ない」と返事をする姿が見られた。(養護) |
| ねらい |
排尿したことに気づき、言葉やしぐさで伝える |
| 内容 |
保育者の声かけや自身でオムツに排尿したことに気づき、交換してもらうことで清潔になった心地よさを感じる。 |
| 環境構成・配慮・援助 |
オムツに排尿しても気にしていないときは、タイミングを見極めながら「ちっちが出たね、きれいにしようか」と声をかけて気づきを促す。オムツを交換しながら、「すっきりしたね」と心地よさを言葉にして伝え、排尿した感覚に気づけるようにし、本児なりに伝えようとするときは、「教えてくれたんだね」と受け止め、自信につなげていく。 |
| 評価・反省 |
自ら排尿を知らせる姿はなかったが、保育者に聞かれると「出た」と答えることもあった。引き続き排尿したことへの気づきを促す声かけを行うとともに、オムツが濡れていないタイミングでトイレに誘いながら、排尿の感覚に意識が向くよう働きかけていく。 |
教育
| 子どもの姿(再掲) |
保育者と一緒に絵本を読みながら、「これなに?」「これは?」と様々な物を指差し、やり取りを楽しんでいた。(教育) |
| ねらい |
絵本を通じたやり取りを楽しむ |
| 内容 |
保育者と一緒に好きな絵本をくり返し読み、簡単な言葉のやり取りをしたり、絵本の中の動きをまねしたりして楽しむ。 |
| 環境構成・配慮・援助 |
興味に沿った絵本を手に取りやすい場所に配置し、自ら選べる環境を整える。一緒に絵本を読む中で、本児の指差しや言葉を受け止め、「Eさんの好きな○○だね」「これは○○だよ」などと丁寧に応えながら言葉のやり取りをしたり、絵本の中の動きやくり返しの言葉を一緒にまねし、楽しさを共有する。 |
| 評価・反省 |
新しい絵本に興味を持ち、盛んに言葉のやり取りを楽しんでいた。最近は野菜の絵本が気に入っているため、絵本に出てくる野菜に実際に触れる機会を作り、さらに興味を育みたい。 |
食事
- 苦手な食材を嫌がることが増えたため、一口分など少量で提供し、保育者が目の前でにおいをかいだり、おいしそうに食べて見せながら、焦らずに興味を引き出す。
- 保育者に励まされて一口でも食べられたときは、その姿を大いに認めて「食べられたんだね」「先生と一緒だね」と声をかけ、意欲を育む。
家庭との連携
子どもの姿(再掲):園庭で泥あそびを楽しみ、泥のついた手を木のベンチや乾いたコンクリートに押しつけて手形を作り、喜んでいた。
- 自然に触れながら発見し、楽しむ様子を具体的に伝え、本児の興味や関心を保護者と共有し、家庭での遊びにも活かせるようにする。
- 友だちへの関心が高まり、トラブルが起こることもあるため、懇談会やおたよりを通じて、言葉が未熟でとっさに手が出てしまいやすいこの時期の発達の特徴を保護者に丁寧に伝えていく。
本登録をして
他の文例を見る
Fさん(中月齢/女児/活発)(1歳9カ月/9月生まれ)
子どもの姿
- 便がゆるい日が続いたことでお尻がかぶれ、オムツ交換の際に痛がって泣くことがあった。(養護)
- 戸外だけでなく、室内でも活発に動きたがり、走ったり、ジャンプなどの動きをする姿が見られた。(教育)
- 特定の保育者との信頼関係が築かれ、一対一の関わりを求めるなど、こだわりがみられるようになった。(家庭との連携)
ねらい/内容/環境構成・配慮・援助/評価・反省
養護
| 子どもの姿(再掲) |
便がゆるい日が続いたことでお尻がかぶれ、オムツ交換の際に痛がって泣くことがあった。(養護) |
| ねらい |
清潔を保ちながら快適に過ごす |
| 内容 |
こまめにオムツを交換したり、排便後や汗をかいたあとにシャワーで体を洗ってもらい、清潔になった心地よさを感じる。 |
| 環境構成・配慮・援助 |
汗をかきやすい時期を快適に過ごせるよう、こまめなオムツ交換や着替えを促し、必要に応じてシャワーで体を洗い流して清潔を保つ。オムツ交換や着替え、シャワーを行う際は、「さっぱりしたね」「きれいになったね」と声をかけ、心地よさに共感する。 |
| 評価・反省 |
オムツかぶれが落ち着いて以降は、肌のトラブルは見られなかった。気温と湿度が高まり、主活動後や午睡明けは特に汗をかきやすいため、必要に応じて着替えを促し、快適に過ごせるようにする。 |
教育
| 子どもの姿(再掲) |
戸外だけでなく、室内でも活発に動きたがり、走ったり、ジャンプなどの動きをする姿が見られた。(教育) |
| ねらい |
十分に体を動かすことを楽しむ |
| 内容 |
室内での運動あそびを通じて、のぼる、くぐる、またぐ、飛び下りるなどの動きを十分に行い、満足感を味わう。 |
| 環境構成・配慮・援助 |
広いスペースにマットの山やトンネル、巧技台などの遊具を十分な間隔を空けて配置し、自分のペースで安全に楽しめるよう配慮する。職員間で連携し、各遊具のそばで見守りながら、本児の動きを認めて「上までのぼれたね」「ジャンプできたね」と声をかけ、満足感を味わえるようにする。 |
| 評価・反省 |
少し高い段差から飛び下りる動きに慣れ、くり返し楽しむ姿が見られた。室内で過ごす時間が増えるため、運動発達に個人差があることに配慮し、ケガを防ぎながら、体を動かして楽しめる環境を整えていく。 |
食事
- 好きなものや柔らかいものをよく噛まずに飲み込むことがあるため、「カミカミしようね」と伝えたり、保育者の口元を見せてまねできるよう促し、噛む習慣が身につくようにする。
- スプーンに多くすくい過ぎてこぼすことがあるため、すくう量を確認し、必要に応じて手を添えて一緒にすくい、食べやすいように援助する。
家庭との連携
子どもの姿(再掲):特定の保育者との信頼関係が築かれ、一対一の関わりを求めるなど、こだわりがみられるようになった。
- 特定の保育者を安全基地として、甘えたり離れたりしながら安心して過ごし、成長を見せる様子を保護者に伝え、園への信頼を深めていく。
- 気温や湿度が高くなるため、体調の変化に留意し、機嫌や食欲など、いつもと違う様子が見られる場合は、こまめに保護者と情報共有する。
本登録をして
他の文例を見る
Gさん(中月齢/男児/静か)(1歳8カ月/10月生まれ)
子どもの姿
- 体力が付いたためか、睡眠のリズムに変化が見られ、午前睡をせずに機嫌良く過ごせる日があった。(養護)
- 体操やリズムあそびでは、体を動かさずに部屋の隅で周りの様子をじっと見ていることが多かった。(教育)
- 保育者と一緒に絵本を読みながら、出てくるものを次々と指差したり、「あ!」と声を出し、保育者に「○○だよ」と答えてもらうことを楽しんでいた。(家庭との連携)
ねらい/内容/環境構成・配慮・援助/評価・反省
養護
| 子どもの姿(再掲) |
体力が付いたためか、睡眠のリズムに変化が見られ、午前睡をせずに機嫌良く過ごせる日があった。(養護) |
| ねらい |
心地よい生活リズムで過ごす |
| 内容 |
必要に応じて休息を取りながら、元気に活動に参加したり機嫌良く給食やおやつを食べ、満足感を味わう。 |
| 環境構成・配慮・援助 |
前日の就寝時間や体調に配慮し、機嫌良く過ごせるよう、必要に応じて適切なタイミングで休息を促す。食事の時間は基本的に一番早いグループに入れるが、午前睡を十分に取ったり時間がずれた場合には、職員間で連携して後のグループにずらし、活動を十分に楽しみ、心地よい空腹感を感じながら給食に向かえるよう、個別の配慮を行う。 |
| 評価・反省 |
午前睡を取らずに、給食まで機嫌良く過ごせる日が増えてきた。水遊びが始まると疲れが出やすいため、本児の様子を職員間で共有しながら、柔軟に対応していく。 |
教育
| 子どもの姿(再掲) |
体操やリズムあそびでは、体を動かさずに部屋の隅で周りの様子をじっと見ていることが多かった。(教育) |
| ねらい |
音楽に合わせて体を動かすことを楽しむ |
| 内容 |
手遊びや体操を通じて、保育者のまねをしながら手や体を自分なりに動かし、面白さを感じる。 |
| 環境構成・配慮・援助 |
一対一で簡単な手遊びを行い、まねできたときは「できたね」「楽しいね」と声をかけ、楽しさを感じられるようにする。体操やリズムあそびの際は、本児のペースを尊重し、嫌がらない程度に手をつないで体を動かす援助を行ったり、保育者が視線を合わせながら、楽しそうに体を動かして見せることで、意欲を引き出していく。 |
| 評価・反省 |
一対一や少人数での手遊びは楽しめるが、集団になると他児の動きに圧倒され、固まる姿が多かった。本児のペースを大切にしながら保育者がそばに寄り添い、周りの様子を一緒に観察し、友だちの楽しそうな様子を伝えながら安心感を育み、焦らずに意欲を引き出していく。 |
食事
- 食材をうまくすくえないときは、様子を見てさりげなく手を支えて援助する。
- 苦手な野菜を口から出したり、「やー」と言って拒否して食べたがらないことがあるため、気持ちを受け止めつつ、「先生が食べるから見ててね」と伝え、食べて見せることで、徐々に興味を持てるようにする。
家庭との連携
子どもの姿(再掲):保育者と一緒に絵本を読みながら、出てくるものを次々と指差したり、「あ!」と声を出し、保育者に「○○だよ」と答えてもらうことを楽しんでいた。
- 家庭でも絵本を通じたやり取りを楽しめるよう、本児が気に入っている絵本を紹介し、本児の反応や発語、それに対する保育者の応答的な関わりを、具体的に伝えていく。
- 週明けは疲れが見られることが多いため、休み中の過ごし方を丁寧に聞き取り、無理なく過ごせるよう配慮する。
本登録をして
他の文例を見る
Hさん(中月齢/女児/静か)(1歳7カ月/11月生まれ)
子どもの姿
- 午睡の途中で目が覚めたときは、信頼する保育者に優しくトントンしてもらったり、抱っこしてもらうことで再入眠できた。(養護)
- 友だちに興味を示し、近づいて頭を撫でるなど、自分なりに関わろうとするものの、力加減がわからず押してしまうこともあった。(教育)
- 戸外では歩行に消極的で、砂場などで座り込んで遊ぶ姿が多かったが、保育者と手をつないで歩くことを喜ぶ姿も見られた。(家庭との連携)
ねらい/内容/環境構成・配慮・援助/評価・反省
養護
| 子どもの姿(再掲) |
午睡の途中で目が覚めたときは、信頼する保育者に優しくトントンしてもらったり、抱っこしてもらうことで再入眠できた。(養護) |
| ねらい |
安心して一定時間眠る |
| 内容 |
快適な環境で午睡を取り、途中で目が覚めたときは、保育者に優しくトントンしてもらったり子守唄を歌ってもらうことで、安心して再入眠する。 |
| 環境構成・配慮・援助 |
午睡の環境は、快適な室温や湿度、採光を保ち、オムツや衣服が汚れているときは清潔なものに替えて、心地よく眠れるよう配慮する。途中で目覚めたときは、優しく体をトントンしたり、子守唄を歌いながらそばで見守り、安心して再び眠れるよう援助する。 |
| 評価・反省 |
体調を崩した影響で、うまく寝付けないときや午睡の途中で目覚めたときに、泣いたり声を出して抱っこを求める姿が増えた。本児の気持ちに寄り添いながら、落ち着いた声かけや優しく体をさするなど、安心して入眠できる援助を続けていく。 |
教育
| 子どもの姿(再掲) |
友だちに興味を示し、近づいて頭を撫でるなど、自分なりに関わろうとするものの、力加減がわからず押してしまうこともあった。(教育) |
| ねらい |
友だちとの心地よい関わり方を知る |
| 内容 |
簡単な手遊びやわらべうたあそびを通じて、保育者や友だちと一緒に気持ちよく体を動かし、楽しさを共有する。 |
| 環境構成・配慮・援助 |
少人数で輪になり、「手をたたきましょう」「おてぶしてぶし」などの簡単な手遊びやわらべうたあそびを行い、保育者が動きを見せながら楽しく参加できるようにする。保育者や友だちと一緒に手足や体を動かしたり動きをまねる楽しさに寄り添い、「おんなじだね」「できたね」と声をかけ、友だちと関わる楽しさを感じられるようにする。 |
| 評価・反省 |
友だちの動きを見てまねしたり、そばにいる友だちと手をつなごうとするなど、子ども同士のやり取りを楽しむ様子が見られた。安全に関われるよう見守りながら、必要に応じて仲立ちしていく。 |
食事
- 意欲的にスプーンで食べ、食べこぼしも減ってきたため、自分で食べる姿を見守りながら、「おいしいね」と声をかけ、安心して楽しく食べられるようにする。
- 徐々に安定した下握りへと移行できるよう、持ち方を観察し、必要に応じてさりげなく手を添えて知らせていく。
家庭との連携
子どもの姿(再掲):戸外では歩行に消極的で、砂場などで座り込んで遊ぶ姿が多かったが、保育者と手をつないで歩くことを喜ぶ姿も見られた。
- 園と家庭で連携しながら本児の歩く意欲を育めるよう、園庭や公園で保育者と手をつないで楽しく歩く様子を伝え、送迎時や休みの日などにも靴を履いて歩く経験ができるよう働きかける。
- 園生活に慣れ、本児なりに生活の見通しを持ちながら安心して過ごす様子を伝え、成長を感じられるようにする。
本登録をして
他の文例を見る
Iさん(低月齢/男児/活発)(1歳6カ月/12月生まれ)
子どもの姿
- オムツ交換や着替えの際に、保育者に促されて、自分でズボンの着脱を行おうとする姿が見られた。(養護)
- 戸外でも室内でも活発に体を動かし、特にすべり台を気に入ってくり返し楽しんでいた。(教育)
- 保育者に手や体を支えてもらいながら、便器に座ることができた。(家庭との連携)
ねらい/内容/環境構成・配慮・援助/評価・反省
養護
| 子どもの姿(再掲) |
オムツ交換や着替えの際に、保育者に促されて、自分でズボンの着脱を行おうとする姿が見られた。(養護) |
| ねらい |
簡単な身の回りのことをやってみようとする |
| 内容 |
保育者に見守られる中でズボンの着脱に挑戦し、できた喜びを感じる。 |
| 環境構成・配慮・援助 |
本児のペースで着脱に挑戦できるよう、時間に余裕を持たせ、「ズボンを脱ごうね」「履いてみようね」と優しく声をかけて誘い、本児なりに取り組む姿をそばで見守る。お尻の部分を引き上げたり、足を入れるなどの難しい部分ではさりげなく援助し、できたときには目を見て「できたね」「頑張ったね」と伝え、達成感を味わえるようにしながら意欲を育む。 |
| 評価・反省 |
保育者に援助してもらいながら、意欲的に着脱に取り組んでいた。水遊びに向けて着脱の機会がさらに増えるため、できることから楽しんで挑戦できるようにする。 |
教育
| 子どもの姿(再掲) |
戸外でも室内でも活発に体を動かし、特にすべり台を気に入ってくり返し楽しんでいた。(教育) |
| ねらい |
様々な体の動かし方を楽しむ |
| 内容 |
室内で、好きな遊具を見つけてくり返し遊びながら、のぼる、おりる、くぐる、またぐといった様々な動きを十分に行う。 |
| 環境構成・配慮・援助 |
室内の広いスペースに、すべり台や巧技台、トンネルなどの遊具を十分な間隔を空けて配置し、保育者は安全に留意しながら各遊具のそばで見守る。くり返し楽しむ姿を受け止めながら、「のぼれたね」「くぐれたね」とできたことを言葉にして伝え、体を動かす楽しさを十分に味わえるようにする。 |
| 評価・反省 |
様々な遊具に興味を示し、十分に楽しむことができた。同じ遊具で遊ぶ友だちを押し退けようとする姿が見られるときは、「次は○さんの番だから、ここで見ていようね」「Iさんの番が来たよ」と順番を丁寧に伝え、安全に遊べるよう援助する。 |
食事
- スプーンを使って食べようとする姿を大切にしながら見守り、自分ですくいやすいように、食材をさりげなく皿の端に集めておく。
- 苦手な野菜を口から出すときは、出した物をさりげなく片づけて衛生面に配慮し、「これはピーマンだよ」「シャキシャキしてるね」と声をかけ、保育者がおいしそうに食べて見せることで、興味を引き出す。
家庭との連携
子どもの姿(再掲):保育者に手や体を支えてもらいながら、便器に座ることができた。
- 便器に座れた際の保育者の援助や声かけを共有し、保護者と一緒に成長を喜びながら、焦らずトイレに親しめるよう、引き続き丁寧に関わっていく。
- 病欠明けは、家庭での様子を保護者から丁寧に聞き取り、必要に応じて園から連絡することを伝え、保護者と連絡がつきやすい体制を整える。
本登録をして
他の文例を見る
Jさん(低月齢/女児/活発)(1歳5カ月/1月生まれ)
子どもの姿
- 手洗いの際に、水や泡に触れることを喜び、遊んでしまう姿が増えた。(養護)
- 友だちの玩具を取ったり、場所をめぐって押したり、噛みつこうと口を開く姿が見られるようになった。(教育)
- 戸外での歩行を楽しむものの、よく転び、ひざをすりむいたり、顔や口元にケガをすることがあった。(家庭との連携)
ねらい/内容/環境構成・配慮・援助/評価・反省
養護
| 子どもの姿(再掲) |
手洗いの際に、水や泡に触れることを喜び、遊んでしまう姿が増えた。(養護) |
| ねらい |
保育者と一緒に丁寧に手を洗おうとする |
| 内容 |
戸外あそび後や食前に、保育者と一緒に石けんを使いながら楽しく手を洗い、清潔になった気持ちよさを感じる。 |
| 環境構成・配慮・援助 |
水や泡に触れる気持ちよさに共感しながら、保育者が楽しい歌を歌いながら手洗いの見本を示し、興味を引き出す。必要に応じて、本児の後ろから手を添えて丁寧に洗えるよう援助し、「泡がいっぱいで気持ち良いね」「さっぱりしたね」と声をかけ、清潔になった気持ちよさを感じられるようにし、徐々に手洗いの習慣が身につくように関わる。 |
| 評価・反省 |
手洗い場で遊ぶ姿が減り、自分なりに手を合わせたりこすって洗おうとする姿が見られた。洗い方や拭き方が不十分な部分をさりげなく援助しつつ、本児の意欲を十分に認め、習慣が定着するようにする。 |
教育
| 子どもの姿(再掲) |
友だちの玩具を取ったり、場所をめぐって押したり、噛みつこうと口を開く姿が見られるようになった。(教育) |
| ねらい |
好きな遊びを見つけ、安心してじっくり楽しむ |
| 内容 |
机上あそびのコーナーで好きな玩具を見つけ、保育者に見守られながら遊ぶ。 |
| 環境構成・配慮・援助 |
一人ひとりのスペースを十分に確保し、安心して遊べる環境を整え、本児の興味や発達に合った玩具を手に取りやすい位置に配置する。本児の選択を尊重し、遊び方を示しながら一緒に楽しんだり、集中して遊ぶ様子を見守り、できたときには「できたね」と伝えて満足感を味わえるようにすることで、くり返し楽しむ意欲を育む。 |
| 評価・反省 |
ぽっとん落としやれんげすくい、お絵描きなどの遊びを、椅子に座って集中して楽しんでいた。机上あそび以外の場面でも、遊ぶスペースを十分に確保し、安心してじっくり遊べる環境を整える。 |
食事
- 食事の前半は自分で食べようとする姿が増えてきたため、「自分で食べられたね」「スプーンですくえたね」と声をかけ、その姿を大いに認めながら意欲を育む。
- 苦手な食材を食べたがらずに拒否するときは、保育者が食べて見せて興味を持てるようにしたり、好きなおかずと一緒に食べられるよう配慮し、徐々に慣れていけるようにする。
家庭との連携
子どもの姿(再掲):戸外での歩行を楽しむものの、よく転び、ひざをすりむいたり、顔や口元にケガをすることがあった。
- ケガをした際は状況を正確に伝え、患部を保護者にも確認してもらい、丁寧に受け答えしながら不安を軽減する。
- 登園時に雨でも、晴れ間が出た際に戸外遊びや散歩に出られるよう、必ず靴を用意してもらうことを周知する。
本登録をして
他の文例を見る
Kさん(低月齢/男児/静か)(1歳4カ月/2月生まれ)
子どもの姿
- 食後に顔を拭かれたり、鼻水やよだれを拭き取られることを嫌がり、顔を背けたり、泣いて嫌がっていた。(養護)
- 歩数が増え、足元が不安定ながらも室内での探索を楽しむ姿が見られた。(教育)
- 休日明けは疲れが見られ、眠りながら登園することもあった。(家庭との連携)
ねらい/内容/環境構成・配慮・援助/評価・反省
養護
| 子どもの姿(再掲) |
食後に顔を拭かれたり、鼻水やよだれを拭き取られることを嫌がり、顔を背けたり、泣いて嫌がっていた。(養護) |
| ねらい |
清潔にしてもらうことを喜び、気持ちよく過ごす |
| 内容 |
鼻水やよだれ、食後の口周りの汚れを優しく拭いてもらったり、保育者に手を添えてもらいながら一緒に拭き、清潔になった心地よさを感じる。 |
| 環境構成・配慮・援助 |
顔を拭く前に、目を合わせて「鼻水が出ているからきれいにしようね」「ふきふきしてさっぱりしようね」と、安心感を与える声かけをする。嫌がるときは、「めんめんすーすー」などのわらべうたあそびを楽しみながら手や顔に触れ、さりげなく拭いたり、本児にガーゼを持たせて鏡を見ながら一緒に拭き、抵抗感を減らしていく。 |
| 評価・反省 |
顔を拭かれることへの抵抗感が徐々に減り、「お顔を拭こうね」と声をかけられると、目を閉じて準備したり、自分で拭こうとすることもあった。本児の意欲を大切にしつつ、最後は必ず仕上げを行う。 |
教育
| 子どもの姿(再掲) |
歩数が増え、足元が不安定ながらも室内での探索を楽しむ姿が見られた。(教育) |
| ねらい |
探索活動を楽しむ |
| 内容 |
室内やテラスを探索し、興味のある玩具や遊具を見つけ、保育者に発見を受け止めてもらったり、一人遊びを十分に楽しむ。 |
| 環境構成・配慮・援助 |
本児の興味を引く玩具を手が届く位置に配置し、安全に探索を楽しめるように、床に落ちている玩具はこまめに片付ける。「あんよができたね」「楽しいね」と歩く楽しさに共感する声かけをしたり、「見つけたね」「面白いね」と伝えて発見に寄り添い、見つけた玩具で安心して一人遊びを楽しめるよう、そばで見守る。 |
| 評価・反省 |
ハイハイや歩行で探索を楽しみ、目的の玩具を手に取ると、その場に座り遊ぶ姿が見られた。保育者が声をかけ過ぎると、玩具を手放して抱っこを求めることがあるため、声かけには配慮し、過度にならないようにする。 |
食事
- 手づかみ食べをする姿が増えてきたため、本児の意欲を大切にしながら見守り、「おいしいね」と声をかけて共感し、楽しい食事の雰囲気を作る。
- 自分でコップを持とうとするが、落としたりこぼしてしまうことが多いため、さりげなく手を添えて安定して持てるよう援助し、「飲めたね」と声をかけて、自信につなげる。
家庭との連携
子どもの姿(再掲):休日明けは疲れが見られ、眠りながら登園することもあった。
- 休み明けは家庭と連携し、休み中の過ごし方を聞き取りながら生活リズムを戻せるよう個別に配慮し、お迎えの際には園での様子を共有する。
- ロンパース型の肌着や衣服が多い家庭には、上下に分かれた服を少しずつ用意してもらうよう丁寧に伝え、自分で着脱しようとする意欲を育めるよう働きかける。
本登録をして
他の文例を見る
Lさん(低月齢/女児/静か)(1歳3カ月/3月生まれ)
子どもの姿
- 散歩やオムツ交換に誘われると、自分のロッカーから帽子やおしりふき、オムツを取り出し、準備に協力しようとする姿が見られるようになった。(養護)
- つかまり立ちから手を離して立っていられる時間が長くなり、一歩踏み出しそうな姿も見られた。(教育)
- 積み木や型落としなど、指先を使う遊びを楽しんでいた。(家庭との連携)
ねらい/内容/環境構成・配慮・援助/評価・反省
養護
| 子どもの姿(再掲) |
散歩やオムツ交換に誘われると、自分のロッカーから帽子やおしりふき、オムツを取り出し、準備に協力しようとする姿が見られるようになった。(養護) |
| ねらい |
簡単な身の回りのことをやってみようとする |
| 内容 |
戸外あそびやオムツ交換の際に、保育者と一緒に準備をしたり、ズボンや靴下などの簡単な着脱に挑戦し、自分でできた喜びを感じる。 |
| 環境構成・配慮・援助 |
本児なりに次の活動の準備をする姿を見守り、「帽子を持ってきてくれたんだね」「オムツを出してくれたんだね」とできたことを言葉にして認め、自信を育む。着脱は安定した場所で座って行えるよう配慮し、難しい部分は保育者が援助し、最後に引っ張り上げるなど、本児ができる部分に挑戦できるよう促し、「できたね」と声をかけ、達成感や喜びを感じられるようにする。 |
| 評価・反省 |
保育者の声かけに合わせて体を動かしたり、促されて靴下を引っ張り上げるなど、意欲的に着脱に参加していた。自分でできた達成感を味わえるよう、声かけや関わりを工夫しながら、さらに意欲を育んでいきたい。 |
教育
| 子どもの姿(再掲) |
つかまり立ちから手を離して立っていられる時間が長くなり、一歩踏み出しそうな姿も見られた。(教育) |
| ねらい |
十分に体を動かすことを楽しむ |
| 内容 |
室内の広いスペースで、ハイハイや伝い歩きで探索したり、手押し車を押して遊ぶ。 |
| 環境構成・配慮・援助 |
ハイハイや伝い歩きをしやすいように、玩具をこまめに片付け、本児の好奇心を刺激する玩具や遊具を配置し、周囲を探索することを促す。手押し車で遊ぶ際は、周囲の安全に配慮し、「進んだね」「楽しいね」と、体を動かす楽しさに共感しながら、歩く意欲を育む。 |
| 評価・反省 |
探索や移動の際はハイハイが多いものの、一人歩きが始まり、両手でバランスを取りながら数歩ずつ歩いて楽しむ姿が見られた。転びやすいため安全に配慮し、歩く楽しさに寄り添いながら見守る。 |
食事
- 日によって食べムラがあるため、嫌がるときは無理強いせず、気分転換を図りながら好きなおかずを勧めたり、早めに切り上げるなど、柔軟に対応する。
- 自分で食べる姿を大いに認め、保育者も同じおかずを食べる姿を見せることで、食事の楽しさを感じられるようにする。
家庭との連携
子どもの姿(再掲):積み木や型落としなど、指先を使う遊びを楽しんでいた。
- 指先の力加減が上手になってきた様子を伝え、現在の発達に合った玩具や手遊びを紹介して、家庭での遊びの参考となるようにする。
- 本児の好きな食材や献立をこまめに共有し、園と家庭で連携しながら食への意欲を育んでいく。
本登録をして
他の文例を見る
その他、ほいくのおまもりプラスのコンテンツ
> その他の【月案・週案・個人案】を見る。