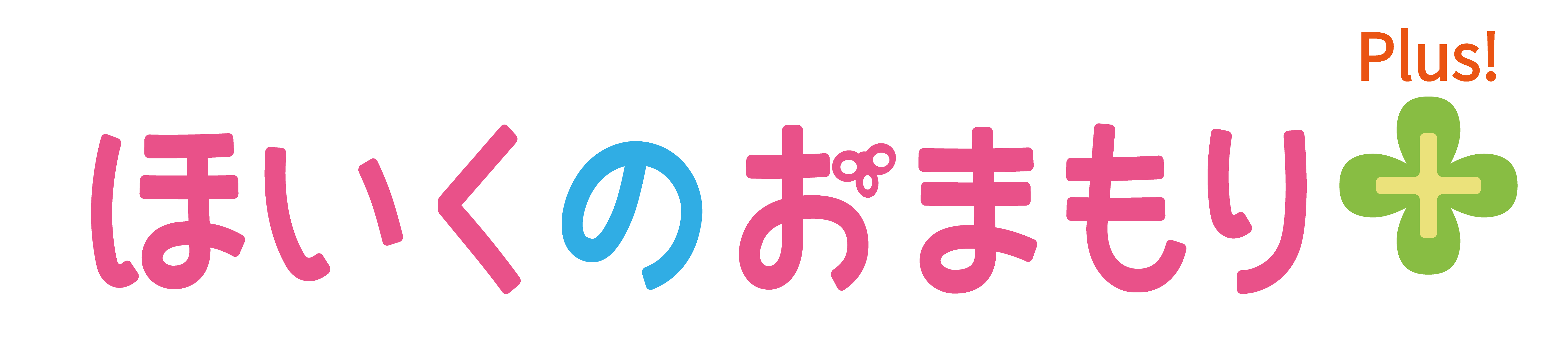個人案PDF
ダウンロードはこちら
敬称と性別表記について
LGBTQ+の観点から、保育士が園児を表記する際は『くん』『ちゃん』を使わず、『さん』で統一、園児が自身を称する際や園児同士のやり取りを記載する場合は『ちゃん』で統一しています。また、発達段階の観点では性差はあると考えられるため、男児/女児としています。
Aさん(高月齢/男児/活発)(2歳10カ月/4月生まれ)
子どもの姿
- トイレでの排尿が安定してきたが、遊びに夢中になっている中でオムツに排尿したときは、言い出しにくそうにもじもじする姿が見られた。(養護)
- 戸外で追いかけっこをしたり、雪や霜柱に触れたり踏んだりして、感触を味わっていた。(教育)
- 買い物ごっこでは、普段の生活の再現をしたり、保育者や友だちと言葉でのやり取りを盛んに楽しんでいた。(家庭との連携)
ねらい/内容/環境構成・配慮・援助/評価・反省
養護
| 子どもの姿(再掲) |
トイレでの排尿が安定してきたが、遊びに夢中になっている中でオムツに排尿したときは、言い出しにくそうにもじもじする姿が見られた。(養護) |
| ねらい |
尿意に気づいてトイレに行こうとする |
| 内容 |
保育者に声をかけられたり自ら尿意に気づいてトイレに行き、排尿する心地よさを感じる。 |
| 環境構成・配慮・援助 |
排尿サインを見逃さずに声をかけて尿意に気づけるようにし、トイレに向かえたときは「間に合ったね」と大いにほめ、自信につなげる。タイミングが合わずにオムツに排尿してしまったときは、本児の気まずさに寄り添いつつ、「またトイレに行こうね」「おしっこがしたくなったら、教えてね」と、次へとつながる前向きな言葉がけを行う。 |
| 評価・反省 |
遊びを切り上げられずにオムツに排尿する場面もあったが、その後に自分なりのタイミングでトイレに向かい、オムツを交換してもらったり、便器に座っていた。本児のペースを大切にしながら、焦らずに見守っていく。 |
教育
| 子どもの姿(再掲) |
戸外で追いかけっこをしたり、雪や霜柱に触れたり踏んだりして、感触を味わっていた。(教育) |
| ねらい |
冬の自然に興味を持ち、不思議さや面白さを感じる |
| 内容 |
戸外で雪や氷、霜柱などの自然物を見つけ、手で触ったり足で踏みながら感触を楽しむ。 |
| 環境構成・配慮・援助 |
気温が下がる前日に、バケツや小さなカップに水を張って氷ができるように準備したり、安全に配慮しながら雪遊びを行う。本児なりに自由に自然物に触れる姿を見守りながら、「ツルツルするね」「冷たいね」「溶けちゃったね」など、感触や形が変わる不思議さや面白さを言葉にして伝え、好奇心を育む。 |
| 評価・反省 |
保育者と一緒に「ぎゅっぎゅっ」と言いながら雪の上を歩き、踏む感触を楽しんだ。暖かくなってきたら散歩に出かけ、園庭にはない自然物にも触れられるようにして、さらに興味を育みたい。 |
食事
- 山盛りに食材をすくって食べようとする姿が見られるので、安全に配慮してさりげなく止め、一口量をすくって示しながら、「このくらいが食べやすいよ」と伝える。
- 姿勢が崩れているときは、椅子や机の高さが合っているか確認するとともに、「前を向こうね」「手は机の上に出そうね」と、わかりやすい言葉がけを行う。
家庭との連携
子どもの姿(再掲):買い物ごっこでは、普段の生活の再現をしたり、保育者や友だちと言葉でのやり取りを盛んに楽しんでいた。
- 特定の友だちとのやり取りが増えてきたので、関わる様子を具体的に伝え、家庭でも園での話をするきっかけとなるようにする。
- 登園時に離れたがらなかったり、逆に帰りたがらないなどの甘えが見られるときは、保護者に協力を仰いで時間をもらい、本児が気持ちを切り替えられるように、思いを受け止めながら関わる。
Bさん(高月齢/女児/活発)(2歳9カ月/5月生まれ)
子どもの姿
- 下痢と嘔吐が続いて一週間ほど休み、登園時は保護者と離れたがらない姿が見られ、食欲も落ちていた。(養護)
- ボタンかけの玩具で遊び、できると「見て!」と保育者に見せていた。(教育)
- 保育者の話や説明をよく覚えており、製作あそびでハサミを使った日は、お迎えの際に「チョッキンしたよ」「ハサミは危ないんだよ」と保護者に伝えていた。(家庭との連携)
ねらい/内容/環境構成・配慮・援助/評価・反省
養護
| 子どもの姿(再掲) |
下痢と嘔吐が続いて一週間ほど休み、登園時は保護者と離れたがらない姿が見られ、食欲も落ちていた。(養護) |
| ねらい |
保健的で安全な環境でゆったりと過ごしながら、安心感を味わう |
| 内容 |
保育者に思いを受け止めてもらったり、体調に合わせて十分な休息を取りながら、快適に過ごす。 |
| 環境構成・配慮・援助 |
感染症の流行が続く時期なので、下痢や嘔吐の処理について再確認するとともに、日々室温や湿度を適切に保ったり、玩具や家具の消毒をこまめに行い、感染症の拡大を防止しながら快適に過ごせる環境を整える。機嫌が悪いときはその後の体調の変化にも注意しつつ、スキンシップを図りながら思いを受け止めたり、静かな環境で体を休められるように配慮し、安心して過ごせるように関わる。 |
| 評価・反省 |
今月も発熱で欠席したり、咳や鼻水などの風邪症状が見られた。引き続き保育室内の消毒や換気を徹底するとともに、本児の体調に合わせて無理なく過ごせるよう、個別に対応する。 |
教育
| 子どもの姿(再掲) |
ボタンかけの玩具で遊び、できると「見て!」と保育者に見せていた。(教育) |
| ねらい |
指先を使った遊びを十分に楽しむ中で、充実感を味わう |
| 内容 |
保育者に見守られながら、ボタンかけや洗濯ばさみ遊びを楽しむ。 |
| 環境構成・配慮・援助 |
椅子や床に座りながら、落ち着いて取り組むことができる環境を整える。集中して楽しむ様子を近くで見守り、本児が保育者に顔を向けた際は、目を合わせながら「できたね!」と喜びに共感し、達成感や充実感を味わえるように関わる。 |
| 評価・反省 |
人形の服のボタンもかけられるようになり、指先の動きが少しずつ巧みになってきた。遊びの中で手指の様々な動きを経験できるように、発達を促す玩具を選んで入れ替えたり、手作りしながら取り入れたい。 |
食事
- 友だちとやり取りをしながら落ち着いて食べる姿を見守り、時にやり取りに加わり、みんなと一緒に食べる楽しさや喜びに共感する。
- 病み上がりで食欲がない日は食べる手が止まっていたので、普段と違う様子が見られるときは、「もうお腹がいっぱいかな」と尋ね、本児の様子に合わせて切り上げるなど、柔軟に対応する。
家庭との連携
子どもの姿(再掲):保育者の話や説明をよく覚えており、製作あそびでハサミを使った日は、お迎えの際に「チョッキンしたよ」「ハサミは危ないんだよ」と保護者に伝えていた。
- 本児なりに保護者に伝えようとする姿を側で見守り、必要に応じて言葉を補いながら、思いが伝わる喜びを感じられるようにするとともに、保護者にも本児の成長を感じてもらえるようにする。
- 様々な自己主張が見られる時期なので、保護者の悩みや不安に寄り添いつつ、思いを受け止めながら関わる大切さを丁寧に伝えていく。
Cさん(高月齢/男児/静か)(2歳8カ月/6月生まれ)
子どもの姿
- 寒さからか、手洗いを嫌がる姿が見られた。(養護)
- シール貼りを楽しみ、たくさん貼ることができると「見て」と保育者に声をかけて見せていた。(教育)
- 着脱を自分なりに行い、「できた」と言って保育者に見せたり、うまくできずに怒る姿も見られた。(家庭との連携)
ねらい/内容/環境構成・配慮・援助/評価・反省
養護
| 子どもの姿(再掲) |
寒さからか、手洗いを嫌がる姿が見られた。(養護) |
| ねらい |
嫌がらずに手洗いをする |
| 内容 |
保育者と一緒に丁寧に手を洗い、きれいになった心地よさを感じる。 |
| 環境構成・配慮・援助 |
本児の思いに寄り添いつつ、「バイキンがついているからきれいにしよう」「このまま食べると、お腹が痛くなっちゃうよ」と手洗いの必要性をわかりやすく知らせ、納得できるように関わる。本児が「やってみようかな」と思えるように、先に洗った友だちや保育者の手を見せて「きれいになったよ」と伝えたり、保育者が手を添えて一緒に行う中で、季節の歌を歌い、本児が楽しさや面白さを感じられるようにする。 |
| 評価・反省 |
保育者と一緒に行いたがっていたが、徐々に一人で洗う姿も増えてきた。自ら手洗いできた姿を大いに認め、意欲を育む。 |
教育
| 子どもの姿(再掲) |
シール貼りを楽しみ、たくさん貼ることができると「見て」と保育者に声をかけて見せていた。(教育) |
| ねらい |
集中して好きな遊びを楽しむ |
| 内容 |
机上あそびのコーナーで、パズルやシール貼り、ひも通しを十分に楽しむ。 |
| 環境構成・配慮・援助 |
好きな玩具を選び、落ち着いて遊ぶことができる室内環境を整える。必要に応じて遊び方や約束事を示したあとは過度に声をかけず、集中して遊ぶ姿を見守るとともに、本児の「見て」を見逃さずに受け止め、夢中で遊んだ満足感に共感する。 |
| 評価・反省 |
ひも通しがうまくできずに怒る姿が見られたが、保育者と一緒に行い、ひもが通ると「できた!」と喜んでいた。うまくできない場面での葛藤を受け止めながら見守るとともに、くり返し遊ぶ楽しさを感じられるように関わる。 |
食事
- 苦手な食材を避けているときは、少量を口に運べるように励ましたり、好きなおかずやご飯と一緒に食べられるようにし、本児が無理なく「食べられた」という感覚を味わえるように工夫しながら関わる。
- 「ごちそうさま」の挨拶を忘れて立ち上がろうとするときは、「おしまいにするんだね、一緒にごちそうさまをしようか」と誘う。
家庭との連携
子どもの姿(再掲):着脱を自分なりに行い、「できた」と言って保育者に見せたり、うまくできずに怒る姿も見られた。
- 意欲的に着脱を行う本児の姿勢や、その日にできた部分について共有し、成長を感じてもらえるようにする。
- 好き嫌いをしたり、自分で食べたがらないという家庭での悩みに寄り添って様子を聞き取るとともに、園での姿や保育者の関わり方を具体的に伝えながら、一緒に見守っていく。
本登録をして
他の文例を見る
Dさん(高月齢/女児/静か)(2歳7カ月/7月生まれ)
子どもの姿
- 室内で過ごす時間は布パンツを履くようになり、遊びに夢中で漏らしてしまうこともあったが、活動前のタイミングや尿意を感じたときには、進んでトイレに行くことができた。(養護)
- 遊具や運動遊びで順番を抜かしてしまう子に対して、やや語気強く「順番だよ!」と伝える姿が見られた。(教育)
- 長靴を履いて登園してくる日があり、戸外遊びの際にも履きたがることがあった。(家庭との連携)
ねらい/内容/環境構成・配慮・援助/評価・反省
養護
| 子どもの姿(再掲) |
室内で過ごす時間は布パンツを履くようになり、遊びに夢中で漏らしてしまうこともあったが、活動前のタイミングや尿意を感じたときには、進んでトイレに行くことができた。(養護) |
| ねらい |
布パンツに慣れ、トイレで排泄する |
| 内容 |
布パンツを履いて安心して過ごす中で、保育者に誘われたり、尿意を感じて自らトイレに行く。 |
| 環境構成・配慮・援助 |
自ら尿意に気づくことができたときは大いに認めて自信につなげ、遊びに夢中になっているときは排尿前のサインを見逃さずにトイレに誘う。漏らしたときは本児の自尊心を傷つけないように配慮しながら関わり、「大丈夫だよ、着替えようね」と安心できる声かけをしながら速やかに片付けや着替えを行う。 |
| 評価・反省 |
漏らす回数は少なかったが、尿意を気にし過ぎているためか、トイレに行く回数が多かった。神経質になっている様子が見られるときはオムツを履く提案をして、本児が安心して過ごせるように配慮する。 |
教育
| 子どもの姿(再掲) |
遊具や運動遊びで順番を抜かしてしまう子に対して、やや語気強く「順番だよ!」と伝える姿が見られた。(教育) |
| ねらい |
思いを言葉で表現し、相手に伝わる喜びを感じる |
| 内容 |
同じ遊びを楽しむ友だちに、自分の思いやしてほしいことを、簡単な言葉で伝える。 |
| 環境構成・配慮・援助 |
上手に話すことができるが、相手に伝わりきらずに歯がゆさを感じると、怒ったり語気が強くなる姿も見られた。子ども同士のやり取りを見守りつつ、必要に応じて言葉を補ったり、伝わりやすい表現に言い換えて仲立ちするとともに、相手にも思いがあることを丁寧に伝え、互いに通じ合う喜びを感じられるように援助する。 |
| 評価・反省 |
「○ちゃん、これちょうだい」「何作ってるの?」など、盛んに友だちと関わり、言葉のやり取りを楽しんでいた。今後も、保育者は遊びに入りながらやり取りに加わり、必要に応じてさりげなく仲立ちしていく。 |
食事
- 献立や体調によって食欲にムラがあるので、量を調整して提供し、励ましながら見守ったり、本児の体調や眠気によっては、完食にこだわらずに切り上げる。
- 皿に残った食材をすくいきれないときは保育者に助けを求めるので、安心できるように「頑張ったんだね、一緒にやろうね」と伝えながら、手を添えて援助する。
家庭との連携
子どもの姿(再掲):長靴を履いて登園してくる日があり、戸外遊びの際にも履きたがることがあった。
- 安全に戸外遊びを楽しめるように、戸外遊び用に履きなれた靴を必ず持参してもらい、長靴は持ち帰ってもらえるようにする。
- 布パンツで過ごす様子を伝え合い、園と家庭で連携しながら本児の排泄の自立を見守っていく。
本登録をして
他の文例を見る
Eさん(中月齢/男児/活発)(2歳6カ月/8月生まれ)
子どもの姿
- 好きな遊びを切り上げることが苦手で、片付けが始まったりお迎えが来ても、「だめなの」「まだ」と言って怒ったり、泣く姿が増えた。(養護)
- 戸外では寒さに負けずに走ったり、遊具で遊ぶことを楽しみ、全身を動かしていた。(教育)
- インフルエンザで欠席したが、登園後は機嫌よく過ごし、食欲もあった。(家庭との連携)
ねらい/内容/環境構成・配慮・援助/評価・反省
養護
| 子どもの姿(再掲) |
好きな遊びを切り上げることが苦手で、片付けが始まったりお迎えが来ても、「だめなの」「まだ」と言って怒ったり、泣く姿が増えた。(養護) |
| ねらい |
思いを受け止めてもらいながら、自分なりに気持ちを切り替えようとする |
| 内容 |
生活の流れを自分なりに理解し、保育者に思っていることや不安を受け止めてもらいながら、安心して次の活動に移る。 |
| 環境構成・配慮・援助 |
次の活動に向けて気持ちを切り替えやすいように、事前に個別に声をかけ、「もうすぐ給食が始まるよ、楽しみだね」「もうすぐお迎えが来るから、○○したらお片付けにしよう」とわかりやすく見通しを伝える。気持ちの切り替えが難しいときは、「もっと遊びたかったね」「また続きをしようね」と本児の思いに寄り添いながら、折り合いをつけられるように関わる。 |
| 評価・反省 |
保育者と一緒にきり良く遊びを終え、気持ちよく次の活動に移る姿が増えてきた。引き続き個別に配慮しながら、気持ちを切り替える援助を行う。 |
教育
| 子どもの姿(再掲) |
戸外では寒さに負けずに走ったり、遊具で遊ぶことを楽しみ、全身を動かしていた。(教育) |
| ねらい |
寒さに負けず、全身を動かして遊ぶ心地よさを味わう |
| 内容 |
保育者や友だちと一緒に、戸外で追いかけっこやしっぽ取りを楽しむ。 |
| 環境構成・配慮・援助 |
散策などで十分に体を温めてから、追いかけっこやしっぽ取りに誘う。楽しくなり興奮してしまうと、一人で違う場所へ走っていってしまう姿も見られるので、遊びの援助を担当する保育者が対応し、本児の楽しさに寄り添いつつルールがわかるように一緒に動き、遊びに戻れるようにする。 |
| 評価・反省 |
最初は喜んで遊びに加わっても、途中で離れてしまう姿が多く、保育者に誘われて戻ることもあれば、違う遊びを始めることもあった。本児の興味関心を大切にしながら、簡単なルールのある遊びを取り入れていき、友だちと遊ぶ楽しさを感じられるように関わりたい。 |
食事
- 隣に座る友だちの姿が気になって横を向いてしまうときは、一緒に食べる楽しさや喜びに共感しつつ、「危ないから前を向いて食べようね」と言葉をかける。
- 意欲的に自分で食べる姿を見守りながら、「たくさん食べられたね」「こぼさず飲めたね」とできた部分をさりげなく伝え、自信につなげる。
家庭との連携
子どもの姿(再掲):インフルエンザで欠席したが、登園後は機嫌よく過ごし、食欲もあった。
- 感染症が流行しやすい時期が続くので、手洗いうがいを奨励して予防を呼びかけつつ、食欲や体調の変化を観察してこまめに伝え合う。
- 連絡帳に何も記載がない日もあるので、受け入れの際に確認できなかった場合は、その日のお迎えの際に、本児の様子を伝える中でさりげなく家庭での様子を聞き取り、情報を共有できるようにする。
本登録をして
他の文例を見る
Fさん(中月齢/女児/活発)(2歳5カ月/9月生まれ)
子どもの姿
- 年末の胃腸風邪の影響で、年始はオムツに排尿することが続いたが、再びトイレでの排尿が成功するようになってきた。(養護)
- 絵本を読みながら、「これはいちご」「これはバナナ」など、物の名前を答えて楽しんでいた。(教育)
- 戸外に出ると寒さから抱っこをしてほしがる姿も見られたが、保育者とふれあいながら遊ぶうちに徐々に気持ちが切り替わり、離れて遊ぶことができた。(家庭との連携)
ねらい/内容/環境構成・配慮・援助/評価・反省
養護
| 子どもの姿(再掲) |
年末の胃腸風邪の影響で、年始はオムツに排尿することが続いたが、再びトイレでの排尿が成功するようになってきた。(養護) |
| ねらい |
尿意に気づいてトイレに行こうとする |
| 内容 |
保育者の声かけにより尿意に気づき、嫌がらずにトイレに行って排尿する。 |
| 環境構成・配慮・援助 |
活動の切れ目にトイレに誘うだけでなく、排尿前のしぐさを見逃さず、「ちっちが出そうかな」「トイレに行ってみようか」と声をかけ、尿意に気づくことができるように関わる。排尿できたときは「ちっちが出てすっきりしたね」と心地よさに共感し、次へとつなげていく。 |
| 評価・反省 |
尿意を感じたり、オムツに排尿した直後に気づいて伝えられる姿が増えてきた。自分から伝えられたことを大いに認め、自信につなげていく。 |
教育
| 子どもの姿(再掲) |
絵本を読みながら、「これはいちご」「これはバナナ」など、物の名前を答えて楽しんでいた。(教育) |
| ねらい |
絵本を通じたやり取りを楽しむ |
| 内容 |
絵本に出てくる言葉や場面に興味を持ち、感じたことを自分なりに伝えようとしたり、気に入った言葉や動きをまねして楽しむ。 |
| 環境構成・配慮・援助 |
季節を感じたり、印象的なフレーズや簡単な仕掛けのある絵本を用意し、一対一や少人数でゆったりと楽しめるようにする。本児が興味を示した場面や、絵本を読む中でのつぶやきを見逃さずに受け止め、目を合わせながら気に入ったフレーズを一緒にくり返したり動きをまねして、楽しさや面白さを共有する。 |
| 評価・反省 |
「バイバイしてるね」「泣いてるね」「○○がいるね」など、場面について思ったことや感じたことを盛んに話しながら楽しんでいた。本児の想像力や言葉の発達をさらに促すことができるように、引き続き応答的に関わっていきたい。 |
食事
- 「これは何?」と聞く本児の好奇心を大切にし、「これは小松菜だよ」「これはにんじんだよ」などと丁寧に伝えながら関わり、食への興味を育てていく。
- 食欲が旺盛でどんどん口に入れようとする姿が見られるため、「おいしいね」と本児の思いに寄り添いつつ、「先生のまねっこをしてカミカミしよう」と誘い、落ち着いて食べられるように関わる。
家庭との連携
子どもの姿(再掲):戸外に出ると寒さから抱っこをしてほしがる姿も見られたが、保育者とふれあいながら遊ぶうちに徐々に気持ちが切り替わり、離れて遊ぶことができた。
- 様々な場面で抱っこしてほしがる姿が見られるが、甘えを受け止めることの大切さを丁寧に伝え、園と家庭で連携しながら情緒の安定を図っていく。
- 家庭での会話のきっかけとなるよう、園で気に入っている遊びや、連絡帳には記載しきれなかった友だちとのやり取りなどの日々の様子を、具体的に伝えていく。
本登録をして
他の文例を見る
Gさん(中月齢/男児/静か)(2歳4カ月/10月生まれ)
子どもの姿
- 鼻水が出ると「出た」と言葉で伝えていた。(養護)
- 友だちの玩具を横から取ってしまうが、保育者が仲立ちすると返すことができる姿も見られた。(教育)
- 「グーチョキパー」の歌に合わせ、自分なりに手を動かして楽しんでいた。(家庭との連携)
ねらい/内容/環境構成・配慮・援助/評価・反省
養護
| 子どもの姿(再掲) |
鼻水が出ると「出た」と言葉で伝えていた。(養護) |
| ねらい |
身の回りのことをやってみようとする |
| 内容 |
自分なりに鼻水を拭き、最後に保育者に仕上げをしてもらう。 |
| 環境構成・配慮・援助 |
鼻水が出たときは「一緒に拭こうね」と誘い、本児が持ちやすい大きさにティッシュを折り畳み、手を添えながら拭き方を伝える。本児なりにやろうとする姿を見守り、最後に仕上げを行いながら「拭けたね」「きれいになったね」と伝え、意欲を育てる。 |
| 評価・反省 |
四つ折りに畳んだティッシュを手に取りやすい場所に置いたところ、積極的に自分で鼻に当てて拭こうとしていた。自分でできた喜びを感じられる言葉がけをしながら、さらに意欲を育みたい。 |
教育
| 子どもの姿(再掲) |
友だちの玩具を横から取ってしまうが、保育者が仲立ちすると返すことができる姿も見られた。(教育) |
| ねらい |
友だちとやり取りする楽しさを味わう |
| 内容 |
友だちとの玩具のやり取りを通じて、「かして」「どうぞ」「あとでね」など、簡単な言葉で思いや要求を表現する。 |
| 環境構成・配慮・援助 |
保育者も一緒に遊びに入って関わったり、子ども同士のやり取りを見守り、必要に応じて仲立ちする。思いがぶつかり合う中で、とっさに言葉が出ないときは、「○○が欲しいのかな」と本児の思いを汲み取るとともに、「かして」「ちょうだい」など簡単な言葉で代弁することで思いの表現の仕方を示し、他者と心地よく関わる感覚を味わえるようにしていく。 |
| 評価・反省 |
「これ○ちゃんの?」「ちょうだい」など、思いを言葉で表現しようとする姿が増えた。まだうまく伝わらない場面もあるので、言葉を補いながら仲立ちしていく。 |
食事
- 器に手を添えることを忘れているときは、さりげなく手を添えながら「器を持とうね」と伝え、食べやすさを感じられるようにする。
- 食事の最中に違う場所に意識が向きこぼしてしまうときは、汚れた部分をきれいにしながら「前を向こうね」「次はどれを食べようね」と声をかけ、食事に集中できるように関わる。
家庭との連携
子どもの姿(再掲):「グーチョキパー」の歌に合わせ、自分なりに手を動かして楽しんでいた。
- 園で楽しんでいる様々な手遊びを紹介し、楽しみながら手指の発達を促す。
- 様々な場面で自己主張をする姿が増えたことに戸惑う保護者の思いに寄り添い、親子共に心地よい関わり方や、日々の対応の仕方を一緒に考えていく。
本登録をして
他の文例を見る
Hさん(中月齢/女児/静か)(2歳3カ月/11月生まれ)
子どもの姿
- タイミングが合い、便器に座って排尿できた。(養護)
- 雪の上を保育者と手をつなぎながら歩いたり、保育者が雪玉を作る様子に興味を持ち、自分なりにまねしようとしながら触っていた。(教育)
- 靴下や靴を自分で履きたがらず、保育者に履かせてもらいたがる姿が見られた。(家庭との連携)
ねらい/内容/環境構成・配慮・援助/評価・反省
養護
| 子どもの姿(再掲) |
タイミングが合い、便器に座って排尿できた。(養護) |
| ねらい |
トイレで排尿する心地よさを感じる |
| 内容 |
オムツが濡れていないタイミングでトイレに行き、保育者に見守られながら便器に座り、排尿しようとする。 |
| 環境構成・配慮・援助 |
本児の遊びの様子や排尿間隔に合わせながら、「ちっちが出るかな」と声をかけてトイレに誘う。排尿がなくても便器に座れた姿を十分に認め、タイミングが合い排尿できたときは、「トイレでできたね」「すっきりしたね」と喜びや心地よさを言葉にして共感し、次への意欲につなげる。 |
| 評価・反省 |
オムツに排尿することの方が多かったが、トイレでも数回排尿できた。遊びのタイミングによってはトイレに行くことを嫌がる姿も見られるので、無理強いにならないように配慮しながら、根気よく関わっていく。 |
教育
| 子どもの姿(再掲) |
雪の上を保育者と手をつなぎながら歩いたり、保育者が雪玉を作る様子に興味を持ち、自分なりにまねしようとしながら触っていた。(教育) |
| ねらい |
冬の自然に興味を持ち、感触の面白さや不思議さに気づく |
| 内容 |
園庭やテラスに出て、冬の空気の冷たさを感じたり、雪や氷、霜柱に触れて感触を楽しむ。 |
| 環境構成・配慮・援助 |
気候や体調に合わせて戸外に出て遊ぶ中で、「風が冷たいね」「息が白いね」と伝えることで冬独特の空気を感じられるように関わったり、雪や霜柱などの自然物に対する興味に寄り添い、「硬いね」「冷たいね」と感触を言葉にして伝える。戸外に出られない場合でも、雪や氷を玄関ホールや室内に持ち込み、落ち着いて触れたり、溶けていく様子を見て楽しめるようにする。 |
| 評価・反省 |
雪が積もった日は、安全のために少人数ずつ園庭に出て、雪の上を歩いたり手で触り、感触を楽しむことができた。戸外遊びの機会が増える季節に向けて、絵本や図鑑を通じて自然への興味をさらに育てたい。 |
食事
- 本児の「見ててね」に応えて見守る中で、「スプーンですくえたね」「大きなお口で食べられたね」とできた部分を具体的に伝え、自信を育てる。
- 苦手な食材に手をつけられないときは、「自分ですくえるかな?」と声をかけたり、「お手伝いしようか?」と提案し、本児が「食べてみようかな」と感じられるように関わる。
家庭との連携
子どもの姿(再掲):靴下や靴を自分で履きたがらず、保育者に履かせてもらいたがる姿が見られた。
- 保護者に対しても同じような姿が見られるとのことなので、甘えを受け止める大切さや園での保育者の関わり方や声かけを共有し、本児の意欲と自信を育んでいけるように関わる。
- 家庭でもトイレに行く機会を作ってもらえるきっかけとなるように、園でトイレに行ったり排尿できたことを伝えながら、共に成長を喜ぶ。
本登録をして
他の文例を見る
Iさん(低月齢/男児/活発)(2歳2カ月/12月生まれ)
子どもの姿
- タイミングが合うと便器に座って排尿するが、遊びに夢中でトイレに行きたがらない姿が増えてきた。(養護)
- わらべうたあそびを通じて保育者とのふれあいやまねっこをくり返し楽しんだ。(教育)
- インフルエンザで一週間ほど欠席し、登園後は情緒が不安定な姿が多く見られた。(家庭との連携)
ねらい/内容/環境構成・配慮・援助/評価・反省
養護
| 子どもの姿(再掲) |
タイミングが合うと便器に座って排尿するが、遊びに夢中でトイレに行きたがらない姿が増えてきた。(養護) |
| ねらい |
嫌がらずにトイレに行く |
| 内容 |
活動の切れ目にトイレに行き、便器で排尿したり汚れたオムツを交換してもらうことで、清潔になった心地よさを感じる。 |
| 環境構成・配慮・援助 |
活動や遊びの切れ目を見計らってトイレに誘い、嫌がるときは、本児が納得してトイレに向かえるように玩具を持って行くなどの提案をしたり、時間をおいてから改めて誘うなど、柔軟に対応する。トイレで排尿したりオムツを交換した際は、「すっきりしたね」と清潔になった心地良さを感じられる声かけをして、意欲を育てる。 |
| 評価・反省 |
同じ遊びを楽しむ友だちと一緒だと喜んでトイレに行くことができ、進んで便器に座り、保育者の「すっきりしたね」という声かけにも「うん」と応えていた。引き続き、トイレで排尿する心地よさを味わえるように関わり、意欲を育む。 |
教育
| 子どもの姿(再掲) |
わらべうたあそびを通じて保育者とのふれあいやまねっこをくり返し楽しんだ。(教育) |
| ねらい |
わらべうたを通じて、保育者や友だちとのやり取りを楽しむ |
| 内容 |
保育者や友だちと一緒にわらべうたあそびを楽しむ中で、簡単な動きをまねし合い、楽しさを共有する。 |
| 環境構成・配慮・援助 |
少人数でのわらべうたあそびに誘い、友だちとのふれあいや簡単な言葉のやり取りを、ゆったりと楽しめるように関わる。まねしやすいように丁寧な発音やわかりやすい動きを意識し、一人ひとりと目を合わせながら、「おんなじだね」「まねっこ楽しいね」と言葉をかけ、その場にいる保育者や友だちと楽しさを共有できるようにする。 |
| 評価・反省 |
積極的に保育者のまねをして、友だちの手を握って揺らしたり、くすぐっていた。ケガを防ぎながらやり取りを見守り、友だちと関わる楽しさを感じられるように仲立ちしていく。 |
食事
- 苦手な食材が最後に残りがちなので、自分で食べ進める姿を見守りつつ、様々な食材に興味を持ちながら食べ進められるように、「この野菜はどんな味だろう」「甘いかな?しょっぱいかな?」とさりげなく声をかける。
- 上握りから下握りに持ち替えていけるように、本児の様子に合わせてさりげなく手を添えて援助する。
家庭との連携
子どもの姿(再掲):インフルエンザで一週間ほど欠席し、登園後は情緒が不安定な姿が多く見られた。
- 寒さや乾燥により体調を崩しやすい時期が続くので、室温や湿度を適切に保つとともに、食欲や機嫌など、普段と違う様子が見られたときはこまめに伝え合う。
- 好き嫌いや遊び食べの悩みが多いので、よく話を聞いて寄り添うとともに、家庭での関わりの参考になるように、園での食事の様子や保育者の対応を丁寧に伝える。
本登録をして
他の文例を見る
Jさん(低月齢/女児/活発)(2歳1カ月/1月生まれ)
子どもの姿
- 友だちの姿を見て、自ら便座に座ることができた。(養護)
- 室内でのサーキット遊びで活発に体を動かして楽しんでいたが、前にいる友だちを押してしまう場面があった。(教育)
- 祖父母が迎えに来る日は、「ママがいい」と泣いていた。(家庭との連携)
ねらい/内容/環境構成・配慮・援助/評価・反省
養護
| 子どもの姿(再掲) |
友だちの姿を見て、自ら便座に座ることができた。(養護) |
| ねらい |
嫌がらずに便座に座ろうとする |
| 内容 |
保育者に誘われてトイレに行き、見守られる中で安心して便座に座る。 |
| 環境構成・配慮・援助 |
トイレに親しみが持てるように、友だちがトイレに行く際に「一緒に行こう」と誘ったり、便器に座る際にリラックスできるように手をつなぎながら見守る。排尿がなくても「座れたね」「お姉さんだね」と本児の姿を大いに認めて意欲につなげ、嫌がるときは無理強いせず、「また来ようね」と安心できるような言葉をかける。 |
| 評価・反省 |
便器に座ることへの抵抗が少なくなり、習慣づいてきた。オムツが濡れた感覚や尿意を感じてトイレに向かえるように、タイミングを見計らって声をかけていく。 |
教育
| 子どもの姿(再掲) |
室内でのサーキット遊びで活発に体を動かして楽しんでいたが、前にいる友だちを押してしまう場面があった。(教育) |
| ねらい |
順番を知り、安全に体を動かす楽しさを味わう |
| 内容 |
友だちと一緒に、園庭の遊具や室内での運動遊びを楽しむ。 |
| 環境構成・配慮・援助 |
のびのびと体を動かすことができるように、高月齢チームの活動に加える。保育者が遊びに入りながら、「○さんの次はJさんの番だね」とわかりやすく順番を伝えて安全に配慮するとともに、同じ遊びを楽しむ友だちの姿に興味を持てるように、「○さんもJさんみたいにできるかな」「見ていてあげようね」と言葉をかける。 |
| 評価・反省 |
高月齢児の運動遊びに加わることで、のびのびと体を動かすことができ、友だちの動きをまねする姿も見られた。友だちとのやり取りを見守ったり仲立ちしながら、楽しさを共有できるように関わる。 |
食事
- 自信を持って自分で食べている姿を見守る中で、「おいしいね」と食べる喜びに共感し、心地よく食事を楽しむことができる雰囲気を作る。
- 様子を見ながら徐々に鉛筆握りに移行できるように、一緒に食べる中で持ち方の見本を見せたり、さりげなく手を添えて持ち方を伝えていく。
家庭との連携
子どもの姿(再掲):祖父母が迎えに来る日は、「ママがいい」と泣いていた。
- 祖父母が迎えに来ることを事前に本児に伝えて心の準備ができるようにし、お迎えの際には「今日は公園に行ったんだよね」「お絵描きしたんだよね」と、日中の楽しかった活動を一緒に報告し、楽しい気持ちで帰れるように関わる。
- 寒さが厳しくなる時期だが、気候が良い日は戸外遊びを行えるように、靴や防寒具を持参してもらう。
本登録をして
他の文例を見る
Kさん(低月齢/男児/静か)(2歳0カ月/2月生まれ)
子どもの姿
- トイレのあとに自分でオムツやズボンを履こうとせず、保育者に声をかけられるまで座っていることが多かった。(養護)
- 友だちとの玩具のやり取りの場面では、「かして」と言われると玩具を持って遠くへ逃げたり、取られそうになるとすぐに手を離して泣く姿が見られた。(教育)
- 便器に座った状態での排尿はまだないが、便器から離れてオムツを履くまでの間に排尿したり、家庭でお風呂の際に排尿することがあった。(家庭との連携)
ねらい/内容/環境構成・配慮・援助/評価・反省
養護
| 子どもの姿(再掲) |
トイレのあとに自分でオムツやズボンを履こうとせず、保育者に声をかけられるまで座っていることが多かった。(養護) |
| ねらい |
簡単な身の回りのことを自分で行う喜びを感じる |
| 内容 |
保育者に見守られたり励まされながら、自分でオムツやズボンを履く。 |
| 環境構成・配慮・援助 |
オムツやズボンを履きやすい向きに整えて置き、「足はどこから出すのかな?」と意欲を引き出す言葉をかけて見守り、保育者にやってもらいたがるときは、「一緒にやろうね」と甘えを受け止めて援助する。一緒に行う場合は、仕上げなどの一部分を自分で行えるように関わり、「自分でできたね」と伝えて自信につなげる。 |
| 評価・反省 |
保育者に甘える姿が多かったが、思いを受け止められると満足し、途中で保育者が援助を止めても自分でやりきることができた。自分で行うきっかけを作りながら関わり、できた姿を大いにほめて意欲を育てる。 |
教育
| 子どもの姿(再掲) |
友だちとの玩具のやり取りの場面では、「かして」と言われると玩具を持って遠くへ逃げたり、取られそうになるとすぐに手を離して泣く姿が見られた。(教育) |
| ねらい |
自分なりの言葉やしぐさで思いを伝えようとする |
| 内容 |
保育者の仲立ちのもと、「かして」「どうぞ」「あとでね」など、簡単な言葉で思いを表現し、受け止めてもらう。 |
| 環境構成・配慮・援助 |
一緒に遊びを楽しむ中で「かして」「どうぞ」「あとでね」などの簡単な言葉を使ったやり取りを促し、本児なりに言葉をまねしたりしぐさで表現できたときは受け止め、思いが伝わる喜びを感じられるようにする。友だちとのやり取りの際には必要に応じて仲立ちし、本児の思いを代弁しながら、双方の思いを橋渡しする。 |
| 評価・反省 |
遊びの中で、保育者や友だちと言葉でやり取りを楽しむ姿が増えてきた。とっさの場面ではまだ思いを表現できずに泣く姿も多いため、思いを受け止めながら丁寧に仲立ちし、思いが通じる喜びや言葉でやり取りする面白さを感じられるように関わる。 |
食事
- 苦手な食材でも励まされると食べられるので、無理強いにならないように配慮しながら、「どんな味かな」「先生と一緒に食べてみようか」と言葉をかける。
- 食べるスピードが落ちているときは、さりげなく介助したり、「次はどれにしようね」と食事に意識が向くように声をかけながら、最後まで楽しく食べられるように関わる。
家庭との連携
子どもの姿(再掲):便器に座った状態での排尿はまだないが、便器から離れてオムツを履くまでの間に排尿したり、家庭でお風呂の際に排尿することがあった。
- オムツがない状態で排尿できることは、トイレで排尿する大切な一歩であることを伝え、引き続きタイミングを見計らってトイレに誘う。
- 生活の中で「自分でやりたい」という姿が見られたときは見逃さずに共有し、家庭でもその姿を大切にしながら見守ってもらえるようにする。
本登録をして
他の文例を見る
Lさん(低月齢/女児/静か)(1歳11カ月/3月生まれ)
子どもの姿
- 給食の前には進んで手洗い場に向かい、自分なりに手を洗っていた。(養護)
- 友だちが登園したり降園する際に、本児なりに名前を呼んだり手を振るなど、あいさつをしていた。(教育)
- 節分に向けた豆まきごっこでは、新聞紙を丸めたボールを投げることを楽しんでいた。(家庭との連携)
ねらい/内容/環境構成・配慮・援助/評価・反省
養護
| 子どもの姿(再掲) |
給食の前には進んで手洗い場に向かい、自分なりに手を洗っていた。(養護) |
| ねらい |
生活の流れを自分なりに理解し、簡単な身の回りのことを自分でしようとする |
| 内容 |
排泄後や戸外遊び後、食前には、保育者に見守られながら丁寧に手を洗う。 |
| 環境構成・配慮・援助 |
手洗いの必要性をその都度わかりやすく伝えながら促し、本児が自ら行う姿を見守りつつ、必要に応じて丁寧なやり方を伝える。石けんをつけ忘れたり、タオルできれいに拭ききれない姿が見られるので、保育者が隣で見本を見せたり、さりげなく援助し、最後は「きれいになったね」と伝えて心地よさを感じられるようにする。 |
| 評価・反省 |
最後に手を拭く習慣は身についてきたが、一人では十分に拭くことが難しかった。少しずつ自分でできるように、見守りと仕上げ拭きを続ける。 |
教育
| 子どもの姿(再掲) |
友だちが登園したり降園する際に、本児なりに名前を呼んだり手を振るなど、あいさつをしていた。(教育) |
| ねらい |
友だちに興味を持ち、関わる喜びを感じる |
| 内容 |
友だちに自分なりにあいさつをしたり、遊びの中で簡単なやり取りを楽しむ。 |
| 環境構成・配慮・援助 |
保育者が「おはよう」「さようなら」などのあいさつを積極的に行い、子ども同士でもあいさつを通した関わりが生まれるようにする。本児なりに友だちに関わろうとする姿を見守りつつ、思いを表現しきれないときは丁寧に言葉を補いながら代弁し、相手に伝わる喜びを感じられるようにする。 |
| 評価・反省 |
気になる友だちの顔をのぞき込んだり、自分なりに話しかける姿や、帰る友だちとその保護者に手を振ったりタッチしに行く姿が多く見られた。保育者が介入し過ぎないように配慮しつつ、必要な場面で本児の思いを代弁し、思いの橋渡しをしていく。 |
食事
- 好きな物を先に食べてしまう姿が多いので、様々な食材をバランスよく食べ進められるように、「これはどんな味かな」「このお野菜は何だろうね?」と、興味を持てる声かけを行う。
- スプーンは上握りや下握りで持っているので、下握りで安定して食べられるように、さりげなく手を添えて援助する。
家庭との連携
子どもの姿(再掲):節分に向けた豆まきごっこでは、新聞紙を丸めたボールを投げることを楽しんでいた。
- 遊びや絵本を通じて伝統行事に楽しく触れる機会を作り、保護者も行事について知ったり、家庭で行うきっかけとなるようにする。
- 発語が少ないことへの不安を受け止め、本児なりの思いの表現に対して「○○なんだね」と丁寧に言葉にして返す大切さを共有し、園でも家庭でも応答的に関わりながら言葉の発達を促すことができるようにする。
本登録をして
他の文例を見る
その他、ほいくのおまもりプラスのコンテンツ
> その他の【月案・週案・個人案】を見る。