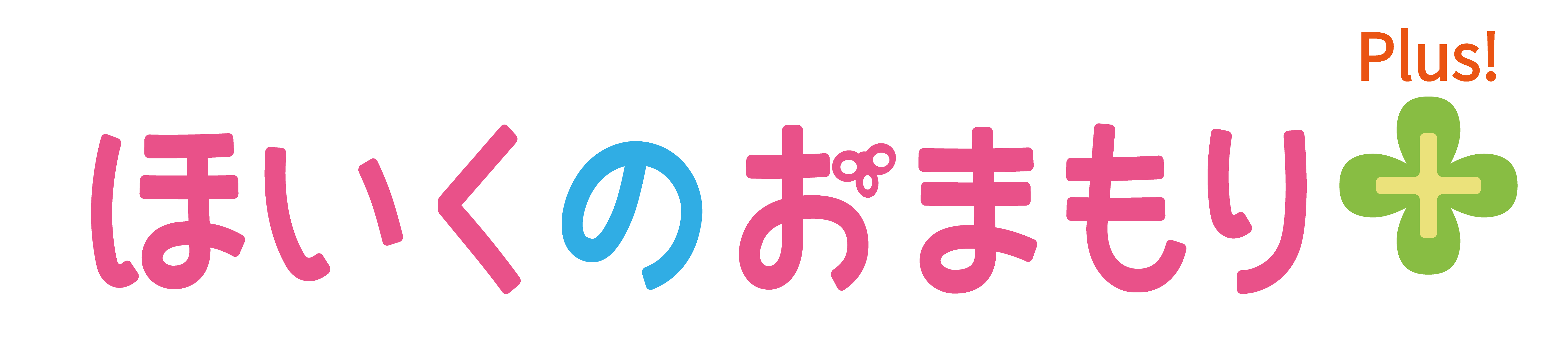もくじ
- 個人案PDF
- 敬称と性別表記について
- Aさん(高月齢/男児/活発)(2歳0カ月/4月生まれ)
- Bさん(高月齢/女児/活発)(1歳11カ月/5月生まれ)
- Cさん(高月齢/男児/静か)(1歳10カ月/6月生まれ)
- Dさん(高月齢/女児/静か)(1歳9カ月/7月生まれ)
- Eさん(中月齢/男児/活発)(1歳8カ月/8月生まれ)
- Fさん(中月齢/女児/活発)(1歳7カ月/9月生まれ)
- Gさん(中月齢/男児/静か)(1歳6カ月/10月生まれ)
- Hさん(中月齢/女児/静か)(1歳5カ月/11月生まれ)
- Iさん(低月齢/男児/活発)(1歳4カ月/12月生まれ)
- Jさん(低月齢/女児/活発)(1歳3カ月/1月生まれ)
- Kさん(低月齢/男児/静か)(1歳2カ月/2月生まれ)
- Lさん(低月齢/女児/静か)(1歳1カ月/3月生まれ)
- その他、ほいくのおまもりプラスのコンテンツ
個人案PDF
敬称と性別表記について
LGBTQ+の観点から、保育士が園児を表記する際は『くん』『ちゃん』を使わず、『さん』で統一、園児が自身を称する際や園児同士のやり取りを記載する場合は『ちゃん』で統一しています。また、発達段階の観点では性差はあると考えられるため、男児/女児としています。
Aさん(高月齢/男児/活発)(2歳0カ月/4月生まれ)
子どもの姿
- 初めての環境に不安を感じて保護者と離れたがらないが、保育者に抱っこされて室内に入ると徐々に落ち着き、玩具で遊び始める姿も増えてきた。(養護)
- 側にいる友だちが持っている玩具を取ろうとする場面があった。(教育)
- 保育者がわらべうたを歌ったり手遊びを始めると、興味を持って見つめていた。(家庭との連携)
ねらい/内容/環境構成・配慮・援助/評価・反省
養護
| 子どもの姿(再掲) | 初めての環境に不安を感じて保護者と離れたがらないが、保育者に抱っこされて室内に入ると徐々に落ち着き、玩具で遊び始める姿も増えてきた。(養護) |
| ねらい | 新しい環境に慣れ、安心して過ごす |
| 内容 | 抱っこなどのスキンシップを通して保育者に不安を受け止められたり、優しく話しかけられる中で、安心感や喜びを感じる。 |
| 環境構成・配慮・援助 | 受け入れや生活面での対応は、職員間で連携しながらできる限り同じ保育者が行い、安心感を育てる。遊びの中では、本児の様子に合わせながら様々な保育者が関われるようにし、優しく名前を呼びかけたり手遊びに誘い、スキンシップを取りながら焦らずに信頼関係を築いていく。 |
| 評価・反省 | 登園時に泣く姿が減り、保護者に手を振って離れられた日もあった。特定の保育者との信頼関係ができてきたので、引き続き思いを受け止めながら関わりたい。 |
教育
| 子どもの姿(再掲) | 側にいる友だちが持っている玩具を取ろうとする場面があった。(教育) |
| ねらい | 自分の思いを、簡単な言葉やしぐさで伝えようとする |
| 内容 | 保育者に思いや行動を受け止めてもらい、「かして」といった簡単な言葉や、指差しなどの自分なりのしぐさで思いを表現する。 |
| 環境構成・配慮・援助 | 本児が友だちの玩具を取ろうとしたときは、ケガを防ぎながら間に入り、「これが欲しいのかな」「遊びたいのかな」と丁寧に気持ちを聞き取る。本児なりの思いを表現しようとする姿を受け止め、保育者がわかりやすい身振りを交えながら「かして」と代弁するなど、やり取りの見本となりながら仲立ちする。 |
| 評価・反省 | 保育者と一緒に「かして」と言ったり、自分なりのしぐさで思いを表現しながら、友だちとやり取りができた。まだとっさに言葉が出づらいため、子ども同士のやり取りを見守りつつ、必要に応じて仲立ちする。 |
食事
- 給食の初日では、椅子に座って意欲的に食べられたので、本児のペースで楽しく食事ができるように、「おいしいね」と声をかけながら見守る。
- 手づかみ食べが多いがスプーンを使おうとする姿も見られるため、「スプーンを持てたね」と認める言葉がけをしたり、さりげなく手を添えて援助し、意欲を育てる。
家庭との連携
子どもの姿(再掲):保育者がわらべうたを歌ったり手遊びを始めると、興味を持って見つめていた。
- 送迎時のやり取りの中で、本児が興味を持っていたわらべうたや手遊びを実際に歌いながら紹介し、家庭でも楽しめるようにする。
- 登園時はできる限り同じ保育者が受け入れ、本児と保護者の不安や緊張を受け止めながら、信頼関係を築いていく。
Bさん(高月齢/女児/活発)(1歳11カ月/5月生まれ)
子どもの姿
- 前年度は自分で入眠できていたが、他児の泣き声が気になって入眠に時間がかかるようになり、保育者にトントンしてもらうことが多かった。(養護)
- 園庭に出ると喜んで探索を始め、保育者がアリやダンゴムシを見つけると興味を持ち、しゃがんで観察していた。(教育)
- 保育者に誘われて嫌がらずにトイレに行き、座って排尿できた。(家庭との連携)
ねらい/内容/環境構成・配慮・援助/評価・反省
養護
| 子どもの姿(再掲) | 前年度は自分で入眠できていたが、他児の泣き声が気になって入眠に時間がかかるようになり、保育者にトントンしてもらうことが多かった。(養護) |
| ねらい | 安心して休息を取りながら、健康的に過ごす |
| 内容 | 保育者に見守られたり優しくトントンしてもらいながら、心地よく入眠する。 |
| 環境構成・配慮・援助 | 午睡の際は、泣いてしまう子と布団を離し、落ち着いて眠れるよう配慮する。本児が入眠しにくそうなときは「トントンしようか?」と声をかけてから優しくトントンしたり、側で子守唄を歌いながら見守り、心地よく入眠できるように関わる。 |
| 評価・反省 | 徐々に周りを気にせず、自分で入眠できるようになってきた。他児の泣き声で途中で目覚めてしまうときは、「びっくりしたね」と優しく声をかけながらトントンし、再入眠を促す。 |
教育
| 子どもの姿(再掲) | 園庭に出ると喜んで探索を始め、保育者がアリやダンゴムシを見つけると興味を持ち、しゃがんで観察していた。(教育) |
| ねらい | 春の自然に親しむ |
| 内容 | 保育者と一緒に園庭や公園で探索を楽しむ中で、春の草花や虫に興味を持ち、近くで見たり、触ってみようとする。 |
| 環境構成・配慮・援助 | 園庭や公園では周囲の安全に配慮しながら、自由に探索する姿を見守る。タンポポなどの草花に一緒に触れたり、ダンゴムシやアリ、チョウチョなどがいることを知らせ、「丸くなって面白いね」「ヒラヒラ飛んでるね」と、その面白さや不思議さを丁寧に言葉で伝え、興味を育てていく。 |
| 評価・反省 | 生き物に対する興味が育ち、ダンゴムシを指で触ろうとする姿も見られた。来月も積極的に戸外での探索を楽しみ、自然に対する興味を育みたい。 |
食事
- スプーンの持ち方が下握りで安定してきたので、自分で食べる姿を見守りながら、「スプーンで食べられてかっこいいね」と認め、自信につなげる。
- 好き嫌いをする姿を受け止めつつ、保育者がおいしそうに食べて見せたり、「お手伝いしようか?」と提案することで、「食べてみようかな」という気持ちが生まれるように関わる。
家庭との連携
子どもの姿(再掲):保育者に誘われて嫌がらずにトイレに行き、座って排尿できた。
- トイレに親しむ本児の様子を伝え、家庭と連携しながら焦らずトイレトレーニングを進めていく。
- 環境の変化による疲れや不安を見逃さず、無理なく過ごせるように、連絡帳を通じて本児の様子をこまめに伝え合う。
Cさん(高月齢/男児/静か)(1歳10カ月/6月生まれ)
子どもの姿
- 登園時は保護者と離れたがらず泣くが、室内では保育者のひざの上に座って過ごすうちに落ち着き、周りの様子を見られることも増えた。(養護)
- 乗り物が好きで、落ち着くと保育者と一緒に絵本を見ながら、車や電車を指差して興味を示していた。(教育)
- 泣き止んでからも持参したタオルを握りしめ、離さずに過ごしていた。(家庭との連携)
ねらい/内容/環境構成・配慮・援助/評価・反省
養護
| 子どもの姿(再掲) | 登園時は保護者と離れたがらず泣くが、室内では保育者のひざの上に座って過ごすうちに落ち着き、周りの様子を見られることも増えた。(養護) |
| ねらい | 新しい環境に慣れ、安心して過ごす |
| 内容 | 保育者に不安を受け止めてもらいながら少しずつ気持ちを切り替え、興味のある玩具を見つけて遊ぼうとする。 |
| 環境構成・配慮・援助 | 保護者と離れる際は不安を受け止め、「ママがいいね」「パパがいいね」と共感の言葉をかけ、抱っこや手つなぎでスキンシップを取る。本児が好む乗り物の玩具を見せ、「大好きなブーブで遊ぼうか」と誘い、興味を引き出すとともに、一緒に遊んで楽しさを共有する。 |
| 評価・反省 | 泣く時間が減り、室内に入ると気に入った玩具のコーナーに向かい、遊び始める姿が増えた。泣かずに保護者と離れられるよう、引き続き思いを受け止めながら、安心感を育んでいく。 |
教育
| 子どもの姿(再掲) | 乗り物が好きで、落ち着くと保育者と一緒に絵本を見ながら、車や電車を指差して興味を示していた。(教育) |
| ねらい | 保育者に親しみを持ち、簡単なやり取りを楽しむ |
| 内容 | 乗り物の絵本を保育者と一緒に読む中で、指差しや自分なりの言葉を受け止めてもらい、思いが伝わる喜びを感じる。 |
| 環境構成・配慮・援助 | 乗り物が登場する絵本を用意し、一対一でゆったりと楽しめる時間を作る。本児の興味に寄り添いながら丁寧に読み進め、指差しを見逃さずに「バスだね」「電車が走っているね」と言葉にして受け止め、やり取りする楽しさや喜びを感じられるようにする。 |
| 評価・反省 | 絵本を読みながら「これは?」と尋ね合い、保育者とのやり取りを楽しんだ。言葉がとっさに出ないときは、代弁したり促すだけでなく、ゆったりとした姿勢で受け止め、安心して思いを表現できるように関わる。 |
食事
- 保育者のひざに座りながらも好きなおかずを食べられたため、その姿を大いに認め、楽しい食事の雰囲気を作りながら、徐々に椅子に座って食べられるよう促す。
- 家庭では好き嫌いや食べムラが多いとのことから、園でも様子を観察し、本児のペースに合った量を提供して無理なく食べられるよう配慮する。
家庭との連携
子どもの姿(再掲):泣き止んでからも持参したタオルを握りしめ、離さずに過ごしていた。
- タオルがあることで安心して過ごしている様子を伝えるとともに、必ずわかりやすく記名してもらうよう依頼し、紛失や返し間違いを防止する。
- 熱性けいれんの既往があるため、入園前面談の際に保護者と確認した発熱時の対応を全職員で共有するとともに、園と家庭で体調の変化をこまめに伝え合っていく。
Dさん(高月齢/女児/静か)(1歳9カ月/7月生まれ)
子どもの姿
- 新しい保育室や保育者に戸惑う様子が見られ、登園後しばらくは、前年度からの持ち上がりの保育者の側から離れたがらない場面が多かった。(養護)
- 新入園児に興味を持ち、少し離れた場所から様子を見たり、保育者のひざで泣いている子には、「よしよし」と言って頭や体に触れていた。(教育)
- 今年度から保育時間が延び、夕方になると眠そうな姿が見られた。(家庭との連携)
ねらい/内容/環境構成・配慮・援助/評価・反省
養護
| 子どもの姿(再掲) | 新しい保育室や保育者に戸惑う様子が見られ、登園後しばらくは、前年度からの持ち上がりの保育者の側から離れたがらない場面が多かった。(養護) |
| ねらい | 新しい保育室や保育者に慣れ、親しみを持つ |
| 内容 | 信頼する保育者に見守られながら食事や排泄、午睡をしたり、一緒に遊ぶ中で自分なりに表現した思いを受け止めてもらいながら、安心して過ごす。 |
| 環境構成・配慮・援助 | 環境の変化に対して不安な気持ちに寄り添い、生活面での対応は、本児が信頼する保育者が担当できるよう職員間で連携し、安心感を育む。遊びの中では、さまざまな保育者が関わり、名前を呼んだり、同じ玩具で遊びながら楽しさを共有し、信頼関係を築いていく。 |
| 評価・反省 | 新しい保育者に対しても、安心して関わるようになった。午睡の際は嫌がる場面もあるため、本児の意思を尊重しながら対応していく。 |
教育
| 子どもの姿(再掲) | 新入園児に興味を持ち、少し離れた場所から様子を見たり、保育者のひざで泣いている子には、「よしよし」と言って頭や体に触れていた。(教育) |
| ねらい | 保育者の仲立ちのもと、友だちと関わる楽しさを味わう |
| 内容 | 保育者や友だちと一緒にわらべうたあそびや手遊びを楽しむ中で、ふれあったり体を動かすことを楽しむ。 |
| 環境構成・配慮・援助 | 少人数でのわらべうたあそびや手遊びに誘い、保育者の動きをまねできたときには「Dさん、まねっこできたね」「○さんもできるかな」と声をかけ、近くの友だちと楽しさを共有できるようにする。「いっぽんばしこちょこちょ」などの簡単なわらべうたを通じてふれあいの機会を作り、保育者や友だちと一緒に遊ぶ面白さを味わえるようにする。 |
| 評価・反省 | 「いっぽんばしこちょこちょ」で保育者や友だちをくすぐったり、「むすんでひらいて」で保育者の動きをまねして楽しんだ。今後も様々なわらべうたあそびや手遊びを取り入れ、他者との交流のきっかけを作っていく。 |
食事
- 食物アレルギーがあるため、前年度に引き続き、アレルギー対応マニュアルに基づいて担当職員が援助を行い、安全に配慮しながら対応する。
- スプーンや手づかみで食べ進めるが、途中で手が止まることもあるため、「次はどれにする?」と声をかけ、食事に意識が戻るようにする。
家庭との連携
子どもの姿(再掲):今年度から保育時間が延び、夕方になると眠そうな姿が見られた。
- 疲れが出やすい時期でもあるため、夕方に30分ほど眠れるよう配慮するとともに、園での睡眠時間を保護者に伝え、家庭と連携しながら生活リズムを整える。
- アレルギーに関する通院時は、必ず結果などの情報を園にも共有してもらうようお願いする。
Eさん(中月齢/男児/活発)(1歳8カ月/8月生まれ)
子どもの姿
- 保育室など環境の変化による不安は少なく、新しい保育者にも積極的に関わり、機嫌よく過ごしていた。(養護)
- 室内ではさまざまな玩具に興味を示すものの、次々に棚や箱から出していき、興味が続かない様子が見られた。(教育)
- 保護者の転職により登園時間が早まり、朝は慌ただしい様子で、遅れて来たり、連絡帳の記載がない日もあった。(家庭との連携)
ねらい/内容/環境構成・配慮・援助/評価・反省
養護
| 子どもの姿(再掲) | 保育室など環境の変化による不安は少なく、新しい保育者にも積極的に関わり、機嫌よく過ごしていた。(養護) |
| ねらい | 安定した生活リズムの中で、健康的に過ごす |
| 内容 | 保育者に見守られながらのびのびと体を動かして遊んだり、十分に休息を取ることで心地よく過ごしながら、新しい環境に慣れる。 |
| 環境構成・配慮・援助 | 登園時に本児の機嫌や様子をよく観察し、必要に応じて休息を促しながら、一日を通して無理なく過ごせるように配慮する。また、気温差で体調を崩しやすい時期なので、気温に合わせた衣服の調整やこまめな水分補給を促し、快適に過ごせるようにする。 |
| 評価・反省 | 家庭での生活リズムの乱れの影響もあり、午睡の時間が安定しなかった。引き続き日中は戸外で十分に体を動かす遊びを取り入れ、家庭と協力しながら生活リズムを整えていきたい。 |
教育
| 子どもの姿(再掲) | 室内ではさまざまな玩具に興味を示すものの、次々に棚や箱から出していき、興味が続かない様子が見られた。(教育) |
| ねらい | 室内で好きな玩具を見つけ、保育者に見守られながらじっくり楽しむ |
| 内容 | 保育者と一緒にブロックあそびを楽しみ、つなげたり重ねたりする面白さを味わう。 |
| 環境構成・配慮・援助 | 扱いやすい大きさのブロックを用意し、消毒時には破損や誤飲につながるパーツがないかを確認し、安全に配慮する。保育者も一緒に遊びながら、ブロックをつなげたり積み上げたりする楽しさを共有したり、集中して遊ぶ姿を見守る中で、「くっついたね」「できたね」と声をかけ、楽しさや面白さを感じられるようにする。 |
| 評価・反省 | 新しい保育室に慣れたことで遊びに集中できるようになり、自由遊びの時間は自らブロックの箱を出し、遊ぶ姿が見られた。声をかけ過ぎると集中力が切れるため、そばで見守りながら楽しさに寄り添う。 |
食事
- 食欲旺盛で、よく噛まずに飲み込んだり口に入れすぎる姿が見られるため、「カミカミしようね」と優しく伝えながらそばで見守る。
- スプーンを上握りして食べようとするものの、うまく食材をすくえず手づかみ食べをすることが多いため、さりげなく手を添え、食べやすいように援助する。
家庭との連携
子どもの姿(再掲):保護者の転職により登園時間が早まり、朝は慌ただしい様子で、遅れて来たり、連絡帳の記載がない日もあった。
- 保護者の日々の大変さに寄り添い、登園時に口頭で本児の様子を聞き取るようにし、お迎え時など時間に余裕がある際に改めて連絡帳への記入を丁寧に依頼し、徐々に理解を得られるようにする。
- 朝晩と日中の気温差が大きくなる時期なので、調整しやすい服装での登園をお願いする。
Fさん(中月齢/女児/活発)(1歳7カ月/9月生まれ)
子どもの姿
- 登園時は初日から激しく泣いており、受け入れた保育者の抱っこで徐々に落ち着き、その後はそばに座って玩具で遊び始めることができた。(養護)
- 保育者に抱っこされて外の景色を見ながら、鳥や車を指差して声を出したり、保育者とわらべうたあそびを楽しんでいる中で笑顔が見られた。(教育)
- 午睡の際、眠気はあっても布団に横になることを嫌がり泣くため、保育者が抱っこで対応した。(家庭との連携)
ねらい/内容/環境構成・配慮・援助/評価・反省
養護
| 子どもの姿(再掲) | 登園時は初日から激しく泣いており、受け入れた保育者の抱っこで徐々に落ち着き、その後はそばに座って玩具で遊び始めることができた。(養護) |
| ねらい | 保育者に親しみを持ち、安心して過ごす |
| 内容 | 不安を感じるときは保育者に抱っこしてもらい、優しく話しかけられる中で、思いを受け止めてもらう喜びを感じる。 |
| 環境構成・配慮・援助 | 登園時は笑顔で挨拶しながら受け入れ、抱っこに応じながら本児の不安に寄り添う。前日に遊んだ玩具や絵本を見せて「一緒に遊ぼう」「この絵本を読もう」と誘い、気持ちを切り替えられるように働きかけたり、「あなたのおなまえは」の歌に合わせて名前を呼びかけ、安心感を育む。 |
| 評価・反省 | 登園時に泣かずに室内に入る姿が徐々に増えてきた。来月の連休明けは再び保護者と離れがたくなることが予想されるため、引き続き不安を受け止めていく。 |
教育
| 子どもの姿(再掲) | 保育者に抱っこされて外の景色を見ながら、鳥や車を指差して声を出したり、保育者とわらべうたあそびを楽しんでいる中で笑顔が見られた。(教育) |
| ねらい | 保育者とふれあって遊ぶ楽しさを味わう |
| 内容 | わらべうたあそびやふれあいあそびを通じて、保育者と一緒に歌に合わせて体を動かしたり、スキンシップを楽しむ。 |
| 環境構成・配慮・援助 | 一対一で落ち着いて関わることができる環境を整え、「ちょちちょちあわわ」や「ここはてっくび」などのわらべうたあそびに誘い、ゆったりとしたふれあいを楽しむ。緊張がほぐれてきたら、広いスペースで「うまはとしとし」「いもむしごろごろ」に誘い、体を動かす心地よさを味わえるようにする。 |
| 評価・反省 | 本児なりに「もう一回」と要求し、くり返し楽しむことができた。動きの大きなわらべうたあそびにも喜んで参加し、友だちとの関わりも見られたので、今後も安全に配慮しながら取り入れていきたい。 |
食事
- 保育者に促されて椅子に座り、初日から完食できたため、「食べられたね」「おいしいね」と伝えながら楽しく食べる雰囲気を作り、意欲を育む。
- 家庭ではよく噛まずに飲み込む癖があるとのことなので、咀嚼の様子を観察しながら、「モグモグしようね」と優しく声をかけ、よく噛んで食べられるように関わる。
家庭との連携
子どもの姿(再掲):午睡の際、眠気はあっても布団に横になることを嫌がり泣くため、保育者が抱っこで対応した。
- 保育園での午睡に少しずつ慣れていけるよう、個別の配慮をしながら関わり、その様子を保護者に伝えて安心してもらうとともに、園と家庭で協力して生活リズムを整えていく。
- 送迎時の口頭でのやり取りだけでなく、連絡帳を通じたコミュニケーションも大切にし、信頼関係を築いていく。
Gさん(中月齢/男児/静か)(1歳6カ月/10月生まれ)
子どもの姿
- 保育室が変わっても泣かずに登園し、朝から室内の探索を楽しんでいるが、新入園児が登園し始めるとつられて泣いたり、保育者の抱っこを求める姿も見られた。(養護)
- 園庭で自由に歩いて探索したり、保育者と一緒に砂遊びを楽しんだ。(教育)
- 前年度に引き続き、給食前に眠くなることがあるため、主活動の前に午前睡を促した。(家庭との連携)
ねらい/内容/環境構成・配慮・援助/評価・反省
養護
| 子どもの姿(再掲) | 保育室が変わっても泣かずに登園し、朝から室内の探索を楽しんでいるが、新入園児が登園し始めるとつられて泣いたり、保育者の抱っこを求める姿も見られた。(養護) |
| ねらい | 新しい環境に慣れ、安心して過ごす |
| 内容 | 自分なりに不安や要求を表現し、保育者のそばで過ごしたり、抱っこしてもらいながら思いを受け止めてもらう。 |
| 環境構成・配慮・援助 | 新入園児が登園する時間帯には、不安を軽減できるよう、人の出入りが少ない場所で絵本や好きな遊びに誘い、落ち着いて過ごせるよう配慮する。不安が見られる場合には「びっくりしたね」と声をかけながら受け止めたり、「○さんが泣いているね」と友だちの様子をわかりやすく伝え、徐々に新しい友だちがいる環境に慣れていけるようにする。 |
| 評価・反省 | 新しい環境に慣れ、不安そうな様子は見られなくなった。登園してくる子のそばに行ってあいさつをしたり、泣いている子を気にして顔を覗き込む姿も見られるので、他者への興味を大切に育みたい。 |
教育
| 子どもの姿(再掲) | 園庭で自由に歩いて探索したり、保育者と一緒に砂遊びを楽しんだ。(教育) |
| ねらい | 戸外で好きな遊びを見つけて楽しむ |
| 内容 | 保育者と一緒に砂遊びを楽しみ、手で触れたり道具を使いながら、砂の感触を十分に味わう。 |
| 環境構成・配慮・援助 | 砂遊びの前には危険物の有無を点検し、安全を確認してから遊びに誘う。保育者が手で砂に触れて見せながら「サラサラだね」「冷たいね」と感触を言葉にしながら興味を引き出すとともに、スコップを使う手首の動きを観察し、上手に扱えたときには「すくえたね」と認め、応答的に関わり楽しさを共有する。 |
| 評価・反省 | 園庭や公園では真っ先に砂場に向かい、手や服が砂まみれになるほど夢中で楽しんだ。砂を触った手を口元に持っていく場面も見られたため、衛生面に配慮し、ノンアルコールのウェットティッシュを必ず用意して対応する。 |
食事
- スプーンを使ったり手づかみで食べる本児の意欲を認めながら見守り、「おいしいね」と声をかけ、食べる楽しさや喜びを感じられるようにする。
- 集中力が切れてくると遊び始める姿が見られるため、「次はどれを食べる?」「どれが好きかな」と声をかけ、食事に意識が戻るように関わる。
家庭との連携
子どもの姿(再掲):前年度に引き続き、給食前に眠くなることがあるため、主活動の前に午前睡を促した。
- 前年度と同じ生活リズムで心地よく過ごしている様子を伝え、保護者が安心できるようにする。
- 環境の変化や気温差により疲れが出やすい時期なので、園と家庭で本児の様子をこまめに共有し、体調の変化に留意する。
Hさん(中月齢/女児/静か)(1歳5カ月/11月生まれ)
子どもの姿
- 初日の登園時、保護者がいないことに気づくと泣き始め、次の日からは保育者の顔を見ると泣いていた。(養護)
- 泣き止んでいるタイミングで絵本を読み始めると、じっと見入っていたが、保育者が体を動かしたり、他の子どもの泣き声を聞くとつられて泣いていた。(教育)
- 関わる保育者が変わると泣いてしまうが、抱っこをしながら歌を歌って体を揺らすと徐々に落ち着き、泣き止む姿も見られるようになった。(家庭との連携)
ねらい/内容/環境構成・配慮・援助/評価・反省
養護
| 子どもの姿(再掲) | 初日の登園時、保護者がいないことに気づくと泣き始め、次の日からは保育者の顔を見ると泣いていた。(養護) |
| ねらい | 保育者に親しみを持つ |
| 内容 | 新しい環境への不安を自分なりに表現し、保育者に丁寧に受け止めてもらうことで、思いが伝わる安心感や喜びを感じる。 |
| 環境構成・配慮・援助 | 泣きながら登園する本児に、「おはよう」「待ってたよ」と笑顔で声をかけながら受け入れ、抱っこなどのスキンシップを取り、保育者への安心感や信頼感を育む。生活面ではできる限り同じ保育者が対応できるよう職員間で連携し、徐々に園生活に慣れていけるよう配慮する。 |
| 評価・反省 | 特定の保育者に対する信頼感が芽生え、登園時に自ら保育者に抱っこを求める姿も見られるようになった。本児の様子に合わせて、様々な場面で他の保育者も関わりながら、信頼関係を築いていく。 |
教育
| 子どもの姿(再掲) | 泣き止んでいるタイミングで絵本を読み始めると、じっと見入っていたが、保育者が体を動かしたり、他の子どもの泣き声を聞くとつられて泣いていた。(教育) |
| ねらい | 保育者とゆったり関わりながら遊ぶ楽しさを味わう |
| 内容 | 保育者と一緒に簡単なわらべうたあそびを楽しむ中で、スキンシップを取りながら安心感を味わう。 |
| 環境構成・配慮・援助 | 落ち着いた環境でわらべうた遊びに誘い、歌に合わせて手や足、顔などに優しく触れることで、スキンシップの心地よさを感じられるようにする。ひざに座らせながら「めんめんすーすー」「いっぽんばしこちょこちょ」を楽しみ、緊張を和らげていけるように関わる。 |
| 評価・反省 | わらべうたあそびを喜び、自分の手を保育者に差し出して「やって」とアピールしていた。本児なりの要求を見逃さずに受け止めていき、思いが伝わる喜びややり取りする楽しさを味わえるように関わりたい。 |
食事
- 保育者の介助により半分以上食べられるため、本児のペースを大切にしながら、「食べられたね」「おいしいね」と声をかけ、自分で食べる意欲を育む。
- 汁物やお茶を好んでよく飲むため、その気持ちを尊重しつつ、バランスよく食べられるように保育者がおいしそうに食べる姿を見せ、さまざまな食材に興味を持てるようにする。
家庭との連携
子どもの姿(再掲):関わる保育者が変わると泣いてしまうが、抱っこをしながら歌を歌って体を揺らすと徐々に落ち着き、泣き止む姿も見られるようになった。
- 職員間で連携し、朝に受け入れた保育者を中心に関わることで、本児が安心感を持って過ごせるよう配慮するとともに、泣き止んだ後の様子を保護者に伝え、安心して預けられるようにする。
- 初めての保育園生活に対する保護者の不安や心配を受け止め、毎日の様子を丁寧に伝えながら、信頼関係を築いていく。
Iさん(低月齢/男児/活発)(1歳4カ月/12月生まれ)
子どもの姿
- 前年度に引き続き、登園後に15分程度の午前睡をすることで、日中眠くならずに活動できた。(養護)
- 室内の様々な玩具に興味を持ち、一緒に遊ぶ保育者と目を合わせながら「あっ」と声を出したり、言葉をまねしようとする姿が見られた。(教育)
- 保育者と手遊びを楽しみ、自分なりに手や腕を動かして喜んでいた。(家庭との連携)
ねらい/内容/環境構成・配慮・援助/評価・反省
養護
| 子どもの姿(再掲) | 前年度に引き続き、登園後に15分程度の午前睡をすることで、日中眠くならずに活動できた。(養護) |
| ねらい | 安定した生活リズムの中で、健康的に過ごす |
| 内容 | 疲れや体調に合わせて十分に休息を取りながら、安全で快適な環境で、体を動かしたり好きな遊びを楽しむ。 |
| 環境構成・配慮・援助 | 主活動の前に午前睡ができるように、落ち着いて眠れる静かな環境を整える。保育時間が長いため、午後に眠気や疲れが見られる日は夕方寝ができるよう職員間で申し送りを行い、一日を通して元気に過ごせるよう配慮する。 |
| 評価・反省 | 日中の活動には元気に参加していたものの、声をかけても起きられない様子が見られたり、体調を崩して欠席する日もあった。休日のお出かけが増えているようなので、週明けは特に体調を観察し、無理なく過ごせるよう配慮する。 |
教育
| 子どもの姿(再掲) | 室内の様々な玩具に興味を持ち、一緒に遊ぶ保育者と目を合わせながら「あっ」と声を出したり、言葉をまねしようとする姿が見られた。(教育) |
| ねらい | 自分なりに思いを表現しようとする |
| 内容 | 保育者と絵本を読みながらやり取りを楽しむ中で、指差しや自分なりの言葉を受け止めてもらう喜びを感じる。 |
| 環境構成・配慮・援助 | くり返しの言葉やリズムを楽しめる絵本を用意し、一緒に体を揺らしたり、本児の発声を受け止めながら読み、楽しさを共有する。また、本児の指差しを見逃さず、「ワンワンがいるね」「だるまさんが笑っているね」など、本児の伝えたい思いを丁寧に言葉にして返していく。 |
| 評価・反省 | 様々な絵本を保育者のもとへ持ってきて「はい」と渡し、読んでもらう姿が見られた。本児なりに話そうとする意欲が高まっているため、丁寧な発音や言葉遣いを心がけ、言葉の発達を促していきたい。 |
食事
- 手づかみ食べが多いため、自分で食べる意欲を大切にしながら、保育者がスプーンを使って食べる姿を見せることで、本児の興味を引き出す。
- 食前に保育者のまねをして手を合わせられたときは、「いただきますができたね」と声をかけてその姿を認め、食前食後の挨拶が自然に身についていくようにする。
家庭との連携
子どもの姿(再掲):保育者と手遊びを楽しみ、自分なりに手や腕を動かして喜んでいた。
- 親子で手遊びを楽しめるように、迎えの際に実際にやって見せて紹介する。
- 戸外あそびを安全に楽しめるように、フードが付いていない上着を用意してもらうよう、丁寧に依頼する。
Jさん(低月齢/女児/活発)(1歳3カ月/1月生まれ)
子どもの姿
- 新入園児が登園し始める時間帯は、不安を感じて保育者のそばで遊びたがる姿が見られ、ひざに座ったり抱っこを求める様子もあった。(養護)
- 室内では積極的に歩いて探索を楽しむ一方、尻もちをついたり転倒する姿も多く見られた。(教育)
- 園庭では保育者に手を支えられながら歩行を楽しんだり、ハイハイの姿勢で段差をのぼりおりして体を動かしていた。(家庭との連携)
ねらい/内容/環境構成・配慮・援助/評価・反省
養護
| 子どもの姿(再掲) | 新入園児が登園し始める時間帯は、不安を感じて保育者のそばで遊びたがる姿が見られ、ひざに座ったり抱っこを求める様子もあった。(養護) |
| ねらい | 新しい保育者や友だちに慣れ、安心感を持って過ごす |
| 内容 | 信頼する保育者と一緒に遊んだり、食事や排泄、午睡を見守られる中で、思いを受け止めてもらう安心感や心地よさを感じる。 |
| 環境構成・配慮・援助 | 他児の登園が重なる時間帯は、人の出入りが気になりにくい場所で遊びに誘い、集中して楽しめるよう配慮する。生活面では、本児と信頼関係が築けている保育者が中心となって対応し、新しい環境への不安を軽減できるようにする。 |
| 評価・反省 | オムツ交換や午睡の際は、信頼する保育者以外との関わりを嫌がっていた。本児の気持ちを尊重しながら、徐々に信頼関係を築けるよう職員間で連携し、対応していく。 |
教育
| 子どもの姿(再掲) | 室内では積極的に歩いて探索を楽しむ一方、尻もちをついたり転倒する姿も多く見られた。(教育) |
| ねらい | 十分に探索を楽しみながら好奇心を満たす |
| 内容 | 保育者に見守られながら室内での探索を楽しみ、興味のある玩具を見つけて遊ぶ。 |
| 環境構成・配慮・援助 | 室内を安全に探索できるよう、落ちている玩具はこまめに片付け、興味を持ちそうな玩具を手の届く場所に配置して意欲を刺激する。探索したり、発見した玩具に触れる姿を見守り、本児が保育者の方を振り返った際には目を合わせ、「良い物を見つけたね」と声をかけて喜びに寄り添う。 |
| 評価・反省 | 新しい環境に慣れ、室内での探索を楽しむ中で、机の下にもぐったり隙間に入ろうとする様子が見られるようになった。室内で安全に運動欲求や好奇心を満たせる環境構成や活動を考えて、取り入れていきたい。 |
食事
- その日の機嫌や体調により食欲にムラがあるため、少しでも食べられた姿を見逃さずに認め、「おいしいね」と声をかけながら食べる意欲を育てる。
- 苦手な食材を口から出すことがあるため、食べることを無理強いせず、保育者が食べて見せることで興味を育み、徐々に慣れるように関わる。
家庭との連携
子どもの姿(再掲):園庭では保育者に手を支えられながら歩行を楽しんだり、ハイハイの姿勢で段差をのぼりおりして体を動かしていた。
- 様々な体の動きを楽しむ姿を保護者と共有し、本児の発達を共に見守りながら、適切な援助ができるようにする。
- 歩行を楽しむ中で転倒することが多いため、安全に配慮しつつ見守り、小さなケガでも保護者に丁寧に伝えることで、信頼関係を築いていく。
Kさん(低月齢/男児/静か)(1歳2カ月/2月生まれ)
子どもの姿
- 保護者から離れる際に泣くが、室内に入ると泣き止み、受け入れた保育者のそばに座って周囲を見回したり、玩具を渡されると興味を示し、遊び始めることができた。(養護)
- ボール落としの玩具を気に入り、ボールが転がり落ちる様子をじっと見つめ、くり返し楽しんでいた。(教育)
- 伝い歩きやハイハイで、少しずつ保育者から離れて探索をする姿が見られるようになった。(家庭との連携)
ねらい/内容/環境構成・配慮・援助/評価・反省
養護
| 子どもの姿(再掲) | 保護者から離れる際に泣くが、室内に入ると泣き止み、受け入れた保育者のそばに座って周囲を見回したり、玩具を渡されると興味を示し、遊び始めることができた。(養護) |
| ねらい | 思いを受け止められながら心地よく過ごし、新しい環境に慣れる |
| 内容 | 排泄や睡眠の要求に応えてもらい、心地よさを感じながら過ごすとともに、自分なりに表現した思いを受け止めてもらい、伝わる喜びを味わう。 |
| 環境構成・配慮・援助 | 登園時の不安やオムツが濡れたとき、眠気を感じた際の不快感を受け止め、「嫌だったね」「眠くなってきたね」「びっくりしたね」など、丁寧に言葉にしながら対応する。泣き止んで落ち着いたときは、優しく名前を呼んだり話しかけ、保育者に対する安心感を育んでいく。 |
| 評価・反省 | 徐々に園生活に慣れ、好きな遊びを見つけると落ち着いて過ごせるようになった。来月は連休があるため、引き続き時間配分に余裕を持たせ、本児のペースを大切にしながらゆったりと過ごせるよう配慮する。 |
教育
| 子どもの姿(再掲) | ボール落としの玩具を気に入り、ボールが転がり落ちる様子をじっと見つめ、くり返し楽しんでいた。(教育) |
| ねらい | 興味のある玩具を見つけて遊ぶ |
| 内容 | 室内を探索する中で、積み木や布、重ねコップなど様々な玩具を発見した喜びを保育者に受け止めてもらったり、一緒に遊ぶ楽しさを味わう。 |
| 環境構成・配慮・援助 | 様々な感触の玩具を、本児の目に入りやすい位置に配置し、興味を引き出す。発見した玩具を自由に触る姿を見守り、一緒に遊びながら感触の不思議さや面白さを言葉にして、楽しさを共有する。 |
| 評価・反省 | ハイハイや伝い歩きで室内を探索し、棚から玩具を取り出して保育者に渡し、一緒に楽しんだ。遊びに飽きると保育者のひざに乗ったり抱っこを要求するので、応答的に関わりつつ、本児が夢中になれる玩具を提供していきたい。 |
食事
- 食欲が少ないため、本児のペースに合わせて食べ進められるように介助し、食べられた際には「おいしいね」「モグモグできるね」と大いに認める言葉かけを行い、意欲を育んでいく。
- 家庭ではドロッとしたおかゆを好み、軟飯も食べられるがむせやすいため、少量ずつ与えながら咀嚼の様子を観察し、安全に配慮する。
家庭との連携
子どもの姿(再掲):伝い歩きやハイハイで、少しずつ保育者から離れて探索をする姿が見られるようになった。
- 初めての保育園に対する保護者の不安を受け止めつつ、少しずつ保育者から離れて過ごせるようになった本児の姿を具体的に伝え、園に対する信頼感を育む。
- 食事の様子を園と家庭で共有し、本児が無理なく食べられる食材の大きさや固さをこまめに伝え合いながら、焦らずに食への意欲を育てていく。
Lさん(低月齢/女児/静か)(1歳1カ月/3月生まれ)
子どもの姿
- 初日から泣かずに登園し、室内の様々な物に興味を持ちながら、ゆっくりとハイハイで探索を楽しんでいた。(養護)
- 布あそびを楽しむ中で、保育者が目の前で揺らす布を掴もうとしたり、「いないいないばあ」に喜び、笑顔を見せていた。(教育)
- 睡眠が浅く、小さな物音ですぐに目覚めてしまった。(家庭との連携)
ねらい/内容/環境構成・配慮・援助/評価・反省
養護
| 子どもの姿(再掲) | 初日から泣かずに登園し、室内の様々な物に興味を持ちながら、ゆっくりとハイハイで探索を楽しんでいた。(養護) |
| ねらい | 新しい環境や保育者に親しむ |
| 内容 | 排泄や食事、午睡の際に保育者と一対一で関わる中で、丁寧に思いを受け止めてもらい、優しく話しかけられる喜びを感じながら、心地よく過ごす。 |
| 環境構成・配慮・援助 | 生活面の援助はできる限り同じ保育者が担当し、園生活の流れに慣れるよう働きかけながら、信頼関係を築いていく。関わる際には優しく名前を呼びかけ、「きれいになったね」「眠たいね」「おいしいね」と丁寧に話しかけることで、他者との関わりを心地よく感じられるようにする。 |
| 評価・反省 | 園での生活や保育者に慣れてきて、排泄や午睡に誘われるとハイハイで保育者の元へ近づいて応じる姿が見られた。クラス全体で鼻水が出る子が増えてきたため、体調の変化に留意する。 |
教育
| 子どもの姿(再掲) | 布あそびを楽しむ中で、保育者が目の前で揺らす布を掴もうとしたり、「いないいないばあ」に喜び、笑顔を見せていた。(教育) |
| ねらい | 保育者と関わりながら遊ぶことを喜ぶ |
| 内容 | わらべうたあそびを通じて、保育者と一対一でふれあう心地よさや、体を動かす楽しさを感じる。 |
| 環境構成・配慮・援助 | 落ち着いた環境でわらべうたあそびに誘い、歌に合わせて手足や顔に優しく触れながら本児の反応を受け止め、ゆったりとやり取りを楽しむ。「おおかぜこい」に合わせて布を揺らして見せたり、保育者のひざに座らせて「おふねがぎっちらこ」「うまはとしとし」に合わせて体を動かすことで、楽しさを感じられるようにする。 |
| 評価・反省 | ひざに座って揺れる動きを気に入り、笑顔を見せて喜んでいた。本児の「もう一回」の要求を見逃さずに受け止め、気に入った動きや遊びをくり返し楽しむことで、満足感を味わえるようにする。 |
食事
- 保育者が介助すると最初は食べるものの、途中で口を開かなくなるため、食材の大きさを工夫したり、保育者も同じものを食べて見せることで、少しずつ興味を育む。
- 食欲にムラがあり、家庭で全く食べたがらない日はミルクを与えているため、給食を食べられなかった場合は、家庭での対応に合わせて食後にミルク120ccを補完する。
家庭との連携
子どもの姿(再掲):睡眠が浅く、小さな物音ですぐに目覚めてしまった。
- 本児が心地よく再入眠できる関わり方を模索し、睡眠時間が不足した日は保護者に伝え、園と家庭で協力して徐々に生活リズムが安定するように関わる。
- 初めて子どもを預ける保護者の不安や、日ごろの育児の悩みを受け止め、園全体で連携しながら丁寧に寄り添う。
その他、ほいくのおまもりプラスのコンテンツ